教育班(徳島教育社会学会)
伴恒信1)・成松絵里1)・大島純子1)
清水俊平1)・斎藤仁美1)・
松原亜希子1)・国見明子1)
1.調査・研究の目的
われわれが、調査・研究をしようとするテーマである向社会的行動とはアイゼンバーグによると、以下のように定義されている。向社会的行動(prosocial
behavior)とは、外的な報酬を期待することなしに、他人や他の人々の集団を助けようとしたり、こうした人々のためになることをしようとする行為のことである(1)。このような行為をする場合には、行為をする側に自己犠牲や危険などの損失が伴い、寛容さ・利他心・同情などの感情が要請される。この行動を引き起こす動機についての意欲をわれわれは向社会性と考え、社会と自己を取りまく環境に対し、よりよい社会を形成しようとする態度、あるいは自分が属する集団においてより望ましい振る舞いを積極的に担っていこうとする意欲、という意味で取り扱う。現在、児童・生徒に関わる際だって凶悪な事件が全国で多発している。このことは多くの人々に危機感を募らせている状況にあることは疑いないであろうが、この状況を誘発した原因となると、これを教育現場に帰するもの、教育環境に帰するもの、また現代社会の病理そのものに言及するものと様々であり、それぞれに一面的理解であると思われる。
「子どもたちの人間関係は極限状況といえるくらいに希薄化している」というのは、深谷昌志の指摘である(2)。以前と比べて、核家族化の進展により家庭内集団がきわめて小さなものとなっていること。学校の中の人間関係も、塾やけいこ事により時間的な制限が加えられていることなどにより、同世代の者同士での遊び仲間(ギャング集団)の形成など、幼児・児童期の社会経験の不足が子どもの成長をゆがめているといわれている。小学校時代に形成されるギャング集団ともいわれる原初的社会は、それが子どもたち独自の未熟な感性により形成されるものであるが故に、非合理な社会ではある。しかし、ここで子どもたちはさまざまな衝突・摩擦・もつれを経験することにより、耐性を身につけ、感受性を養い、社会集団の一員として身につけるべきマナーやルールを徐々に内面化していくのである。
本研究は、質問紙による調査で子どもたちの日常生活や意識を分析し、われわれの考える向社会性の形成過程・形成要因・阻害過程などを明らかにしていくことを目的としている。
2.調査方法の概略
平成10年7月上旬に、穴吹町内の三島小・穴吹小・初草小・宮内小・半平小の4・5・6年生を対象として質問紙調査を行った。有効回答の内訳は、三島小74人、穴吹小121人、初草小17人、宮内小21人、半平小2人の計235人である。
質問紙を構成する領域は、日常生活、家庭生活、学校生活、友人関係、自分自身の5領域である。
3.調査・研究の結果と考察
質問紙調査の単純集計の結果から明らかになったことを、いくつか考察していくことにする。
学校での学習・行事に対する児童の満足度を4段階に分けて回答させた調査では、当初予想されたように、サッカー、ポートボールなどの球技系の満足度が、「とても楽しい」・「割と楽しい」と回答した者が合計で80%を超えており、最も高く、理科実験・図工における絵画がそれに続き、70%を超えており、教科書の音読や、発表などは、「あまり楽しくない」・「全く楽しくない」が、「とても楽しい」・「割と楽しい」を上回っている(図1)。一般に中学、高校では、座学系の授業と、体験・実験系の授業の満足度の差は縮まる傾向にあるが、小学校高学年の段階では体験・実験系の授業の方が楽しいようである。さらに、校外学習・遠足・運動会・音楽会などのリクリエーション系の行事では、楽しいと感じている子の方が圧倒的に多い。
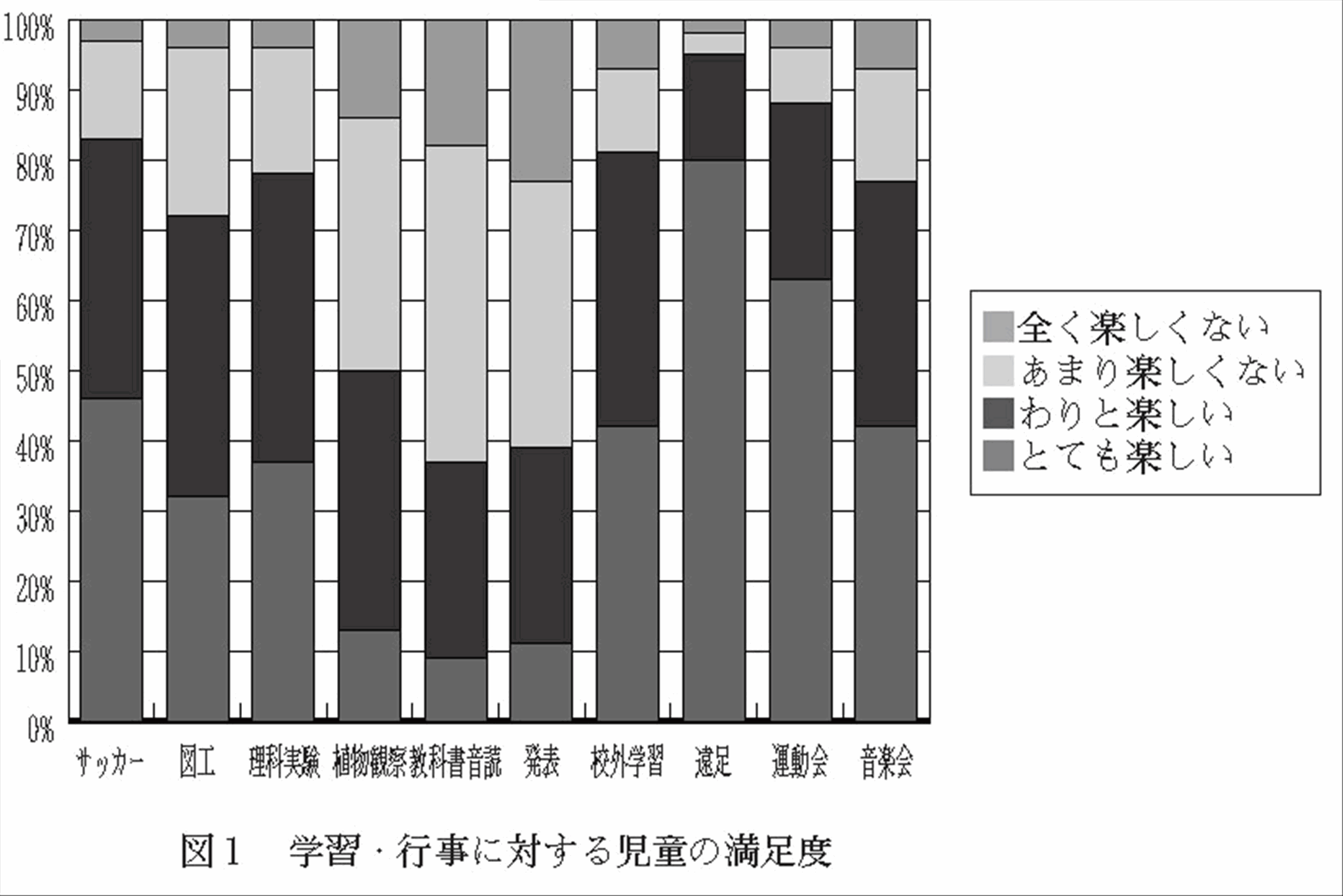
次に、授業中の様子を尋ねた質問では(図2)、むずかしくてよくわからなかったことが、「よくある」・「割とある」と回答した者が、「あまりない」・「全くない」をやや上回っているものの、自分から進んで手を挙げて発表したことのある者の割合も、「よくある」・「割とある」が 「あまりない」・「全くない」を上回っている。授業中わからないところを先生に質問する児童は、「あまりない」・「全くない」が合わせて67%で、「よくある」・「割とある」をかなり上回っているが、授業を聞くことができずにぼうっとすることや、授業中手紙やメモを回すなど、授業に参加しないことに関する質問では、「あまりない」・「全くない」が「よくある」・「割とある」を大幅に上回っており、授業中に関係のないおしゃべりをすることはあるけれども、授業に対する態度は少なくとも自己申告のレベルではおおむね良好であることがうかがえる。大阪などの大都市圏では、学級崩壊といわれる現象が頻発し、授業それ自体が成立しないという深刻な事態が発生している。しかし、この結果をみる限りにおいては、このような傾向はここではまだ見受けられない。
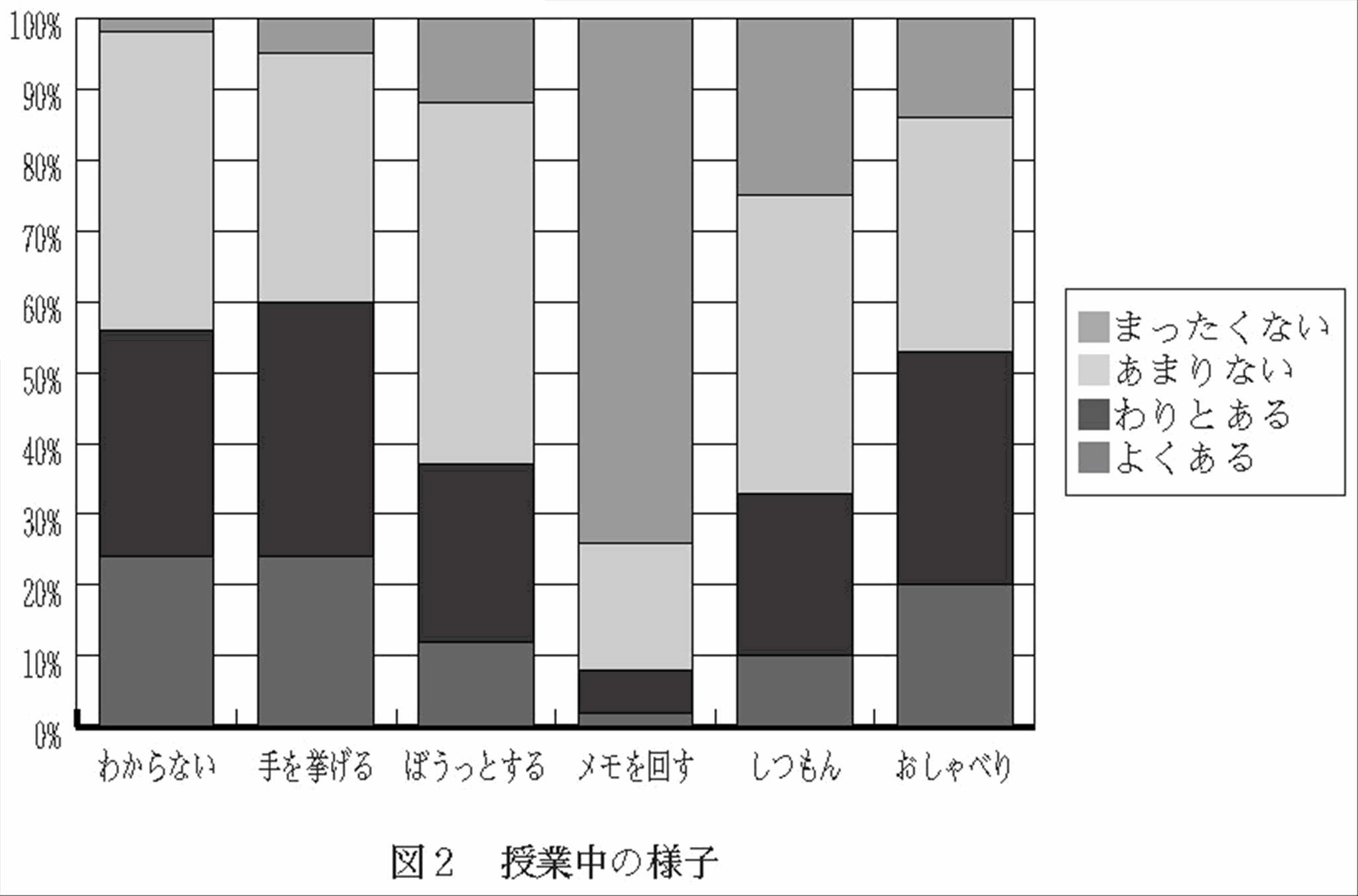
さらに、なんのために勉強をしているのかという複数回答を含めた質問では(図3)、「自分のやりたい仕事に就くため」が合計で98人と圧倒的に多く、「楽しくいきるため」76人、「親に喜んでもらうため」75人がほぼ同数で続き、「幸せな家庭をつくるため」59人、「人々の役にたつ人間になるため」59人が全くの同数で並んでいる。この結果から小学校高学年では、社会に対する信頼感、および自己効力感が十分に機能しており、自分の勉強に対する努力が、将来自分の仕事に結びつき、社会に貢献することができるという思いが内面化されていると理解しても差し支えないであろう。
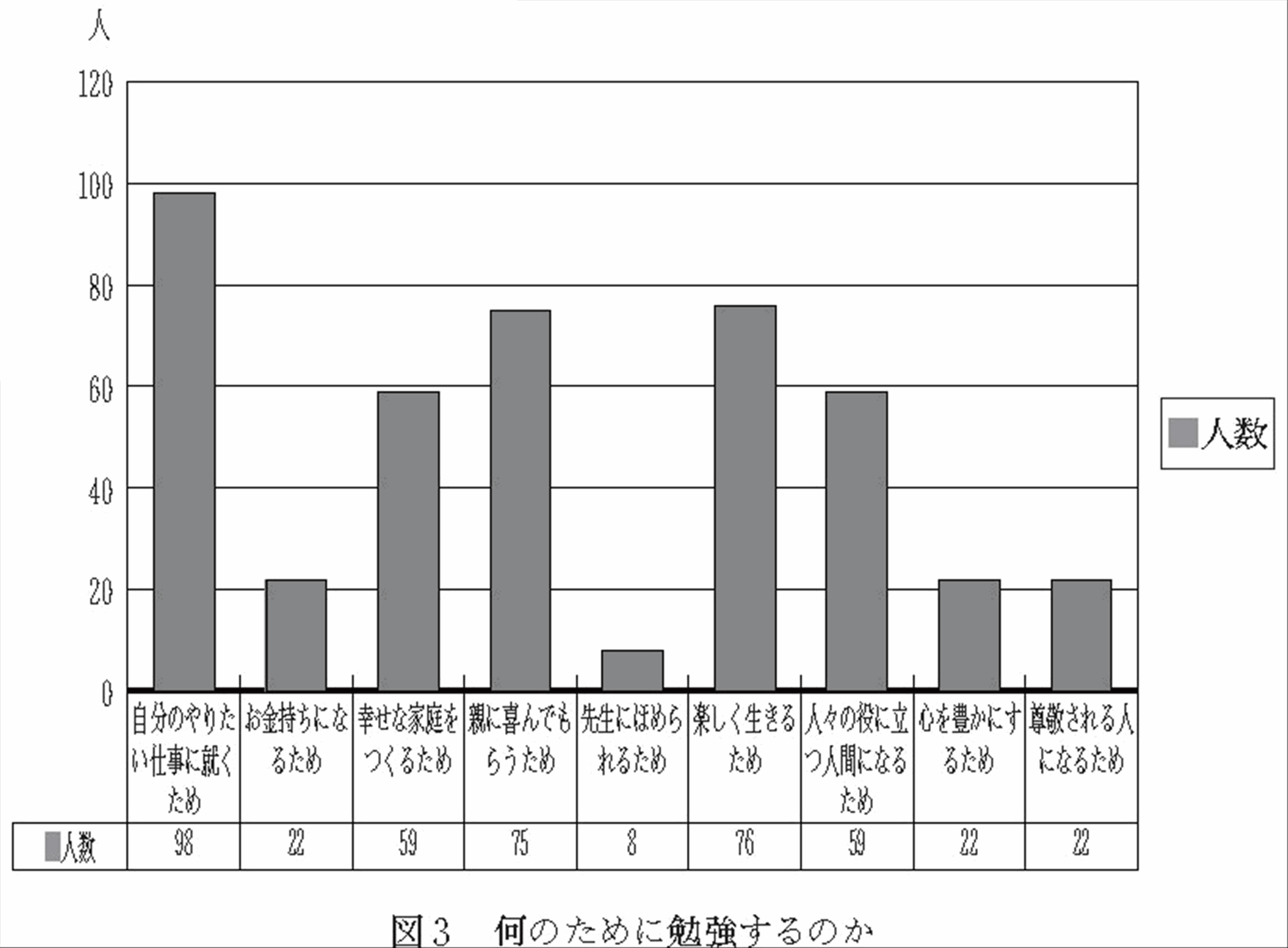
クラスの様子を尋ねた質問項目の単純集計を検討すると(図4)、「みんな仲良くのびのびしている」・「困っている人をみんなで助ける」に関しては、「とてもそう」・「割とそう」が過半数を占めていて、人間関係に関してはおおむね良好であると判断されるが、「熱心に係り活動や掃除をやっている」においては「あまりそうでない」・「全くそうでない」が「とてもそう」・「割とそう」を若干上回っており、「チャイムが鳴ったらすぐ授業が始められる」では、「あまりそうでない」・「全くそうでない」が「とてもそう」・「割とそう」を大幅に上回っている。さらに「自分勝手な人が多い」では、「あまりそうでない」・「全くそうでない」が「とてもそう」・「割とそう」を若干上回っているが、「みんながきまりをよく守っている」では、「あまりそうでない」・「全くそうでない」が、「とてもそう」・「割とそう」を若干上回っている、という結果が表れている。
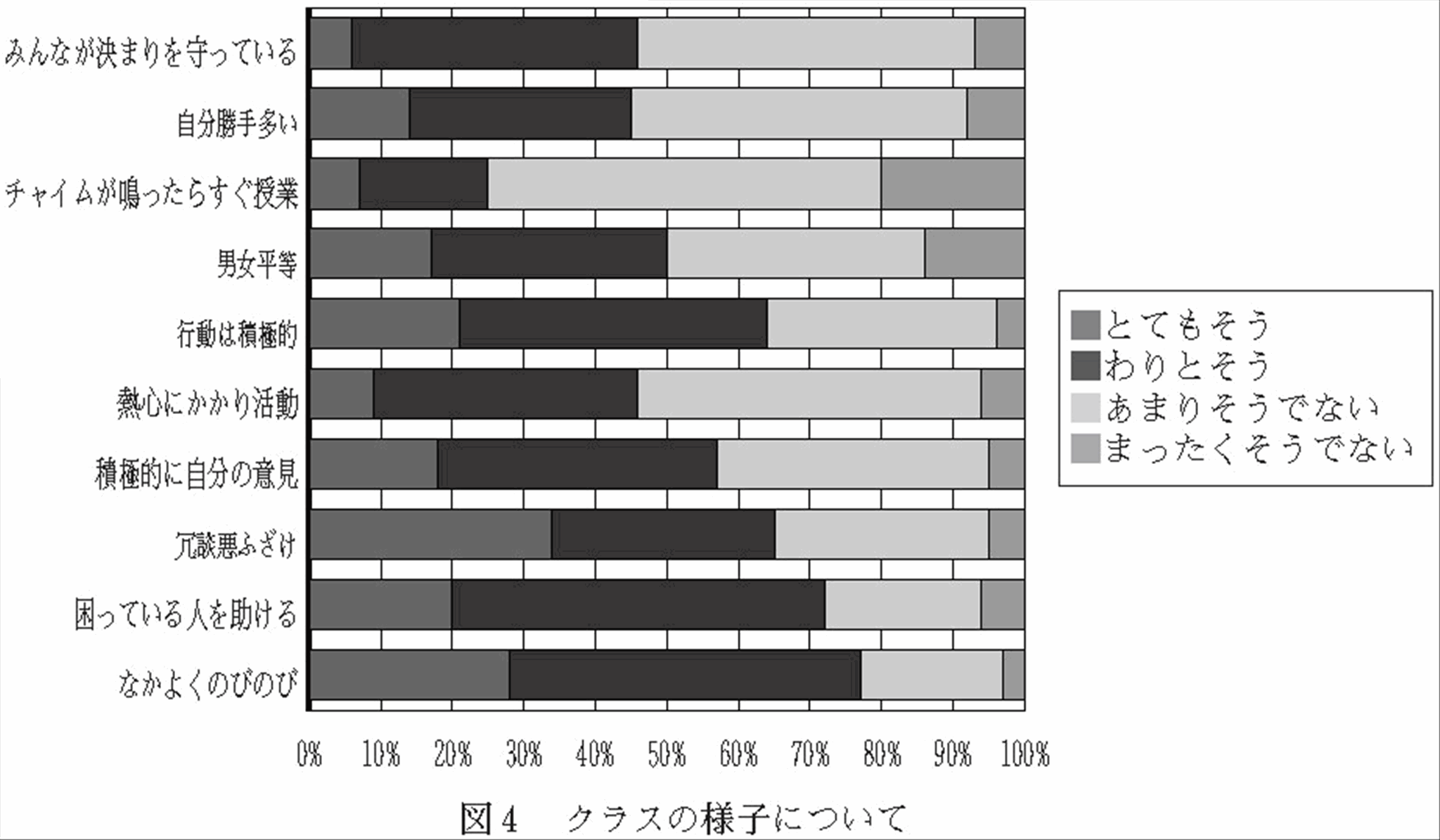
級友同士の私的な人間関係が良好であると見受けられるのに対して、係り活動や始業の態度などの、公的領域における行為に問題があると感じている児童が多いことが印象的である。従来は、子供の成長とともにその行動も公共性を帯びてくると考えられていたが、児童相互の印象では、自分勝手できまりを守らないと感じている生徒が過半数を上回っている。これは、私的なエゴが公共性を浸食しつつある兆しと見ることができるのではないかと思われる。
さらに、同様なことをした場合、先生から叱(しか)られる場合と両親から叱られる場合を比較した。
注目すべきは、テストの点数が悪かったとき先生からは「必ず叱られる」・「たぶん叱られる」がそれぞれ、4%、16%で、半数以上が叱られないと思っているのに対して、同様の質問に、両親からはそれぞれ20、33%で、大多数の児童が叱られると考えていることである(図5,6)。先生はテストの点数に関しては、必ずしもほめることもしないが、まして叱るということはまれなことである。しかし両親の場合は、点数が良かったときはおおいにほめるが、また悪かったときも叱るのである(図7、8)。つまり、テストの点数に敏感に反応するのは、先生よりも両親なのである。テストの点数という序列のはっきりしたことに対して、教師はどちらかというとあいまいな態度をとり、両親ははっきりとした姿勢を見せる。これはテストの点数による抑圧・圧迫という批判に対して教師は過敏になっているためと想像することができる。また一方、現実の点数の前に子どもたちをしった激励するのは両親であるという事実は興味深い。できれば序列付けを回避したいというのが教師の本音であり、わが子に高い成績を望むのが両親である。したがって、教師のあいまいさがかえって明確な評価を求める両親の競争心を過熱化するのである。
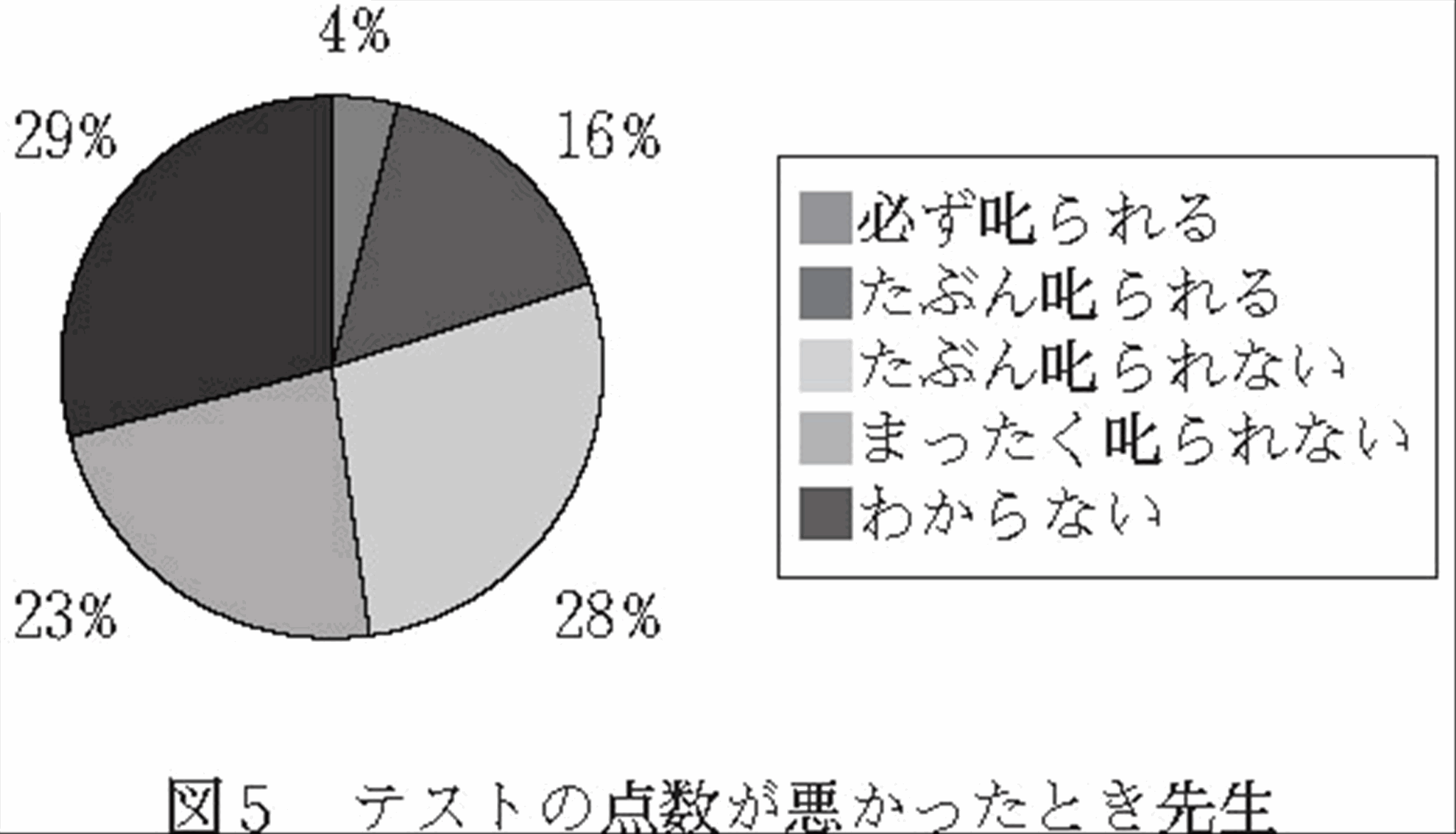
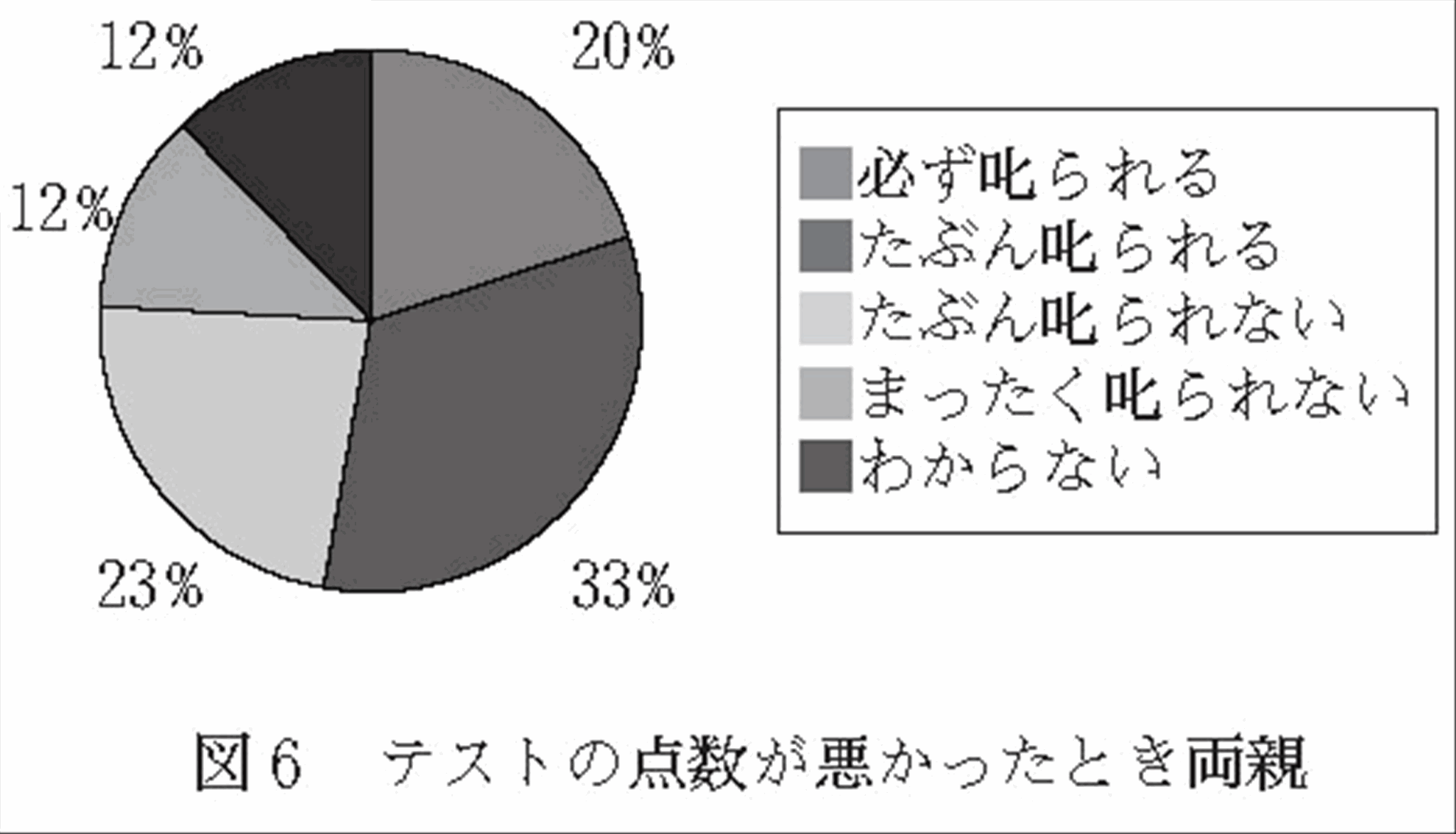
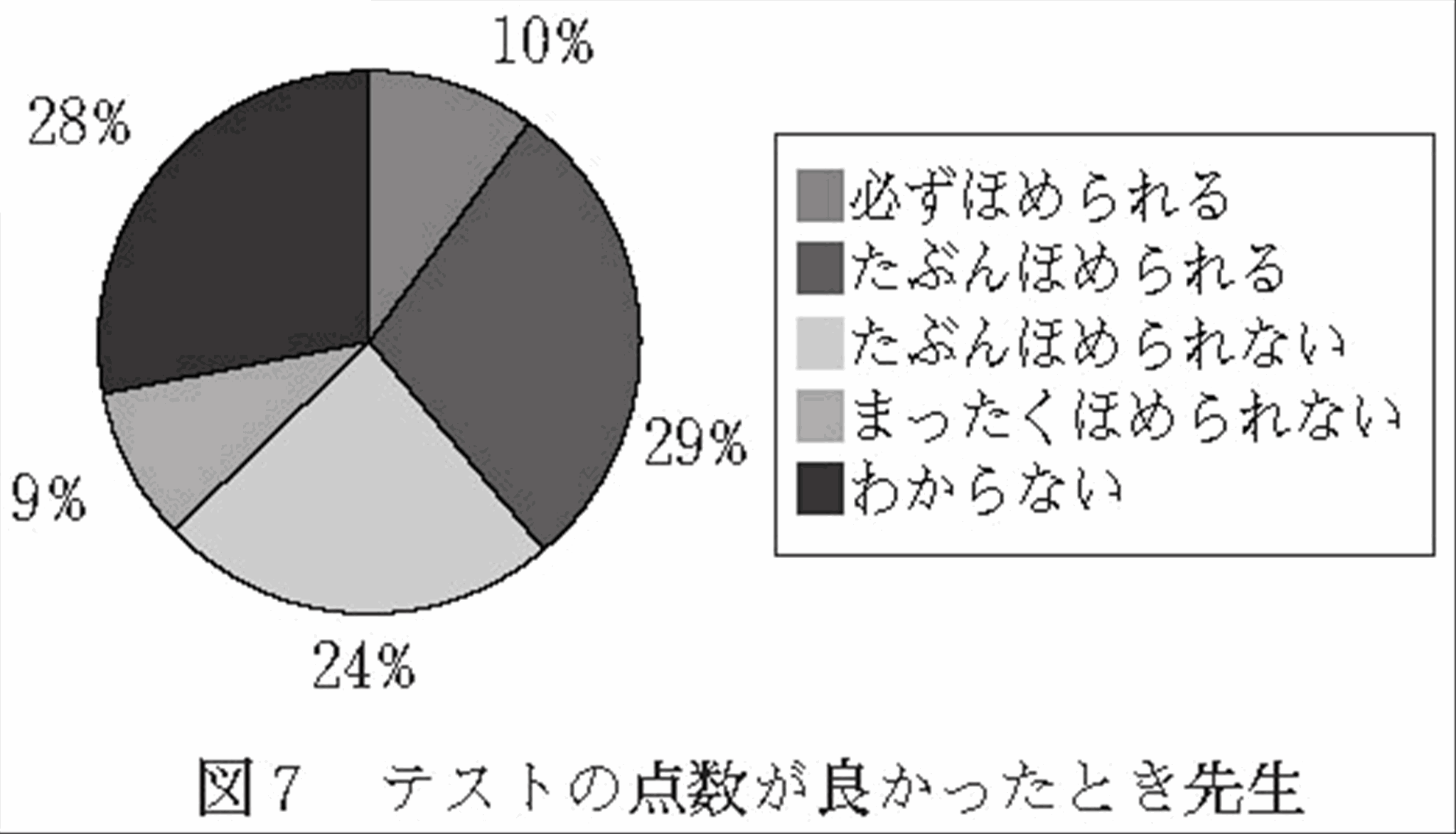
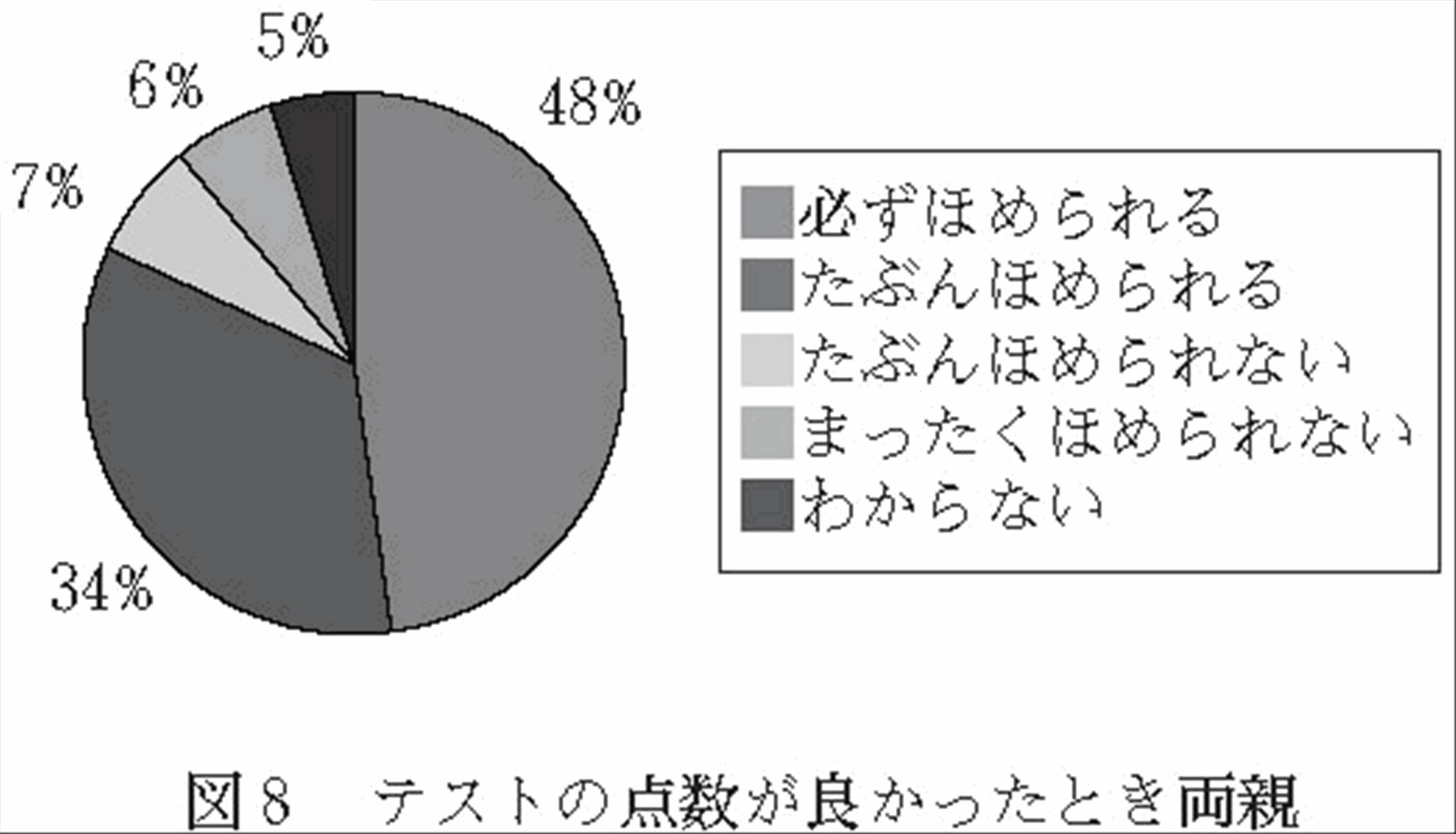
しかしまた一方、一生懸命勉強したテストで思い通りの点数をとれなかったときの感じ方を尋ねた質問では、「もっと頑張ろう」と「これまでと同様に頑張ろう」が圧倒的に多く、「運が悪かった」・「努力が足りなかった」という自己認知が、自信喪失や能力不足というあきらめの感情をはるかに上回っている。テストの点数にたいする自己評価は、いわば健全であり、原因帰属も自己の努力に帰している点では、自己効力感を喪失していない。
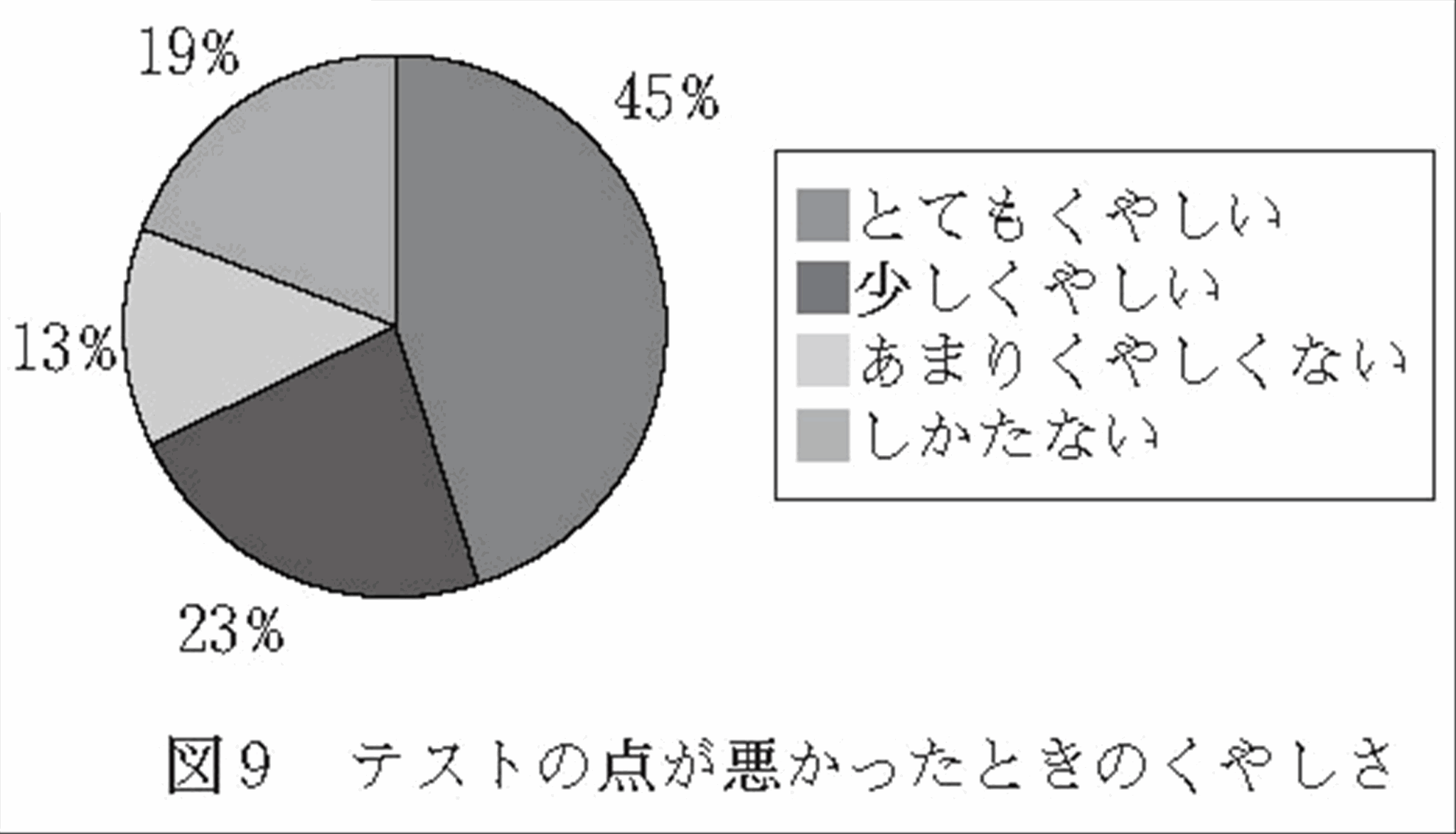
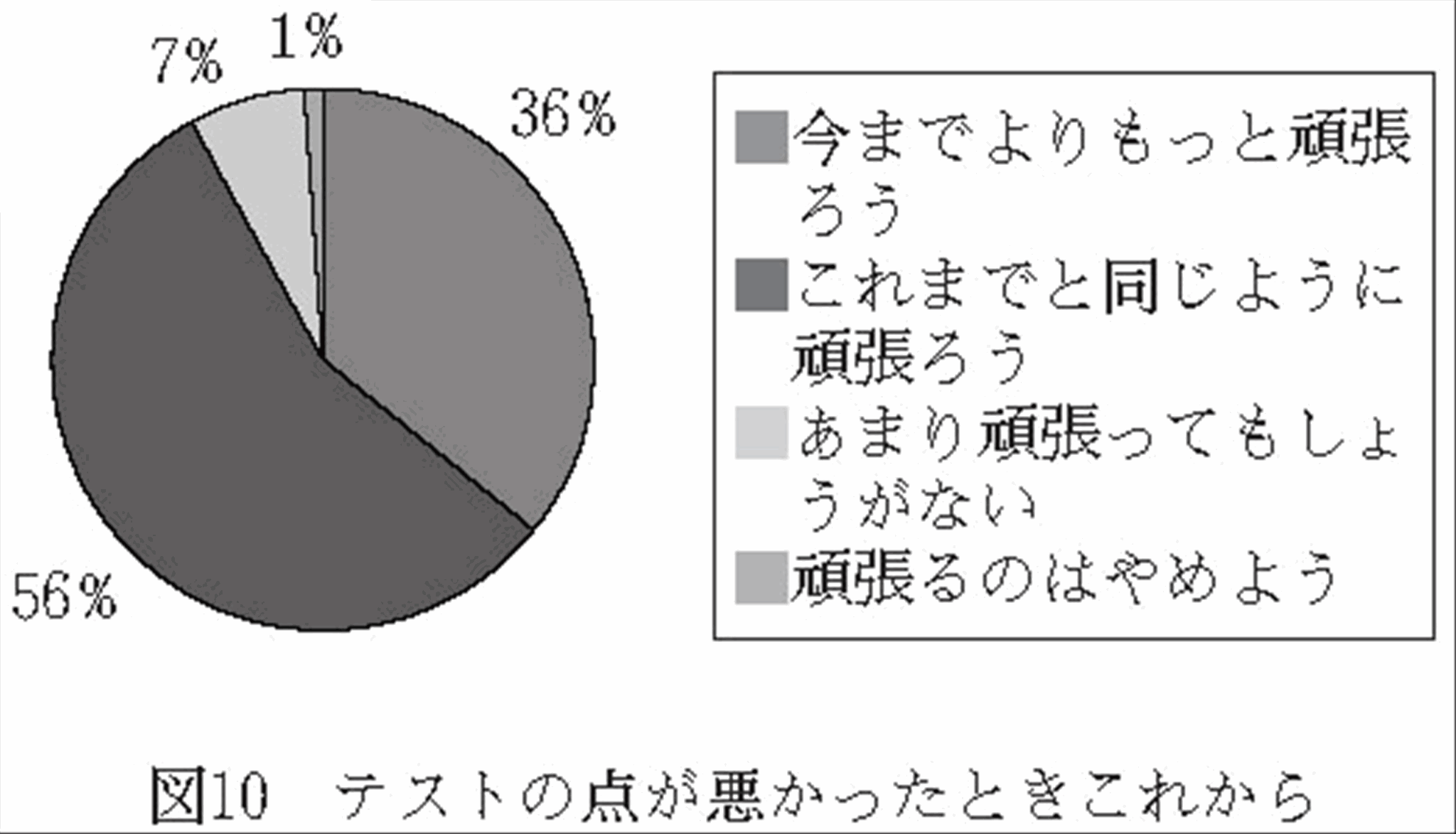
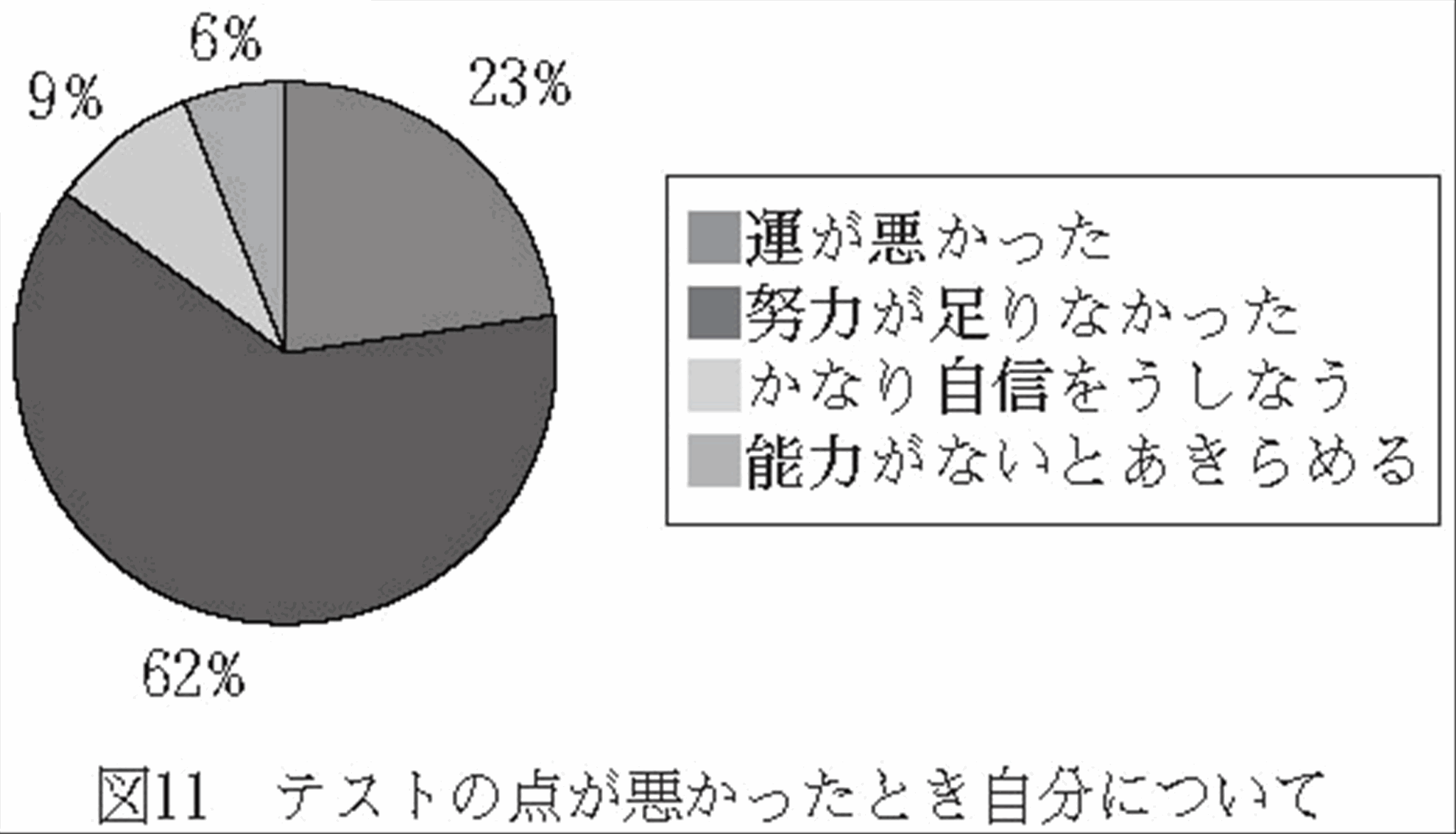
さらに、「自分のことをどのような子どもと感じているか」という質問の下に、12の項目を因子分析の主成分分析法にかけ、バリマックス回転の結果、以下のような因子を析出した。
「あなたは自分のことを、どのようなこどもだと感じていますか。」
F1 F2 F3
1 いつも明るく元気 .78293 .05181 .18434
2 最後までがんばることができる .53112 .51584 .04952
3 友だちに親切 .31365 .67240 .22844
4 忘れものをしない .08362 .63895 .03426
5 決まりをまもる .29988 .70185 .11474
6 自分のまちがいは、すなおに認める .13252 .51451 .54991
7 人にたのまれたら、いやとはいえない .12324 .19714 .56228
8 一人でも正しいと思ったことは主張する .68037 .29104 .14176
9 けんかをしても仲直りでできる .65172 .21039 .12716
10 自分は友だちからごかいされやすいと思う .05709 .04319 .79450
11 人に自分からあいさつをする .62405 .01470 .30324
12 大事なものをなくすことがある .25378 .54665 .46407
そこでわれわれは、向社会的行動に関わる感情として、それぞれ、F1には「いつも明るく元気」「一人でも正しいと思ったことは主張する」という項目が析出されたことから「自律意欲」、F2には「決まりを守る」「友だちに親切」という項目が析出されたことから「協調指向」、F3には「他者指向」と名づけることにした。このような感情が家庭での生活とどの程度関わっているのかをみるために、家庭での生活に関する質問とクロス集計をしてみることにした。質問項目にたいして、「とてもそう思う」を2点、「割とそう思う」を1点、「あまりそう思わない」を−1点、「全くそう思わない」を−2点として得点化する。従って抽出した因子項目が五つある
F1は10点から−10点まで、析出された因子項目三つずつの F2および
F3は、6点から−6点までの各得点が示される。さらにそれを段階化して、F1では−10点から−6点までを「低い」、−5点から−1点までを「やや低い」、0点から各5点までを「やや高い」、6点から10点までを「高い」と分類し、因子項目が三つの
F2および
F3では、−6点から−4点までを「低い」、−3点から−1点までを「やや低い」、0点から3点までを「やや高い」、4点から6点までを「高い」として分類する。家庭での生活に関する質問は、以下の六つである。
1 家族に起こされる前に自分で起きる。
よくする わりとする あまりしない まったくしない
2 夕食を家族全員で食べる。(夕食)
よくする わりとする あまりしない まったくしない
3 夕食の後、家族でおしゃべりをする。(家族団らん)
よくする わりとする あまりしない まったくしない
4 家族そろって旅行をする。
よくする わりとする あまりしない まったくしない
5 あなたの友だちが家に泊まりにくる。
よくする わりとする あまりしない まったくしない
6 心配事や悩みを相談する。(悩み事の相談)
よくする わりとする あまりしない まったくしない
それぞれのクロス集計表からカイ二乗検定の結果、0.004以下のものを有意差ありとみなしてグラフ化したのが、図12〜16である(いずれも%表示)。
図12は、自律意欲の高低と、家族全員で夕食を食べる頻度の関係をグラフ化したものである。このグラフに見られるように、自律意欲の「高い」子どもに着目すると、家族全員での夕食は、「よくする」から、「まったくしない」までが、なだらかに少なくなってきている。
図13は、自律意欲の高低と家族団らんの頻度の関係をグラフ化したものである。自律意欲の「低い」子どもで、家族団らんをよくすると答えたものが全くいないことがまず注目されるが、自律意欲の高い子どもが家族団らんをよくすることがはっきりと示されている。
図14は協調志向と家族団らんの関係、図15は協調志向と悩み事の相談の関係をグラフ化したものである。どちらも、「やや低い」、「やや高い」の段階ではそれほどはっきりとした傾向は表れないが、「低い」、「高い」の両極で比較した場合には、協調指向の高い子どもは家族団らんに費やす時間が多く、悩み事の相談もよくするが、協調指向の低い子どもは家族団らんも少なく、悩み事の相談もあまりしないという関係が明白に表れている。
図16は他者志向と悩み事の相談の関係をグラフ化したものである。他者志向の「高い」および「やや高い」が、悩み事の相談を「よくする」、「わりとする」に集中し、「やや低い」が「あまりしない」、「まったくしない」に集中する傾向をみせている。それぞれの因子と、質問項目の夕食・団らん・悩み事の相談では有意差が表れたが、「家族に起こされる前に自分で起きる」、「家族そろって旅行をする」、「友だちが家に泊まりにくる」には顕著な有意差はみられなかった。したがって、自分で起きる前に家族から起こされたり、家族で旅行したり、友だちが家に泊まりにくるといったことは、抽出された因子とはあまり関係がないと考えられる。
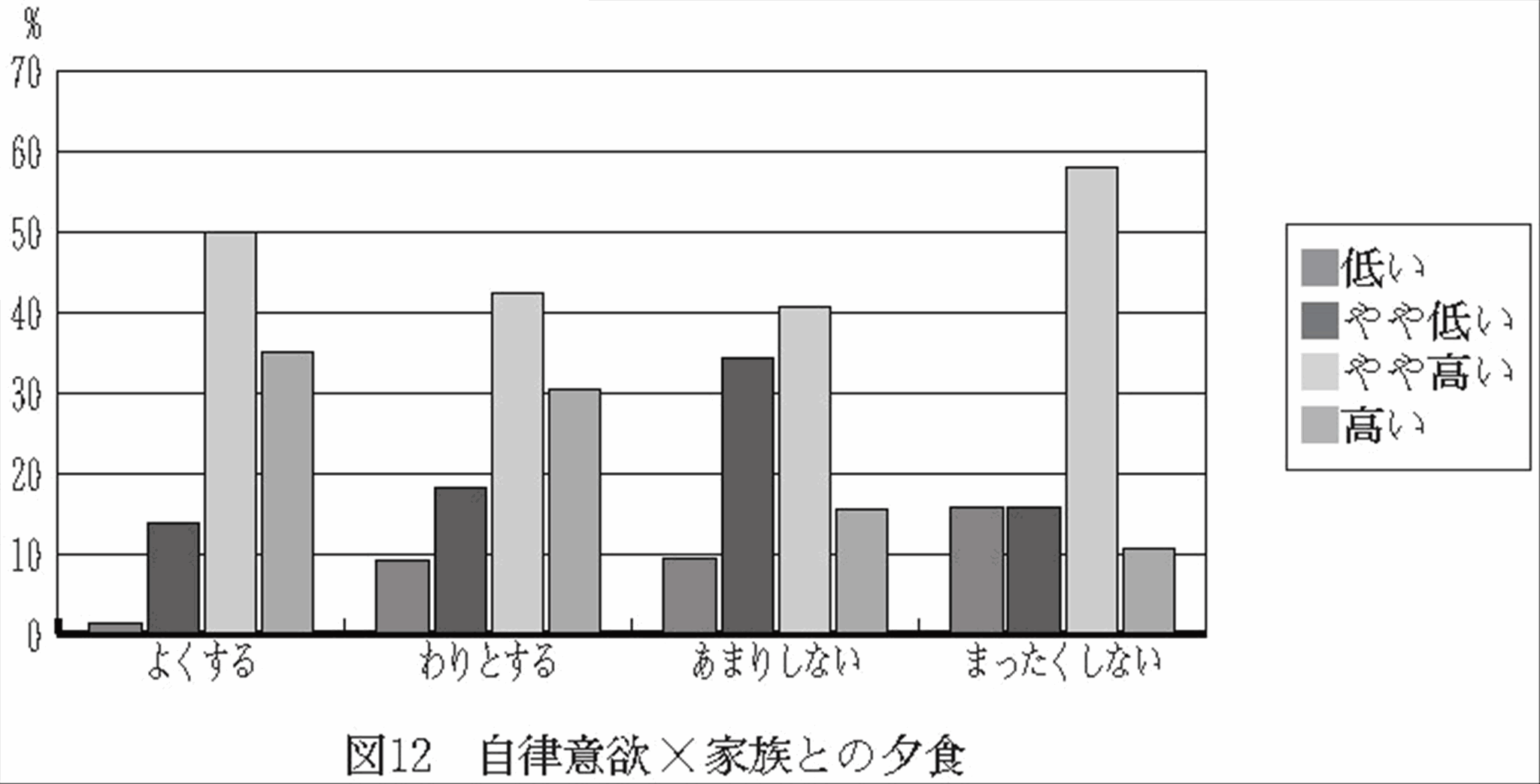
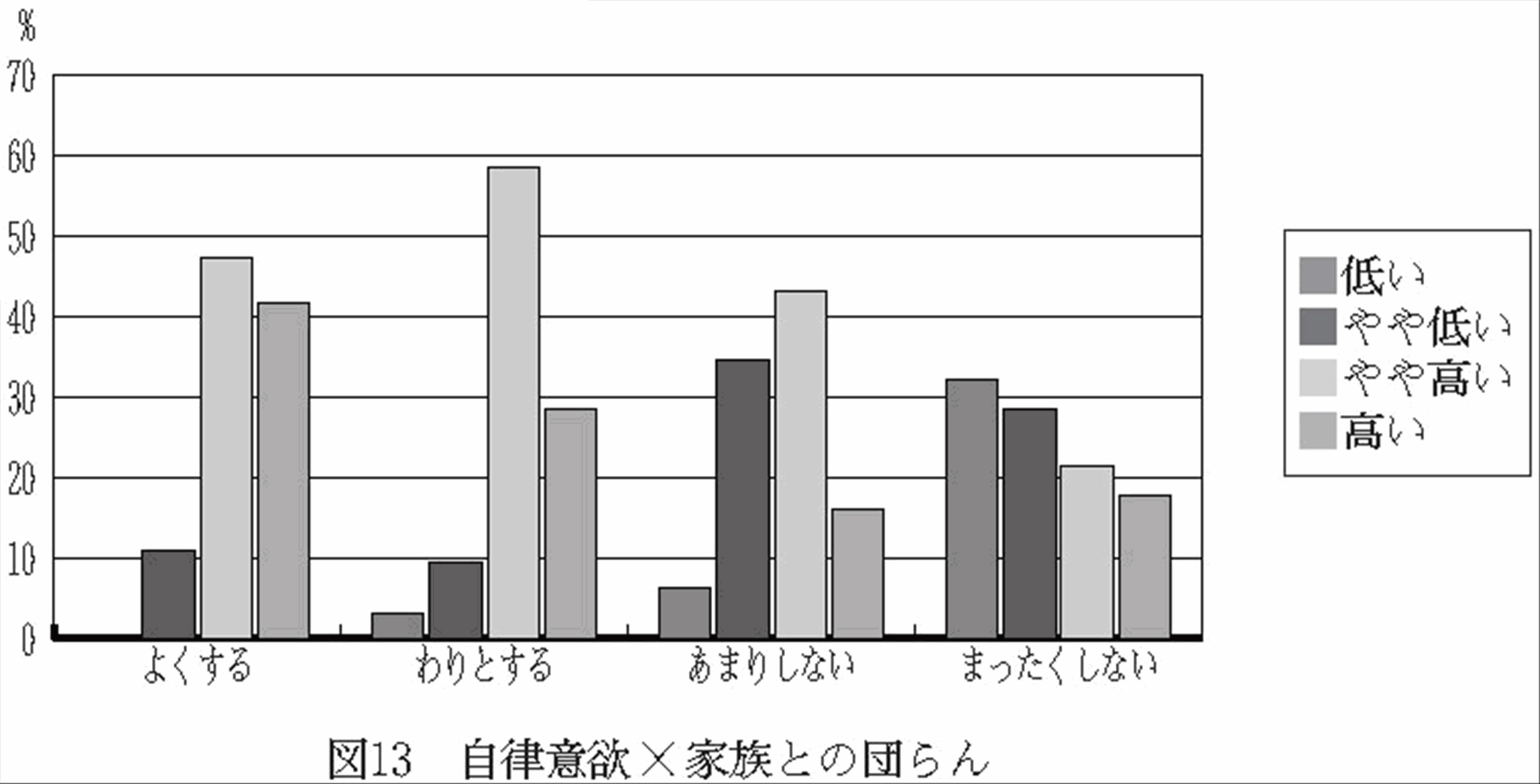
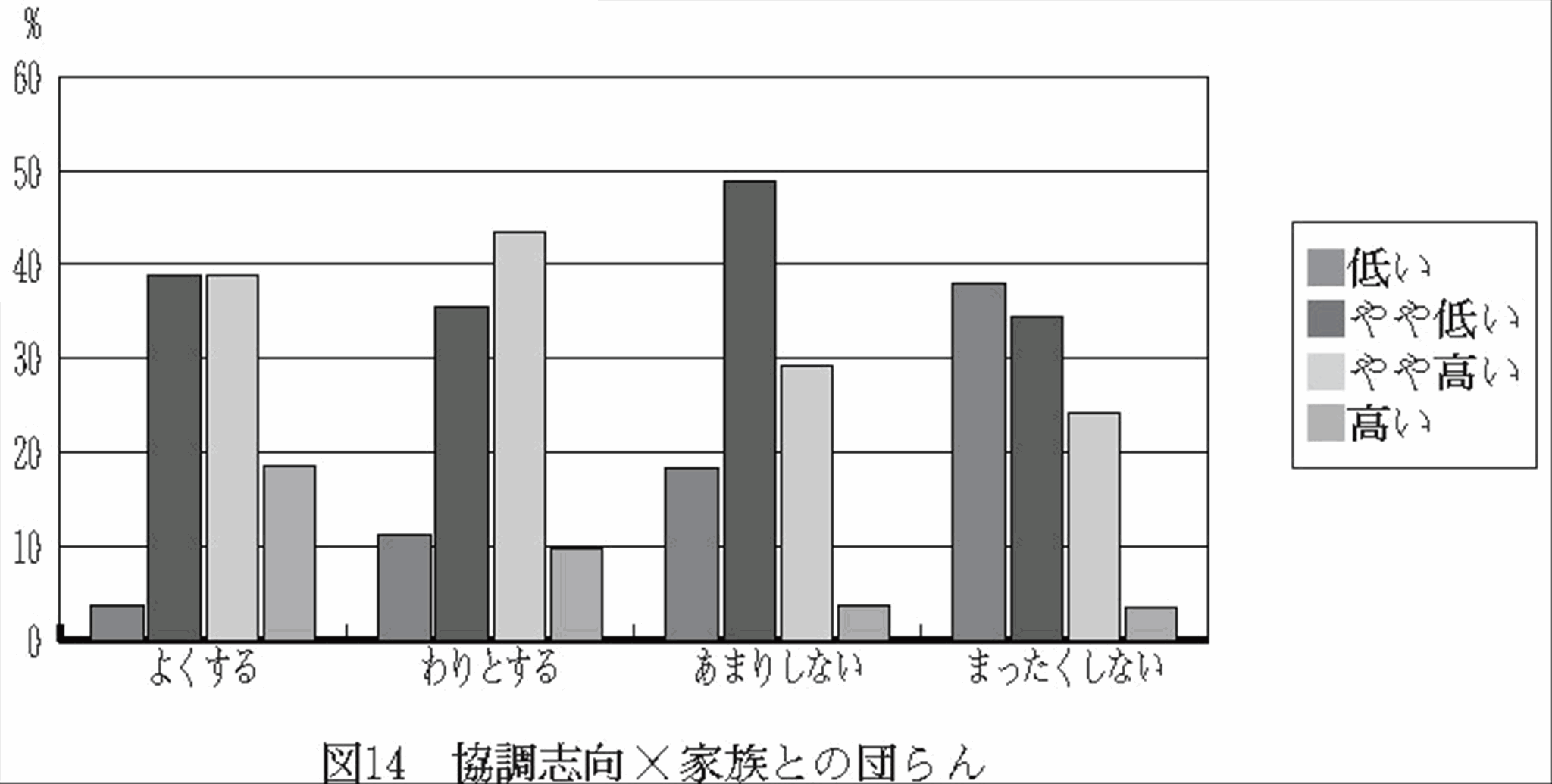
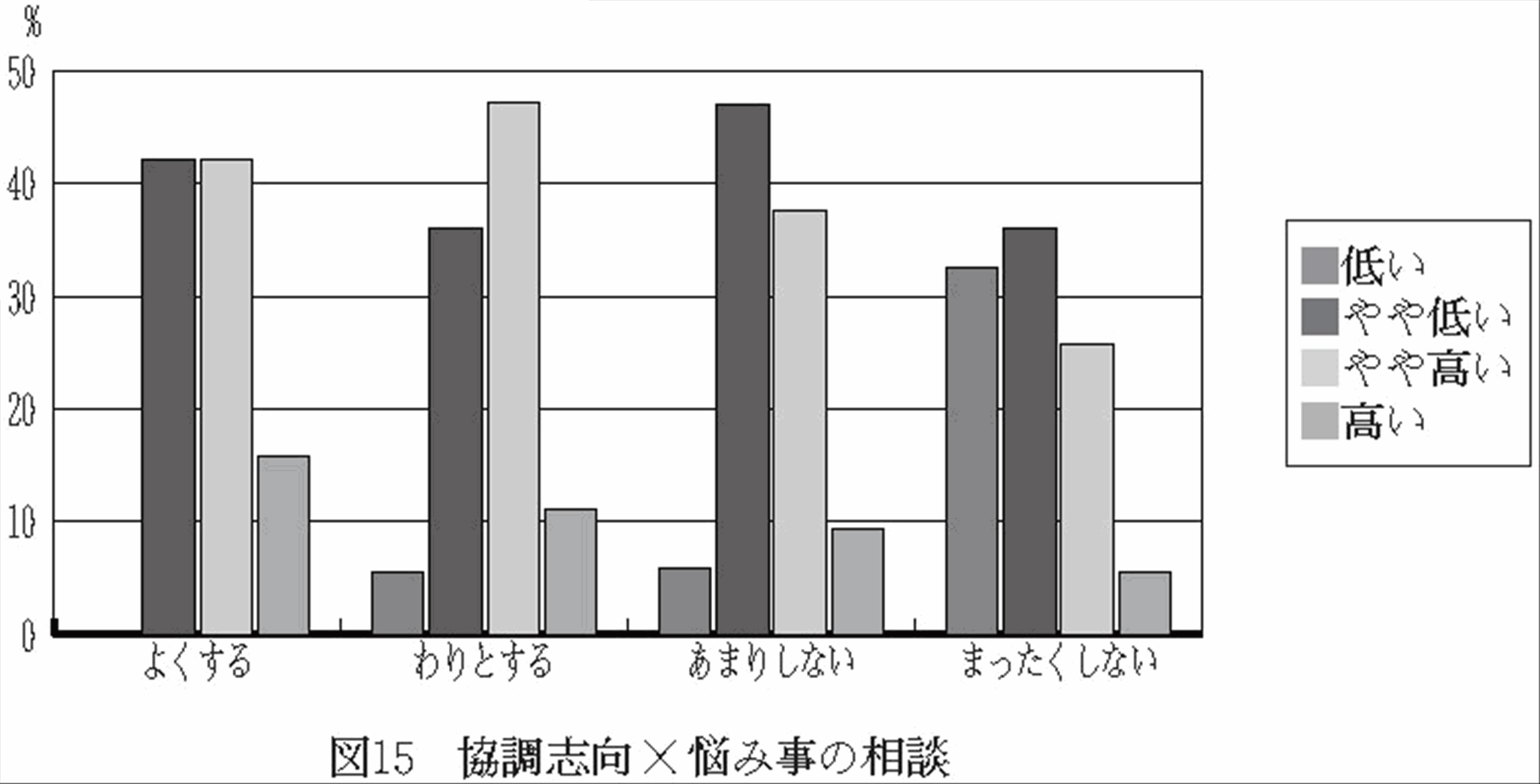
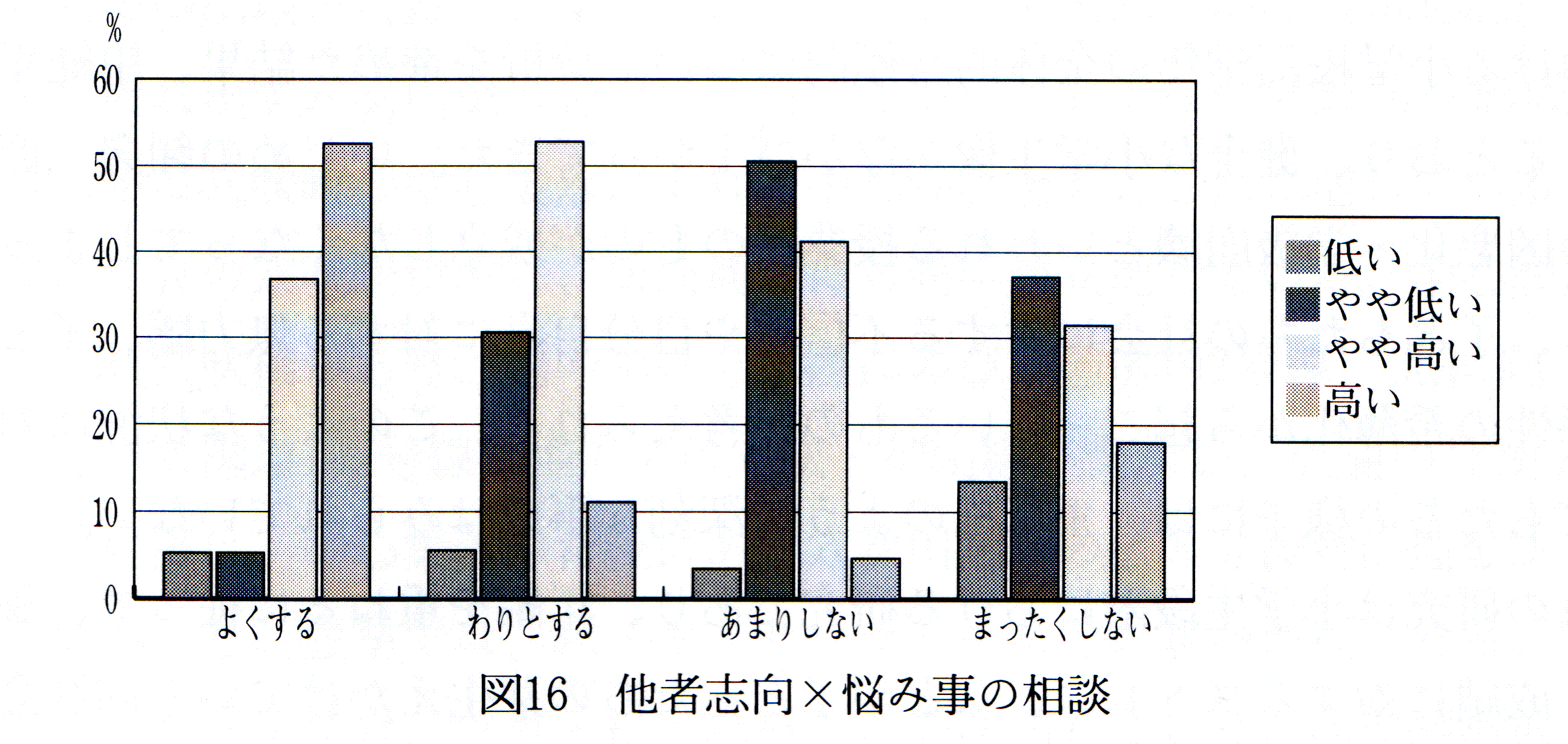
4.課題と今後の展望
本研究では、われわれが当初解明したいと意図して設定した、向社会的行動に関する質問項目の分析が不十分であったことが今後の克服すべき課題として残されている。しかし、穴吹町における小学校高学年の全体的な傾向について分析を進めた結果、単純集計の考察から見られるとおり、健全な小学生像が浮かび上がってきた。いじめの頻発・低年齢層の非行事件の凶悪化・学級崩壊といわれる授業そのものが成立しなくなってしまっている深刻な事態は、子どもたちの社会に対する不信感や自分自身に対する無力感、子どもたちどうしの関係性の希薄化から起こっているものと考えられる。このような状況に対して、穴吹町の子どもたちの様子には、まだそのような深刻な事態はみられていない。
われわれの研究は小学生段階における研究であり、年齢を重ねるに従って、価値観の変容、学習・成績に対するストレス、などが子どもたちの芽生えかけている向社会性を抑圧していく可能性は十分考えられる。したがって、子どもたちの年齢的変化に対する研究、あるいは大阪などの都会での現象がどのように穴吹町に波及してくるか、などの時間軸を考慮に入れた調査研究が一層必要になってくると思われる。 (文責 清水)
参考文献
(1)P.マッセン,N.アイゼンバーグ(菊池章夫、二宮克美訳)「思いやり行動の発達心理」 金子書房.1980
(2)深谷昌志「モノグラフ小学生ナウ」Vol.14.1994〜1995
1)鳴門教育大学