考古班(徳島考古学研究グループ)
岡山真知子1)・大塚一志2)・ 中川尚3)・
三宅良明4)・福原智子5)
1.はじめに
考古班は、「穴吹町における後期古墳の研究」をテーマにして、三島古墳群の調査を実施した。三島古墳群は、穴吹町三谷に所在する横穴式石室を主体部とする後期古墳3基(1号墳〜3号墳)からなる古墳群で、狭い範囲に近接して築造されているのが特徴である。また、1号墳は同一墳丘内に2基の横穴式石室を構築し、1号石室は埋没したままの状態である。そこで、考古班は1号墳の墳形確認のための発掘調査と1号墳・2号墳の石室の実測調査を行った。調査にあたって、穴吹町教育委員会・穴吹町文化財保護委員会・三島中学校の多大な協力を得た。記して感謝したい。なお、執筆分担は章末に明記した。
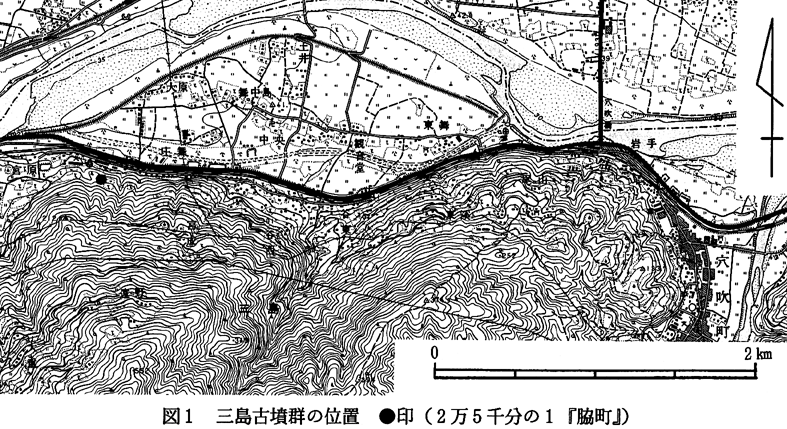
2.調査結果
1)調査の経過
期日 1998年7月31日(金)〜8月11日(火)
所在地 美馬郡穴吹町三谷365番地 後藤甚助氏所有地(穴吹町指定文化財)
調査員 小林勝美、三宅良明、中川 尚、大塚一志、岡山真知子、柏野寿一、
北條芳隆、下田順一、市川欣也、笠井信也、三木寿美子、福原智子、
四宮貴美子、関屋良平、谷川真基
調査協力 穴吹町教育委員会、穴吹町文化財保護審議会、三島中学校、野々村拓也
内容 三島1号墳墳丘裾(すそ)部の発掘調査と三島1・2号墳横穴式石室の実測調査
2)三島古墳群の立地
三島中学校の裏山に位置する古墳群で、かつて笠井新也が三谷学校上東古墳・中古墳・西古墳と呼んでいた古墳である(笠井、1957)。これを西から1号墳・2号墳とする。また、谷一つ隔てて東には3号墳が位置する。これを総称して三島古墳群と呼ぶ。現存しないが、谷一つ西には遊佐古墳が立地していた(笠井、1957)。このように非常に狭い地域に5基もの古墳が立地するのが、この古墳群の特徴である。
3)三島1号墳外部構造
三島1号墳は、かつて岡山真知子が前方後円墳と報告した(岡山、1983)が、今回の発掘調査・墳丘測量調査結果から全長15m・高さ3m
の不定形墳と考えられる(図3)。以下、発掘調査結果から、詳細に外部構造について述べてみる。
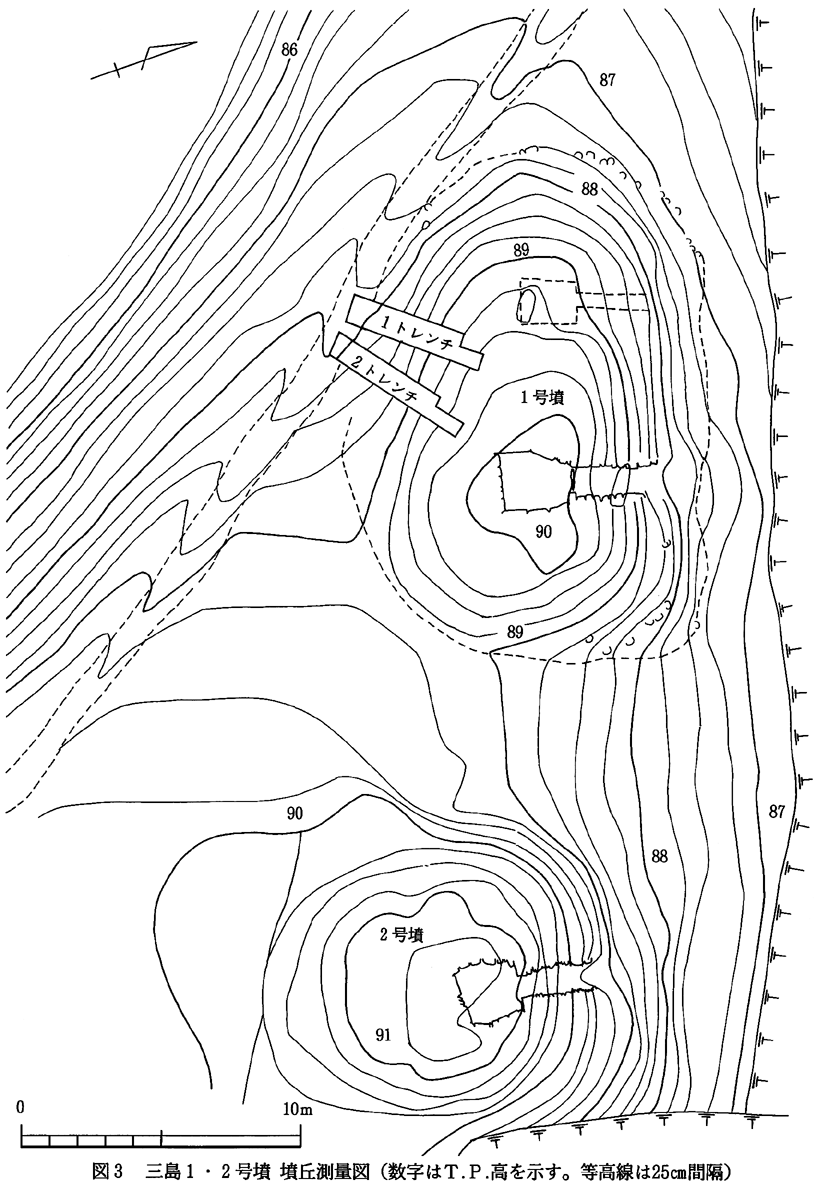
発掘調査は、前方後円墳かどうかの確認をするのを主目的とした墳形の確認に重点をおいて実施した。そのために、くびれ部の想定できる地点にトレンチ(1トレンチ・2トレンチ)を入れた。その結果、図2のように
T.P.88m
前後で葺(ふき)石が巡り、その地点で盛土が急に薄くなることから、裾と考えられる結果が得られた。また、この裾部ではくびれを形成しないとの結果も得られた。また、88.5m・89m
でも葺石が巡らされていることも判明した。また、土層は4層からなる。1層は表土(腐食土層)、2層は褐色(10YR4/6)土、3層は黄褐色(10YR5/6)土、4層は明褐色(10YR6/6)土でべース(地山)である。したがって、盛土は、2・3層だけで最大20cm
程度の厚さしかなく、石室を覆う程度でしかなかったことがわかる。墳裾から須恵器高坏(すえきたかつき)片が1点出土し、その周辺は焼土や焼石・炭化物が検出されており、祭祀(さいし)が行われた可能性がある。本来は、1・2号石室の中間にトレンチを入れたかったが、石室の崩れが心配されたので実施しなかった。そのため、外部構造の把握としてはやや物足りない調査となってしまった。
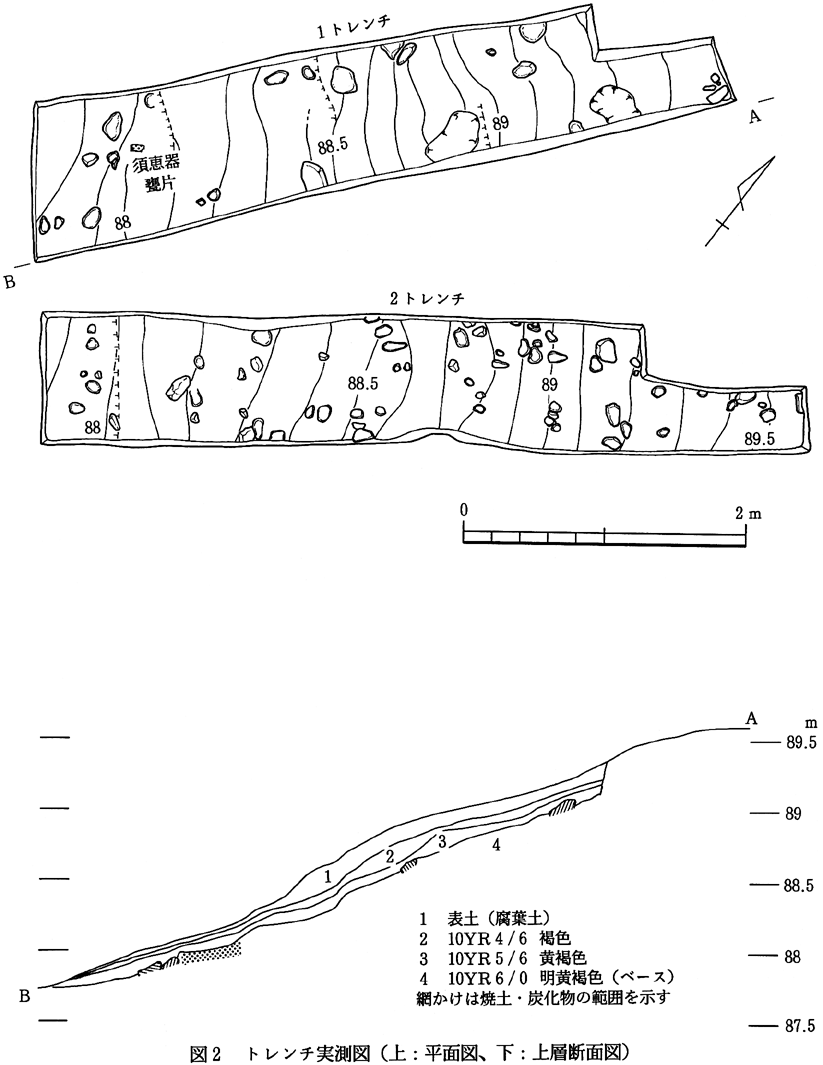
今回、併せて、水準測量を行った。墳頂は標高91.5m
で、石室の床面が88.2m
である。さらに、墳裾にかなりの大形石材を据えているのが検出された。また、葺石が1号墳全体に回っていたと考えられる。なお、詳細には精密な発掘調査が待たれる。 (三宅 良明)
4)三島1号墳内部構造(2号石室)
(1)はじめに
三島1号墳は、主軸に直交して築かれた2基の横穴式石室を内部主体とする。西から1号石室・2号石室と呼ぶが、1号石室は埋没したままの状況である。今回は、すでに開口している2号石室の実測調査を実施した。以下、2号石室について述べる。
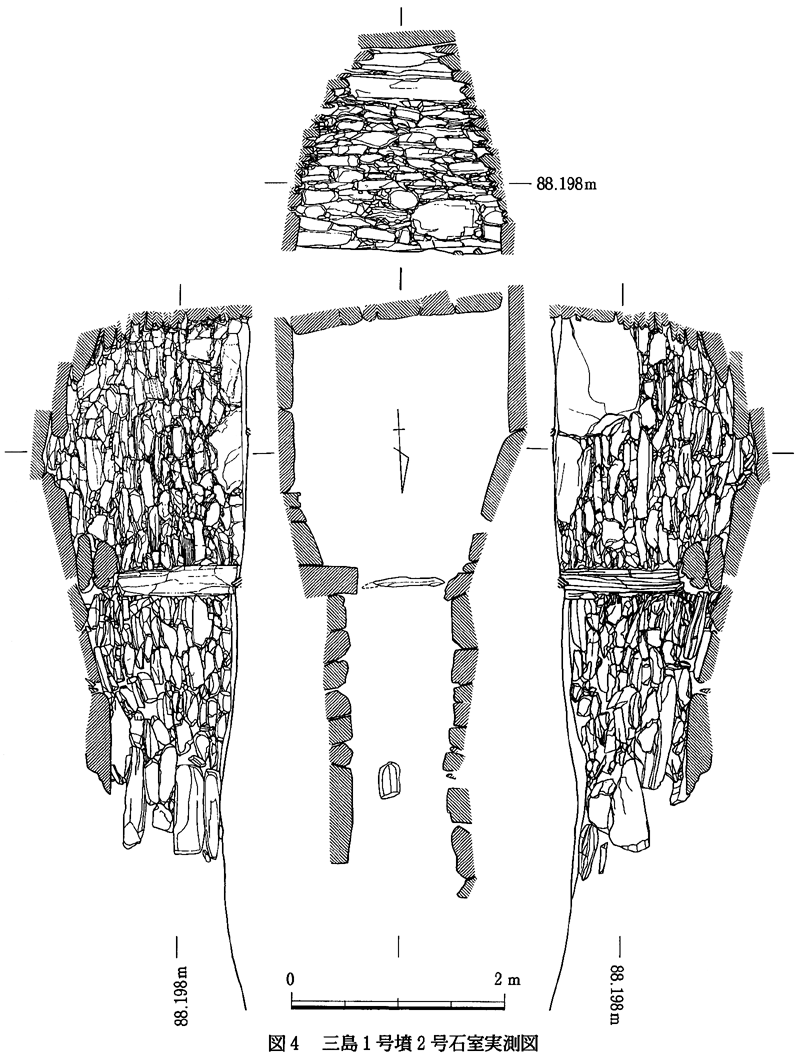
2号石室は、N1°Wに開口する横穴式石室である。胴張りの平面形に持ち送りの天井構造をもち、段ノ塚穴型石室に属すると考えられる。石室規模は全長547cm、玄室長235cm・最大幅204cm・奥壁幅204cm・最大高194cm、玄門長25cm・幅82cm・高113cm、羨道(せんどう)長287cm・幅100cm・最大高140cm
である。全体的に見て、他の段ノ塚穴型石室に比べて小規模な石室であると言える。以下、石室の様相を平面形、立面、天井構造、玄門構造に分けて述べる。なお、本石室の調査は石室内部の発掘調査を実施していないので、ここで述べる数値は現状での計測値である。
(2)平面形
平面形について玄室と羨道に分けて述べる。まず、玄室平面形は、長幅比(玄室最大幅/玄室長)0.86である。2号墳ほどではないが、やや正方形に近い。ただ、奥壁が石室主軸に直交せず約6°右側にせり出しているため、少しいびつな形となっている。
奥壁と側壁が交わる隅部では、奥壁に近い側壁の石材を石室主軸に対して平行に置き、その中に奥壁の石材をはめ込んでいる。東側壁では奥壁から115cm、西側壁では155cm
で最大幅となる。逆に入り口に対して幅が狭められ、玄室前壁幅が最小となるようゆるやかな弧状を描いて石材が配列されている。袖(そで)と側壁が交わる隅部の平面形は隅丸ではなく角状となっている。袖の幅は左袖32cm、右袖20cm
で袖幅率(袖幅/玄室前面幅×100)は38.5となり、段ノ塚穴型石室の中では一般的な袖幅率である。
羨道の平面形はハの字には開かず、幅約95cm
でほぼ両壁平行のまま外へ延びていく形であるが、入り口付近で若干開き、幅100cm
となっている。
(3)立面
玄室壁面は結晶片岩の割石積みで構築されている。石材の大きさをみると、奥壁ではいわゆる鏡石にあたるような大形の石材は見られないが、67cm×38cm
という大きな石材と長さ30〜40cm、幅10〜15cm
の石材を小口に積み、隙間を小礫(れき)で埋めている。側壁においては、側壁下半に東壁は長さ70cm 前後の大形石材、西壁は一番奥に長さ110cm
以上(奥壁に入り込んでいる)・高さ80cm 以上(埋まっている)、2個目に長さ80cm・高さ25cm
の石材を基盤に据えている。それ以外は、奥壁と同様、30〜40cm
前後のほぼ似通った大きさの石材で構築されている。1号墳の場合は、東壁奥の大形石材とほぼ同じ高さまではまっすぐに積み上げ、ここから上は持ち送っている。続いて、積み方の特徴をみてみる。奥壁隅部では奥壁側の西壁の大形石材から上は持ち送りとなると同時に隅丸となっている。玄室側壁の持ち送りは顕著で、断面図を作成した部分での床面幅194cm
に対し、天井幅90cm まで狭められている。床面から110cm
の高さから持ち送りが始まるが、全体として持ち送りは緩やかである。
羨道壁面も玄室と同様、結晶片岩割石の小口積みとなっている。入り口付近では長さ80〜90cm
の大形石材が使用されている。西壁は崩れが大きいが、東壁と同様である。積み方も、玄室と異なり、持ち送りがほとんどみられず、ほぼ垂直に積まれている。
(4)天井構造
玄室の天井は、奥壁側から玄室中央に向かって2枚の天井石が、玄門側から玄室中央に向かって1枚の天井石が、それぞれ階段状に斜めに架けられ、中央部の水平に架けられた1枚の天井石が最高となるようにつくられている。この結果、側壁の持ち送りとあいまって、天井全体がドームのような形状を呈する。玄門部では、立石の玄室側が天井石の後肩に接するように架けられている。さらに、その上にもう1枚の天井石を架け、ここを起点に玄室部、羨道部の天井石が架けられていく。羨道は現状では3枚の天井石が架けられており、玄室のような階段状ではなく、外に向かって下がり気味に架けられている。
(5)玄門構造
玄門は太い柱状袖石一石で構成し、東壁が幅25cm・高さ115cm
以上、西壁が幅20cm・高さ110cm
以上を測る。また、この玄門部床面中央部に長さ80cm・幅9cm・高さ7cmの敷石がおかれている。前述もしたが、立石に接して天井石が2枚架けられ、さらにその上に玄室・羨道の天井石が架けられている。これは、天羽利夫分類の第3類型(天羽、1977)にあたる。 (岡山真知子)
5)三島2号墳内部構造
(1)はじめに
三島2号墳は、1号墳の東に隣接する円墳で、墳頂間にして19.5m
の距離しかない。
2号墳の主体部はN14°30′Wに開口する横穴式石室である。1号墳同様、胴張りの平面形に持ち送りの天井構造をもち、段ノ塚穴型石室に属すると考えられる。石室規模は全長473cm、玄室長205cm・最大幅212cm・奥壁幅187cm・最大高197cm、羨道長196cm・幅90cm・最大高118cm
である。全体的に見て、他の段ノ塚穴型石室に比べて小規模な石室であると言える。以下、石室の様相を平面形、立面、天井構造、玄門構造に分けて述べる。なお、本石室の調査は石室内部の発掘調査を実施していないので、ここで述べる数値は現状での計測値である。
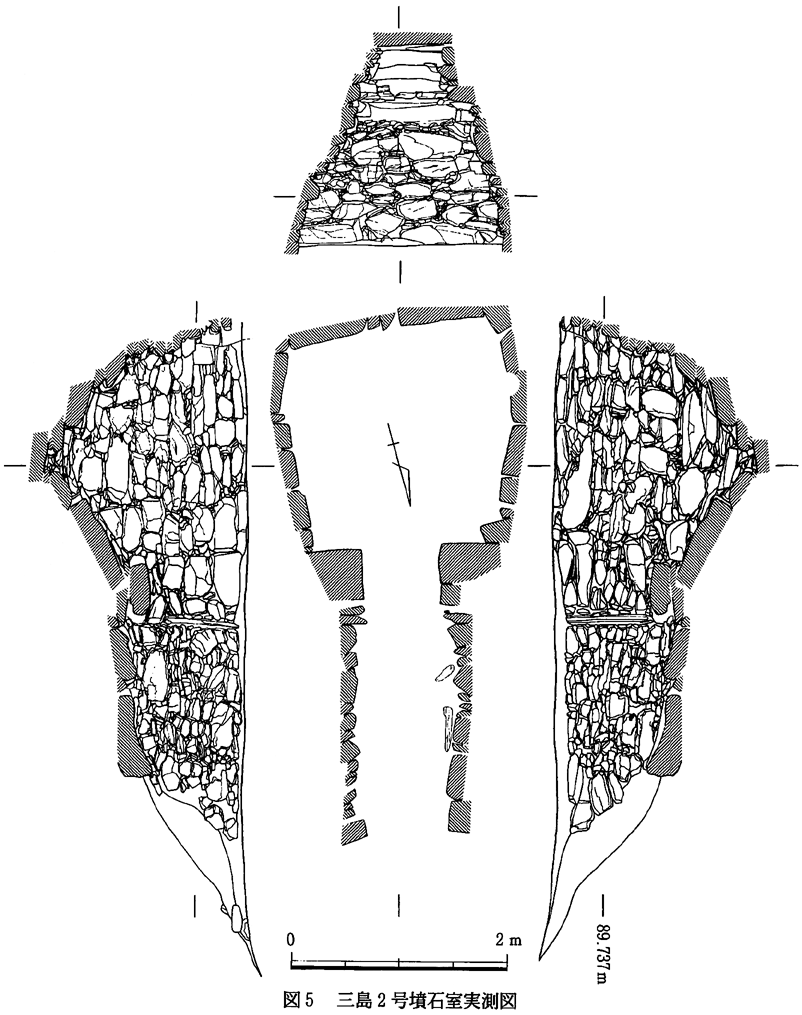
(2)平面形
平面形について玄室と羨道に分けて述べる。まず、玄室平面形は、長幅比(玄室最大幅/玄室長)0.97と正方形に近い。ただ、奥壁が石室主軸に直交せず約11°右側にせり出しているため、少しいびつな形となっている。
奥壁と側壁が交わる隅部では石材を石室主軸に対して斜めに置き、平面形が弧を描くようになる、いわゆる隅丸を志向して築造されている。特に、右側壁と交わる隅部では隅丸が顕著である。玄室側壁の平面形では胴張りがみられる。奥壁から玄門に向かって85cm
の部分が最大幅となり、玄室前壁幅が最小となるようゆるやかな弧状を描いて石材が配列されている。袖と側壁が交わる隅部の平面形は隅丸ではなく角状となっている。袖の幅は左袖43cm、右袖42cm
で袖幅率(袖幅/玄室前面幅×100)は53となり、段ノ塚穴型石室の中でも玄室幅に対する袖幅率の高い石室の一つであるといえる。玄門は内側に突出する形となっている。
羨道の平面形はハの字には開かず、幅約90cm
でほぼ両壁平行のまま外へ延びていく形である。
(3)立面
玄室壁面は結晶片岩の割石積みで構築されている。石材の大きさをみると、奥壁ではいわゆる鏡石にあたるような大形の石材は見られず、ほぼ似通った大きさの石材で構築されている。側壁においても、1号墳の側壁下半にみられるような大形の石材は用いられず、奥壁と同様、ほぼ似通った大きさの石材で構築されている。ただし、奥壁側天井石の下端とまぐさ石の下端を結ぶ線上に一本目地が通るが、この目地より上には70cm×20cm
程度の比較的大きな石材が使用されており、ここから持ち送りが急となっている。続いて、積み方の特徴をみてみる。奥壁隅部では平面形で述べたように、すでに床面から隅丸が指向されているが、2段目以上は石材が奥壁と側壁の両方にわたるように積まれており、完全に隅丸となっている。一方、玄室前方の袖部では、床面では前述したように袖が形成されているが、壁面が上にいくにしたがって袖部が狭められ、まぐさ石の直下では袖はなくなり、玄室壁面と玄門壁面が一体となっている。
玄室側壁の持ち送りは顕著で、断面図を作成した部分での床面幅190cm
に対し、天井幅57cm
まで狭められている。なお、本石室の持ち送りは直線的ではなく、何カ所かでの持ち送りの角度の屈曲がみられる。
羨道壁面も玄室と同様結晶片岩の割石の小口積みとなっているが、石材の大きさは玄室に比べて小形のものが多い。また、積み方でも、玄室と異なり、持ち送りがほとんどみられず、ほぼ垂直に積まれている。
(4)天井構造
玄室の天井は、奥壁側から玄室中央に向かって3枚の天井石が、玄門側から玄室中央に向かって2枚の天井石がそれぞれ階段状に斜めに架けられ、中央の水平に架けられた1枚の天井石が最高となるようにつくられている。この結果、側壁の持ち送りとあいまって天井全体がドームのような形状を呈する。羨道は現状では2枚の天井石が架けられており、玄室のような階段状ではなく、若干外に向かって下がり気味に架けられている。
(5)玄門構造
玄門部は幅約70cm、玄門長71cm
で、構造は羨道側に天井までとどく厚さ10cm
ほどの板石状の立石が立ち、立石から玄室までの側壁が若干はりだす形となっている。これは、天羽利夫分類の第2類型(天羽、1977)にあたる。玄門の側壁や立石はほぼ垂直に積まれている。天井には玄室、羨道の天井よりも一段低く天井石が架けられ、いわゆるまぐさ石のようになっている。 (中川 尚)
6)三島1・2号墳横穴式石室の特徴
まず、1号墳と2号墳の前後関係であるが、2号墳の玄門部が天羽分類の第2類型にあたることや、天井の持ち送りが急であること、平面形が正方形に近いことなど、段ノ塚穴型石室の中でも比較的古い要素をもっているのに対し、1号墳は玄門部を太い柱状袖石一石で構成する天羽分類の第3類型に属し、天井の持ち送りが緩やかである点など比較的新しい要素がみられる。よって、2号墳→1号墳という順で構築されたと考えられる。
続いて、1号墳と2号墳とを比較した際の異なる要素、共通する要素を検討してみる。まず、異なる要素では、前述した玄門構造、天井の持ち送りのほか、平面形でみてみると、2号墳がゆるやかな弧を描くような胴張りであるのに対し、1号墳では玄室中央あたりから直線状に玄門に向かって玄室幅が狭まっている点である。また、玄室側壁の持ち送りに関しても、1号墳では大きな持ち送りの角度に変化がみられないのに対し、2号墳では前述したように持ち送り角度の変化が数カ所で見られる点があげられる。これらの差異は両石室の時期差に起因するものと考えられる。
一方、共通する要素をみてみると、奥壁が主軸に対して直交せず、斜めに交わるようにつくられ、奥壁の主軸に対する傾きもほぼ一致する点があげられる。これは、両石室に共通するテリトリーの存在が想定できる。さらに、奥壁から玄門外側までの長さがほぼ一致する点、現床面での比較ではあるが、玄室高もほぼ一致する点もあげられる。
段ノ塚穴型石室では時期が新しくなるに従って長胴化していく特徴があるが、この三島古墳群においては古い段階に属する2号墳と新しい段階の1号墳の玄室長や玄室高がほぼ一致する。このことは、石室構築に対してなんらかの規制が働いていた結果とも考えられる。 (中川 尚)
3.考察
1)三島古墳群の立地
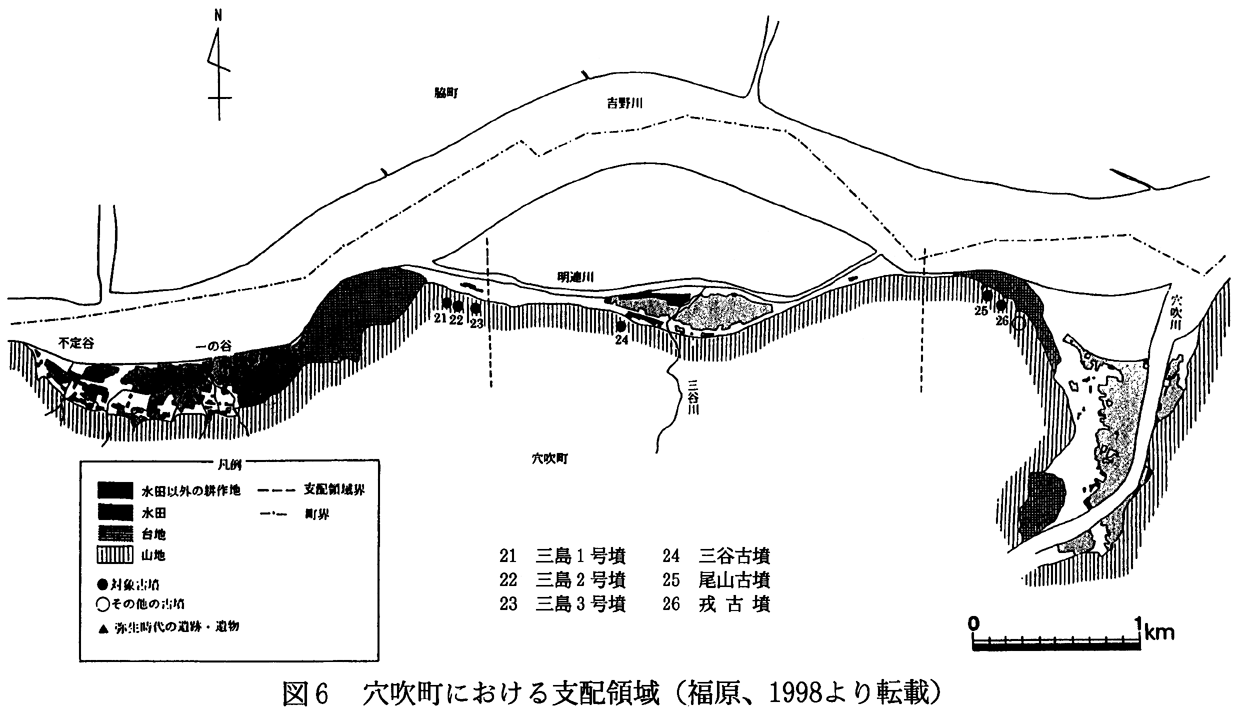
三島古墳群は、徳島県を西から東に流れる吉野川中流域の南岸、現在の美馬郡穴吹町三谷に所在する。三島中学校の東の裏山の山腹に、西から1号墳(図6-21)、2号墳(図6-22)、小さな谷を隔てて3号墳(図6-23)の3基が近接して分布している。いずれも横穴式石室を有する後期古墳であり、美馬町の段ノ塚穴に代表される「段ノ塚穴型石室」を採用している。
段ノ塚穴型石室構造を有する古墳は、美馬郡と阿波郡阿波町の西端に分布する(1)(図7)。この地域には、中央に吉野川が東西に流れている。吉野川北岸は、吉野川の支流によって形成された扇状地・河岸段丘が大規模かつ顕著にみられる地域であり、氾濫原(はんらんげん)には吉野川の流路変遷の足跡も残っている。これに対して、吉野川南岸は、吉野川に山が迫っており、平野部を形成する所は非常に少ない。穴吹町もその例外ではなく、吉野川と穴吹川によって形成された一部の河岸段丘と氾濫原を除けば、山地が川に突き出す地形を呈している。そのためか、古墳すべてがその山腹部に立地している。
穴吹町には、「段ノ塚穴型石室」を有する古墳が全部で6基確認されている。三島古墳群のすぐ東には三谷川に近接して三谷古墳(図6-24)が、穴吹川左岸の穴吹橋の裏山に尾山古墳(図6-25)・戎古墳(図6-26)の2基が立地している。三島古墳群が同じ「段ノ塚穴型石室」を有する脇町の国中古墳と、尾山古墳・戎古墳が脇町の拝原古墳群とちょうど対峙(たいじ)する位置にあることに注目しておきたい(図7参照)。三島古墳群西の遊佐台地には遊佐古墳の存在が確認されている(笠井、1957)が、消失してしまっている。また、同台地から弥生時代・古墳時代の遺物が発見されている(野々村、1987)ことから、この地域にも古墳時代以前に人々が生活を営んでいたことがうかがえる。
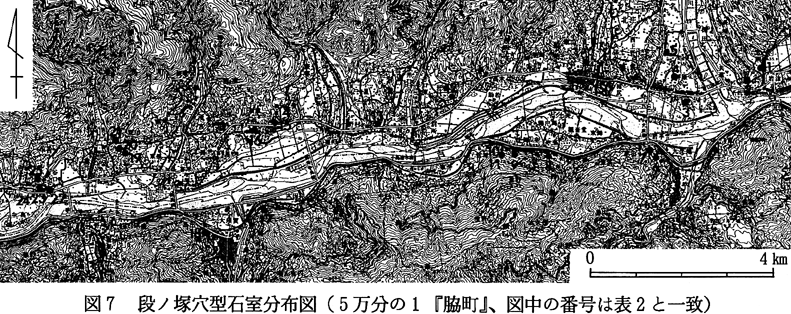
古墳の立地が前述のように3地点に分かれていることから、穴吹町には三つの首長集団による支配領域を推定できる。三島古墳群以西から貞光町の町界との範囲を支配する三島古墳群、三谷川の灌漑(かんがい)範囲を支配する三谷古墳、穴吹川の灌漑範囲を支配していた尾山・戎古墳である(図6)。この区分ごとに支配領域面積を比較すると、三島古墳群の支配領域が最大となる。古墳時代の首長の支配力が領域面積に反映すると考えるなら、穴吹町において三島古墳群が最大の支配力をもち得たと考え得る。 (福原 智子)
註1) 昨年度の阿波学会の調査により、井川町須賀古墳も「段ノ塚穴型石室」であった可能性が高い(「井川町における考古学的研究」『阿波学会紀要第44号』1998年)が、明確でないので今回は省略した。
2)三島古墳群の研究―横穴式石室の特色―
三島古墳群の研究は、笠井新也(1922)により石室構造の特異性が紹介され、その後、天羽利夫(1977・1978・1983)や岡山真知子(1975・1983)によって「忌部山(いんべやま)型石室」と「段ノ塚穴型石室」の研究において、三島古墳群の位置づけが試みられた。この研究では、天井構造からみて、三島1号墳は忌部山型石室に近く、三島2号墳は段ノ塚穴型石室に近いことが裏付けられた。また、平面プランの胴張り度からは、三島2号墳が三島1号墳よりも玄室中央で外側に張り出すことから、平面プランでは2号墳の方が段ノ塚穴型石室に近いことが報告されている。この結果、三島古墳群は「忌部山型石室」と「段ノ塚穴型石室」の折衷様式であり、徳島県内の後期古墳の性格を考えていく上で重要な鍵を握っている古墳群だと位置づけている。
こうした研究の成果をふまえて今回、三島古墳群の調査を実施し、1号墳の墳丘形態と1・2号墳の石室構造がより明らかになった。そこで、これらの調査結果を基に徳島県内の後期古墳における三島古墳群の位置づけを試みてみたい。なお、「忌部山型石室」と「段ノ塚穴型石室」を有する古墳の多くが発掘調査が実施されておらず、石室構造からの検討となることを断っておく。
三島古墳群は、西から1号墳・2号墳と並び、谷を隔てて東に3号墳が位置する。1号墳は2基の石室を有している。現在、西の1号石室は埋没しており詳細は不明であるが、徳島県内の後期古墳の中で三島古墳群のように隣接して築かれている例は少ない。こうした意味からもこの古墳群の中で石室構造の変遷を明らかにする意義は大きい。
発掘調査が行われた徳島県内の群集墳の調査報告では、忌部山型石室の特徴を有する横穴式石室の変遷過程が指摘されている(藤川ほか、1994)。平面プランに着目すると、玄
室中央部がやや膨らみ、奥壁部の隅を丸く積む平面形態から、玄室中央部がやや膨らみ長方形に近い平面形態へと変遷していることが指摘されている。つまり、だんだんと細長く膨らみの少ない平面形態に変化しているのである。このことから三島古墳群の変遷を以下の表などを基に考察していきたい。
まず、長幅比の大きい順に並べると、3号墳→2号墳→1号墳2号石室の順になる。次に、長高比の大きい順に並べると、同様に3号墳→2号墳→1号墳2号石室の順になる。前述もした仮定にたつと、3号墳→2号墳→1号墳2号石室の順に構築されたと考えられる。
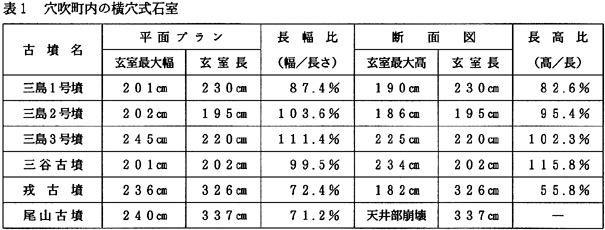
三島古墳群は段ノ塚穴型石室の中では、高所に立地する。3号墳が標高150m、1・2号墳が標高90m
前後に位置する。段ノ塚穴型石室の中で、高所に立地する古墳を挙げると、大国魂古墳の標高約100m
である。これに対して、忌部山型石室では、忌部山古墳群や鳶ケ巣(とびがす)古墳群Aが標高250m
という高所に立地するなど対照的である。忌部山型石室を有する古墳が分布する板野・阿波・麻植郡と、段ノ塚穴型石室を有する古墳が分布する美馬・三好郡とでは吉野川流域の地形の違いはあるものの、三島古墳群は高所に築かれた後期古墳であると言える。両者とも高所に位置する古墳ほど平面プランの長幅比が大きいという傾向が認められる。
以上の特徴から、三島古墳群は、徳島県内では後期古墳出現の比較的早い時期に3号墳が築造され、その後、2号墳、1号墳の順に築かれた可能性が高い。次に、三島古墳群の石室構造は基本的には段ノ塚穴型石室の規制を受けているが、1号墳・2号墳の石室の天井構造から忌部山型石室の持ち送り度の小さい丸みのある構造との類似性も指摘できる。
ところで、段ノ塚穴型石室を平面プランの長幅比に着目して類別すると、大きく四つにグループ化できる(表2)。このグループ化において、三島古墳群は、3号墳と2号墳がA類に、1号墳2号石室がB類に属する。A類は、初現的様相を示す石室構造である。表2からもわかるように、三島3号墳は大国魂古墳と、三島2号墳は三谷・平野古墳と、三島1号墳2号石室は西山古墳と平面プランが類似した様相を示している。同時に、高所に立地する例が多いのも特徴である。また、戎古墳も長高比が55.8%と小さく、忌部山型石室の長高比とよく似た数値であり、玄室平面両隅に丸みが認められる。
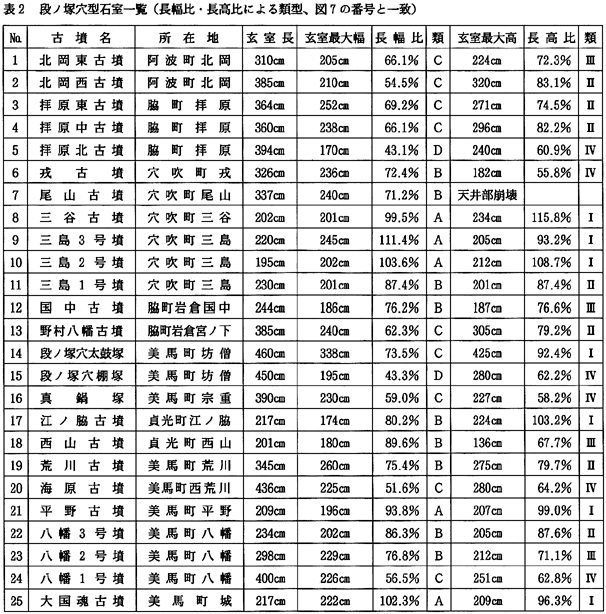
以上からも、穴吹町の後期古墳は、段ノ塚穴型石室の構築方法を基調としながらも、忌部山型石室の構築方法の影響も受けていると言える。
さらに、今回、試案として、段ノ塚穴型石室の長幅比と長高比を算出し、それらを組み合わせて総合類型を試みてみた(表3、図8)。今後、さらに詳細な分析によって、三島古墳群の位置づけをしていきたい。
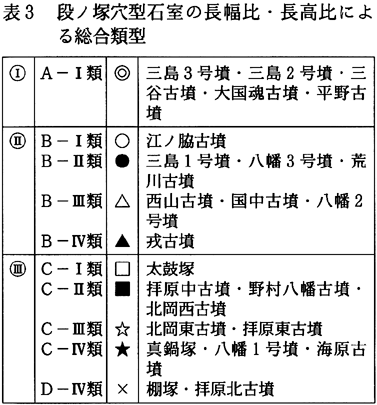
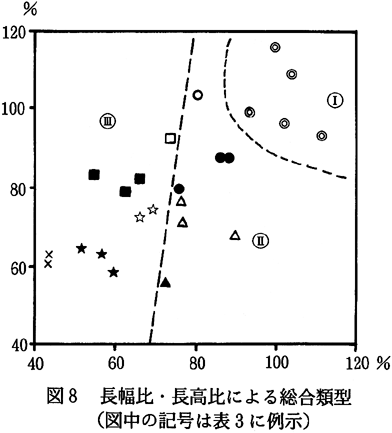
以上のことから、三島古墳群は、段ノ塚穴型石室の範疇(ちゅう)に属する後期古墳群で、比較的早い時期に築かれた古墳群であると言えよう。平面プランから類別したA類の段ノ塚穴型石室では、発掘調査が行われた古墳はない。前述したように、三島古墳群は段ノ塚穴型石室の初現的様相を示す群集墳であることから、発掘調査による詳細な調査が待たれる。 (大塚 一志)
3)出土遺物
今回の発掘調査で出土したのは、三島1号墳墳丘から出土した須恵器片2点である。また、三島1号墳の出土品としては、穴吹町誌ほかに野々村拓也が報告した須恵器がある(野々村、1985・1987)。これらを基にして三島古墳群の築造年代を考察したい。
野々村(1985)によると、三島1号墳からの出土品は、昭和59年(1984)5月24日に腐葉土を採取していた三島中学校生徒が発見した須恵器である。内容は、ほぼ完形の■(はそう)1点・坏(つき)片6点・甕片11点である。特に、■は年代決定において重要であるので紹介する。
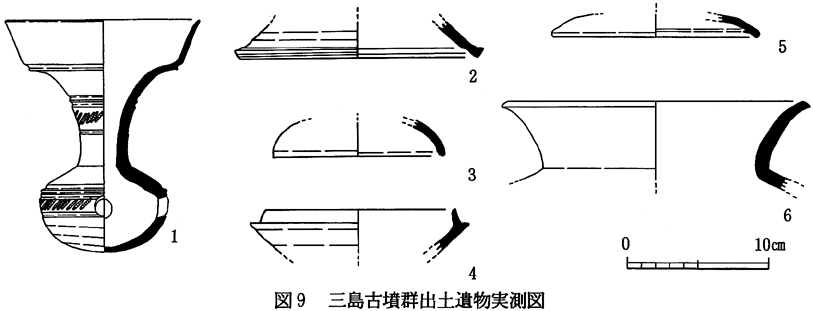
■(図9-1)は、口径13.8cm・器高16.2cm・体部最大径9.2cm・頸(けい)部径3.2cm・頸高6.7cm
を測る。口縁部を外方に開き気味に立ち上がり、端部を丸くおさめる。口縁部と頸部の境に稜(りょう)をつくり、沈線が回る。頸部は緩やかに外反し、中央に文様を巡らす。文様は、ヘラ描き沈線を2条、その下の刺突文、さらにその下にヘラ描き沈線1条で構成される。体部は肩が張り、体部中央よりやや上が最大径となる。体部中央には頸部と同様の文様帯を巡らす。径1.4cm
の円孔を有する。内外面ともヨコナデで調整されているが、体部外面下半は左回転のヘラケズリ痕跡を残す。これらの特徴から、中村編年(中村、1978)の
II-5型式6世紀後半に位置づけられる。
今回出土したのは、高坏の脚片(図9-2)で、脚端部径17.0cm
で端部を肥厚させ、凹線を1条巡らしている。黒釉(ゆう)がかけられている。これらの特徴から■と同じく、中村編年(中村、1978)II-5型式6世紀後半に位置づけられる。
これに対して、穴吹町誌編集中に三島3号墳でも玄室から須恵器が採集されている(野々村、1987)。坏片は、蓋と身の口縁部の小破片である。蓋(図9-3)は、口径12cm
で、口縁端部を丸くおさめている。身(図9-4)は口径11.6cm で、立ち上がりは1.1cm
でまっすぐに立ち上がる。受け部をもち、受け部径12.1cm
である。これらの特徴から中村編年(中村、1978)II−4型式の年代が想定できる。
次に、三島古墳群のすぐ西には、かつて遊佐古墳の存在が確認されていた(笠井、1957)が、その周辺の遊佐台地からも須恵器片が採集されている(野々村、1987)ので、紹介したい。甕(図9-6)は口径16.4cm、口縁が外反して開き、端部が若干肥厚する。内外面ともヨコナデで調整され、体部外面にカキ目を施す。6世紀後半の年代が与えられているが、若干新しくなると考えられる。坏片の中に、返りを持つ蓋(図9-5)が出土している。口径14.3cm
でかなり浅い器形と考えられ、返りの形から中村編年(中村、1978)III−3型式、飛鳥
III(西、1978)(7世紀後半3/4)が想定できる。遊佐台地に存在していた遊佐古墳が三島古墳群より若干新しいことがわかる。
以上の出土遺物の考察から、三島1号墳、3号墳とも6世紀後半の築造で、3号墳が古いと考えられる。ただし、横穴式石室は何度も追葬をするので、出土した須恵器が築造期のものとは判断できないが、出土須恵器の最も古いものでの比較の結果である。 (岡山真知子)
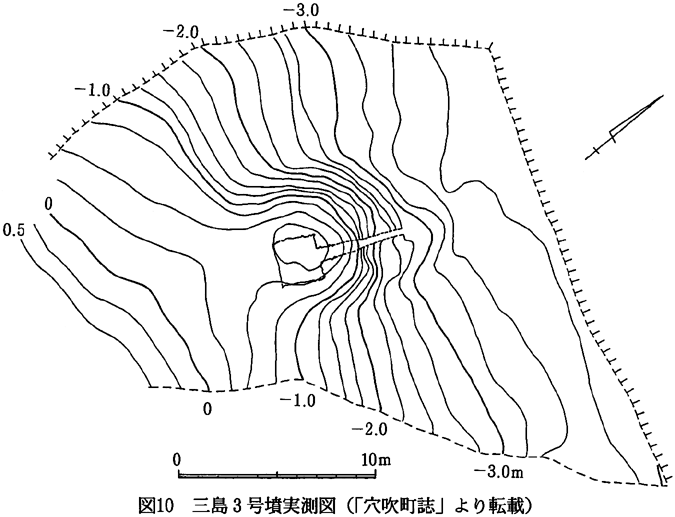
4.まとめにかえて
今回の調査に当たっては、穴吹町教育委員会をはじめ、三島中学校等地元の関係者の多大な協力を得た。特に、三島中学校の大石真裕校長先生をはじめ先生方、生徒の皆さんには暑い中大変お世話になった。三島中学校の裏山にある三島古墳群は、穴吹町指定文化財であり、徳島県の古代史を解明する貴重な資料で、皆の財産である。今回の調査中に、以前三島中学校生徒が発見した須恵器■が行方不明となっていた。今のところ、三島古墳群がいつごろ築造されたかを知る唯一の手がかりが失われたわけである。こうしたことが起きないよう、しっかりと三島古墳群を守ってほしいと願っている。
参考文献
天羽利夫(1977):徳島県下における横穴式石室の一様相―その2―.『徳島県博物館紀要』第8集.
天羽利夫(1978):阿波忌部の考古学的研究.『徳島県博物館紀要』第9集.
天羽利夫ほか(1983):忌部山古墳群.徳島県博物館.
岡山真知子(1975):段ノ塚穴型石室の研究.徳島県博物館学術奨励研究.
岡山真知子(1983):三島古墳群の研究.『徳島考古』創刊号.徳島考古学研究グループ.
岡山真知子ほか(1998):井川町における考古学的研究.『阿波学会紀要』第44号.
笠井新也(1922):阿波国美馬郡段ノ塚穴.『人類学雑誌』第37巻5号.
笠井藍水(1957):新編美馬郡郷土誌.
中村浩(1978):和泉陶邑窯出土遺物の時期編年.『陶邑
III』.大阪府文化財調査報告第30輯.大阪府教育委員会.
西弘海(1978):土器の時期区分と型式変化.『飛鳥・藤原宮発掘調査報告
II』.奈良国立文化財研究所学報第31冊.
野々村拓也(1985):三島古墳群出土の須恵器.『阿波のあゆみ』第65号.
野々村拓也(1987):原始・古代.『穴吹町誌』.
福原智子(1998):段ノ塚穴・忌部山両古墳群の支配領域.『地域研究』第14巻.鳴門教育大学地理学教室.
藤川智之・須崎一幸ほか(1994):柿谷遺跡・菖蒲谷西谷B遺跡・山田古墳群A.四国縦貫自動車道に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書.(財)徳島県埋蔵文化財センター.
1)徳島県教育委員会文化財課 2)脇町立脇町小学校 3)徳島県立富岡東高等学校 4)徳島市教育委員会社会教育課 5)鳴門教育大学学校教育学部学生