民俗班(徳島民俗学会)
青木幾男・西田素康2)
1.はじめに
「何処(いずこ)もおなじ秋の風」という言葉がある。秋の風情をたたえることばではなくて、「秋はどこまで行っても同様だ」ということらしい。改めていうまでもなく、「夏に吹く山の風」は涼しく、「冬の街を吹いてくる北風」は冷たい。当然のことを強いて思い起こすほど現代人は閑(ひま)ではない。人々は忙しいから、季節の移り変わりなどあまり考えなくなった。大人も子供も含めて、最近は「季節感が無くなった」とよくいわれる。季節感がなくても、人々にはテレビも娯楽もあり、結構生活を楽しんでいる。
それはそれでよいのだが、季節の移り変わりはさておいて、「忙しいから考えない」ということについては「これで良いのか」と考えさせられる。
2.町村立資料館の現状と問題点
最近各地の市町村に資料館がつぎつぎと設立されている。地域では急速な文化の進展のために、生活器具も、生産器械も、農具もめまぐるしいように変って行く。これから2、30年もすれば、どのように田んぼで稲を刈ってどのように脱穀したのかわからなくなるだろう。「その地方の最も大切な文化財」とは、高価な美術品や武具類ではなくて、民具ではないのか。「庶民が、どの様な道具で、どのような工夫をしたか」について、資料館の民具は、それを見る人に確実に物語ってくれる。
「民具が語る」とは、街頭で「拡声器」から声が流れるように、問わず語りに叫ぶのではない。問えば(考えれば)答えてくれる。今までの資料館を見ていると、過疎地などから先に、失われてゆく民具を後世に伝えようと、乏しい財政の中から立派な歴史民俗資料館をつくり、資料を集め、住民や外来者に来館を呼びかけている。その関係者の懸命の努力とは裏腹に、住民の足は次第に間遠になっているのが実状ではないだろうか。
このような現状に対して、最近はマスコミも含めて「地方資料館批判論」が起こりはじめている。2、3年前に、板野地方に資料館が新設されてしばらくしたころ、地方新聞の支局長が「どこも農具や生活器具ばかりを展示していて、変化がない」と論じていた。一般の人もそのように考えていると考えてよいだろう。資料館を建てた自治体は、無駄な失費をしたのであろうか。いま地域の住民に生活に自信を持たせる方法とは何であろうか。美術品を見せることや趣味、娯楽、運動、学校教育を支援することではなくて、「地域の先人たち」が、過去のきびしい生活環境にいかに対応し、どう工夫して生きてきたか、その知恵を学びとることが最も大切であると考える。
3.民具の地域差
先に述べたように、一般の人たちは、農具も生活器具もどこへ行っても同じだ、唐鍬(とうぐわ)は唐鍬、籠(かご)は籠だ、と思っている。たとえば、米、麦を精白する足踏みの「からうす」は、前方に穀物を入れる「石臼(うす)」が埋めこんであり、2〜3m離れて人が上がる「足台」がある。臼と足台の中間に「ホロロ」という石製の支点が地中に埋めこんであり、「棹(さお)」という2〜3m
の木が、ホロロの上に天秤(てんびん)状にかけられている。棹の前端、臼の上にあたる部分には、棹に直角に太さ10cm
ばかりの杵(きね)が組み込まれていて、台の上の人が片足で棹の1端を踏むと他端の杵が上り、足を離すと杵が下がるようになっている。これが一般的で、日本国中どこへ行っても同じだ、と人々は思っている。
ところが平成4年の阿波学会三好町総合学術調査に参加した時に、三好町の「からうす」が、人が台の上にいて踏むのではなくて、棹の上に上り、天井から綱をたらし、人は綱にすがって「ホロロ」の後方を前後し、杵(棹)を上下させる、というまったく他の地方では見られないものであることに気がついた。この様式の「からうす」の分布を調べてみると、池田町、三野町の山間部、香川県側では千
m
の峠を越えて仲南町、南は吉野川を越えて井川町、三加茂町、半田町、東祖谷山村に及んでいることがわかった(図1、2)。ところがこの「からうす文化圏」をよく調べてみると、幾つもの文化が重なっていることを知った。それは「借耕牛(かりこうし)」の道であり、「通婚圏」であり、「塩の道」でもあった。筆者は三好町調査報告書に、財田町から仲南町、三好町を経て、東祖谷村に至るルートを「古代の道である」と報告した。

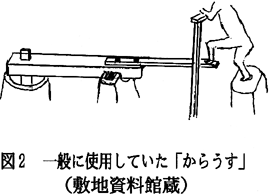
今回の調査でも、からうすについて農家を尋ね歩いたがからうすを知っている人さえなかなか見つからなかった。たまたま平成9年9月20日、萩原晴巳さん(66歳。井内西2886)にお会いできてたが、萩原さんは「急な坂道を登り降りする私たち山の人間は、からうすに乗って移動するのが楽なのですよ」と語ってくれた。実際に民具を使用した人の体験を聞けたことはとても嬉しかった。今回の調査で最も大きな収穫であったかも知れない。干mを前後する阿讃山脈や剣山系の峠道を行き来する山の人たちは、自然とそれに見合う体力を身につけていたのであろうか。
4.井川町の餅(もち)つき臼
井川町立資料館に餅つき臼がある(図3、写真1)。これが餅つき臼であると知ったのは萩原晴巳さんに会ってからであった。臼はケヤキの丸太製で、直径70cm、高さ31cm、臼面の直径55cm、臼の深さ5.5cm。これが高さ48cm
の3本脚の台の上に乗っている。胴に2個所の鉄環があり、これで自由に移動ができるようになっている。これだけなら特別に報告する程のことでもないのだが、口径が広い割に深さがきわめて浅く、口径の
1/10 しかない。普通は図4のように、口径の 1/4
前後が多いようである。この臼では、搗(つ)く時に臼の外に米がこぼれ落ちるかも知れない。他町村ではまったく見られない臼である。
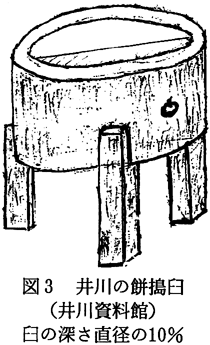

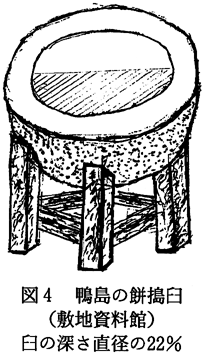
萩原晴巳さんは、餅つき臼の歴史と井川町の臼のことについて語ってくれた。「餅つき臼を特別にこしらえるようになったのはごく新しいようで、昔(明治時代)は餅も、麦、粟(あわ)の精白も、資料館にあるような立臼(たちうす)と立杵(たてぎね)(図5、写真2)で搗いていました。明治の中ごろから煙草(たばこ)栽培の景気がよくなって、正月をにぎやかに祝うようになり、年末には餅をたくさん搗くので多くの人が集まり、そのにぎやかさを自慢にする家もありました。一般的に餅を多く搗くようになって臼の底が浅くなりました。早く搗くほど餅は熱いうちに出来上がり、大量だと熱過ぎて餅が取り出せないからです。臼の底が浅いのは早搗きのためですが、それは大量の餅をいかに早く搗くかということの現れです」とのことであったが、「最近は若者も居なくなって、みな電気餅搗き機ですよ」とさびしく笑っていた。
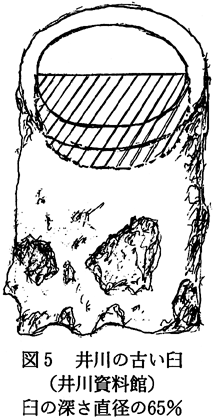

萩原晴巳さんの説明で、井川町の好景気時代の繁栄を垣間見ることができた。これを実感するために表1を掲げる。これで見ると、煙草は明治中ごろから換金作物として良いようであるが、大正から昭和、昭和も戦後までも好況期が続いていたことが分かる。その好況期は、この餅つき臼が井川町で活躍した時期でもあった。
その時代の繁栄は、現代の我々の想像を超える好況であったとの古老の声もあるが、それを証明できる記念物はあまり多くない。社会の変遷を越えて、人の生活の中で使用された民具類は、これからの人たちに必ず何かを教えてくれるはずである。吉野川を越えた北岸の脇町では、「三味線もちつき」という芸能があるが、それとも関係があるかも知れない。
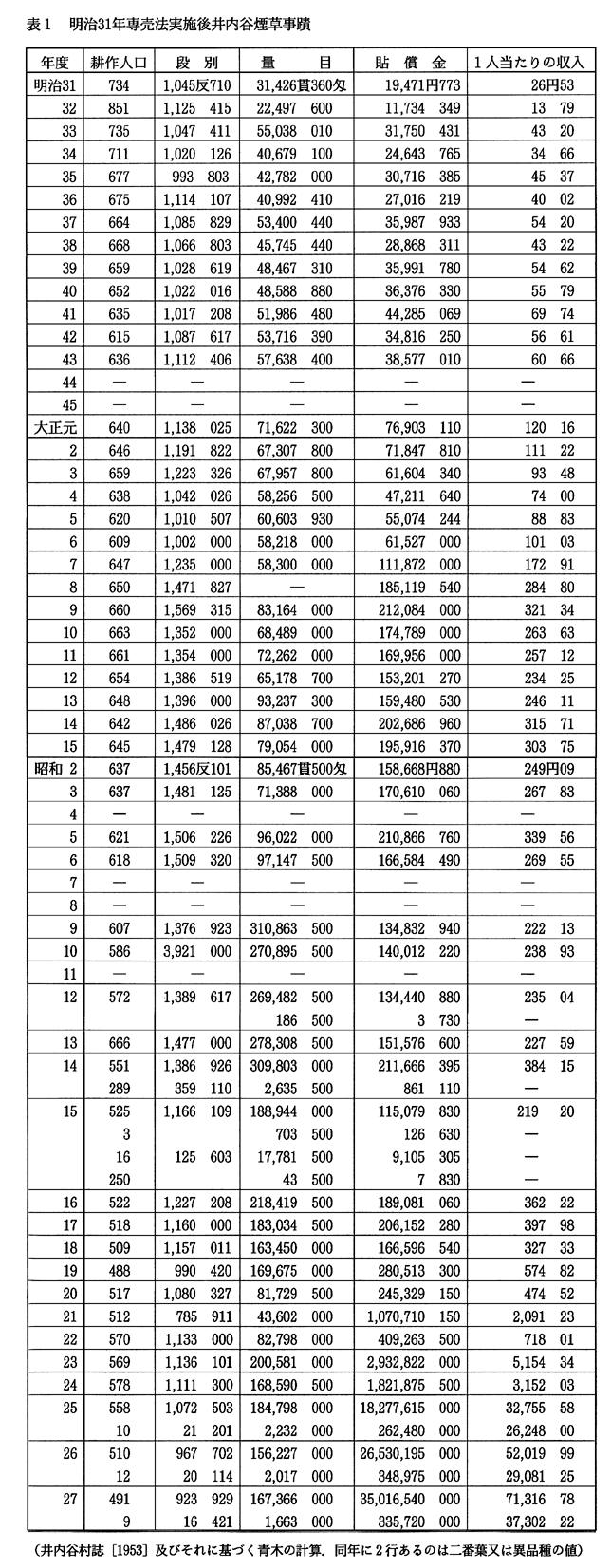
5.まとめ
以上述べたことは、井川町の民具を調べ、報告する、というのが本旨ではない。資料館の現状に対して「何処も同じ秋の風」ではない、問えば必ず答えてくれる、ということを強調したかったのである。
2)鳴門市役所