考古班(徳島考古学研究グループ)
岡山真知子1)・三宅良明2)・
大塚一志3)・中川尚4)・小林勝美5)
1.はじめに
考古班は、「井川町における考古学的研究」をテーマにして、大きく二つの調査研究を実施した。一つは、「井川町における後期古墳の研究」として、須賀古墳の実測調査と周辺の分布調査を実施した。他の一つは、「井川町出土遺物の研究」として、前井川町教育長吉岡浅一氏所蔵の考古遺物の実測調査を実施した。前者は主に岡山真知子・大塚一志・中川尚が担当し、後者は三宅良明・小林勝美が担当した。
2.井川町における後期古墳の研究
1)調査の経過
期日 1997年7月26日(土)〜7月27日(日)、12月6日(土)
調査員 小林勝美、三宅良明、中川 尚、大塚一志、岡山真知子、福原智子
調査協力 吉岡浅一、川西 栄、川西 譲
内容 井川町所在の後期古墳として須賀古墳の実測調査と周辺の分布調査を実施した。
2)調査の概要
(1)須賀古墳の立地
須賀古墳は、別名「風呂」とも呼ばれる井川町西井川178番地に所在する後期古墳である(図1参照)。西に延びる尾根上に立地し、横穴式石室を主体部とする。標高102m
という後期古墳としては高所に立地する古墳である。また今回の調査で、川西栄氏から御教示を頂き、新たに2基の古墳の存在を確認した。1基は、須賀古墳から北東約20m
に位置する御森古墳である。西井川169番地に所在するが、横穴式石室が存在した痕跡をとどめるだけである。もう1基は、南西約80m
に位置する古墳である。竹林の中に埋まった状態であり、詳細は不明である。
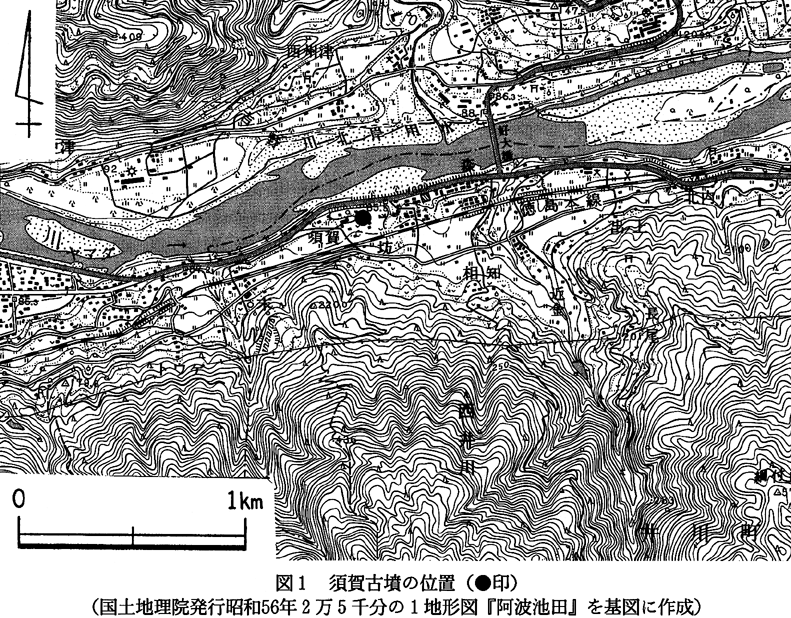
(2)須賀古墳の外部構造
後世にかなり積み替えられていると考えられる墳丘の残欠も確認できた。現状は、封土を一部残すのみであるが、円墳と推定される(図2)。
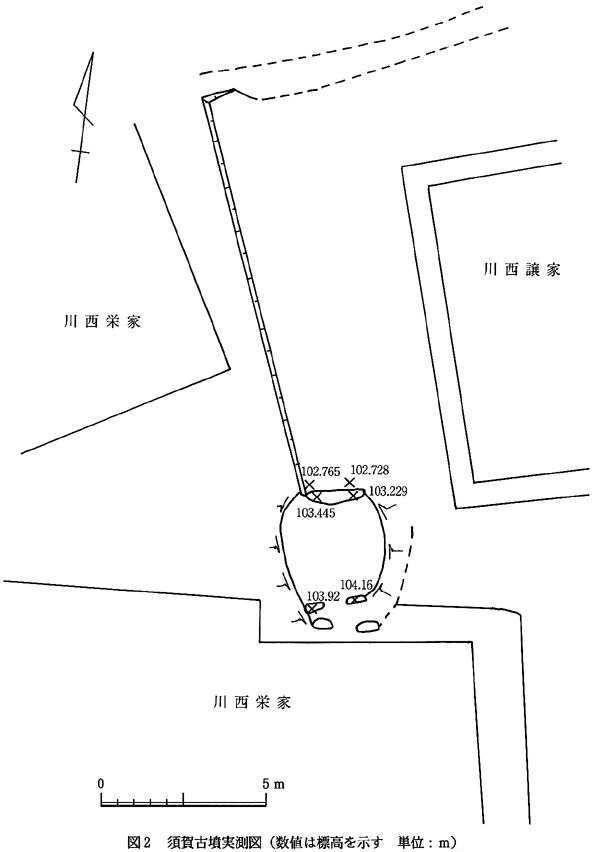
(3)須賀古墳の内部構造
南に開口する横穴式石室を内部主体とする。ほとんどが崩壊しており、奥壁(幅170cm・高さ70cm・厚さ18cm
が現存)と玄門立石の上部(幅60cm・厚さ20cm)が残されているだけであった。残存する盛土の中には、天井石と考えられる石も2個積み込まれていた。その大きさは、長さ180cm・幅80cm・厚さ20cm
と長さ120cm・幅65cm・厚さ20cm である。以上から、玄門部での幅60cm、奥壁部での幅150cm、玄室の長さ2.7m
は復元できる。以上から長さ2.7m・幅2m
程度の中央部が膨らむ形の玄室が想定できる(図2)。羨道(せんどう)部は全く不明である。また、気がかりな点としては、玄門立石が2組立っている点である。この立石が築造当時のものとすれば、いわゆる複室構造と考えられる。もし、複室構造とすれば、鴨島町の西宮古墳に次いで、本県では2例目となる。
3)考察
今回の須賀古墳の調査成果により、従来あまり知られていなかった、三好郡内の後期古墳の特徴の一端が明らかになった。
まず須賀古墳は、胴部が膨らみ、玄門立石をもつ横穴式石室を内部構造とする後期古墳であることが判明した。いわゆる段ノ塚穴型石室注1の特徴(平面プランが長方形でなく胴膨らみで、天井石を持ち送る)をもち、複室構造の可能性もある。また、少なくとも3基がこの近辺に存在しており、群構造での分布も同じ特徴と言える。
次に、横穴式石室としてはかなり高所に築造されているという特徴がある。吉野川中・上流域の後期古墳の立地と比較してみる。第一グループに、忌部山型石室の忌部山古墳(山川町)や鳶ヶ巣古墳群A(川島町)の標高250m
前後があり、第二グループとしては、標高150m〜200m
の忌部山型石室の鳶ヶ巣古墳群B・峰八古墳群(川島町)がある。須賀古墳は、この次の第三グループに属する。このグループには段ノ塚穴型石室の吉野川南岸の三島古墳群(穴吹町)や西山古墳(貞光町)などが属する。段ノ塚穴型石室の吉野川北岸の荒川古墳・海原古墳もこれに次ぐ。一般に、段ノ塚穴型石室の古墳は河岸段丘端部に築かれるため、標高50m
前後に位置する。
吉野川中・上流域の後期古墳の一覧表(表1)と分布図(図4)を作成したが、これを見ると、段ノ塚穴型石室・忌部山型石室と不明の三好郡グループがみられる。この分布の中で、須賀古墳は不明の三好郡グループに属していた。従来は段ノ塚穴型石室は、東は阿波町・鴨島町から美馬郡にかけて分布すると考えられてきた注2が、今回の調査成果により、少なくとも井川町まで段ノ塚穴型石室のタイプが広がっていることが指摘できる。また、立地等により、忌部山型石室とも共通性がみられるなど、段ノ塚穴型石室と忌部山型石室の関連性も強まったと言える。
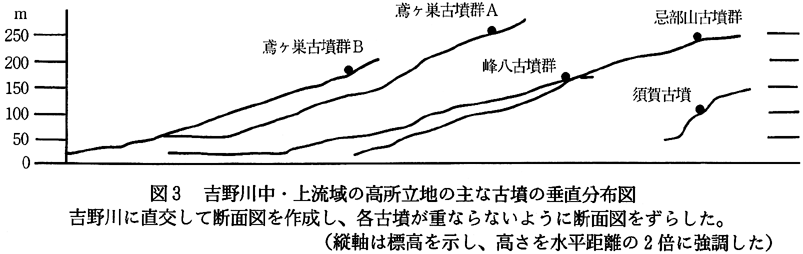

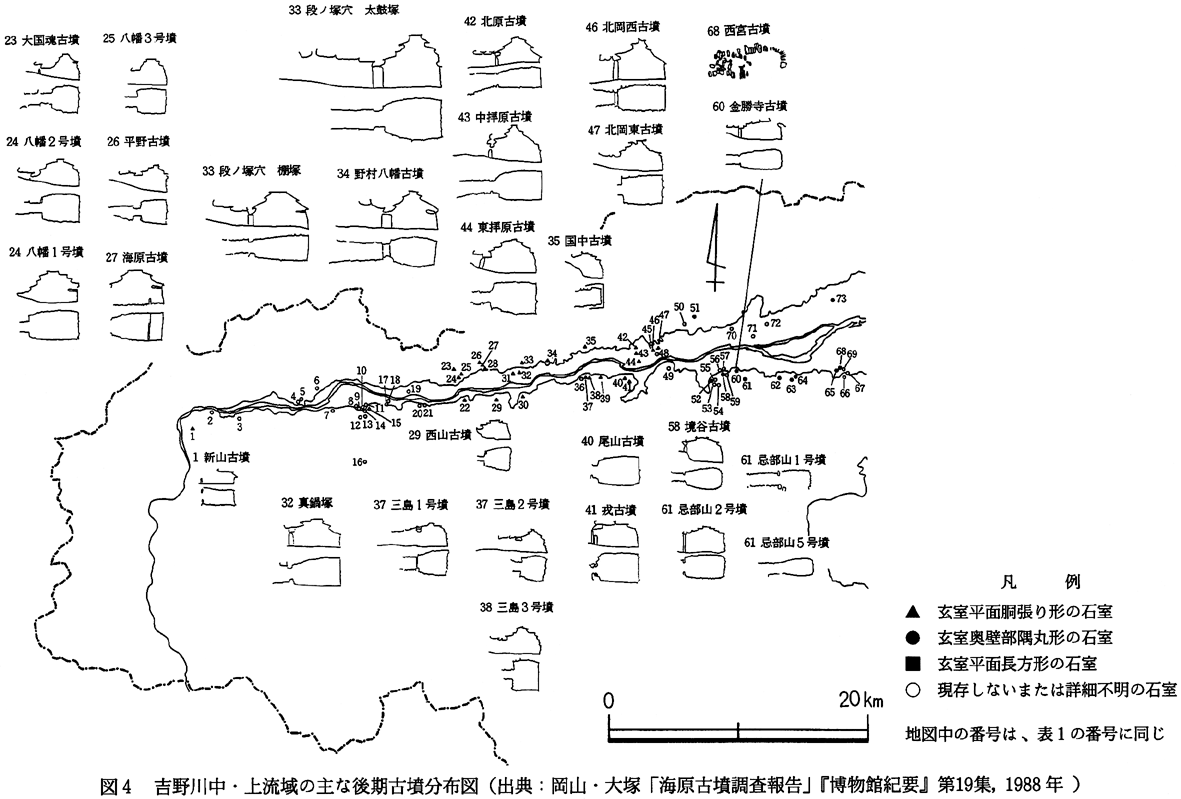
3.井川町出土遺物の研究
1)中村遺跡採集の遺物
ここに紹介する資料は、井川町吉岡99番地の4に在住の吉岡浅一氏が自宅南側の畑で採集され、所蔵されている遺物の一部である。
採集地点は、吉野川に注ぐ小河川である中村谷川の沖積作用によって形成された標高100m
前後の低位段丘上に位置し、当該地名から「中村遺跡」と呼称されている(図5)。以下、おもな採集遺物について概要を述べる。
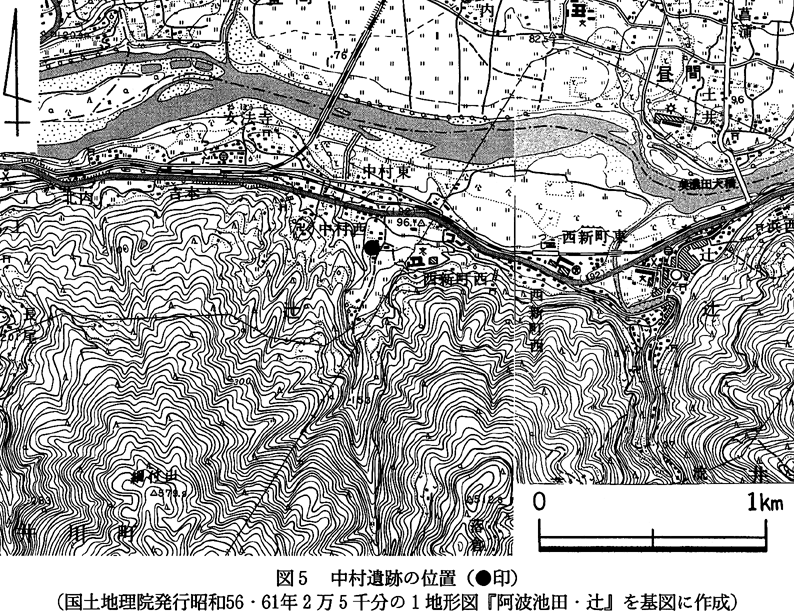
(1)石鏃(ぞく)
今回実見した中村遺跡出土遺物の中で、器種別にみて最も多く採集されているのが石鏃であり、合計26点を数える。そのうち2点は欠損が著しく、全体の形状・法量等が不明なため、あえて除外し、ここでは完形品および欠損品の中でも比較的欠損度が低い24点について紹介する(図6・図7)。なお、石材はすべてサヌカイトである。

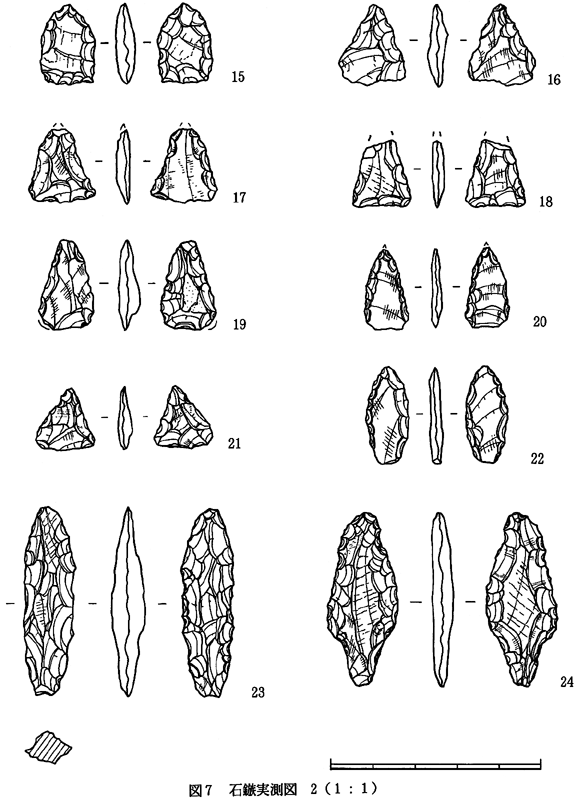
24点のうち完形品と考えられるものは10点(4、11、14〜16、19、21〜24)であり、他の14点は先端あるいは基端を多少なりとも欠く。基部の形状に基づき形態分類を行うと、凹基式13点(1〜13)、平基式8点(14〜21)、凸基式2点(22・23)、有茎式1点(24)に分類される。ただし、14のように凹基式にも分類可能なものが存在する場合、分類基準はあくまで主観的なものとなるので、必ずしも妥当な分類とは言えないかも知れない。また、例えば凹基式にも、凹部が比較的深いもの(2、3、5、6、8)や浅いもの(10、11、12)が存在したり、側辺が外反するもの(8、11)や内湾するもの(12)、先端角度の違いによって鏃身が正三角形に近い形状を呈するもの(1、4、5、6、7、9)や二等辺三角形状を呈するもの(2、3、10)などが存在し、その形態は多様であり、さらに細分することも可能である。なお、側辺部周辺の調整剥(はく)離が浅いために、素材剥片剥離時に生じた剥離面がそのまま鏃身の両面(5、10、14、15、17、18、22、23)あるいは片面(2、3、4、6、8、11、12、13、19)に残されている例が目立つ。
次に大きさと重量については、23が4.5cm で4.0g、24が4.1cm で3.35g
を測り、24点の中では傑出した数値を示している。この2点を除く22点は欠損部を復元しても長さ1.4〜2.4cm(平均長1.9cm)、幅1.0〜2.05cm(平均幅1.4cm)に収まる小型の石鏃である(表2)。

石鏃は言うまでもなく、矢柄に装着して矢として用いられるものであり、その形態と装着法には密接な関係があるとされる。発掘調査でも、矢柄に鏃身が装着されたままの状態で出土する例は極めてまれであるが、一般的には、有茎式やそれに近い凸基式の鏃身は中空の矢柄に差し込んで装着され、凹基式や平基式の鏃身は矢柄の先端を割ってそこに挟む、いわゆる「根挟み」の方法によって装着された可能性が高いと考えられている。この推論に基づけば、23・24は前者の方法で、他は後者の方法によって装着されていたと想定することも可能である。なお、23は少し規模が小さいが、槍(やり)の先端と考えることも可能かも知れない。
石鏃の製作の時期については、同じ遺構から年代決定の指標となる土器などを伴出しない限り、単独で時期を決定するのは難しい。例えば、狩猟具として考えられる縄文的要素の強い小型の石鏃は、引き続き弥生時代にも用いられ、弥生時代前期ごろの集落遺跡からも出土する。逆に、縄文時代においても4cm
前後の中・大型の石鏃は存在する。ただ、弥生時代になると、24のような有茎式の石鏃が武器として大型化することが指摘されている。以上の諸点や、採集遺物に後述する縄文土器が含まれていることなどから、大型で凸基式の23と有茎式の24を弥生時代の石鏃として、小型品は縄文時代(後〜晩期)の石鏃としてとらえることが可能である。
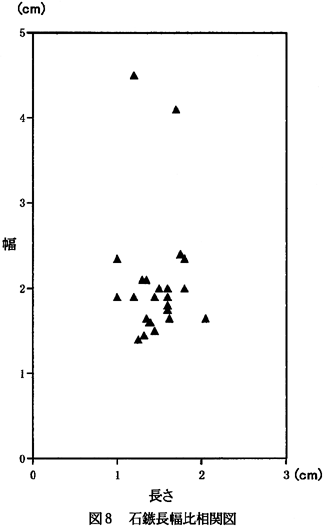
以上、石鏃について触れたが、石鏃の採集数以上にサヌカイトの剥片類が採集されていることも付記しておく。
(2)縄文土器
破片3点が採集されている(図9)。1は、深鉢の口縁部の破片であり、外反する口縁端部を外側に肥厚させ、その外面に横位のRL縄文を施した縁帯文土器である。縁帯文は幅10〜15mm
で、縁帯下部には横方向のミガキの痕跡が認められる。縄文時代後期前半ごろのものと考えられる。2も深鉢の口縁部の破片である。ほぼ垂直に立ち上がる先すぼまりの口縁をなし、内外面ともに無文である。3は非常に微細な胴部の破片であり、断面が浅いU字型を呈する沈線を1条とどめているのみである。なお2・3の製作時期については、縁帯文土器1と同時期の可能性もあるが、不明である。

(3)扁平(へんぺい)片刃石斧(せきふ)
扁平片刃石斧(図10)は、弥生時代前・中期に普及した代表的な磨製石器で、柱状片刃石斧などとともに、伐採後の木材を二次的に加工する斧おのである。
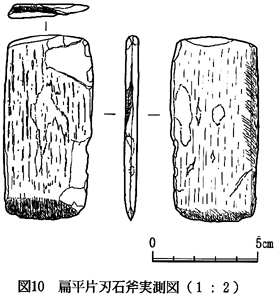
本資料はその斧身で、長さ86mm、幅41mm(刃幅37mm)、厚さ6mm、重さ49.8g
である。石材は頁岩(けつがん)質のものと思われるが、不詳である。
製作された当初は、現状の2倍程度の厚みがあったものと思われるが、おそらく使用過程で生じる衝撃等によって2枚に剥離分割したため、その剥離面側に新たな刃面を作り出して、再度石斧として使用されたものと考えられる。
刃部の形態は、使用と研磨の過程を経て両刃に近い状態になっている。両刃面には、上下方向の擦痕と斜め横方向の擦痕が認められる。おおむね前者を使用痕、後者を研磨痕と想定することも可能であるが、特に上下方向の擦痕についての使用痕と研磨痕の区別は困難である。なお、基端面および側面の一部にも磨いた痕跡が認められる。
2)井川町西ノ浦採集の太型蛤(はまぐり)刃石斧
太型蛤刃石斧(図12)も、弥生時代前・中期に普及した代表的な磨製石器で、木材供給の最初の段階である伐採において、用いられた斧である。
本資料は、垣采春文氏がかつて西ノ浦4288付近において採集され、その報告を受けた岡本福治氏(現井川町教育長)によって現在保管されているものである。採集地は、吉野川の支流である井内谷川を直線距離で3.5km
ほど逆上った西岸の、標高約460m の山稜(さんりょう)上であり(図11)、西方約1.5km
には中世山城である八石城跡(標高約800m)がある。
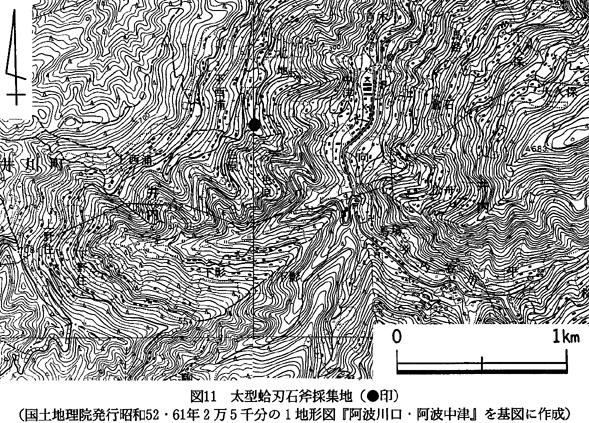
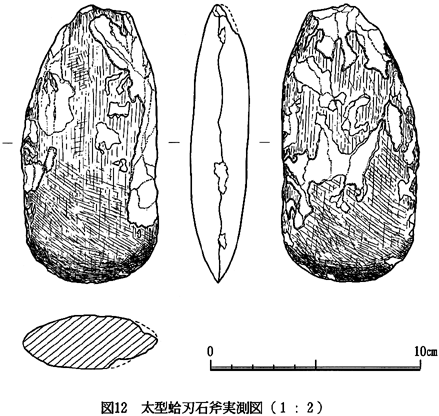
斧身の法量は、長さ130mm、幅63mm(刃幅60mm)、厚さ26mm、重さ371.5g
である。泥岩質の石材を用いており、表面の剥落や刃つぶれが著しい。平面形は、側縁のラインが主軸に対して左右非対称である。また、側面観は比較的薄手で、基端部もほとんど面を構成しない。典型的な太型蛤刃石斧に比べてやや扁平な形態の蛤刃石斧である。
本資料については、まずその採集地の地理的環境に注目すべきであろう。太型蛤刃石斧は木材の伐採道具とはいえ、木材供給地である山林から単独で出土することはまれで、集落跡の発掘調査で出土するのが一般的である。このことは、山林部での発掘調査例が少ないことにも起因しているが、本資料の採集地は、本来太型蛤刃石斧が使用されたと考えられる場所(環境)であり、木材の生産活動の一端を反映する貴重な事例である。今後、当該地周辺で土器なども含め、採集例が増加する可能性もあり、期待される。
4.おわりに
今回は、調査期間中に台風の襲来などもあって充分なことはできなかったが、三好郡の横穴式石室の一端を解明できたことに一つの意義を見いだしたい。また、前井川町教育長吉岡浅一氏所蔵考古資料の実測もさせていただいた。今回報告したのは、出土地が明確なものだけとし、出土地不明の資料(鼎の脚部・土釜等)については省略させていただいた。出土地不明ではあるが、井川町内に古代(奈良・平安時代)の遺跡が存在することは確かである。最近、四国縦貫道関連で弥生時代の坊・須賀遺跡が調査されるなど、井川町の歴史が明らかになりつつある。今後の成果に期待したい。
最後に、今回の調査にあたって、井川町教育委員会をはじめ、吉岡浅一氏・川西栄氏・川西譲氏等地元関係者のご協力を得た。記して、感謝したい。
1)徳島県教育委員会文化財課 2)徳島市教育委員会社会教育課 3)脇町小学校
4)徳島県立富岡東高等学校 5)徳島県立文書館