社寺建築班(郷土建築研究会)
尾方洋子1)・坂口敏司2)・富田眞二3)
中野真弘4)・永見哲也5)・原田知美6)
松永佳史7)・森兼三郎8)・龍野文男9)
1.はじめに
井川町は県西部に位置し、北に吉野川を、南には四国山地を望む。明治22年(1889)市制町村制施行により、西井川村と東井川村が合併して井川村となり、同40年(1907)辻町となる。この時期、一村であった井内谷村が、昭和34年(1959)にこの辻町と合併して現在の井川町となる。
私たち社寺建築班は7月25日から町内に入り、社寺建築を建築学的見地から調査した。神社は10カ所を、寺院は5カ所を調査し(図8)、それぞれの建築様式や構造などを一覧表にまとめ、うち7カ所については詳細調査を行い、実測図を作成した。
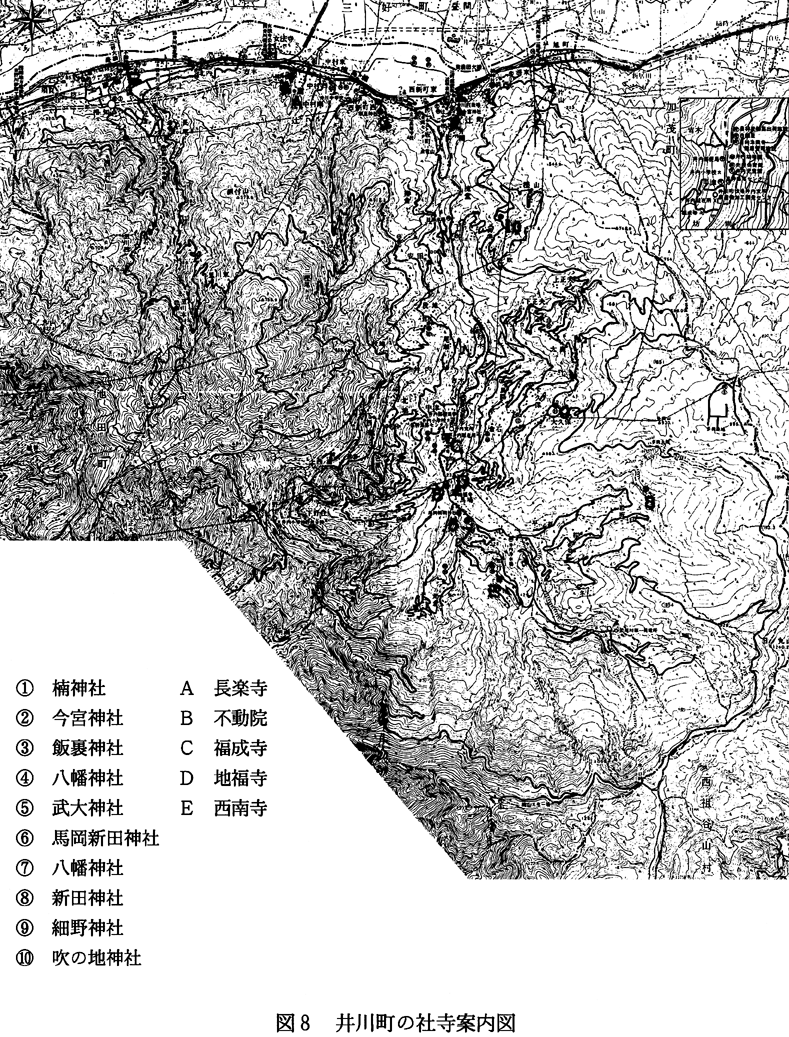
神社では、井内谷の馬岡新田神社など4社に使われていた一切の加工を施さない切り放しのままの肘木(ひじき)と頭貫木鼻(かしらぬききばな)に、また大久保の細野神社(中の森神社ともいう。図1)などの素朴な青石積みの拝殿に調査の成果をみたが、寺院では特筆すべきものはみられなかった。以下、その内容について報告する。
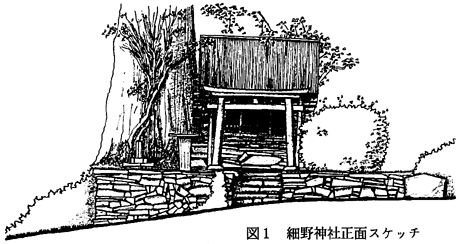
2.井川町の社寺建築概要
1)神社建築の概要
神社は10社を調査し、社殿の建築様式や建立年代などを一覧表にまとめた(表1)。その中で、18世紀中期建立(推定)の辻の八幡神社本殿以外は、近世にさかのぼる社殿は見当たらなかった。本殿の建築様式では地神碑を祀(まつ)る吹(ふき)の地神社を除き、4社が流造(ながれづくり)、5社が入母屋造であった。流造はすべて一間社であったが、入母屋造は、辻の八幡神社を除く4社(飯裹(いいつつみ)神社、武大(たけお)神社、馬岡新田神社、井内谷の八幡神社)が桁行(けたゆき)3間梁間(はりま)2間の三間社の規模であり、これらはすべて正面に千鳥破風(ちどりはふ)を置き、向拝(こうはい)部を軒唐(のきから)破風とした、いわゆる権現造(ごんげんづくり)の様式である。県下全般をみても圧倒的に流造様式が多い中で、今回の比率には驚かされた。5年前(平成4年)の阿波学会調査で入った吉野川対岸の三好町にも権現造が4社見られたことから、この地域における本殿建築様式の一つの傾向とみてとることができる。

また細部の特徴として上げられるのが、一切の加工を施さない直線の肘木を持つ組物と、彫刻を施さない切り放しのままの頭貫木鼻である。これは馬岡新田神社を始め、井内谷の八幡神社(図2)、武大神社、楠(くすのき)神社の4社にみられた。肘木は下面の端部を緩く曲面加工するのが一般的である。寺院建築では、その形状によって和様か禅宗様か(図3)などの判別をするが、ここでは既存の様式を無視して角材のまま使用している。この直線肘木に呼応するように、身舎(もや)の円柱(まるばしら)から突き出す頭貫の木鼻も切り放しのままである。それ以外の細部は通常の手法で造られており、匠(たくみ)の挑戦意欲がうかがえる社殿群となっている。全体としてみたとき、直線構成が新鮮に映り、美しい本殿を造り出している。全国的にみても、幕末から明治にかけて社寺建築の装飾は特にエスカレートしている。県内では池田町の箸蔵寺の伽藍(がらん)に代表されるように、匠の技は細部意匠の装飾へと注がれていくが、それを逆手にとった試みがここで見事に開花している。半田町にある同時期(明治24年〔1891〕)建立の石堂神社本殿(町指定)も同じく直線の肘木をふんだんに使っているが、木鼻には通常手法の彫刻が施されており、ここの4社とは微妙に手法が違っている。
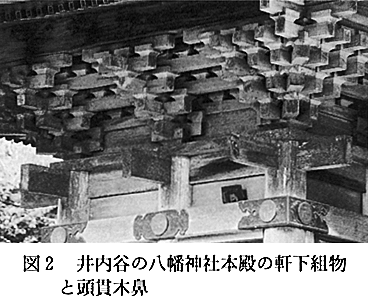

町内の神社建築でもう一つ興味深かったのが、庶民の石積み文化である。大久保の細野神社のほかに、吹の地神社、大久保の雨の森神社、井内谷岩坂の新田神社や毘沙門天(びしゃもんてん)など、素朴で力強い青石積みの神社と多く出会った。細野神社の拝殿を兼ねた鞘堂(さやどう)(図4)や吹の地神社の拝殿(図5)は、3面を青石で積み上げて建造物にまで仕上げていた。雨の森神社や新田神社では、境内の至るところに薄い青石を積み上げ石垣を築いていた。薄く割れる青石は、素人の施工に好都合だったのであろう。素朴な仕上がり具合が氏子たちの共同作業であることを物語っている。
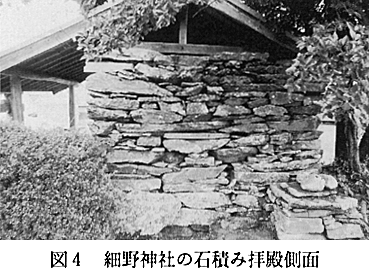
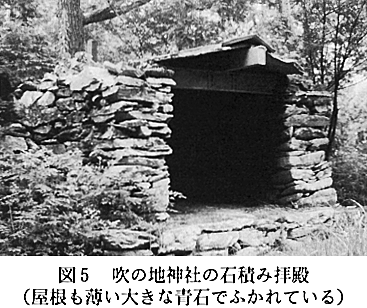
今回のように一地域に数カ所まとまって発見されたことは、この地に青石の野積み工法が定着し、一時期かなり広まっていたと考えられる。築造年代は江戸末期から明治前期と推察するが、庶民の石積み文化遺産としての価値は高い。
2)寺院建築の概要
寺院は5カ寺を調査し、建物の建築様式や建立年代などを一覧表にまとめた(表2)。年代のわかる中では地福寺の本堂(図6)と鐘楼が古く、文政年間(1818〜30)の建築である。本堂は入母屋造で入母屋破風の玄関を挟んで庫裏と連結しているが、度々の増改築で往時の面影はない。一方の鐘楼はやや内に転ぶ四脚鐘台で、禅宗様を基調とした入母屋造の建物である。
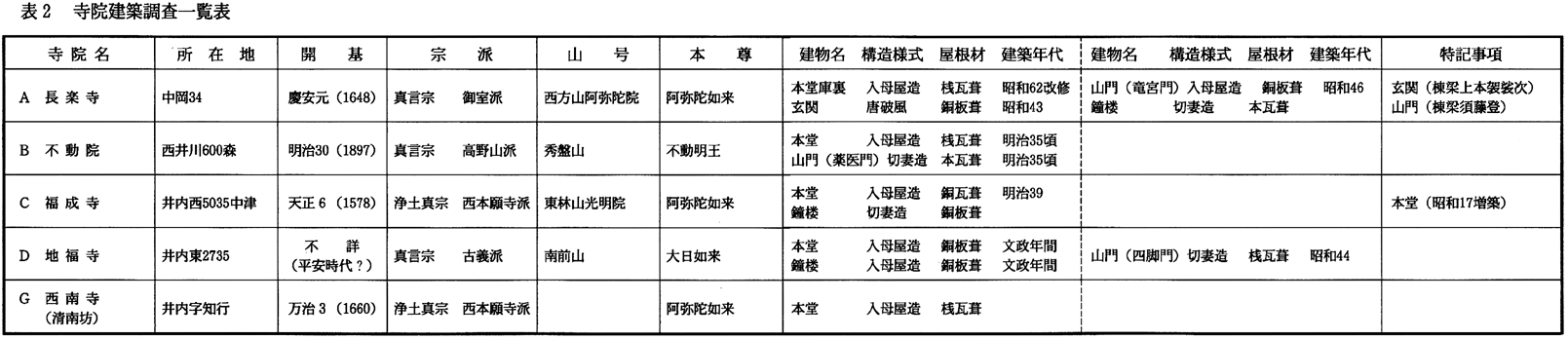
門は3カ寺にあり、長楽寺の竜宮門(図7)、不動院の薬医(やくい)門、地福寺の四脚門、とそれぞれ様式を異にしている。その中では薬医門が古く、明治35年(1902)ごろの建築である。総体的にみて、寺院建築は成果の乏しい調査結果となった。


3.井川町の各社寺建築
1)楠神社(表1−1
) 鎮座地―辻字片山233
[本殿]木造 一間社流造(ながれづくり) 銅板葺(ぶき) 〈明治25年(1892)〉
身舎−円柱 腰長押(なげし) 切目(きりめ)長押 内法(うちのり)長押 頭貫木鼻(寸切り) 台輪(留め) 三手先(みてさき)(直線肘木) 中備詰組(なかぞなえつめぐみ) 妻飾(つまかざり)・二重虹梁大瓶束(にじゅうこうりょうたいへいづか) 二軒繁垂木(ふたのきしげたるき)
向拝−角柱(かくばしら) 虹梁型頭貫木鼻(獅子(しし)) 出三斗(でみつど) 中備彫刻 手挟(たばさみ) 擬宝珠高欄(ぎぼしこうらん) 四方切目縁 背面隅行障子(すみゆきしょうじ)(透彫(すかしぼり)) 腰組二手先(ふたてさき) 木階(きざはし)五級(木口) 浜床
千木(ちぎ)−千木なし 堅魚木(かつおき)−3本
(図9、10、11)
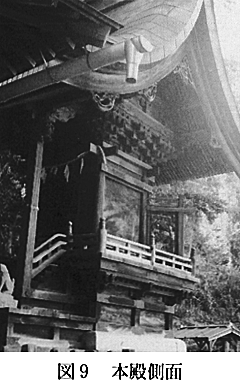
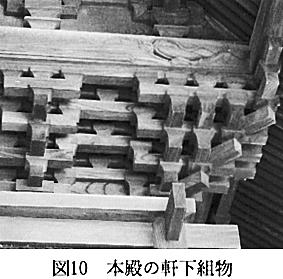
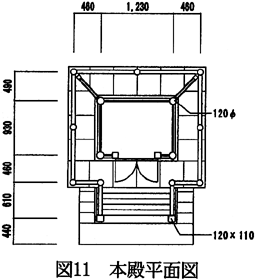
この社は町北東部の美濃田(みのだ)橋南詰に位置する。国道192号線沿いにある注連縄(しめなわ)鳥居をくぐり、急な石段を登り詰めた右手側に社殿(拝殿と本殿)がある。この社は今宮神社の飛地境内社であり、明治23年(1890)には今宮神社境内にあった八坂神社の分霊を合祀(ごうし)している。
現本殿は明治25年(1892)の建立でやや小振りな一間社流造銅板葺である。身舎部は井内谷の3社にみられるように、一切の加工を施さない直線の肘木と頭貫木鼻を用いた造りの社殿である。3社の入母屋造に対して流造と建築様式は違うが、細部の納まりにはかなりの共通性がみられる。棟札を確認できなかったが、3社と同時期なので、同大工の造営による可能性が強いと思われる。独創的な組物を始め、細部のち密さなどに質の良さを感じさせる本殿である。
拝殿の建立年代は不明であるが、本殿と同時期と推察する。桁行3間梁間2間の入母屋造銅板葺で、外壁は漆喰(しっくい)塗りの大壁造である。向拝虹梁部の頭貫木鼻も本殿と同様に彫刻を一切施さない寸切りの角材を使用している。
2)今宮神社(表1−2
) 鎮座地―辻字辻316
[本殿]木造 一間社流造 銅板葺 〈大正5年(1916)〉
身舎−円柱 切目長押 内法長押 舟(ふな)肘木 妻飾・扠首(さす)組 二軒半繁(はんしげ)垂木
向拝−角柱 丸桁(がぎょう) 大斗(だいと)肘木 繋(つなぎ)虹梁 刎(はね)高欄四方切目縁 木階五級(木口) 昇(のぼり)擬宝珠高欄 浜床
千木−置千木垂直切 竪魚木−3本
[舞殿(まいどの)]木造 方広(ほうひろ)一間 妻入(つまいり)入母屋造 銅板葺 〈大正5年(1916)〉 角柱 土台 切目長押 内法長押 舟肘木 妻飾・木連(きづれ)格子 二軒疎(まばら)垂木 格(ごう)天井
[神門]木造 一間(2.72m) 妻入切妻造 銅板葺 〈大正5年(1916)〉 円柱 控(ひかえ)円柱 舟肘木 一軒疎垂木 中備蟇股(かえるまた) 妻飾・扠首組
(図12、13)
この社は町北東部の辻に位置する。現社殿は大正3年(1914)8月に着手し同5年(1916)1月に上棟式が行われている。設計は当時徳島県立工業学校の建築技師福永嘉吉で、徳島市二軒屋の忌部(いんべ)神社を模範にして造られたといわれている。この社殿の配置は、日吉(ひえ)造様式にみられる神楽殿(かぐらでん)のような四面吹き放しの舞殿を手前に置き、その奥を瑞垣(みずがき)で囲い、中に一間社の流造本殿を置く。県内では土成町の日吉神明(ひよししんめい)神社にこれと同じ形態がみられた。また、舞殿と本殿間の線上には神門が置かれ、切妻造の妻入として正面性を強調している。瑞垣は幅10.5m
奥行15.3m
の総桧(ひのき)造りの透塀(すきべい)で、塀内には玉砂利が敷き詰められている。大正期における本格的な造りの社殿群である。
棟札は8枚確認したが、うち解読可能な最古のものは天明7年(1787)で、大工多田吉右門長□、次の文政13年(1830)のものにも大工多田吉兵衛貞義と、多田姓が名を連ねている。

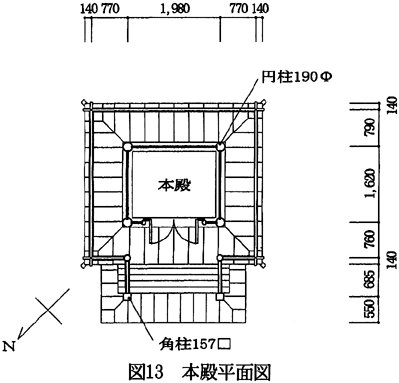
3)八幡神社(表1−4
) 鎮座地―辻字八幡102
[本殿]木造 桁行一間(背面二間)梁間一間 入母屋造 向拝一間縋(すがる)破風 銅板葺 〈延享2年(1745)〉
身舎−円柱 腰長押 切目長押 内法長押 頭貫木鼻 台輪(留め) 板支輪
出組 中備詰組 中備蟇股 妻飾・豕子(いのこ)扠首 二軒繁垂木
向拝−角柱 虹梁型頭貫木鼻(錫杖彫(しゃくじょうぼり)) 連三斗(つれみつど) 中備彫刻 手挟 刎高欄三方切目縁 背面脇障子(板) 昇擬宝珠高欄 木階五級(木口) 浜床
千木−置千木垂直切 堅魚木−3本
(図14、15)
この社は町北部の役場の西方約1.7km、国道192号線沿いの南に位置する。『徳島県神社誌』によると、由緒は古く、応永年間(1394〜1428)大西四郎が当地開発にあたって守護神として長尾に創建したと伝え、その後兵火で焼失し、延宝5年(1677)現在地に再建されたという。
本殿は桁行8尺、梁間7尺の入母屋造で、ほぼ方形に近いが、背面のみ二間とした造りである。身舎組物は出組で中備に詰組を配し、組物間には蟇股を置くなど賑やかに仕上げている。また彫刻では身舎正面両側の二つの頭貫木鼻に、木の葉をモチーフとした籠彫(かごぼり)を施し、正面性を強調しているのが目につく。向拝柱上部の組物は連三斗とし、身舎とは手挟で繋いでいる。町史によると、棟札は延宝5年(1677)を始め、元禄、延享、明和、安永、文化など10枚残されているという。現本殿は虹梁の彫刻などから延享2年(1745)のものと推察する。また拝殿は、大唐破風の向拝を持つ正面千鳥破風付き入母屋造桟瓦葺の建物である。向拝部の天井は格天井で板絵が描かれている。


4)馬岡新田神社(表1−6
) 鎮座地―井内字馬場ノ西22
[本殿]木造 桁行三間 梁間二間 入母屋造 正面千鳥破風付 向拝一間唐破風 銅板葺 〈明治16年(1883)〉
身舎−円柱 腰長押 切目長押 内法長押 頭貫木鼻(寸切り) 台輪(留め) 三手先(直線肘木) 腰組二手先(直線肘木) 二軒繁垂木
向拝−角柱 虹梁型頭貫木鼻(寸切り) 出三斗 中備彫刻蟇股 手挟 刎高欄四方切目縁(透彫) 隅行脇障子(彫刻) 昇擬宝珠高欄 木階五級(木口) 浜床
千木−置千木垂直切 堅魚木−3本(千鳥及び唐破風部の各1本含む)
(図16、17、18、19、20、21)
この社はかつての郷社で、井内谷川上流の地福寺の対岸に位置する。創建は不詳であるが、井内谷村史によると明暦2年(1656)、延宝3年(1675)など13枚の棟札を保存している。上(かみ)にある八幡神社(図22)と下(しも)の武大(たけお)神社(図23)とを併せ「三社の杜(もり)」と呼ばれている。
本殿は明治16年(1883)建立で、当時桧皮(ひわだ)葺の建物であったが、昭和28年(1953)に銅板に葺(ふ)き替えられている。屋根形態は間口三間の入母屋造に正面に千鳥破風を置き、一間の唐破風向拝を付けた賑(にぎ)やかなもので、通称権現造と呼ばれる建築様式である。この社で注目すべきは組物の肘木と頭貫の木鼻部分であり、加工や彫刻を一切施さず角材のまま使用している。これは様式を重んじる社寺建築では一見異様に感じるが、技術レベルの高さは細部をみても明らかであり、既存様式への匠の挑戦とみる。「三社の杜」の他の2社はやや小規模であるが、同じ造り、同じ大工で、同時期に造営されている。棟札より、大工は千葉春太(太刀野村)と佐賀山重平が携わっていることがわかる。
拝殿は正面に千鳥破風を付けた入母屋造で、大唐破風の向拝を付ける。建立年代は本殿と同じ明治16年で、同大工によって造られている。技術の高さは向拝部の彫刻にも表れている。頭貫木鼻や虹梁上部に施された龍(りゅう)の彫刻は匠の技を遺憾なく発揮している。
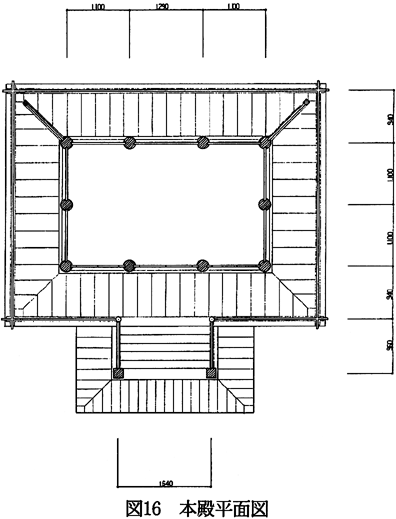
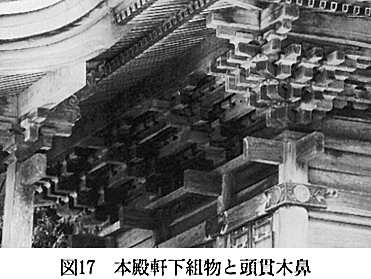
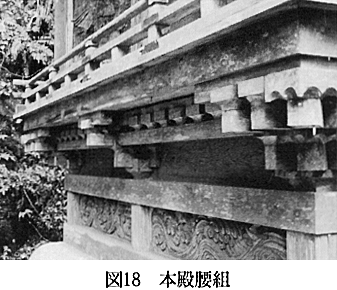





5)細野神社〈別名:中の森神社〉(表1−9
) 鎮座地―井内字大久保
[本殿]木造 一間社流造(小社殿) 銅板葺 〈年代不詳〉
[拝殿兼鞘堂]石造(三面青石積み) 屋根木造切妻造 向拝縋破風 波トタン葺
(図24、25、26、27、28、29、30、31)
この社は井内谷川沿いから多美山に登る中腹の、大久保という地にある。この集落はどちらを向いても近藤か阿佐の姓ばかりである。近くまで来て尋ねたお宅も近藤さんであった。「石積みのお社ならその下に見える大きな椋(むく)の木のところだよ」と教えられ、たどり着くことができた。樹齢数百年は経ているであろう椋の老木に、石積みの拝殿が寄り添っていた。薄く割った青石(緑泥片岩)を氏子たちが積み上げて造ったのであろう。不ぞろいであり、決して美しいとはいい難いが、どこかから信仰のこころが伝わってくる。それは共同で造り上げたものの持つ力であろうか。
この拝殿は鞘堂を兼ねた建物で、壁3面を青石で2.5m
の高さに積み上げ、木造の小屋組に波トタンの屋根を載せている。正面だけに格子の建具が入り、中に小さな本殿が祀られている。素朴な石積みと安価な波トタンの組み合わせが周りの風景に溶け込んでいた。
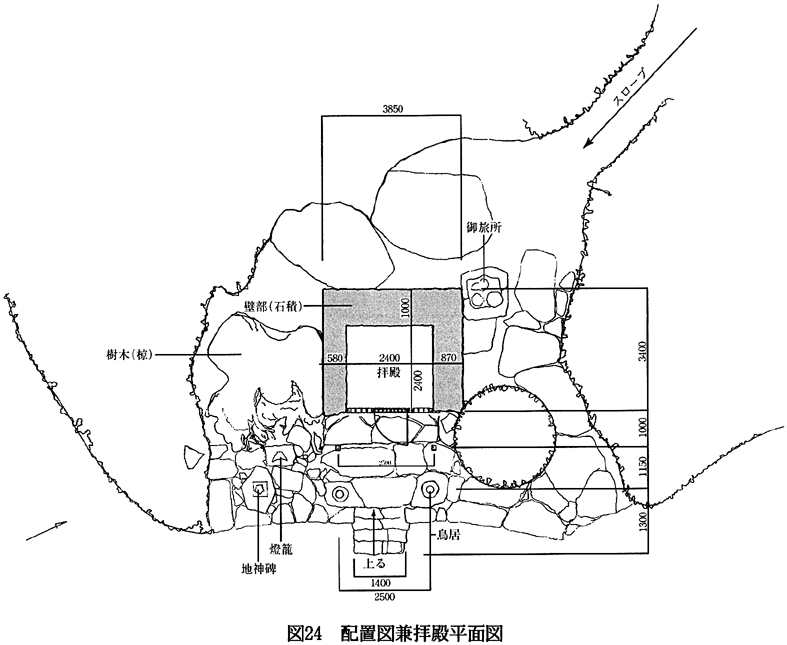
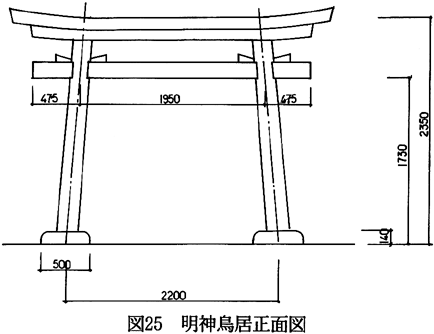
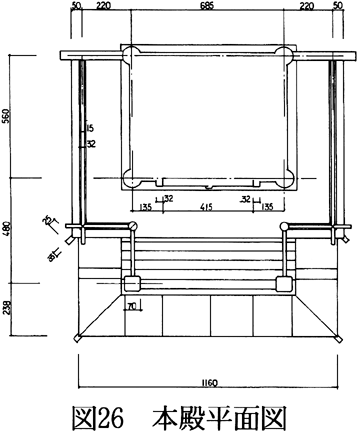
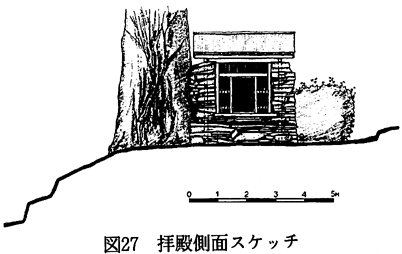
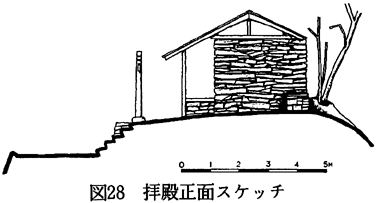
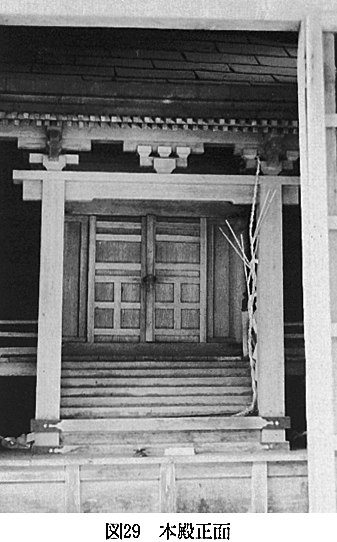


6)不動院(表2−B) 所在地
― 西井川600森
山 号 ―
秀盤山 宗派―真言宗・高野山派
[山門]木造 薬医門 切妻造 本瓦葺 〈明治35年(1902)ごろ〉
親柱五平柱(ごひらばしら) 冠木(かぶき) 男梁(おうつばり) 女(めうつ)梁 控柱角柱 腰貫 内法貫 虹梁型飛貫(ひぬき) 妻飾・豕子扠首 一軒疎垂木
(図32、33、34、35)
この寺院は町北西部の三好大橋南詰の国道192号線沿いに位置する。開基は明治30年(1897)と新しく、本堂(入母屋造桟瓦葺)と山門も明治35年(1902)ごろの建築である。
山門は比較的規模の大きい一間の薬医門で、正面に両開きの桟唐戸(さんからど)が付き、両脇に切妻一間の比翼を配し、右側に潜戸(くぐりど)が付く。頭貫の上に冠木を載せ、その上下に直交して女梁と男梁が架かり、男梁を3本載せて控柱の虹梁位置につなぐ。柱は五平(矩形(くけい))で、控柱は角柱とする。男梁両端部は三斗組で桁梁を受け、中央部は蟇股を置き虹梁を受ける。妻面は簡素な豕子扠首で飾る。屋根は本瓦葺の切妻造で、棟部に鬼瓦(がわら)と鯱(しゃちほこ)を付け、天井には格天井を張るなど丁寧な造りの薬医門となっている。



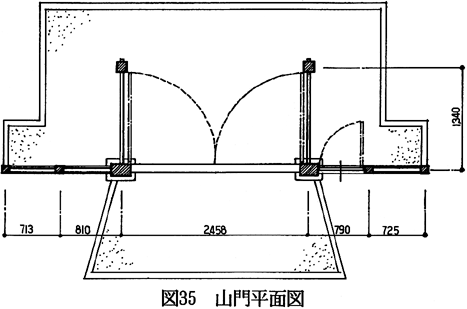
7)地福寺(表2−D) 所在地―井内東2735
山 号―南前山 宗派―真言宗・古義(こぎ)派
[鐘楼]木造 四脚鐘台(しきゃくしょうだい) 入母屋造 銅板葺 〈文政年間(1818〜30)〉 角柱(内転び)腰貫 飛貫 頭貫木鼻(欠落)台輪(留め)出組 中備詰組 彫刻板支輪 二軒扇(おうぎ)垂木 隅尾垂木 妻飾・木連格子
(図36、37、38)
この寺院は井内谷川上流に位置し、対岸にある馬岡新田神社の神宮寺である。町史によると、もと日の丸山の中腹の坊の久保にあったが、18世紀前期か中期ごろに現在地に移ったといわれている。現在の境内は山すその高台にあり、谷沿いの車道からは見上げる格好になり山門と鐘楼が見える程度である。石段を登り山門(昭和44年
〔1969〕)をくぐると、正面に本堂、右側に鐘楼が配置されている。
本堂は文政年間(1818〜30)の建築であるが、明治40年(1907)に茅(かや)から瓦(かわら)にさらに昭和54年(1979)には銅板に葺き替えられた。また度重なる増築で当時の原型を留めていないのが惜しまれる。
鐘楼は総欅(けやき)造りで方形平面を持つ入母屋造銅板葺の四脚鐘台である。組物は出組で中備を詰組とする。やや内転びの角柱上部は、頭貫と台輪で固めているが木鼻は欠落している。台輪が留めの納まりをしているので上にむくった木鼻が付いていたものと推察される。扇垂木・板支輪・肘木形状などに禅宗様がみられ、全体に禅宗様の色濃い鐘楼である。
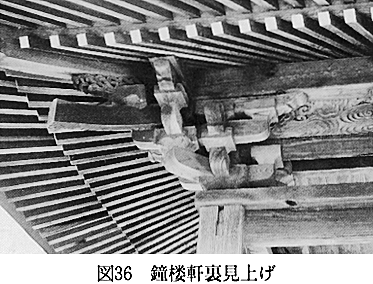


4.おわりに
結団式のあと、地元の藤丸正春さんが突然私たちの班にやってきて、「石積みの神社があるのだけれど一度みてもらえないか」ということから調査は始まった。吹にある地神さんと大久保にある細野神社(別名:中の森神社)がそれであるという。そのころなぜか石に縁があって、尾崎家(美郷村中谷)と着藤(ちゃくとう)家(木屋平村麻衣(あさぎぬ))の石造りの倉を見つけ喜んでいたところだった。
今回の2社も感動的な出会いとなった。吹の地神さん自身は天保10年(1839)に撫養石で造られたごく普通の五角形であったが、手前にある拝殿というか祭場のような空間が、青石積みで造られていた。屋根を受ける梁が鉄骨で架けられていたのが少し気にはなったが、屋根にも大きな平たい青石が載せられ、素朴そのものであった。石積みの空間を通り抜ける地神さんへのアプローチがまた良かった。正面を階段として小さく繰り抜いているので、石積みの暗い祭場に光が差し込んでくる。地神さんは普通北側からのアプローチになるので、階段まで近づくと、後光を差して地神さんが浮かび上がってみえる。こんな演出を一体誰が考え出したのであろうか?。一方の細野神社はまた違った魅力を持っていた。見晴らしの良い中腹にある大きな椋の木が目印となり、そのご神木に寄りかかるように石積みの小さな拝殿があった。吹の地神さんと同じように3面を青石で積み上げている。割った石を割れたままに使う野積みは、素朴で力強い。その青石に守られるように、中に小さな本殿が静かに鎮座していた。時間が止まったような穏やかな風景だった。
井川町調査の成果は、馬岡新田神社など4社にみられた明治期の新しい社殿造営の息吹と、この庶民の石積み文化に尽きる。広くて大きい徳島を改めて痛感した調査になった。

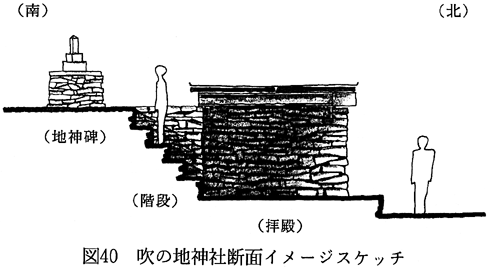
[参考文献]
・『井川町史』井川町役場発行 昭和57年3月31日
・『井内谷村史』井内谷村役場発行 昭和28年11月3日
・『辻風土記』山下待夫著・発行 昭和10年1月20日
・『徳島県の近世社寺建築(近世社寺建築緊急調査報告書)』奈良国立文化財研究所編・徳島県教育委員会発行 平成2年3月
・『徳島県神社誌』徳島県神社庁発行 昭和56年1月1日
・『角川日本地名大辞典・36徳島県』角川書店発行 昭和61年12月8日
1)小松島市小松島町 2)坂口建築設計室 3)富田建築設計室
4)真建築都市研究室 5)名西郡石井町 6)穴吹カレッジ
7)Y.
M. 設計室 8)A+U 森兼設計室 9)龍野建築設計事務所