史学班(徳島史学会) 小原亨
1.樵木の里・日和佐川
1)日和佐川
日和佐川(写真1)は、町の西端相生(あいおい)町との境界にある八郎山(918m)を源として、大越・ツバ谷・西山を流れ落合において支流山河内谷川を合して西河内を流れ、宝木橋において北河内谷川(後世山を源流とする流長14km)を合して日和佐港に注ぐ流長22km
の2級河川である(図1)。

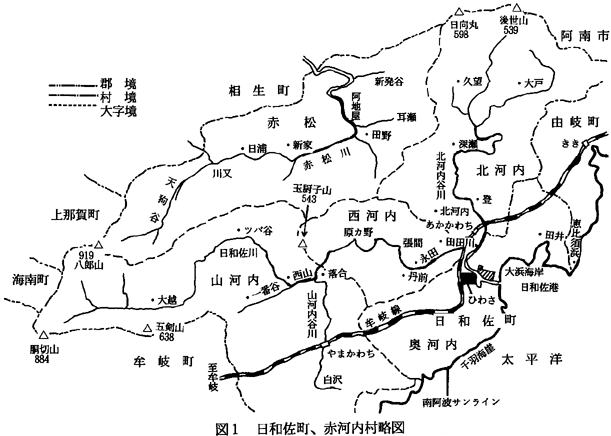
この日和佐川流域には、古くから北河内・西河内・山河内・奥河内の四つの村が形成されていた。明治22年(1889)10月の市町村制施行にともない、北河内・西河内・山河内の3か村と赤松村が合併して赤河内村が誕生した。67年後の昭和31年(1956)9月に赤河内村は日和佐町と合併し、新しい日和佐町が発足した。
この地域は、全面積の92%までが天然林(黒木)の繁茂する山林によって占められていた。こうした関係から黒木を原料とする全国的に珍しい択伐矮林更新法(たくばつわいりんこうしんほう)〈注1〉による阿波を代表する樵木(こりき)林業地帯として、その名が知られていた。その樵木林業に大きな役割を果たしたのが日和佐川の管流(くだながし)〈注2〉(散流)であった。
日和佐川本流と支流の山河内谷川・北河内谷川流域から切り出された樵木は、林地に設けられた「上場(どば)」(山木場)に集積され、乾燥後水流を利用して一斉に河口の日和佐土場(木場)まで管流され、日和佐港より機帆船(イサバ船)によって徳島・阪神地方へ積み出された。この日和佐川の樵木流しは、中世より近代にかけての唯一の搬出手段で、昭和初年まで行われた。明治以降に土佐街道を始め林道の改修整備が進むとともに、流送から陸送に切り替えられていった。特に昭和14年(1939)の福井〜日和佐間の牟岐線開通にともない、樵木・木炭の搬出は、日和佐港の海上輸送とともに赤河内・山河内・日和佐駅から鉄道輸送によって積み出されることとなった。
2)樵木の里
日和佐川流域の北河内・西河内・山河内の3か村は、ウバメガシ・アカガシ等の樫(かし)類や椎(しい)・椿(つばき)などの薪(しん)炭材に適した暖帯広葉樹林が広く繁茂していた。こうした林地を樵木山と呼び、ここで生産された樵木は阿波材の名をもって中世以降、徳島や阪神地方の燃料材として重宝がられた。
樵木とは薪(まき)・割木の別名で、榑(くれ)・ボサ・オロ・玉木・ホダ木とも言われ、長さ2尺に玉切にされた。この樵木生産に従事する者は樵木師と呼ばれ、中世以降の樵木林業を支えてきた。
〈注1〉択伐矮林更新法=林地の広葉樹が樹齢15年ぐらいになると、樵木林として伐採する。伐採の方法として、皆伐(かいばつ)矮林更新法(林地の広葉樹の全部伐採)と択伐矮林更新法がある。択伐矮林更新法は、全部伐採するのでなく胸高で直径1寸(3cm)以上の広葉樹を伐木し、1寸以下の木は次の伐採時まで残しておく。伐採率は60〜80%ほどである。ただし伐採・搬出の不便な奥地林は、林地の樹木を全部伐採する皆伐矮林更新法がとられていた。
〈注2〉管流(くだながし)=散流(さんりゅう)・バラ流ともいう。林地で長さ2尺に玉切された樵木を川ぶちに設けた木場(きば)(土場)に集積して乾燥させた後、川に放流、水流を利用して河口の日和佐木場(土場)まで運んだ。この樵木材の流送を管流しという。
〈注3〉木場(土場)=日和佐川に設けられた木場には、山木場と河口木場(かわぐちきば)があった。山木場は、林地で玉切された樵木を川へ放流しやすい場所(何か所か設置)に設けた樵木集積場をいう。日和佐川河口の寺前(てらまえ)の集積場を河口木場といった。
2.樵木林業のあけぼの
1)兵庫北関入船納帳
日和佐川流域の樵木は、15世紀の室町時代から榑と称して板材・樵木の類が京阪方面に移出されていることが、「兵庫北関入船納帳(ひょうごきたぜきににゅうせんのうちょう)」に記録されている。
「兵庫北関入船納帳」は、兵庫の港北関に入港する船に対して関税をとった日記体の記簿である。この記録によると、文安2〜3年(1445〜6)における海部・那賀郡沿岸地方の平島・橘・牟岐・海部・鞆・麦井・赤松・宍喰・甲浦等の港から榑材を積んだ船が、兵庫北関へ146回にわたって入港している。積載量からみて100石から200石程度の船とみてよい。
入船納帳には、次のように記録されている。(一部抄出。海部関係のみ)
文安2年2月3日入
船籍地 積載品目数量 関料納入月日 船頭 船主(問丸)
甲浦 材木300石メ 820文2月29日公方へ 七朗三衛門 二郎三郎
400文受取板料也杉桁10丁也 820文代替2月6日
甲浦 材木120石メ 350文杉桁10丁也 2月9日 技舟 かす200文 二郎三郎
海部 榑180石メ 520文榑5以上 2月12日立用 孫左衛門 二郎三郎
●文安2年10月18日入
赤松海部 榑140石目 400文11月9日 左衛門三郎 藤二郎
由良 榑180石メ クレ210文 内殿へ上立用510文同日 掃部太郎 木や
―略―
●文安2年11月15日入
海部 クレ140石メ 410文11月20日 技舟 孫左衛門 藤二郎
海部 クレ140石メ 400文11月27日 技舟 三郎右衛門 藤二郎
海部 クレ160石メ 445文11月27日 庄官兵衛太郎 藤二郎
2)藩政期の樵木文書
藩政期の林野は、藩主の直轄林(御林)として厳重に取り締まられ、農民による伐採の自由は許されなかった。ただし藩は、農民の生活を支えるうえから、種々の規制をもうけて林野を貸与している。なかでも運上銀または冥加銀と称する税金を納めさせ、材木の伐採を許した渡世(とせい)山・稼(かせぎ)山・野(の)山・入会(いりあい)山と呼ばれた林野があった。こうした林野をとおして樵木の生産が行われていたことが、藩政文書にみることができる。
1
杉桧植付仕置達書
「…此れ海部郡の義は場広の郡柄にて御建材・定請林そのほか検地林(名負検地)を始め取山(稼山)渡世山等の名目にて百姓共所持或は数か所組合(野山)持居り候林野等も多くこれ有り材木を始め炭・薪(樵木)等仕成また里郷の村々灘筋の浦々にても…」とある(天保弘化年間)。
2
樵木問屋申付書
「海郎谷中より年々仕出候、榾材木問屋の儀先年より山師共方より立置来り候処子細之有り当夏以米右問屋裁判の義一旦中絶仕り候処尚山師手支の旨を以先頃願い出…山師共手支に罷成義に候はば我等了簡次第人柄□詮議申し付くべく旨仰せ出され候に付其方共三人右問屋申付け候條古来より勉懸の旨願い相勉べく候…略…」とあり、正徳年間には樵木問屋が誕生し樵木の取引を引き受けている(正徳5年(1715)12月)。
3
申上御受書之覚
「海部郡中出産川下の榑木これ迄九拾歩一銀御役所御取立仰付られ…九拾歩一之儀は郡中当戌年より御取立の儀御指止仰付られ候に付其の段小仕百好共へ申渡候様仰付られ…一統有難く畏れ奉り候…九拾歩一銀先年は之無き処寛政拾弐参年之頃よ召上られ候処此の度より御免仰せ付られ候」とあるように、海部地方で生産された樵木に対して、寛政年度以来九拾歩一銀が課されていたが、文政年度に入って税制が廃された(文政9年(1826)戌4月)。
4
盗木・盗伐に関する達 〈阿波藩民政資料〉
「海部川長諸材木並玉木ほだ木等盗取者これあるに於ては心懸百姓其外何者に依ず見附次第訴人出すべく然るに於ては御褒美銀子拾枚下るべく或は一家の諸役五か年の間御赦免或は盗人控の田地これ有る者三分の一下さるべく…常々油断なく心懸け見付次第御奉行方へ申来るべき事」とある。阿波藩の盗木盗伐に対する厳しい処置がみえる(寛文11年(1671))。
3.樵木林業の盛衰
1)樵木生産時代
樵木の生産は中世以降行われてきたが、明治・大正期の資本主義の発展と都市の拡大にともない、薪炭の需要の増大をきたし、大正初期には1万5千棚〈注4〉の生産を誇る全盛期を迎えている。この生席も、大正期に入って石炭が燃料用として導入されるにともない、表1に示すように、生産は下降して大正末期には1万棚となり、昭和に入ると全盛期の1/3の6千棚の生産量にとどまっている。
こうした生産傾向も、戦中の国家統制と戦時増産体制、戦後の経済復興の波に支えられ、再び脚光を浴び、表2に示すように、昭和20〜30年代には、樵木20〜30万束(そく)〈注5〉・木炭10万俵 (1俵は4貫、15kg)が生産され、総林産額の7割を占め、日和佐川流域の農林家の主要な産物であった。
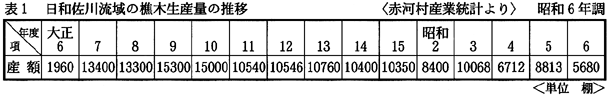

赤河内村役場の調べによると、昭和30年代の農家所得の割合は、林業収人が全収入の61%を占め、農業収入は37%に過ぎなかった。このような傾向は日和佐川流域に限らず、海部郡全域・那賀川上流域山村の実態であった。
〈注4〉棚=長さ2尺の樵木を、高さ、幅ともに5尺に層積した50立方尺を1尋(ひとひろ)といい、これ2尋(ふたひろ)を1棚という。これを4棚並べたものを1椪という。土場(河口木場)においては1椪を単位として積みあげて取引を行った。
〈注5〉束(そく)=樵木材には、8寸樵木・尺2樵木・尺6樵木・長6樵木・長尺樵木がある。尺6樵木は、長さ1尺6寸で、胴径2尺5寸の束を1束という。
2)木炭生産期
海部地方の木炭の生産は、江戸期の文献に見えている。享保の「小川村棟付帳」に「海部郡牟岐浦泉屋庄左ヱ門炭焼目付小屋四軒」とあり、文政11年(1828)の「稼山渡世山樵木伐流許可書」には「相川村笹無谷稼山六百四拾八町雑木伐流炭仕成共…冥加銀五百参拾目…略…」とある。生産量がどの程度であったかは、藩政期は不明であるが、藩直営の製炭と農民による自営製炭が行われていた。製品は、日和佐港より機帆船(30〜40t)によって阪神方面に移出された。木炭には、白炭と黒炭の2種類があった。これは炭窯の構造と製法の違いによるもので、大正時代は白炭の生産が中心であった。
樵木生産が主流を占めていた大正10年代の生産状況は、年間15万貫程度、炭俵(1俵4貫)に換算すると、3万7千俵ほどの白炭の生産がされている。昭和初期には樵木材にかわって木炭の生産量は増加の一途をたどり、昭和30年代には年間生産量は10万俵に達している。これらの木炭は、日和佐の薪炭仲買人であった水口、橋口、森林組合の手によって山元で取引され、オート三輪、トラックで日和佐港まで運搬されて大阪・堺・岸和田・西宮の薪炭問屋に売却されていた。

表3に示したように、樵木・木炭の生産額は総農林産物の7割を占めている。すなわち、昭和30年代の日和佐川流域の林業は、樵木・木炭の生産が主要部門をしめ、農林家の経済を大きく支えていたことが知れる。
「海部樵木林業誌」(平成6年1月海部農林事務所刊)に「昭和35年の赤河内地区の製炭家数は全農家の1/3。林家の4割に当たる173戸が生産に従事し各製炭家とも年間500俵程度の生産高をもち、樵木材とともに農林家の経済を支えた重要な部門であった。」と報告されている。この木炭の生産も昭和35年(1960)以降の高度経済成長とともに、農山村の労働力が2次・3次産業へ吸収され、このころより急速に進んだ燃料革命(石油・ガス・電気への転換)によって、表2のように樵木・木炭の需要は激減し、樵木材は昭和44年(1969)には昭和20年代の1/20の9千束、木炭は1/10に満たない8千俵と衰退し、林業の不振は農林家の生活基盤を根底から揺り動かす結果となる。
3)人工造林時代
樵木・木炭の不振から脱却し林業経営の活性化を図るため、日和佐川流域においては昭和30年後半より杉・桧(ひのき)の人工造林化が進められた(写真2)。その人工造林化の歩みをとらえてみたい。

日和佐川流域の林業の主流は樵木林業であることは今まで述べてきたところで、建築用材(天然林材杉桧栂欅(つがけやき)等)は、表4をみてわかるように、その生産量は限られていた。

第1次世界大戦の好況期であった大正8〜10年(1919〜21)ごろ、1〜2万石の生産を見ているが、大正14年(1925)以降は、3〜5千石に減少し、昭和の恐慌期に入った昭和5年(1930)以降は1千石台にとどまっている。このように、大正昭和の戦前期における天然用材の生産は低調で、農林家は樵木生産を主業としていた。海部川(川上地区)流域の天然林用材の生産に対し、日和佐川流域は全く別の樵木生産を主業としたのである。
この日和佐川流域の人工造林は、明治中期より小規模ながら行われ、大正12年(1923)に176町の植林(官行造林)をみるに至ったが、表5に示すように全林野面積の2.5%に過ぎない。86.2%が天然林で占められている。

昭和に入り、村有林644町の官行造林が行われたが、私有林の人工林化は進まなかった。これも杉桧の植林の適地が少なかったことと、樵木生産で生計が維持されてきた地域性もあった。本格的な植林が始まるのは、昭和35年以降の高度経済成長と燃料革命による薪炭依存から電化時代に入るとともに、樵木林業から杉桧の人工林時代へと林業転換が行われたのである。
日和佐川流域の人工造林の推移を、表6によってとらえてみたい。
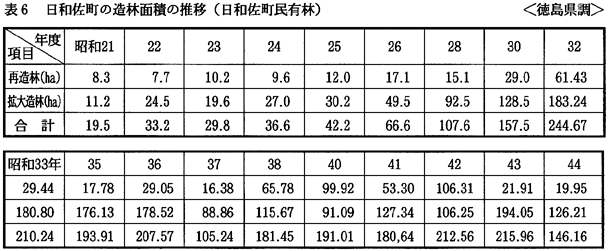
表6でみるように、昭和25年(1950)までは40ha
程度の造林状況であったが、昭和28年(1953)以降、農家経済の向上と木材価格の上昇により植林は急テンポに進んだ。とりわけ拡大造林による新規造林の増加は顕著で、昭和32年(1957)以降5か年間の造林面積は昭和24年(1949)の5倍になっている。
昭和35年以降の木炭・樵木材の低迷衰退と建築用材価格の上昇が、人工林化に一層の拍車をかける結果となった。かくて昭和28年に天然林は約7千町歩あったが、昭和30〜40年代の木材景気に支えられて約3千町歩の人工林野が誕生したのである。平成8年(1996)における人工林化の状況は、私有林8582ha
のうち人工林野は5049ha、人工林率も6割を占め、天然林野は3358ha
となっている(日和佐町農林水産課調)。
このように急速に進められた人工林化の波も、昭和40年代に入り外材(北洋材)の輪入が鰻(うなぎ)上りの増加を示し、昭和45年(1970)には木材総供給量の50%が外材によって占められるに至り、それが内地材の需要と価格の低迷を招き、昭和44年以降人工林化・植林熱は衰え、農林家にとって厳しい年を迎えている。とりわけ日和佐川流域の林業は、海部川流域の林業と比べ、生産に大きな開きが見られる。すなわち、海部川の人工林化は大正時代から進み、高齢人工林野が広い面積を有するのに対し、日和佐川流域は昭和30年代からの人工林のため、伐期に達した林地はごくわずかであり、加えて樵木・木炭の需要の低迷と不振は、日和佐川流域旧3か村の経済生活に大きな影響を与えている。
4.樵木の生産手段
1)択伐矮林更新法
樵木の生産手段において、上灘(由岐・日和佐・牟岐)と下灘(海南・海部・宍喰)地方では異なっていた。すなわち、下灘地方の皆伐矮林更新法に対し、上灘地方は択伐矮林更新法がとられていた。
上灘の日和佐川や牟岐川流域は、択伐矮林更新法の代表的地域である。択伐矮林は、10〜14年ごとに胸高直径1寸(3cm)未満の小径木を残し、それ以上の木材を樵木として採取する。伐採期は、萌(ほう)芽更新を重視する関係から春の木の芽の出る前に切っておくことか大切であり、またそれが良質の樵木材の条件で、秋から冬の伐採が最適期である。
長さ2尺(60cm)に「玉切り」された樵木は、数か月林地において乾燥させた後「木馬(きんま)」〈注6〉によって山木場(写真3)まで搬出する。山木場に集められた樵木は陸送(陸出(かちだし)・カチ)か水運(管流・流し)のいずれかの方法で寺前河口木場(日和佐川河口)まで運び出された。

2)山木場と河口木場(土場)
山木場では、樫類など沈む重量木と軽量木を積み分けて置き、適当な出水をみた時に、先に軽量木を流し、重量木を後に流す。流送途中の数か所の地点に土場を設け、一時この土場に水揚げして乾燥させ、再び放流するという要領で終点、寺前河口木場まで流した(写真5)。

樵木を流送する途中で、一時水中より水揚げして集積する所を土場という。日和佐川には落合(図2)・一番谷・ツバ谷・大越・ウケガ谷・小谷の6か所の土場があった。支流の山河内谷川にも2か所、北河内谷川にも1か所あった。土場〈注7〉は止場の意味で、樵木を乾燥させて流れやすくしたり、不時の洪水の際の流失を防ぐ目的で作られた。
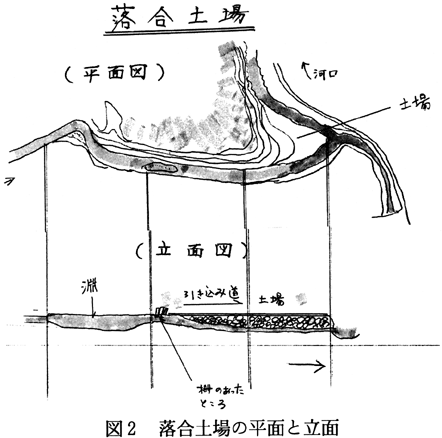
寺前河口木場は、樵木の集材場であるとともに、樵木商人(問屋)によって樵木材の売買取引が行われたところである。
藩政期の日和佐川の樵木は管流が主であったが、大正末期〜昭和初年代は、管流で2/3、陸送(かち出し)1/3の運送量であった。道路の整備にともない、漸次、荷車、大八車による陸送(陸出し)が行われるようになり、昭和に入ると自動車輸送へと移行し、藩政時代から続けられて来た管流による樵木の搬出方法は姿を消して行った。
〈注6〉木馬(きんま)=写真4、略図2を参照。

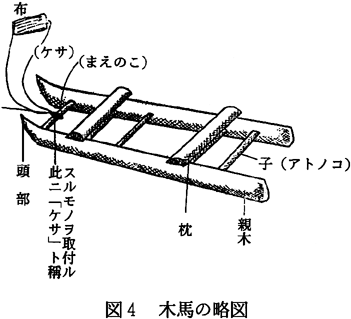
〈注7〉土場(アバ)=丸太材3本を組み合わせて、これに横木を渡し大石を載せて、川の中を斜めに張り巡らせ、浮木(丸太材)を張って流下して来る樵木を集材し、貯木池で管理する設備を総称してアバ(留メ・止メ)という(図3)。
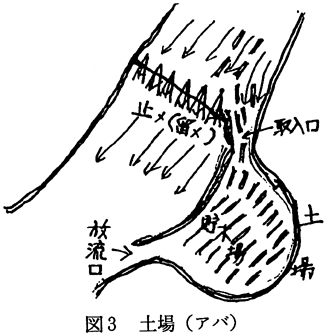
5.樵木商人と日和佐港
1)藩政期の日和佐港
安永5年(1776)の「樵木問屋口銭増額願」のなかに、「海部谷中諸木売問屋正徳年中に私共祖父仰付られ只今迄七十か年程相勉御願を以テ御役並に渡世仕申條偏に有難き仕合に存奉候…」とあるように、海部郡地域の各河川流域の河口では、樵木材を取扱う樵木問屋が大きな実権を握っていた。日和佐川流域の樵木問屋も同様に、日和佐港周辺に軒を並べ、繁盛を極めていた。「阿波淡路の国絵図」(1667〜78)藩主綱道のころの港に関する分野に「日和佐川口北は砂、南は岩船通56間、深さ弐尋余、はへ多く、口悪し常に船出入不自由東南之大風には波高く船出入無之」とある。日和佐港は、阿波藩内の南方廻(かい)船業の1拠点として近世以降発展した港で、漁港としてよりむしろ商港として栄えた港である。
この港を拠点として、藩政期より明治にかけて樵木の生産販売を一手に掌握して来たのが樵木問屋谷屋甚助である。谷屋は庄屋役を兼ね、日和佐川流域一帯で生産される樵木材の販売を引き受けるとともに、名負林(なおいりん)と呼ばれる山林を4〜500町も所有する山林地主であった。
嘉永3年(1850)以降になると、谷屋外8軒の問屋があった。これらの問屋は樵木・木炭・木材・魚貝類を大阪・堺・兵庫に移出し、肥料・陶器・綿・油といった日用品を帰り荷物として積んで帰った。
文久3年(1863)には、高知の赤間・清水方面との樵木・木炭の取引も行い、廻船数も14隻に増加したと日和佐町史に記録されている。文化9年(1812)の日和佐浦棟付帳に廻船の状況が次のように見えている。
・和 吉 7端帆 大阪廻船 壱艘 約94石
・六之助 6端帆 大阪廻船 壱艘 約50石
・貞 七 8端帆 大阪廻船 壱艘 約111石
・吉兵衛 7端帆 大阪廻船 壱艘 約94石
・甚 助 7端帆 大阪廻船 壱艘 約94石
なお、当時の海部の樵木材・材木を扱った問屋が大阪に出店している。正徳年間の「諸国問屋並ぶ船宿」(海事資料叢書8巻)によると、海部郡関係の問屋船宿として次のような名が見えている。
・宍喰 宍喰屋五兵衛 新天ま町
・橘浦 錦屋善市 新大ま町
・梼泊 今津屋四郎兵衛 新大ま町
・木岐阿部浦 今津屋徳右衛門 川丁(かわちょう)
・浅川 南部屋三郎兵衛 川丁
・志和岐由岐 塩飽屋弥兵衛 西浜町
これらの問屋を通じて樵木の移出販買が行われていたと考える。当時、海部郡内には、樵木市場が、日和佐・牟岐・浅川・鞆奥・宍喰の5か所にあった。
2)近代以降の日和佐港
明治に入り、藩有林は民間に払下げられて民有林化が進むとともに、樵木材も、今まで支配して来た谷屋の独占支配体制は崩れ、代わって谷屋に従属していた谷兵吉・太田虎吉・白河虎太郎・白鯛虎吉といった樵木商の台頭によって世代交代が行われた。なかでも、谷兵吉は山河内地域に2千町歩の広大な山林を所有し、樵木の山出し管流を始め、私有の運送船をもって直営による阪神地方との取引を行った。
大正13年(1924)にいたり、「海部山産物同業組合」が設立された。この同業組合は、前述の日和佐を始めとする5樵木市場の樵木の取り扱いや、人夫の雇用、売買の周旋、代金の取立手数料(口銭)の協定などが行われている。樵木代金について、海部山産物同業組合と大阪問屋との間で次のような協定書がかわされている。
◆海部山産物(樵木代金)協定書
1.仕切書 10日以内 即時2割渡し
1.樵 木 3寸口未満 小丸とす
3寸口以上 小丸代金の5掛とす
1.太 丸 2尺5寸廻り(8寸口以上)以上 小丸代金の7掛半とす
1.曲木・あら 小丸代金の3掛とす
1.クサリ木 小丸代金の2掛とす
右の通於鞆奥町大阪薪炭問屋代表員と協定即時実行可申候也
大正13年9月8日 海部山産物同業組合 ■
なお、山産物同業組合の調査書によって、表7に示すように、大正・昭和初期における日和佐川流域の樵木商人及び樵木海上輸送船舶保有数・樵木生産状況を知ることができる。
日和佐川流域は延長距離も短かく、樵木の流送も容易で、海部川などと異なり、生産運搬費が軽微ですむことができた。ために他地域に比して有利性をもっていた。日和佐川の樵木は、長さ2尺の樵木を、高さ幅各々5尺に層積みにした50立方尺を1尋として、これ2尋を1棚とする量目で、大阪・堺の樵木商と取引を行っている。
このころの阪神地方の仕向先樵木問雇は、表8に示す通り、大阪の7店を始め15店に及んでいる。

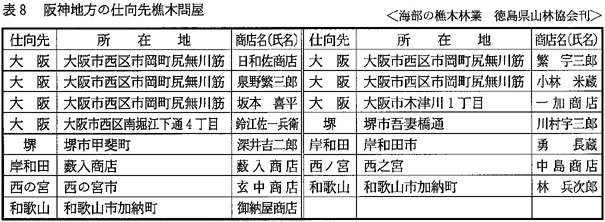
大正期の全盛期に引き続き、昭和初期・第二次大戦後における日和佐港の主要貸物の移出状況をみると、移出総数の大半が、日和佐川流域旧3か村で生産された木材・板材・樵木材・木炭等の林座物で占められ(表9、10)、日和佐港は商港としての機能をになっていたことがわかる(写真6、7)。
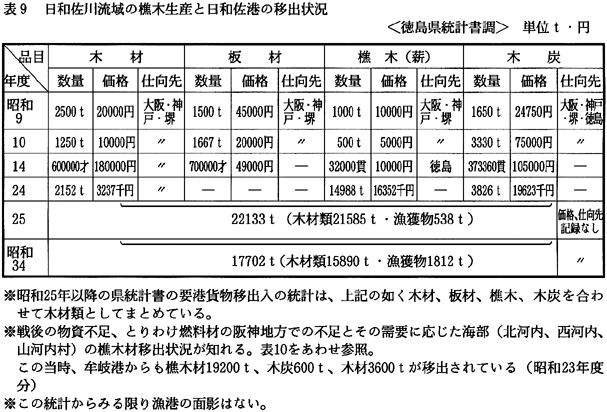
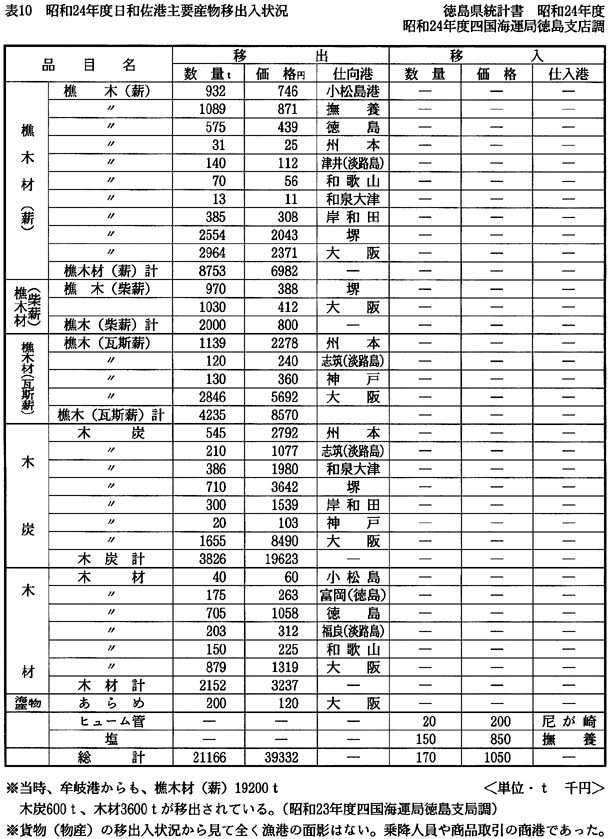
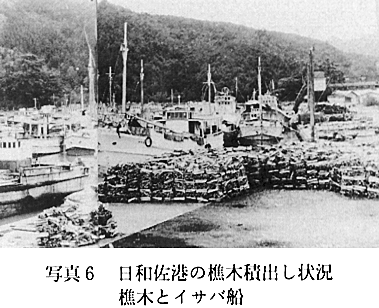

藩政以降、昭和の第二次大戦後(昭和35年の高度経済成長期に入るまでの間)までの日和佐港は、日和佐川流域の樵木材で支えられ、流域の樵木農民も樵木材の生産に従事することによって、安定した農家経営が維持されてきたのである。
6.雇われ兼業−樵木の里
−林業の活性化ははたして−
表11の1・2・3表にみるように、文化9年(1812)以降、昭和30年(1955)までの約140年間の戸数・人口は、670戸、3800人前後と大きな変動もなく、樵木材を生業とする林業経済の安定した平穏な村であった。それが4・5表でみるように、昭和35年以降の日本経済の驚異的発展・高度経済成長とともに起こった燃料革命(石炭石油・電力化)等による。木材景気の低迷と樵木材の不振は、日和佐川流域旧3か村の住民の生活が根底から揺れ動く要因となった(表1、表2参照)。
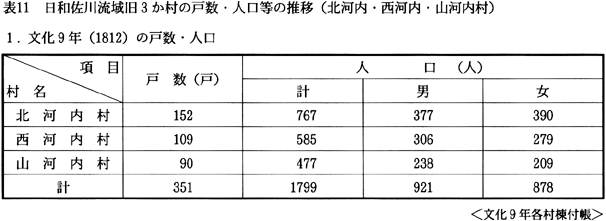
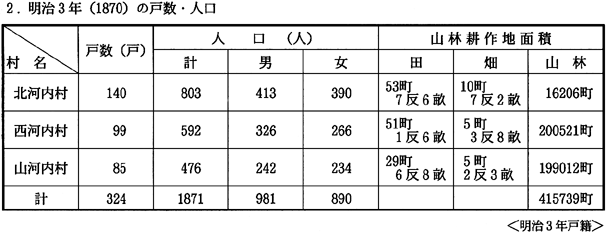



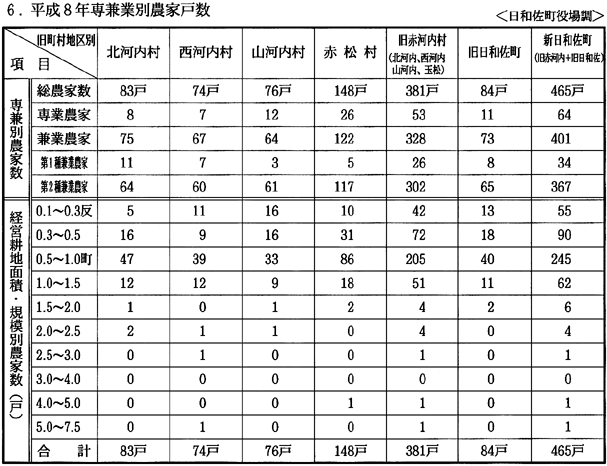
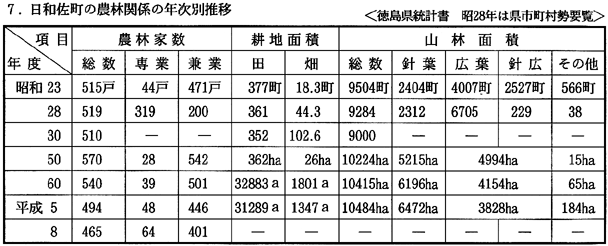
樵木林業の不振は、林業労働から外れて第2次・第3次産業部門に労働力を提供することによって、流域住民が生計を維持するという「雇われ兼業」時代を迎える原因となっている。
昭和34年(1959)の農林業センサスでは、雇われ農家は164戸であったが、昭和40年代の木材価格の低迷と林業不振期に入ると、表12にみるように昭和40年(1965)に413戸(65.7%)と全農家の2/3に達し、昭和45年(1970)には全農家数の81.1%の481戸と増加を見せている。しかも、やとわれ兼業種別では人夫・日雇・出稼といった不安定な兼業である。
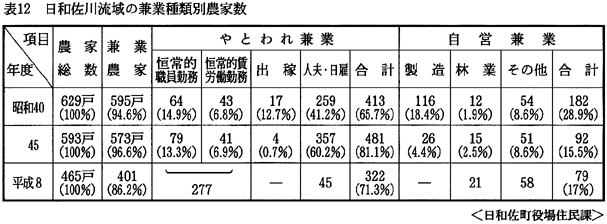
平成8年に入ると、農家総数も昭和40年の629戸から465戸と164戸の減少を見せている。
日和佐川流域は林業を除いて労働力市場はなく、有利な兼業機会に恵まれていないため、樵木林業・木炭生産を奪われた農林家にとっては、不安定な兼業への就業はやむを得なかった。なお、不安定兼業の大部分を占める人夫・日雇の7割が、林業賃労働従事であった。
また、昭和40年以降住みなれた村を離れ、都市の第2次・第3次産業労働者となる離農・離村による流出が相ついで、村の過疎化現象に拍車をかけている。
日和佐川旧3か村の農家戸数・離村者数は、徳島県全体の減少率を上回り、表11の3・5表でみるように、昭和30年の戸数675戸・人口3800人が、平成8年には人口2537人と約1300人の減となっている。しかも高年齢化が急速に進み、65歳以上が687人、全人口の27.6%を占める状況となっている。また図5でみるように、昭和35年の農家数656戸が、平成8年には465戸と減少、毎年20〜30戸の農家が減少している。
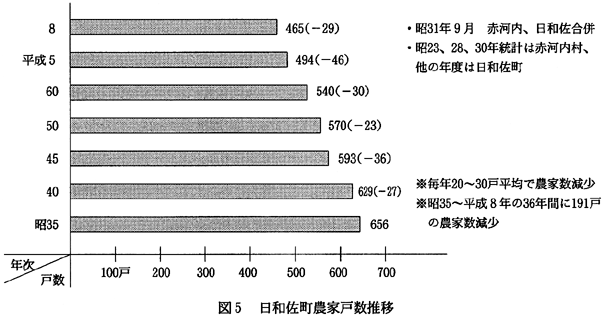
このような人口の流出と若者の離村による村の過疎化・高齢化現象が大きく、これからの町の課題として、また行政施策として、その対応が求められている。
日和佐川流域旧3か村の労働力は、地域の自然環境より考え、林業対策を切り離しての対応は考えられない。
労働力を林業に定着させるためには、労働者の雇用の安定と労働者の所得の増大が実現されない限り、日和佐川流域旧3か村の過疎化の歯止めは無理であろうということを、実地踏査をとおして強く筆者は感じとることができた。
今、町がかかえる課題の解決は、いつにかかつて林業の活性化と農林家の労働力の安定化にあると言って過言でない。