由岐町における古文書、石造文化財について
郷土班(阿波郷土会)
真貝宣光・柳田清・佐藤嘉隆・石川重平
1 はじめに
今度の総合学術調査において、郷土班は由岐町に残る古文書と石造文化財の調査を実施した。
古文書調査は、町史編纂室の全面的なご協力を頂き円滑に進めることができた。そして、調査テーマとして「由岐町と九州とのかかわりについて」「桜間の大石海上運搬等について」「ノース・アメリカン号難破事件」を選び、関連資料の収集、聞き取り調査を行った。「由岐町と九州とのかかわりについて」は、棟付帳の記載以外直接的な史料が全くなく、「なぜたくさんの人が薩摩へ赴いたのか?」という基本的疑問すら解明できず、問題提起に終わらざるを得なかった。「桜間の大石海上運搬等について」は、由岐町には未発掘の資料が残存するに違いないとの希望的観測を基に、調査に着手したが、「これは」といった史料を見いだすことができず、既存の史料を用いての記述にとどめざるを得なかった。
また「ノース・アメリカン号難破事件」は、聞き取り調査、史料調査により大きな収穫を得ることができた。特に、同事件を調査するには欠かすことができない第一級の史料である、「外交文書」の提供を受けた。しかしながら余りにも字数が多く、この報告書に史料として活字化することはできなかった。興味を持たれる読者は、『ふるさと阿波 157号』(平成5年12月刊)に、救助功労者に日本政府より贈られた紅綬褒章、アメリカ合衆国大統領より贈られた救命銀牌の写真とともに、「ノース・アメリカン号難破事件関係文書」として全文掲載しておいたので、そちらを参照頂きたい。
石造文化財調査については、由岐町には多種、多彩、かつ貴重な石造物が存在し、調査・報告対象の選択に苦慮したが、当報告書では、真福寺の宝篋印塔、由宇の九州型板碑、東由岐の康暦2年の板碑、阿部寺谷の近江式宝篋印塔、木岐の弘治3年銘の五輪塔の5件にしぼり、解説を加えた。
以下、それぞれのテーマについて報告する。
由岐町と九州とのかかわりについて 真貝宣光
棟付帳、検地帳の類は県内各地に数多く残されていて、近世史研究の第一次史料となっている。由岐町役場にも、管内に属する藩政期の村浦の棟付帳、検地帳が相当数収蔵されている。本稿で取り上げたのは、寛文12(1672)年11月7日に棟付改めが行われ、延宝2(1674)年12月28日に清帳された『海部郡之内西由岐浦棟附人改御帳』である。筆者はしばしば県内各地の棟附帳を見る機会を得ているが、西由岐浦のそれは実に特徴的な内容を含んでいる。すなわち、「さつまへ参り居合不申候」と右書された人物が多く見受けられることである。そして当時の西由岐浦の世帯数127戸のうち22戸から、都合32人が薩摩に渡っていることが判明するのである。本稿では、『西由岐浦棟附人改御帳』(以下「西由岐浦棟付帳」と記す)の分析を中心に、由岐町と九州のかかわりについて述べてみたい。
まず「西由岐浦棟付帳」より、加子本役 八右衛門家とその小家についての記載部分を資料として掲げる(図1)。
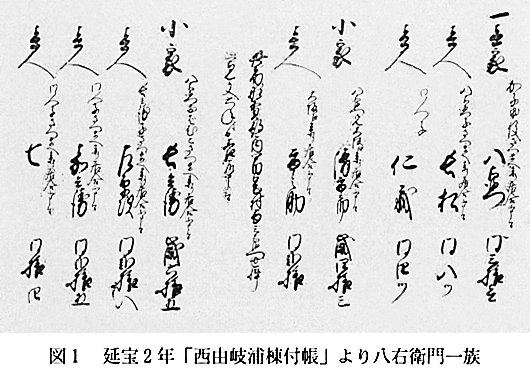
図1にみられるように、壱家 加子本役 八右衛門家にあっては、当主の八右衛門(31)はその子長松(8)と共に薩摩に渡っていて、村に残っているのは仁蔵(4)だけである。そして、八右衛門の兄で分家していた清市郎家は、当主清市郎(43)が養子の市之助(20)と共に大坂へ出ていて、八右衛門家のもう一つの分家である長兵衛家(八右衛門のおば婿)からは、当主の長兵衛(65)とその子左平次(28)、嘉兵衛(25)、七(14)の3人が、薩摩に赴いている。すなわち、八右衛門家は4歳の仁蔵を残し薩摩へ、清市郎家の男2人は大坂へ、長兵衛家の男4人はすべて薩摩に行っている。八右衛門一族でみると、男9人のうち、西由岐浦に残っているのは4歳の仁蔵一人ということになる。延宝期の棟付帳という性格上、女性についての記載がなく、推測ではあるが、祖母、母、妻、姉妹等の女性が、男たちの留守をまもり、男は生活の糧を得るため、他国へ稼ぎに出ている構図が浮かびあがる。
「西由岐浦棟付帳」によると、西由岐浦の棟数(戸数)は127戸で、人数は302人(女性を除く)である。田畠はごく少なく、高にして28石9斗(約3町歩)しかない。そして高(田畠)を所持する家は、庄屋役を勤める安右衛門家(高22石余)と、年寄役を勤める弥右衛門家(高1斗余)の2軒であり、他は、漁業、商い、手職、出稼ぎ、賃稼ぎ等で生計を立てざるを得ない土地柄であることが理解できる。
「西由岐浦棟付帳」を分析し、作表したものが表1〜表4である。表1は村の壱家、小家の構成であり、表2は当主、あるいは家族が国外に出ている家の行先別数をあらわし、表3は一家の大黒柱である当主が国外に出ている家について行先別数を作表した。表4は国外に出ている人の年齢区分である。最年少者は8歳、最年長者は65歳であり、ともに薩摩に行っている。
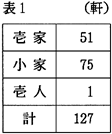
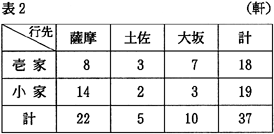
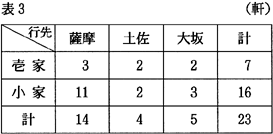

若干の説明を加えると、西由岐浦から大坂へ出ている者は11人(表4)であるが、1軒から2人出ているのは清市郎家だけである。また土佐に出ている者は6人(表4)であるが、1軒から2人出ているのは1軒である。薩摩には32人(表4)が出ているが、1軒から1人が14軒であり、2人が7軒、4人が1軒(長兵衛家)である。また、表1〜表4により、西由岐浦から国外に働きに出ているのは、総戸数127軒(表1)のうち37軒(表2)からであり、その中には一家の当主が働きに出ている家23軒(表3)が含まれている。人
数でみれば、総人口302人(女性を除く)のうち、49人(表4)が国外に出ていることがわかる。そしてその65%余にあたる32人(表4)の行先は、薩摩なのである。
江戸時代初期に属する延宝2年(1674)に、“なぜ薩摩へ…”“薩摩のどこへ…”“薩摩まで何の為に…”という疑問が生ずるところであるが、この一番重要な問いに明確な解答を与え得る史料を、筆者は持ち合わせていない。本稿が「延宝2年現在において西由岐浦から薩摩に32人もの人が行っている」という事実関係の発表にとどまらざるを得ない理由である。しかしながら、この3点の疑問を避けて通る訳にもいかないので、断片的な資料を用い、筆者なりの推測を加えてみたい。
まず“なぜ薩摩へ”との疑問であるが、由岐と薩摩は、黒潮を利用した海運により、交流が行われていたのではないかと考えられる。貞応2(1223)年に定められた「廻船定法之事」という古文書によると、薩摩坊之津、土佐浦戸、兵庫(現・神戸)を結ぶ海運の大動脈が鎌倉時代初期には存在し、由岐は天然の良港であり、かつそのルート沿いに位置している。あるいは寄港地の一つとして存在したのかも知れない。だとすれば、この頃には薩摩との直接交流も行われ、その交流が中世、近世と継続され、由岐の人々にとり、薩摩はその距離に比して案外身近な土地であったとも推測される。
石造文化財の項で取り上げられるが、東由岐の由宇に、石材、型式の一風変わった板碑が建立されている。九州の日向、大隅、薩摩を中心に分布する、典型的な九州型板碑であり、徳島県内では唯一のものである。安山岩で作られており、鎌倉時代末期から南北朝時代に製作されたものと考えられる。九州型板碑の存在は、これもの地域と由岐に人的、文化的交流があった証左であろう。
“薩摩のどこへ”との疑問であるが、由岐町木岐の蒲生忠雄家に、江戸時代中期以降に書写されたと考えられる家系図『蒲生氏家系』が伝えられている。その記載事項から九州、薩摩に関係する個所を抽出すると、次のごとくである。

上記略系図にある弥三郎の左書に「蒲生弥三郎ト称ス 室ハ赤松邑岡久氏ノ女一男ヲ生ム後九州ニ赴キ遂ニ消息ナシ」(傍点は真貝。以下同)。三郎兵衛の左書には「蒲生三郎兵衛ト称ス父三平死後延命寺ニ養育セラレ生長ノ後兄弥三郎ヲ尋九州ニ赴キ是亦便宜ナシ」。久三郎の左書には「蒲生久三郎ト称ス父弥三郎万治三年八月十七日ヲ以九州ニ赴キ久三郎三歳ノ時ナレハ母ニ養育セラレ生長ノ後両度九州ニ赴キ父ト叔父ヲ尋タレトモ卒ニ行方知レス薩州コシキノ島竹中長五郎ト申ス浪人ノ家ニテ逗留イタシ帰国ス享保十七(1732)年八月廿二日卒ス行年七十六法名楽岸浄全 室ハ志和岐浦藤野氏女ナリ」とある。また千右衛門の左書には「幼名千之助後千右衛門ト改ム幼年之時久三郎ニ従ヒ九州ニ赴キ薩州コシキノ島ニテ逗留イタシ後父久三郎ト共ニ帰リ家名ヲ継ク元文三(1738)年午三月廿五日卒法名 春澄浄覚 行年五十一 室ハ志和岐浦藤野氏女ナリ」と記されている。
これらの記述が事実だとすると、弥三郎が万治3(1660)年に九州に渡って以来、弥三郎の弟三郎兵衛、子久三郎、孫千右衛門が九州に渡ったことが明らかであり、そしてその場所は薩摩のコシキノ島である可能性が大きい。コシキノ島とは現在の鹿児島県薩摩郡甑(コシキ)島列島であり、上甑島、中甑島、下甑島の三島を中心として形づくられている。甑島は、古く『続日本紀』に宝亀9(778)年11月に遣唐の第4船が薩摩国甑島郡に来泊した旨の記述がされている。上甑島の中甑に甑(セイロ)の形に似た巨岩があり、これを神石と尊崇して甑島大明神と称し、甑島の名はこの巨岩に由来するという。
近世甑島は密貿易の基地として栄えたと伝えられてはいるが、基本的には漁業、水産業を中心とする島である。蒲生家の弥三郎、三郎兵衛、久三郎が九州、甑島へ渡った時期と、西由岐浦の32名が薩摩に出かけている時期が一致することから、西由岐浦の村民も甑島に赴いたのではないかという推測がなり立つであろう。
では“薩摩まで何の為に”という疑問の解を、西由岐浦の住民が甑島へ赴いたという仮定に立って推測すると「甑島では江戸時代中期からイワシやマグロ漁が盛んに行われた。特に寛文年間(1661〜1673)と元禄・宝永(1688〜1711)の頃は、鹿島(下甑島)を中心に全島にわたってイワシの大漁が続き、世に『イワシ世間』と称せられる黄金時代を生んだ」という『鹿児島県地名大辞典』(角川書店)の記述がヒントになる。西由岐浦の人々も、出稼ぎとして甑島に渡り、大漁が続くイワシ漁に携わっていたのかも知れない。だとすれば、蒲生家系図から薩摩行きの記述がなくなり、文化九年の西由岐浦棟付人数御改帳に薩摩との関係が全く見られなくなることとも符合する。恐らくは、甑島でのイワシの大漁も宝永期に終わりを告げ、出稼ぎに出る魅力がなくなったものであろうと推測する。また「西由岐浦棟付帳」に、「かたぎ商人」(天びん棒で物を担い、行商する商人)を生業とする家が三軒存在する。このうちの一人次郎兵衛(65)は、子の八十郎(31)と共に薩摩に赴いている。親子共、他の西由岐浦の村民と一緒にイワシ漁に携わっていた、と推測するのが自然ではあるが、あるいは彼地でかたぎ商いを行っていたかも知れない。由岐町阿部の“いただきさん”は、岡田一郎氏の研究等により広く知られているが、同じ行商でありながら、「かたぎ商人」の歴史、民俗的研究は全くなされていないようである。延宝2年の棟付帳に、「かたぎ商人」の肩書が出(図2)、第二次大戦後まで存在したのであるから、その実態を調査研究することが今後の課題であろう。
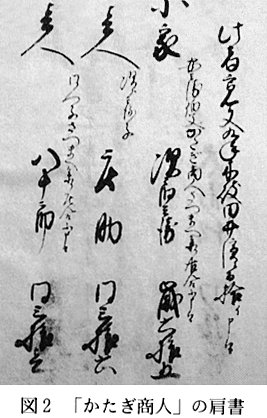
以上、今から320年前に調製された「西由岐浦棟付帳」を素材に、“薩摩に参り居合不申候”(薩摩に参り居(お)り合(あ)い申さず候)と右書のある32名が“なぜ薩摩へ”“薩摩のどこへ”“薩摩まで何の為に”行ったのか、という観点から私見を述べてきた。結論的に記すと、「中世以来交流のあった薩摩の国の甑島で、イワシの大漁が続いているというので、大挙して出稼ぎに行った」ということになる。もとより明確に結論も得る史料を見いだすことができなかったために、二次、三次的資料を用いての結論である。確信が持てないことはいうまでもない。
「由岐町と九州とのかかわりについて」と題すると、まず由岐町漁民による五島、東シナ海漁場の開拓が思い浮かぶ。明治21年に西由岐浦の石垣弥太郎(1861−1933)が博多沖に出漁し好結果を得たことに触発された近隣漁民が、弥太郎に追随し、段々と盛況に至り、大正中頃には、五島列島の玉之浦漁港は阿波出漁団の手によって日本一の漁港になったという。この間の事情については、『由岐町史 上巻 地域編』(昭和60年刊)に詳述されているので本稿では割愛したが、東シナ海における彼等の活躍の基盤、ルーツは、「西由岐浦棟付帳」の記述からすると、江戸時代初期に遡る可能性が高いと考えられる。
史料紹介、問題提起の域を出ない報告となったが、今後も引き続き調査を進めたいと考えている。新しい史料の発掘等により三つの疑問点が解明できたなら、再度稿を起こしたいと考えている。
ノース・アメリカン号難破事件 佐藤嘉隆
四国を襲った台風のため、明治25年7月23日志和岐で起こったノース・アメリカン号難破事件で22人の乗組員が地元住民の決死的努力により救出された事についてはあまり知られていない。また記録としても、明治31年9月に如瑩生が聞き書きした『米国船救助之記』と、当時の徳島日日新聞、徳島県と外務省・アメリカ公使館との往復文書(以下「外交文書」と記す)が残っているぐらいである。遺物として残っている物も年と共に少なくなり、また地元でもこの件について話せる人が少なくなって来ているので、ノース・アメリカン号難破事件について既略を記す。なお紙面の都合上、年表仕立として報告する。
明治25年7月21日 米国ワイタアク会社の商船ノース・アメリカン号(1520トン)は、樟脳、樟脳油、陶器類、雑貨類を積んで、午後11時、ニューヨークに向かって神戸港を出航。(米国船救助之記・外交文書)
同 7月22日 午後5時頃から暴風になり、同6時頃に日ノ岬沖合670海里で帆が暴風のため破られ、漂流を始める。(外交文書)
同 7月23日 午前7時頃陸地に近寄り、午後9時頃海部郡三岐田村(現在の由岐町)大字志和岐字田井ケ浦荒磯上へ乗り上げ、船が傾斜した(図3)。この時コックの中国人「アバーオ」が甲板から高浪にさらわれ行方不明となる。乗組員はマストにのぼり、救助を求め、やがて村民の発見するところとなったが、高浪のため近づけず、船中より綱を流して陸地からは竿でとり、その綱を木の根とマストに結束して、一人ずつ救助した。日本語の話せない15人は、荘厳寺に日本人通訳と止宿した(図4)。その他の者は網元宅などへ別かれ止宿した。(米国船救助之記・外交文書)


同 7月24日 海部郡長・警察署長が県庁へ朝第一報、夕方第2報を発遣する。(外交文書)
同 7月25日 24日の第一報が桑野が洪水であったため夜の11時県庁に到着。(米国船救助之記)
同 7月26日 24日の第2報が朝県庁に到着し、難船の事実を知った徳島県知事は至急電報で外務大臣に事件を伝える。(外交文書)
同 7月27日 合衆国公使館書記官へ難船の詳報を外務省政務局長が報告する。(外交文書)
同 8月2日 兵庫県知事より外務大臣へ外国船遭難の件に関し保険会社関係者2名の外国人内地旅行の許可につき問い合わせる。(外交文書)
同 8月10日 特命全権公使フランク・L・クームスが外務大臣に徳島県ならびに救助者に対し謝意の伝達を要請する。(外交文書)
同 9月27日 米国国務大臣ジョン・W・フォスターから在東京特命全権公使フランク・L・クームスにノース・アメリカン号難破の際、志和岐の人々が勇敢慈善なる処置をした事を報告書で知ったので、村民の称誉すべき行いに対して350ドルを贈るが、使い道については村民が漁船・漁網及びその他の漁具、またその職業の助けとなる品々を買入れるように、また日本政府に良い考えがあれば指導して下さいと問合せるように、さらに特に我が身の危険を顧みずに救助に尽力し、最も功労のあった人の姓名を彫刻した救命銀牌を贈るので、その姓名を日本政府に問い合わせるように訓令あり。(外交文書)
同 11月21日 外務大臣から徳島県知事に、350ドルの使い道については難船者救護に尽力した者に最も有益な方法で使用するのがよいので、同人等及び村長の意見を聞いて使用法を決め、外務省へ報告するように、また救助に関して特別に功労のあった者の姓名も併せて報告すること、が通達される。(外交文書)
同 12月9日 徳島県知事より外務大臣へノース・アメリカン号難破の際志和岐村民等が救助した件について、米国公使より救護に尽力した者へ米金350ドルを贈るとの知らせがあった件につき、使用方法は救助に従事した者及び村長の意向を聞き、各自に分配せず、漁船漁具を購入する共有資本として保存し、利殖を図ることとしたことと、救護につき特別功労のあったものの氏名を以下の通り報告する。(外交文書)
海部郡三岐田村志和岐浦村
松田益太郎 松田 勘吉 濱本兼太郎 谷脇 磯吉
押上 松藏 吉田島次郎 松本善三郎
三岐田村長 村上 新平
同・書記 宮脇豊太郎
同 12月29日 米国政府より贈られた350ドル(円換算520円余)を志和岐浦総代春木忠次郎以下19名が代表で受領する。(外交文書)
明治26年11月30日 米国商船ノース・アメリカン号難破の際救助した人々に、米国政府より外務省を通じ、徳島県に救命銀牌を転送してくる。
同 12月 救命銀牌を本人に交付(外交文書)
明治27年1月11日 外務大臣から合衆国特命全権公使エドウィン・ダンへ、救命銀牌贈与につき謝意を表する書簡を送り、前徳島県知事関義臣よりの謝状写1通、領収票10枚を同封する。(外交文書)
同 7月20日 人命救助に特に功労のあった5名に日本政府より紅綬褒章が贈られた。
紅綬褒章受賞者氏名
志和岐浦村140番屋敷 橋本益太郎(旧姓松田)
187番屋敷 松田 勘吉
146番屋敷 濱本兼太郎
12番屋敷 谷脇 磯吉
田井ケ浦134番地 押上 松藏
(善行録 明治41年 徳島県)


おわりに
この稿を終わるに当たって、資料の提供をいただいた町史編纂室の先生方、荘厳寺住職夫人の宮本敬子さん、地元の丸田好子さん、志和岐漁業協同組合長の川西さん、又現場へ案内してくれた志和岐の皆様方に深く感謝申し上げる。
参考資料
・米国商船ノールス・アメリカン號難破乗組人徳島縣下へ漂着之件(明治25年7月 外交文書)
・米国船救助之記(明治31年9月 如瑩生記)
・徳島日日新聞(明治25年7月24日)
桜間の大石海上運搬等について 柳田 清
桜間池石碑は、今名西郡石井町高川原桜間字池田に建つ。
文政年間第12代藩主齊昌が、ある日江戸城殿中において、扶木和歌集之懐中抄に「鏡とも見るべきものを春来ればちりのみかかる桜間の池」と詠まれている名所桜間池のことを聞かれたが、即答できなかった。そこで参勤交代を終え帰国してから、名東・勝浦郡代太田(武市)章三郎、御作事方長浜文兵衛に調査を命じた(粟の抜穂)。
文政11(1828)年7月25日
両人、芝原村秋田忠助方へ出張し、近郷の庄屋に桜間池の伝承を聞き、場所を名西郡桜間村の桜間池と決める(桜間池原由抄)。後、桜間の池を永久に顕彰するために池を整備し、小山を築き、その上に壮大な碑石を建設した。その碑石は、海部郡西由岐浦から東由岐浦(現由岐町)への飛入地であった由宇の海岸、通称まわりが鼻を回った小島の磯に、雌雄一対の鏡石と称する名石があり、その内の雌石をあてた。これを小山の上に建てると、その形があたかもヒキガエルが座っているのに似ているので、俗に蛙(かわず)石といわれるようになったという。(三岐田町史他)
文政11年8月28日
太田章三郎・長浜文兵衛両人命を受け、碑石としてこの巨石の採用を決める(碑陰文)。
この石は小島の磯のワラウチの浜波石の近くにあったのを採ったもので、今なお近傍にはクヮンカケ波石、ロクロ波石等と呼ばれる岩礁が残されており大きな仕掛けであったと考えられる(三岐田町史)。この石は長さ2間半、幅9尺、厚さ8尺、重さ2万貫あった(元木家記録、他)。

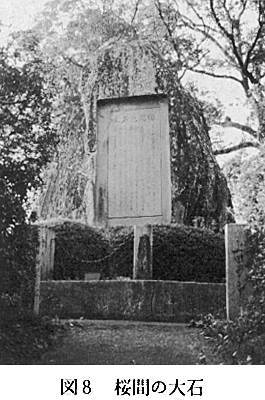
文政11年11月2日
起程(碑陰文)。この巨石を筏に載せて、千余個の浮桶(四斗樽)で海上に浮かせ、三千余隻の引船で三千余人の引夫に引かせた(粟の抜穂)。
文政11年11月中旬
那賀郡中島沖で颶風のため巨石が海中に落ち込む。夫より五百石積之船弐隻四斗樽五百挺つける(元木家記録)。
文政11年12月上旬
勝浦郡和田沖(現小松島市)で颶風のため浮き樽が切れ又々落ち込む。地方(じかた)より沖合六丁半の処(年々諸事控)。しかし海底沼深く、なかなか引き揚げることが出来なかった。
そこで長浜文兵衛は国中の鍛冶を集め、年明け迄色々工夫を凝らし、取道具を考案し、鋏の長さ3丈、柄の長さ7丈の釘貫のような大鋏二つと、長さ5丈の鉄帯に紐釦のような細工をしたものを作り、巨石に鉄帯を取り付け、この石の上で筏を組み、筏が巨石で安定するように鉄帯に固定し、二つの大鋏を筏の左右から落とし込み、巨石を挟み数千本の松丸太を組んで引き揚げた(年々諸事控)。浮桶一千有余、引船三千余隻、引夫六千余名を要した(碑陰文、桜間池原由抄)。
この事に関し桜間池原由抄は「海底沼深き故海士の人夫甚だ困り、既に人命を失う者有し故海中にて自由ならず。」また「左あれば二臣殆ど困却に至り黙然たり。然るに不計心付今や神国の一派照らさんと海中に入りて身を清め、心中には赤心を凝て神徳を祈り奉るに、翌朝に至るに海上の波淳然として海中明鏡の如し。神教の誠に至則は神の如しとは是ならんや。」と記している。太田・長浜両人の心労、また現場の人夫たちの苦労は計り知れないものがあった。そしてあまりの厳しさに、最後は神仏の加護に頼るしかなかった。
三岐田町史に「西由岐浦の大黒屋庄右衛門が頭となり志和岐浦から弥右衛門(多賀安蔵祖父)貞右衛門(玉野長太郎祖父)外一名が潜水夫となって出たが寒中の事であったので一潜りしては火に温まりしながら任務を果たした。其の後孰れも褒賞に預かった」(史料3参照)とある。また大黒屋庄右衛門に対する口碑伝として「彼の桜間石を運搬中落し沈めた当時に命に応じて習覚えた三十八結を応用して成功した。」とあり、海士の大活躍があった。
文政12年11月14日
漸く三日の間海中は晴天であったので、所願円満に至り恙なく別宮川口鬼門堂に着く(桜間池原由抄)。
ここに起程から1年。海上15里颶風のため2度の漂没に遭った海上輸送は終わる。造用金1万両を要したと伝えられる(元木家記録)。それから2年間、別宮川口に置かれ、その間、碑の表面の建碑の趣旨を屋代弘賢が和文で、裏面に海上運搬の辛苦を柴野碧海が漢文で記し、斉藤惟裕が碑文の彫刻をした。
文政13年3月21日
長浜文兵衛ならびに絵図師同勢8人桜間迄の引き場所を検分。(桜間池原由抄)
天保2年10月3日
再起程(碑陰文)。大岡より鬼ケ崎まで川筋を運び、それより地方に引き上げ高崎―南新居―岩延―桜間と陸路4里を運搬する。(元木家記録)
天保2年12月1日 桜間の新築山の上に大石が引き上げられる。(桜間池原由抄)
天保6年6月25日 藩主斉昌御出 桜間の新築山で盛大に上棟式が挙行される。(桜間池原由抄)
となるが、陸上運搬については、紙面の都合上省略して、若干の史料を掲載する。

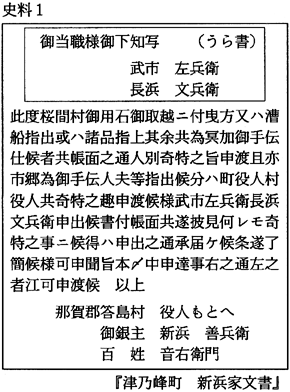
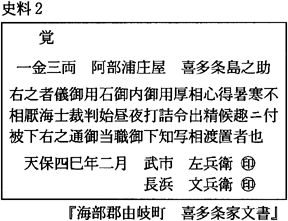
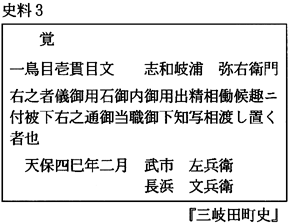
参考史料ならびに文献
・粟の抜穂人の巻(飯田義資著)
・桜間池原由抄(石井町桜間 清水家蔵)
・碑陰文(碑石裏面の銘文)
・三岐田町史
・元木家記録(石井町高原元木家蔵)
・年々諸事控(鴨島町牛島 藤井家蔵)
由岐町の石造文化財
1.真福寺の宝篋印塔

宝篋印塔とは、一切如来心秘密全身舎利宝篋印陀羅尼経を納めた石塔のことで、我国では、平安末期から鎌倉時代に現れる石造供養塔である。木岐真福寺東側山ろくに宝篋印塔がある。材質は凝灰岩で、河内国二上山産の白色の軟らかいものである。この石材は、鎌倉時代から、南北朝時代の石塔や石仏に広く使用された。この宝篋印塔は俗にヨリマサさんと呼ばれ、治承4年(1180)4月9日、以仁王を奉じて平氏討伐の檄文を出した源三位頼政の供養塔と言われている。源三位頼政の子孫(多田源氏流)が、鎌倉時代に北条氏に追われ、この地に落ちてきた。その子孫である浜氏が、その祖先のために建立した供養塔とも言われている。『阿波志』に「源三位祠真福寺にあり、けだし、木岐氏等置き以て其祖頼政を祀る」とある。また、『阿州古城諸將記』には、木岐城に「木岐太膳太夫正時、源姓、紋矢筈車、添紋四連銭、馬印幕紋竹丸、百五十〆、浜氏日和佐氏ノ正統、源三位頼政ノ孫仲綱ノ子伊豆右衛門尉有綱守護職トナリテ正持マテ相続」と記している。以上のごとく『阿波志』にも、『阿州古城諸將記』にも源三位頼政の名がみえる。
この宝篋印塔については、笠井藍水の『三岐田町郷土読本』(昭和25年2月刊)に、15分の1の実測図が載っている。今度阿波学会が由岐町の総合学術調査のため解体実測を行ったが、笠井氏の実測図と異なっていることがわかった。笠井氏の実測図では、笠の段丘が3段になっているが、写真で見るごとく段丘は5段であり、笠の幅は基礎の幅とほぼ同じ51cm
で、軒の厚さ8.5cm、1段目の高さ5cm、2段目は4cm、3段目から各段とも3cm である。笠の底部に幅18cm、深さ8cm
の穴をあけ、塔身の中央に幅15.5cm、高さ6.5cm の突起を作り出し、笠の穴に挿入している。笠の上端には幅18cm、深さ8cm
の穴をあけ、九輪の露盤を差入れている。このような宝篋印塔の様式は、石田茂作博士の宝篋印塔の発展形式によると、全階式宝篋印塔と称し、鎌倉矢倉発見の、宝治2年(1243)の古式な様式によく似ている。今度の解体実測により、今までは、鎌倉末期か南北朝時代の造塔といわれていたが、形態様式の上から見て鎌倉初期か中期を下るものではないと確信した。今まで言われている源三位頼政の供養塔としても、頼政の没年とあまり年代の差はないものである。
今度の解体実測に協力して下さった、地元の蒲生忠雄先生や真貝宣光・柳田清両先生に御礼申し上げる。
2.由宇の九州型板碑
東由岐由宇の山林内には九州型板碑がみられる。
日本の板碑には、四つのタイプがあり、大分県を中心とする九州型板碑、徳島県の吉野川下流を中心とする阿波型板碑、阿波型板碑と形態がよく似ている埼玉県を中心とする関東型板碑、宮城県あたりに分布している東北型板碑。この四つの形式に分けることができる。阿波型板碑と関東型板碑は材質として緑泥片岩を使っているが、九州型板碑は、ほとんどが安山岩を使用している。

九州型板碑の形態は、上部を山形にとがらし、その下に2条の横線を刻む。碑身と2条の線の間を額部と言うが、その額部を残し、碑身の碑面を額部より奥の方へ入れて造る。
その碑面に標識の仏尊とか種子を現し、その下部に造立の趣意や年月を彫刻するのが九州型板碑の形態である。徳島県内に現存する板碑の中でこの由宇の板碑のような本格的な九州型板碑は、この1基だけである。
なにゆえ九州から遠くはなれた由岐の地に九州型板碑が建てられているのか。これは非常に興味がある問題である。
第一に考えられることは、大分県や熊本県の漁師達が魚を追って黒潮に乗って漁をしながら、天然の良港であるこの由岐港に来て永住し、故郷の先祖の供養塔をこの由宇に建てたということである。
第二には、いわゆる中世という時代には、日本各地に土着の勢力が血縁などによって結びつき、武士団が形成された。彼等はたがいに領地をめぐって果てしない争いを続けていた。他人の領地を奪い、あるいはやぶれて一族郎党ともども新天地を求めて日本中を流れ歩いた時代である。このような鎌倉末期から南北朝時代に九州の武士団が、戦にやぶれ、一族郎党をひきつれてこの由宇の地に来た時に、先祖の墓を一緒に持って来たものかも知れない。
いずれにしても、天然の良港である由岐ゆえに、異国の文化が輸入されたものと考えても差しつかえない。この板碑は鎌倉時代末期の形態で、上部の2条の横線の切り込みも側面にまで回り、線の幅も広く、一見してドッシリしている。これは鎌倉時代の強健な武士の思想が碑の形態にもよく現れたものである。このような珍しい九州型板碑の発見は、中世における仏教文化の活動の証しともなり、九州地方との経済交流のあったことを知る貴重な手がかりともなる。
3.康暦二年の板碑
由岐町の石造文化財で、一番に挙げなければならないのは、東由岐町イヤ谷にある康暦二年(1380)在銘の板碑である。銘文に、四季供養、造立塔婆、書写□経、康暦二庚申霜月廿六日とある。標識に釈迦三尊の種子、![]() バク(釈迦)、
バク(釈迦)、![]() アン(普賢)、
アン(普賢)、![]() マン(文殊)を現し、下部には7段に60人あまりの人名を刻んである。いわゆる結衆板碑である。総高152.5cm、幅78.5cm、厚さ8.6cm、材質は和泉砂岩で、俗に竹ケ島石と称している。この板碑の造立の趣意は、『阿波国徴古雑抄』等により康安元年(1361)の大地震の津波に引き込まれた人達の供養とされている。
マン(文殊)を現し、下部には7段に60人あまりの人名を刻んである。いわゆる結衆板碑である。総高152.5cm、幅78.5cm、厚さ8.6cm、材質は和泉砂岩で、俗に竹ケ島石と称している。この板碑の造立の趣意は、『阿波国徴古雑抄』等により康安元年(1361)の大地震の津波に引き込まれた人達の供養とされている。
『太平記』巻第36の大地震の記事には、「同年ノ六月十八日ノ巳刻ヨリ、同十月ニ至ルマデ、大地ヲビタダ敷動テ、日々夜々止時ナシ、山ハ崩テ谷を埋ミ、海ハ傾テ陸地ニ成シカバ、神社仏閣倒レ破レ、牛馬人民ノ死傷スル事、幾千萬ト云数不知、都テ山川、江河、林野、村落此災ニ不合云所ナシ、中ニモ阿波ノ雪ノ湊ト云浦ニハ俄ニ太山ノ如ナル潮漲来テ、在家一千七百余宇、悉ク引塩ニ連テ海底ニ沈シカバ、家々ニ所有ノ、僧俗、男女、牛馬、鶏犬、一モ不残底ノ藻屑ト成ニケリ」と記されている。

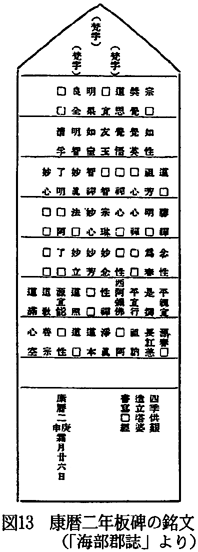
この文中の雪の湊が現在の大池周辺であろうことは、半ば定説化している。この地震はマグニチュード8.4という強大なものであったらしい。由岐港は津波に弱い入江状を呈しており、特に奥部に位置する大池周辺に大きな被害があったであろうことは想像に難くない。
次にこの板碑の造立の趣意について考えてみよう。この銘文は現在では見えないが、『海部郡誌』(昭和2年刊)では、右に「四季供養」、中に「造立塔婆」。左端に「書写□経」とあり、その下横に「康暦二庚申霜月廿六日」の銘文が載っている。「四季供養」は、春夏秋冬の四季のことで、この板碑造立のため四季の季節ごとに供養の法要を行い、最後の冬の霜月廿六日にこの板碑を建てたということである。「造立塔婆」は、板碑とは石で造った卒都婆のことで、当時は板碑の名称を使わず塔婆と称していたことである。「書写□経」とあるのは、経文を書写したことで、何経を書写したか文字が読めないので、詳細はわからないが、こうした書写する経文は如法経(法華経)の場合が多いので、おそらく如法経を結衆者六十余人が手わけして書写し、この塔婆の下に埋経して供養したものと考えられる。
このように考えてみると、この板碑は一般の板碑造立の趣意と違っていて、康安元年の大地震の津波で死亡した多勢の人達の供養の結願の霜月に、埋経して造立したことが想像される。これは康暦の板碑が、中世の歴史的事実と結びつく、数少ない石造物として貴重な存在であることを示している。
4.近江式装飾文様宝篋印塔
阿部の寺谷という所に近江式装飾文様宝篋印塔がある。県道を20m
ほど下りた所に、コンクリートで土台を作り、その上に建てられている。現在では上部の九輪が傷失していて、現在の総高は80cm
あまりであるから、いわゆる四尺塔である。

写真で見るごとく材質は和泉砂岩で、基礎の台石、基礎、塔身、笠と四個の石で造られている。基礎の台石には、蕊(しべ)の二つある複蓮弁を立体的に刻み、基礎は上部に2段の段丘を付け、基礎の側面に輪郭を巻き、その中に格狭間を入れ、その中に三茎蓮華文様の装飾文様が彫られている。この三茎蓮華文様は滋賀県東浅井郡野瀬の大吉寺跡の建長3年(1251)のものが最初で、その後近江一円に広がり、その名を近江式装飾文様と言うようになった。他の地方ではこの近江式装飾文様を施したものは比較的少なく、徳島県では土成町の虚空蔵庵に基礎だけが1個あるのみである。塔身には円形の月輪を入れ、その中に四方仏の種子、東に![]() ウーン阿
ウーン阿![]() 、南に
、南に![]() タラク宝生、西に
タラク宝生、西に![]() キリーク弥陀、北に
キリーク弥陀、北に![]() アク不空成就の梵字を彫ってある。笠は軒下に2段の段丘を入れ、上部に5段の段丘を彫り出している。笠の隅飾はほとんど垂直に立ち上がり、二重弧に仕上げ、弧の外側に1線を刻んである。基礎と笠の高さは同一寸法である。
アク不空成就の梵字を彫ってある。笠は軒下に2段の段丘を入れ、上部に5段の段丘を彫り出している。笠の隅飾はほとんど垂直に立ち上がり、二重弧に仕上げ、弧の外側に1線を刻んである。基礎と笠の高さは同一寸法である。
塔を造立するにあたり、一定の規格があったと考えられ、まれに5寸単位のものもあるが、1尺単位のものが普遍的で、四尺塔、五尺塔、八尺塔などとして造立された。総高が決定すると、次は各部の高さが割り当てられる。さらに、それぞれに応じて幅が規制される。このような割り当ての中で、基礎は背の低いものが古く、塔身は背の高いものが古いと言われているように、少しずつ変化してゆくが、塔の総高は常に一定している。
この近江式宝篋印塔はその規格により造られたもので、総高は基礎の幅の3倍と考えられる。このような近江式装飾文様宝篋印塔がなぜこの阿部の僻地に造立されているのか、また近江との交流関係について非常に興味がある。それについては、阿部東谷の観音庵にある位牌に、「藤川貞■君霊位」、裏に「近江箕作城主箕作左京太夫義賢入道祥貞三男、佐々木左近太夫■賢改、天正四年丙子年十一月二十有五日於勢州討死」とある。また『由岐町史』によると、「箕作左京太夫義賢は、室町、戦国時代に近江南部を治めた、佐々木六角の最後の城主で、永禄十一年(1568)九月織田信長の近江進軍まで、安土町と五個荘町にまたがる箕作城を本拠とした武將であり、天正四年(1576)丙子年十一月二十五日には、伊勢、三■および田丸城で合戦が行われた記録がある」と記している。
こうした事情から考えると、室町、桃山時代には、阿部と近江との間に交流があったと推測され、このような事情から近江式装飾文様の宝篋印塔が造立されたものと考えられる。
この宝篋印塔は形式的に見て、室町、桃山時代の造立であることは間違いない。
5.弘治三年の五輪塔
弘治三年の銘のある五輪塔が木岐延命寺裏山、喜多地という墓地にある。この五輪塔は、昭和9年に延命寺の墓地にあったものをここに移転したもので、木岐の蒲生忠雄家の祖先の墓であると言っている。
この五輪塔は各輪共別石で造られ、基礎、地輪、水輪、火輪、風輪、空輪は各一石で造っている。総高1mあまりの中形の五輪塔で、地輪の面に5行に、「弘治三暦、三忌、常光禅定門、大菩提、七月廿七日」の銘文が読める。弘治三年は西暦1577年で、今年から416年昔の造立である。徳島県で弘治年号のある五輪塔は、徳島市丈六寺と海部郡宍喰町の行願寺のものと、2基しか私は知見していない珍しいものである。この五輪塔の銘文で注意すべきは年号の弘の字で、普通弘の字は弓偏にムの字を書くが、この銘文では方偏に口の字を書いてある。この書体は鎌倉時代に多く使われた古文字で、この銘文の文字に鎌倉時代の余韻が残っていることは注目すべきことである。

次に蒲生忠雄家の系図を示す。
蒲生京四郎所持 家系写
其先河辺魚名公五代ノ孫俵藤太秀郷ヨリ出タリ、世々江州蒲生郡日野ノ城ニ住ス因是子孫蒲生ヲ氏トス、(藤原正持)蒲生石見守ト称ス、蒲生下野守定秀ノ同族ナリ、後阿州木岐城主トナリ木岐大膳太夫ト改ム、天正十壬午年長曽我部大軍ヲ率再海部ニ攻入ノ時利ナ
クシテ、赤松邑ニ引退病ニ罹テ卒享年五十八、赤松邑ニ葬、城山大権現ト追号、(秀名)蒲生好左衛門尉ト称ス、父石見守ニ従テ赤松退陣後木岐徳竹谷ニ住ス、天正十二甲申年三月卒ス(正邑)木岐三平ト称ス、或時狩出徳竹山中ニテ天狗ニ行逢片足ヲ切落シ無難ニ家ニ帰所家焼失シ妻子ハ無恙出レトモ、家蔵ノ旧物尽灰塵トナル、其後病ヲ得テ卒、(某)幼名蒲生五郎剃髪シテ僧トナル木岐円明寺ヲ住職ス、蓬庵公御巡國ノ御砌僧代々長命ナルヲ聞召寺号ヲ延命山ト御改寺領高五石ヲ賜ル(下略)