地理班(徳島地理学会)
横畠康吉1)・寺戸恒夫2)・
藤田裕嗣3)・板東正幸4)・
大道厚子5)・平井松午6)・
立岡裕士7)
I はじめに
半田町は町域の大半が山地で占められ、過疎化・高齢化が進行しつつある。こうした現象は、農業や素麺製造業などの基幹産業にも少なからぬ影響を及ぼしている。そこで地理班は、半田町の産業構造を多面的に把握するとともに、産業構造の変化と過疎化の関連にも注目した。
II 自然生活基盤としての地すべり
(1)地すべり地に見る全般的傾向
半田町の地形は、阿波半田駅付近から松生にかけて、あるいは上ノ原から長瀬に広がる段丘面、および半田・八千代両中学校付近の谷底平野(半田盆地)を除くと、町域の大半は傾斜地にある。それゆえ、その成因ならびに現在の生活に地すべりが深く関与している。
図1は空中写真と現地調査による地すべり地の分布図である。原図は半田町全図(縮尺5千分の1)に記入し、町役場へ届けてあるので、詳細はそちらを参照されたい。図中で示した地域は、滑落崖と崩積地がペアになっている地すべり地形と、風化土層が厚く豪雨時などに崩落するおそれのある部分である。
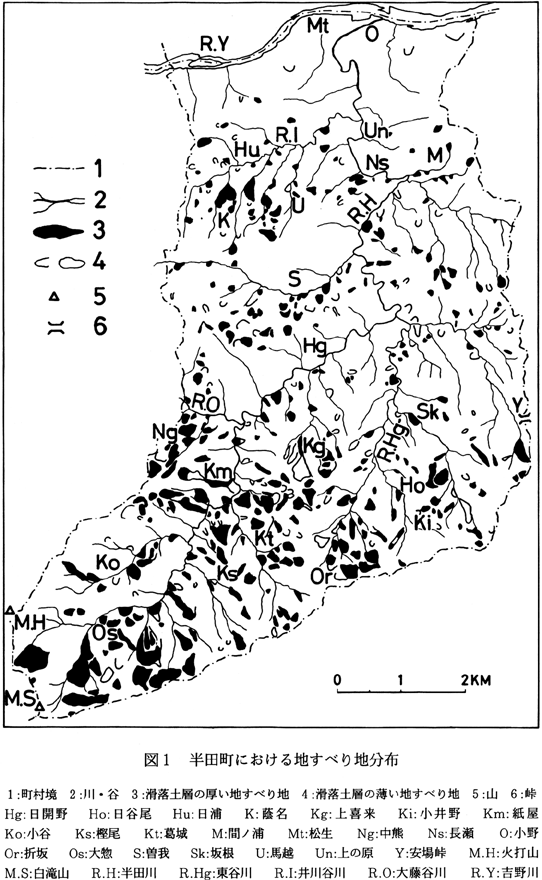
町内に見る地すべり地の地形および地質上の傾向は以下の通りである。
A.大局的には、分布は町内全域のようであるが、地域により疎密があり、北に少なく南に多い。また、東に少なく西に多い。
B.分布で目立つのは、斜面の向きで著しく差がある点である。北に面した斜面に多く、南に少ない非対称分布を示している。稜線(尾根筋)を挟んで非対称なのが、八千代支所北方稜線で、曽我側に多く日開野側に少ない。谷を挟んで非対称なのが井川谷川流域で、北向きの右岸陰名地区に多く、南向きの左岸日浦地区に少ない。これらは基盤をなす結晶片岩の構造に由来するとみられるが、土地分類基本調査の表層地質図「脇町」と「剣山」によれば、日浦地区や紙屋−坂根線以南ではおもな片理面は南傾斜のようで、大惣・折坂・日谷尾などの大規模地すべり地の地表面の傾斜が、地層の傾斜と反対方向(受け盤)となり、疑問をもった。現地調査では、日谷尾は北傾斜であり、折坂・大雄も周辺の谷が一般に北傾斜であるので、地すべり地もその可能性が高い。いずれも、地層の傾斜方向に動く層すべりに起因していると考える。
図1 半田町における地すべり地分布
1:町村境 2:川・谷 3:滑落土層の厚い地すべり地 4:滑落土層の薄い地すべり地 5:山 6:峠 Hg:日開野 Ho:日谷尾 Hu:日浦 K:蔭名 Kg:上喜来 Ki:小井野 Km:紙屋 Ko:小谷 Ks:樫尾 Kt:葛城 M:間ノ浦 Mt:松生 Ng:中熊 Ns:長瀬 O:小野 Or:折坂 Os:大惣 S:曽我 Sk:坂根 U:馬越 Un:上の原 Y:安場峠 M.H:火打山 M.S:白滝山 R.H:半田川 R.Hg:東谷川 R.Hg:井川谷川 R.O:大藤谷川 R.Y:吉野川
C.南部ほど地すべり地の規模は大きくなる傾向がある。最大は大惣で、折坂・中熊・葛城・上喜来・日谷尾が続く。
D.上記の傾向は、地形発達の段階と対応していると思われる。つまり、長期間地表面であったため厚い風化層が形成された地域に、地すべり地の分布が目立つ。早くから川の下刻が進んで谷が発達した町域の北半分(陰名・間ノ浦など)では、地すべり地は谷底から離れた山の中腹や谷頭に散在するものが多いのに対し、南になるほど地すべり地の末端が谷底に近くなっている(葛城・小谷・大惣)。
E.地すべり地の分布は、谷密度とも関連している。小さな谷や山脚が数多く見られる地域や、逆に発達が著しく劣っていて、山腹斜面が急である割に屈曲の少ない部分では、地すべり地は少ない。後者は断層崖や断層線崖あるいは受け盤地域で、一般には落石や崩壊の多発地域になっている。地すべり地は、谷密度が多過ぎず少な過ぎない地域にある。この点は、上記Dの地点とも関連している。密度が著しく発達する斜面には、往時の大規模地すべりの崩積地に、その後の侵食によって生じたと思われる地形が含まれているように思う。倉尾谷や小井野谷の源流部はその例である。
G.大規模地すべり地はすべて2〜5段程度に分化しており、滑落崖の形態から低位のものほど新しく滑動したと考える。
H.地すべり地と断層の関係としては、陰名を通る東西性の断層が注目される。馬越南東端の町道カーブには、N80°W・50°N
の断層がある。その南側に東西方向の谷がある。西北西への延長には、松尾富夫氏宅すぐ北にかけて急斜面が続き、さらに日浦奥〜三加茂町宗森へ凹所が延びる。また陰東上部の新田利春氏宅背後より、ほぼ東西に延びる急崖や同方向の谷があり、断層が推定される。町の南にある小谷・葛城・上喜来の地すべり地は、町南西端の白滝山と火打山の間から、貞光町境の安場峠に延びる西南西−東北東の断層と関連するものと考えられる。
I.前記Aの井川谷川沿いの地層はほとんど直立しており、層すべりが発生しやすい状況ではない。陰名側の下部に地すべりが少ないのは、以下の理由によると考えられる。井川の山崎太師堂から陰下へ登る稜線と新しい道路の交差点、つまり坂本勝義氏宅南西のカーブすぐ南西の標高約
250m
の切り通し(長さ約30m)に礫層がある。結晶片岩礫からなる土石流堆積物と河成堆積物の混合した地層で、礫層の腐りや赤色化の状況、また井川谷川との比高(約70m)などより、穴吹町中野宮の御崎神社東の標高
230m
の河成礫層に対比できるもので、おそらく10〜20万年前の堆積物と考えられる。当時はこの部分は川が流れており、新しい地表であった。付近には仮に地すべり地があったとしても、崩積物が流亡していたことは確かである。その後の急速な井川谷川の下刻により、谷密度が増し、陰名側だけでなく、日浦側も大きな地すべりを生じなかったものと思われる。
(2)地すべりと過疎
『半田町誌 別巻』(昭和53年刊)と現在の戸数を比較すると、この約15年間の変化は、地すべり地域で顕著である(表1)。

具体例として大惣地区を取り上げる。約30年前に実際に居住していた家は33戸である。現在の常住は14戸、時に居住2戸、域外居住であるが住居残存15戸、同じく住居消滅2戸となっている。ただし、常住の中には住居が焼失して域内に転居したもの1戸が含まれる。域外転住の時期は昭和40(1965)年頃2戸、45年頃1戸、50年頃2戸、55年頃3戸、59年頃4戸、62年頃3戸で、この10年前後に過疎化が進んでいる。挙家離村は7戸で、このうち老人のみの家庭が5戸に達する。域内、域外への転居16戸の中には、地すべりに危険を感じてというのが2戸、台風で納屋が流失してというのが1戸あった。同様な例は折坂や日谷尾でも存在した。地すべり地は土層が厚く緩傾斜であるので、山間では重要な生活空間となるが、交通が発達した今日では、危険を感じて域外に転出するというのが一般的である。これに反して、往時は危険でも現住所を守らざるを得ない立場にあった。大惣の男性に嫁入りした女性の出身地をみると、判明分24名のうち、地元大惣生まれが17名と70%に達し、背後の山の裏側の一宇村木地屋より2名、石の小屋より1名、その他1名で一宇村が計4名となり、下流側の旧八千代村(小谷・葛城各1名)の2名より多い。昔の通婚圏の一端を示すとともに、過疎の底にあるものをうかがうことができる。
(文責 寺戸恒夫)
III 人口変化と過疎化・高齢化
半田町について、毎回の国勢調査時における人口を示したのが表2である。
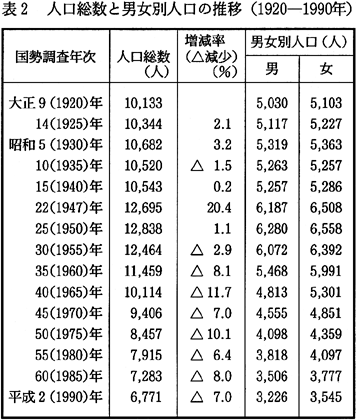
合併前の年次については、合併後の現在の境域に合わせ調整を施してある(総務庁統計局『昭和55年10月1日の境域による各回国勢調査時の市区町村別人口』1985年による)。この表を見ると、人口はまず戦前についてはほぼ一万人強の数字となっており、横ばい状態で推移したことがわかる。戦争直後、人口は急増し、昭和25(1950)年にそのピークを迎えた。同30年代からの高度経済成長期は、農村から都市への人口流出現象が全国的にみられた激動期で、徳島県全体としても人口が減少している。本町も例外ではなく、その時期から減少に転じている。都市部への人口移動が続き、過疎化現象が指摘されるに至った。しかし、全国的には次第に極端な向都離村現象は影を潜め、人口流出に歯止めがかかった。県レベルでみると、昭和50〜60年には僅かながらも再び増加に転じている。とはいえ、本町では昭和35年から一貫して毎回6〜10%台の減少を見せており、最新の平成2(1990)年にはピーク時の約半数の水準にまで落ち込んでいる。なお、男女別人口では昭和10年を除いて女子が男子を上回っている。
次に年齢別構成について検討する(図2)。
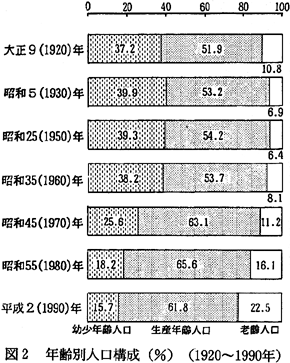
大正9(1920)年以降、15歳未満の幼少年齢人口、15歳〜65歳未満の生産年齢人口、65歳以上の老齢人口のそれぞれ比率をとり、グラフで示したものである(但し、大正9年のみ生産年齢人口は15−59歳、老齢人口は60歳以上)。この図によると、昭和35年以降とくに幼少年齢人口の比率の減少が際だっている。高度経済成長期の都市への人口流出に加えて、出生率の低下現象があるためである。また、この現象と呼応する形で、一貫して老齢人口比率が上昇している。昭和60年にはついに幼少年齢人口比率を上回っており、平成2年には22.5%を占めるに至っている。つまり、町民の4.5人に1人は65歳以上の高齢者である。若年層の都市への人口流出のみならず、医療技術の進歩による死亡率の低下も大きく作用している。 (文責 藤田裕嗣)
IV 在来型商品作物の衰退と主要農産物の生産状況
(1)半田町の農業を取り巻く環境
半田町は半田川の河床を軸とし、両サイドに急傾斜の山林原野が迫る耕地率8.1%の山村農業地域である。主要な水田農業地帯は半田川下流の主谷河床沿い(半田盆地)と水利に恵まれた支谷沿いに分布し、水田率は15.4%である。36を数える農業集落の大部分は、標高
300〜500m
に分布している。畑率35.5%で、経営方法によっては高冷地野菜作農業の振興可能な集落が多い。山間傾斜地農業集落では、工芸農作物のタバコ・茶の栽培と養蚕業が農業経営の中心となって農家経済を支えてきた。傾斜畑地の有効利用の推進のために、アタゴ柿と茶の栽培強化が行われ、アタゴ柿と緑茶が町の特産品としての地位を占めるに至っている。標高
500m
前後の北斜面では、コンニャク芋の栽培が行われている集落もある。冬場の農家の副業として、コンニャクの製造・販売を行う農家やワラビ・ゼンマイなどの山菜加工を行う農家もあって、小規模ながら地域の特性を生かした農業経営がみられる。
平成2(1990)年の農家1戸当たりの農業生産額は28.5万円で、美馬郡平均の44.8万円、徳島県平均の85.9万円と比べると農家当たりの生産性は低い。土地生産性は5.3万円で、美馬郡平均の8.2万円、県平均の12.4万円と比較しても土地生産性が著しく低いものとなっている。労働生産性は28.3万円と、美馬郡平均の64.9%、県平均の29.7%にしか達せず、極めて低いことが理解できる。土地生産性・労働生産性ともに、美馬郡平均・徳島県平均をはるかに下回る生産規模の零細な山村農業が、半田町農業の特徴である。さらに、ここ20年間に、農家数は44.5%、農業専従者数は52.3%、耕地面積は35.0%もの減少を示した(表3)。

総農業粗生産額に対する作物別の比率をみると(表4)、畜産部門(48.2%)、野菜類(11.1%)、工芸農作物(9.0%)、養蚕(8.0%)、果実類(7.4%)の順となって、畜産類の比重が高い。1975年からの変化をみると、畜産類、野菜類、果実類が増加したのに比べ、伝統的な換金作物であった養蚕、工芸農作物の生産は停滞から減少傾向を示し、構成比をかなり低下させている。
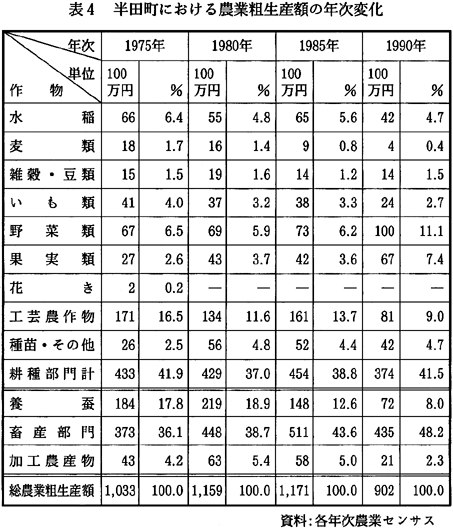
専業・兼業別農家の構成を表5に示した。

その構成比は、専業農家28.6%、第1種兼業農家6.8%、第2種兼業農家64.6%となり、農業経営を主体とする農家(専業と第1種兼業農家)は35.4%にしかならない。1970年以降の農家の推移から、第1種兼業農家の比率が高率であることを考え合わせると、一般的にいわれる農家崩壊の過程としての専業→第1種兼業→第2種兼業→脱農の過程を経て、農家数を減少させているようである。
1990年における経営規模別農家数は、77.0%(592戸)が
0.5ha 以下の階層に属し、1ha 以上層農家は3.2%(25戸)となって、山村地域での中規模自立経営農家は、0.7ha
層以上の約70戸の農家群と考えられる。商品農産物は、養蚕、果実、工芸農作物、養鶏(ブロイラー)などであるが、地域的にまとまりのある生産量をもった主産地形成にはほど遠く、複合経営による補完作物の組み合わせが、自立経営農家を成立させていると考えられる。
(2)商品生産農業
半田町における農産物の販売1位の部門別農家数を表6に示した。

販売農家率49.1%で、販売される農産物は養蚕、果実(アタゴ柿)、工芸農作物類(タバコ・茶・コンニャク芋)、養鶏(ブロイラー)である。これが、自立経営農家の商品生産部門となっている。単一経営による自立農家は少なく、複合経営によって農業経営の安定化を図っている。複合経営の基幹作物は養蚕、柿、タバコであるが、いずれも小規模経営であって、生産農家は各農業集落に分散し、生産の地域的集中は図られていないようであるが、小規模経営農家が地域的にややまとまったタイプの特産地を形成している。とくにアタゴ柿、養蚕、工芸農作物、養鶏がそれである。
資料の関係で、1985年の農産物販売規模別農家数から、商品生産販売による自立経営農家数を推測すると、300万円以下販売農家729戸(71.3%)、300〜500万円販売農家8戸(0.8%)、500万円以上販売農家は13戸(1.3%)である。このことから、1985年時点における自立経営農家数は13戸と考えられる。半田町の農業は、兼業農家による自給的性格の強い山間畑作農業地域で、特定作物の集中的栽培による主産地形成までに至らない専業農家の複合経営と兼業農家の農外産業に依存した農業経営によって、商品生産農業が域内農業集落に分散的に存在する農業地域である。
特産地形成の過程にあって生産基盤である耕地面積の絶対量の制約の中、耕地面積の減少が進んでいることを考えると、耕種生産部門農家は、規模拡大への指向制限を受けるため、兼業化に向かわざるを得ない。しかし畜産部門は、土地集約的経営が可能であり、食品加工との関連の上に、生産規模の拡大を図ることも可能である。また茸類の生産や施設園芸部門などは、土地集約的で労働力の粗放化が達成されたならば、新たな商品生産農業を推進することで特産地・主産地農業の形成が可能であろう。
養鶏(ブロイラー) ブロイラーの飼養農家数は1985年には13戸で、農家総数に占める割合は1.3%に過ぎないが、出荷羽数は51万羽を数えている。販売金額では第1位で、販売農家総金額に占める割合は4割強となっている。ブロイラー飼養農家のすべてが商社との契約飼育のため、価格の最低保証はされているものの、1羽当たりの収益性は低い。このため、飼養農家は多羽飼育の傾向にあり、規模拡大を余儀なくされている。
《養蚕》半田町のような山地性の強い農業地域にあって、養蚕業は重要な商品生産農業である。半田町の養蚕農家は農産物販売1位部門別農家数の36.3%(137戸)を占め、最も高率である(表6、1990年)。1988年における半田町養蚕組合協同組合員は230名で、半田町全域に分布している。このことは、半田町全域で養蚕業が行われていることを意味し、養蚕業は農家に現金をもたらす換金作物となっている。
工芸農作物
1
タバコ 吉野川中・上流域山間地域のタバコの栽培の歴史は古く、山間地農業地域の農家経済に大きく貢献してきた。タバコは山間急傾斜畑地に在来種の阿波葉がおもに栽培されてきたが、近年減反の傾向にある。その理由は、原料の貿易自由化による買い上げ価格の据置や、労働集約的であるにもかかわらず耕作者の高齢化の振興が影響したものである。栽培地域は半田川支流の大藤谷川左岸で、南東斜面の標高
500m 前後の猿飼集落が栽培の中心地である。1985年のタバコ耕作農家は100戸で、20ha 程度の栽培面積である。
2
茶 茶の栽培は、半田川支流東谷川の左岸・右岸の標高 300m の坂根・上蓮集落や半田町北西部の標高 300m
前後の陰・日浦集落、中心市街地に近い逢坂集落、吉野川右岸の小野・松生集落などが生産地域である。組合員46名で、半田茶生産組合を結成し、茶の生産に取り組んでいる。茶の生産は、製茶工場の整備にともない、特産品としての緑茶が製造されるようになったことが生産強化につながっている。1985年の茶園経営農家は282戸で、16.7ha
の栽培面積を数えた。販売農家数は69戸で、販売農家率24.5%であった。
3
コンニャク芋 コンニャク芋の栽培は、半田川の支流大惣谷川の北斜面傾斜地の小谷・大惣集落が生産の中心地である。標高 500m
の日照時間のやや短い北斜面の小集落が栽培適地のようである。15戸の農家で栽培し、面積は 15ha
である。コンニャク芋の生産過程は、木子を4月下旬に作付し、10月下旬に掘り下げ、翌年の4月下旬に植え付け、5年後に2〜3kg
になった芋を加工業者に販売する。一部に、自家加工して小売店に売り渡す農家もある。コンニャク芋の単位当たり収量は 2,250〜2,625kg
程度である。加工業者へは1kg 当たり350円前後で取り引きされる。
4
アタゴ柿 アタゴ柿栽培は、平良石・大床の集落を中心に、西山・西地・上の原など19集落の77戸の農家で生産され、栽培面積は約 40ha
に及ぶ。収穫は10月下旬より始まり、ドライアイスで渋抜きされた後、箱詰めされて市場出荷される。アタゴ柿栽培農家は、10 a
当たり50〜60万円の粗収入になる。
(3)まとめにかえて―これからの農業のあり方について―
以上のような分析結果と調査の過程から、半田町の農業を次のように要約することができる。
1
養蚕業は収入もかなり安定した商品生産農業であるが、桑園の規模拡大を図ることができない現状と営農者の高齢化とをクリアし、徹底した省力飼育法を積極的にする以外に基幹農業部門とはなれない。
2
工芸農作物は、半田町の農業環境にうまく適合した作物のみが自然淘汰される形で残存している。
3
アタゴ柿の生産は、市街地に比較的近い集落で栽培されており、その労働配分や高収益性という面から、基幹周年出荷作物との補完関係(複合経営)を保つならば、専業農家・兼業農家とも期待できる作物である。
4
高齢者を対象とした新たな農業施策として、徹底した省力化による施設園芸部門農業の推進が図られ、新たな農業活動が展開されているが、市場情報・生産情報の入手、生産費の低廉化、輸送費の低コスト化を図り、収益を上げる必要がある。
5
高松空港の臨空地域に当たる半田町は、徳島県の半田町としてではなく、むしろ東京・名古屋・大阪・福岡を結ぶ太平洋メガロポリス圏と結び付いた半田町を考えるべきである。また、1990年代後半には徳島県も高速道路が部分的に供用されるはずである。これに対応し、京阪神地区からの自家用車観光レジャー客に直結する農業部門としての観光農業やレジャー農業の育成を考える必要があろう。(文責 横畠康吉・板東正幸・大道厚子)
V 素麺産業の伸長と立地変化
独特の太さで「半田の糸」として知られている半田手延素麺は、今日、半田町第一の基幹産業となっている。その起源は近世期に求められ、大正14(1925)年には64戸の手延素麺製造戸を数えた。昭和3(1928)年には半田町素麺組合が結成され、同11年には組合員数130戸、生産量
675t
に達した。その後、第二次大戦中には、原料である小麦統制のために素麺生産は一時中止され、本格的に生産が再開されたのは戦後のことである。
半田町の素麺生産は、本来、農閑期の農家副業として成立し、典型的な農村型地場産業として発展してきた。こうした半田素麺の成立過程や生産工程などについてはすでに詳細な報告がある1)。そこで本節ではおもに、戦後における半田手延素麺の転換期となった昭和50年前後の素麺製造業者の動向、およびその立地変化について報告したい。
昭和29年の半田手延素麺協同組合の再編は、戦前の出荷・販売の共同体制に加え、電動機械化、新設機械や乾燥設備の導入などによって、生産工程が近代化されることとなった。当時の組合員数は32戸2)で、組合員は18戸が集中した小野地区をはじめ、逢坂、田井、西久保、東久保の半田盆地内一円にも分布した(図3)。このほかに、組合不参加の製造戸が6戸3)、また当時は機械麺を生産していた専門業者が3業者を数えた。

組合員はいずれも経営主体は稲作・養蚕・酪農といった農業にあり、素麺生産は冬季の副業であった。それゆえ、原材料の仕入れや製品の販売は農協を通じて行われ、組合員は農協からの委託加工という生産形態をとった。しかしながら、冬場のみの家族労働を中心・とした零細な生産形態では生産量が限られ、また昭和30年代には即席メンの爆発的普及の煽りで需要が伸びず、手延素麺の生産は長らく
100t
前後で推移した。
こうした生産の停滞のために、組合内では生産調整が行われる一方、農業の脱農化や後継者難によって廃業する組合員も続出した。昭和50年には半田町の素麺製造業者は18戸にまで減少した。うち、13戸が組合員で、残りの5戸は自営形態の専業者であった。このように、当初組合加盟の32戸は激減したが、この間組合員の入れ替えも若干みられた。
素麺製造を中止した組合員は小野地区以外の組合員に多く、結果的に昭和50年には自営専業者も含め、大半の製造業者が小野地区に収斂することとなった(図3)4)。こうした小野地区への製造業者の集積は、直接的には廃業した組合員の離農(転業)や高齢化などによってもたらされたものであるが、段丘で半田盆地と隔てられた吉野川沿いの小野地区が素麺生産にとって重要な気象条件に恵まれたこと5)、また、段丘中の豊富な井戸水を利用できたこと、阿波半田駅に隣接していることなどが、その要因と考えられる。
しかしながら、昭和40年代後半以降、消費者ニーズの変化により自然・手作り食品が見直される中で、半田町の手延素麺の生産も増加傾向を示した。こうした中で、手延素麺協同組合は農協による生産調整、さらには生産増による製品の粗悪化という問題を克服するため、昭和50年には農協の委託加工生産を中止した。すなわち、各組合員の生産意欲を高め、品質向上のために、仕入れ・販売を組合が直接行うこととし、農協から独立した。その結果、多くの組合員(9戸)は組合に残ったものの、一部の組合員の中にはそのまま農協委託加工を続けるもの(1戸)と、専業自営業者として独立するもの(2戸)とがみられた(ほか1戸が廃業)(図3)。その後、組合には新規に4戸が加入し、平成3(1991)年7月現在、組合員数は13戸を数えている。新規に加入した4戸のうち、2戸は下尾尻・日開野といった半田川上流域の山間集落に位置する。
他方、昭和46年には約
200t だった生産量は昭和55年には 1,000t を越え、同60年には 3,220t
、生産額20億1177万円に達した6)。平成元年の『事業所統計』によれば、半田町における従業員4人以上の事業所47件中24件、従業員603人中254人(42.1%)、製造出荷額等276,292万円のうち167,588万円(60.7%)が、食料品関係の事業所(この大半が手延素麺製造業者)で占められた。こうした生産の急増は、多数の新規製造業者の参入と周年操業化によるところが大きい。
平成3年7月現在、半田町における素麺製造業者は40業者を数え、うち先の協同組合員は13戸7)、農協委託業者は5戸で、残りの22業者はいずれも専業の自営業者である。この22戸の専業自営業者の中には、戦前期より機械麺を手掛け、昭和40年代以降手延素麺に参入した大手3業者や、昭和50年以降協同組合から独立した自営業者(2戸)が含まれるほかは、その大半がブームを背景として昭和50年以降に新規参入した業者である。これらの業者の中にはまったく新たに起業したものがあるが、かつて素麺製造業に従業員として携わっていたものが分派・独立したケースもみられる。
協同組合員あるいは農協委託業者の場合には、基本的には農家の副業として行われ、一般に生産規模は零細(2〜4人の家族労働)で、操業期間は10月〜翌年4月の冬季に限られ、「カド(庭)干し」などの伝統的製法によっている。これに対して、専業の自営業者は多くの場合、組合員よりも生産規模が大きく、従業員を雇い8)、周年操業している点で大きく異なる。とくに自営業者は、工場の冷暖房化などの設備投資が進んでおり、周年操業がいち早く可能となった。この点も、半田手延素麺生産量の急増に大きく寄与している。後発の自営業者の工場の多くは、国道192号線沿いや半田盆地内に立地しているのが特徴で、黒石・白石・高清・日開野といった山間地域へも拡大している点が注目されよう(図3)。周年操業を行う自営業者の場合、従来の製法に欠かせなかった「カド干し」を工場内で行うため、必ずしも気象条件が立地条件として作用しなかったことが、こうした素麺製造業者の立地変化に影響を及ぼしたと考えられる。
現在、素麺製造業に着手するには、家内操業の場合でも2,000〜3,000万円程度の資本が必要とされる。昭和52年に出稼ぎをやめて下尾尻で創業したT氏(協同組合員)の場合には、当時600万円ほど投資したとされる。こうした投資を必要とするにもかかわらず、昭和50年以降、盆地奥の山間部で6戸が新たに操業を開始している。半田町の山間集落(旧八千代村域)では、かつて養蚕を中心とした農業経営に、宇多紙と呼ばれた和紙製造の副業が盛んであったが、昭和30年頃から障子紙などの需要域にともない、次第に出稼ぎや離村が相次いだ。また、基幹産業であった養蚕も生糸相場の下落から不振を極めた。かかる農業経営の不振などのために、これらの新規業者は農閑期の副業もしくは主たる収入源として、新たに素麺製造を導入したのである。
以上、簡略ではあるが、半田町における近年の手延素麺製造業について、とくにその立地変化に焦点を当てて概観してきた。昭和29年の手延素麺協同組合設立時点では、製造戸は小野地区を中心に半田盆地内にも広く分布したが、昭和40年代前半までの生産停滞期に減少し、操業を続けた業者の多くはほぼ小野地区に限られ、生産地域の縮小がみられた。しかしながら、昭和40年代後半から始まる需要・生産の拡大にともない、自営業者を中心に新規製造業者が参入するとともに、生産地域も国道沿いを中心に拡大した。同時期、出稼ぎや農業経営などから素麺製造への転換によって、過疎化が進む山間部への立地も進んだ(図4)。こうした山間部に立地する手延製造業者の多くは家内生産である。操業には多額の資本を必要とするものの、過疎・出稼ぎ対策の一つの手段として、地場産業の果たす役割も今後注目されるのではないだろうか。
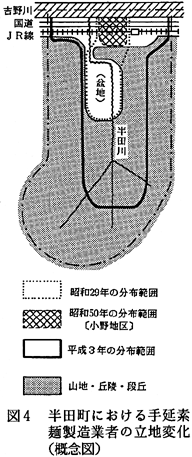
他方、これまで冬季操業を厳守し、製品の品質向上を目指してきた協同組合では、組合員の高齢化が進んでおり、また、新規参加組合員を中心に操業の周年化・専業化が進みつつある。こうした中で、今後、いかに伝統的な半田素麺の品質を維持するかが問題になってこよう。さらに、ここ10数年間生産量・業者数とも急増してきた半田素麺も、近年はやや頭打ちの傾向にある。それゆえ、すでに指摘されているように9)、異なる3つの生産組織形態(協同組合、農協委託、自営)の間での、原料仕入れや規格、価格の違いなども、今後解決されねばならない課題であろう。半田手延素麺と同様、昭和40年代後半以降、兵庫県と並ぶ産地にまで成長した長崎県西有家町を中心とする島原地方の素麺製造は、三輪素麺問屋の傘下に入ることによって生産量を伸ばしたが、独自ブランド流通の開拓も急がれている10)。その点、半田手延素麺はその独特の太さに由来するブランドではあるが、積極的な需要・市場の拡大も望まれよう。 (文責 平井松午)
VI 半田町の商店分布
半田町の商業については、すでに昭和63(1988)年の調査による徳島県商工労働部経営指導課ほか編『半田町広域商業診断報告書』(1989年)の中で、1
平均的に規模が零細である、2 業種の構成は最寄り品が中心をなす、3 県平均と比べた場合、一部の買い回り品業種は販売効率が良い、4
購買力の吸収率はやや上昇してきている、などの点が指摘されている。これらの一般的な特徴は現在もさほど変わっていないように思われる。商店は国道もしくは県道などの主要幹線に沿って(換言すれば吉野川に面する北端部以外では半田川もしくはその支流の谷底に)分布し、急斜面に立地する集落の中には見られない。主な商業集積地は以下の4地区である。a:国道192号線沿線、b:県道半田〜貞光線沿線=北部中心商店街(中藪・小野・敷地・高橋)、c:中央盆地の県道上蓮〜小野線・蔭名〜小野線沿線=南部中心商店街(逢坂・木の内・田井・長谷保・東中・東南)、d:半田川中流域(川又・日開野・下喜来・万才)。なお、このほかにも半田川上流部の紙屋、東谷川流域の下尾尻・折谷、井川谷川流域の井川、などにも若干集積がみられる(図5)。
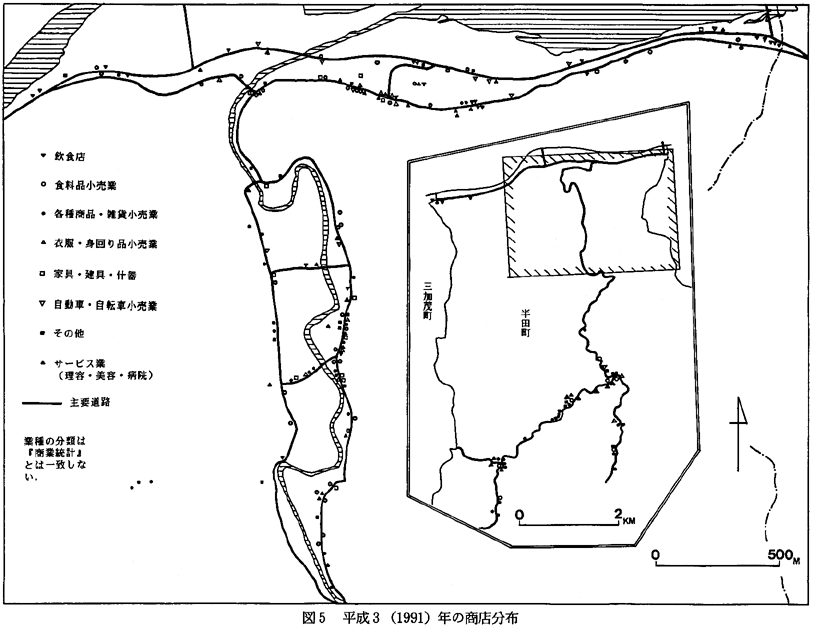
a:国道沿いに並ぶのは、特産品販売店・飲食店・自動車関連店など、郊外型のロードサイドショップであり、新規に出店されたものが多い。店舗の消長が著しく高いことも特徴的で、1989年以降の3年間に少なくとも9店の増加があった一方で3店がなくなっている。かなり企業的な経営が行われているためであろう。b:北部中心商店街ではその店舗数の割にほとんど変化がないが、飲食店を中心に若干の変動がみられる。c:南部中心商店街では、半田川東部で4軒以上がなくなった一方で、西側の蔭名〜小野線沿いを中心に少なくとも7軒増加した。上述『診断書』が指摘する半田川西部における発展の可能性が現実化してきたものと思われる。d:半田川中流域に関しては、半田町誌出版委員会編『半田町誌 別巻』(1978年)の部落小誌に収められた地図と対比してみた。その結果、現在の商店のほとんどは当時も存在し、大きな変動は認められない。ただし商店ではないが、万才ではすでに理髪店が1軒存在していたにもかかわらず、この15年ほどの間にさらに1軒ずつ理髪店・美容院が出現しているのがやや特異である(万才に限らず、半田町では全体として理髪・美容店がかなり多いのではなかろうか。国道沿線に1、北部中心商店街に5、南部中心商店街に10、半田川中流域に7店が、確認された。)(文責 立岡裕士)
VII おわりに
以上のように、本町の過疎化・高齢化はかなり深化しており、また、養蚕・タバコといった在来型の農作物生産に依拠してきた農業も、その立地環境の制約から衰退傾向にあるといえる。こうした中で、とくに昭和50年以降の素麺製造業の伸長は本町において顕著であり、その立地も国道沿いや半田盆地といった町中心部への集積のみならず、山間部の過疎地域(在来型農業地域)へも波及した点は注目される。素麺製造業の場合、需給バランスの点から今後の大きな伸びは期待できないものの、新たな農産品とのリンクによって付加価値を高めることはできよう。また、それが本町の農業の再活性化、あるいは過疎化の歯止めの一施策に結び付くことも期待できるのではないだろうか。(文責 平井松午)
末筆ながら、半田町役場、半田町教育委員会をはじめ、調査の際にお世話になった方々に謝意を表します。
脚注
1)疋田信正(1977):「半田手延素麺の人文地理学的考察」高校地歴13、1〜14頁。このほか、半田町誌出版委員会編(1981):『半田町誌 下巻』同事務局、282〜298頁。
2)「創立者名簿」昭和29年12月4日付(半田町手延素麺協同組合資料)。
3)この6戸は、その後いずれも転出もしくは廃業している。
4)昭和50年の製造戸については、『半田町誌 下巻』288頁の分布図によった。ただし、疋田(1977)によれば、昭和50年の製造戸は小野地区に12戸が集中したほか、西山地区に2戸、天皇・逢坂・東地地区に各1戸となっている。
5)半田中学校の生徒の気象観測によれば、小野地区は半田盆地内よりやや湿度が高く、盆地内の風向が変わり易いのに対して、小野地区では西→東方向に一定して吹き、素麺生産の重要な作業である「カド(庭)干し」には好条件であるとされる。「広報 はんだ」No.97、1991年2月。
6)平成2年の徳島県の手延素麺の生産量は
3,003t(大半が半田町産)で、全国生産量(35,210 t
)の8.5%を占める。『食料タイムス』。
7)ただし、うち1戸は平成2年より休業中である。
8)徳島県物産観光事務所が昭和61年度に行ったアンケート(回収36業者)によれば、協同組合員以外の業者22業者の従業員数は1〜4人が9業者、5〜9人が6業者、10〜19人が3業者、20〜29人が1業者、30人以上が3業者であった。これに対して、協同組合員はいずれも4人以下である。徳島県物産観光事務所編『半田そうめん(徳島の物産 No.16)』1987年。
9)前掲8)。
10)上野和彦(1986):「島原の素麺業」、井出策夫ほか編『地方工業地域の展開』大明堂、255〜266頁。
1)四国女子大学 2)徳島文理大学 3)徳島大学総合科学部 4)板野中学校
5)土成小学校(鳴門教育大学・院) 6)徳島大学教養部 7)鳴門教育大学