郷土班 石川重平・武田寛一・柳田清
佐藤嘉隆・森本嘉訓
阿波郷土会員で組織する郷土班は、3つの役割を分担し調査を進めた。
まず武田寛一が調査班長として総括及び事務・進行の役割を果たした。調査班は、中世石造物調査班と産業遺跡調査班に分かれそれぞれ調査し報告を行った。石造物調査班は、石川重平・柳田清・佐藤嘉隆の3名が上那賀町に所在する中世石造文化財の所在確認・写真撮影・拓本・計測及び考察を行った。報告文執筆は石川重平が担当した。中世石造文化財は、最近注目されつつある中世考古学の基礎的一分野を構成するものであり、徳島県内でも少しずつ蓄積が進んでいる。今回の調査でも、新発見はなかったものの銘文解読に新しい説を提唱した。
一方産業遺跡の調査は森本嘉訓が担当した。調査における日数や人員等の不足もあって分布調査や悉皆調査には遠く及ばずまた産業遺跡の視点とすこしずれたが、「拝宮和紙」が衰退しつつあることから、その緊急調査の必要性と民俗文化財的意義に着目し、不完全ながら調査を進め報告を行った。ご支援下さった上那賀町の方々には厚くお礼を申し上げます。
上那賀町の中世石造文化財について(石川重平)
1 宝簾印塔
宝篋印塔は、基礎・塔身・笠・相輪の4部から成り、軒の4隅に隅飾りを立てている石塔を宝篋印塔という。従前、宝篋印塔の祖形は、中国後期の顕徳2年(955)に、呉越王銭俶が造った金塗塔や銀塔および鉄塔など一連の金属小塔と説かれなお定説がない。これらのうち銀塔が知られるようになったのは昭和10年代に入ってからであり、鉄塔は戦後中国で出土し初めて知られたもので、それまでは中国においてさえ全く知られていなかっただけでなく、わが国へ伝来した証拠もない。しかも銀塔説や鉄塔説を論じた者に、銀塔や鉄塔を見たものがないだけでなく写真や挿図を見て論じているにすぎないのであるから、まさに机上の空論といわなければならない。
これに対して金塗塔は中国で造られてから4年後にわが国へ招来されたことが記録に見えるだけでなく・遺品若干が各地に伝蔵され、中でも紀伊那智山の経塚から出土した1例が東京国立博物館に収蔵されているなどから、その伝来が平安後期にさかのぼる。
全国に分布している宝篋印塔の総数は明らかでないが、約5,000基と推定されている。しかし徳島県で中世の宝篋印塔の数は極めて少なく、現在知られているものでは、阿波郡市場町山ノ上の大野寺境内にある砂岩製の塔で、この塔には永和元年(1375)の年号の造立銘が刻まれている。紀年銘のある塔では県下最古の塔である。しかしこの塔は上部が欠損していて全体の形態はわからない。また徳島市の丈六寺には先年掘り出された、鎌倉時代と推定される宝篋印塔の笠の部分があるが、これも笠のみで各部の形態はわからない。
私の今までに実見したものの中で、中世の塔の中で造立当初のまま一部の欠損もなく残っているのは平谷のもの唯一である。宝篋印塔は宝塔と並び中世の石塔中最も形式手法が複雑であり高級の石塔といえよう。すなわちその分布が地方経済的基盤を反映するものとして、中世地方史研究上注目すべき資料といわなければならない。
A 平谷の宝篋印塔
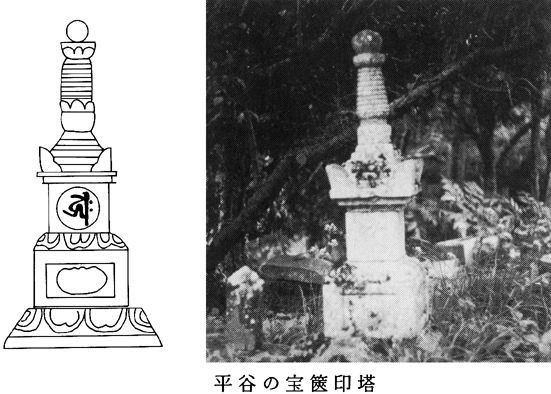
平谷16番地にあるユニエイト工場裏の西隅に立っている。材質は花崗岩製で全高120cmあり、いわゆる4尺塔であり全形態が完全に残っていて実に見事である。この宝篋印塔は元この工場敷地内にあったものを今の所に移したものであるという。その時相輪の部分はここから約20mほど北の畑の中かり掘り出して持って来た。また塔身はここから南約
50m
ほど南にある道路の石段に使っていたものを持って来て重ねたものだと、工場の主人が語った。しかし異質の物でなくもともと1つのものであったものが何時かの時期に別々の所へ散って行ったものであろう。
では各部を説明する。
基礎は2段式になっていて、初段の高さ 13cm
に下部に1区画をおき、その上に複蓮弁の反花を刻出していて、花弁も立体的で力強い感がする。2段目は高さ
22cm、幅 29cm 方形の基礎の下部の一部を高さ 17cm、幅 29cm
の面に 16×10cm
の輪郭を刻しその中に格狭間を刻り出している。上部は基礎と同じ複蓮弁の反花を立体的に周刻している。塔身は、
17.5cm
の正方形であり各4面に月輪を入れその中に全剛界四仏の四方仏鎧![]() (キリーク弥陀西)
(キリーク弥陀西)![]() (タラーク宝生南)
(タラーク宝生南)![]() (ウーン阿■東)
(ウーン阿■東)![]() (アク不空成就北)の種子(梵字)を刻している。
(アク不空成就北)の種子(梵字)を刻している。
笠は、下2段上6段、隅飾りは二弧輪郭付の定形式である。笠の上の伏鉢と上下の請花の高さ
9.5cm、上部の請花にはそれぞれ小花入単弁の4葉を刻り出している。その上に九輪を置き、宝珠の下部にも蓮花単弁4葉を刻するという実に入念な造りである。全体から受ける感じでは南北朝時代後期か室町時代初頭のものであろう。
2 板碑
板碑とは、仏を供養するための卒都婆の一種で、つまりこれを造立することは、お寺や塔を建てるのと同じ意味をもち、造立する人すなわち供養者が仏に対して善根功徳を施したことを意味するのである。徳島県では、鎌倉時代の文永7年(1270)の在銘のものから、天正18年(1590)のものまで320年間に約5,000基あまりの板碑が現存している。
阿讃山脈と四国山脈にかこまれた、吉野川下流の名東・名西・麻植・板野・徳島市の各郡市部に最も多く、美馬・三好・勝浦・阿波・那賀・海部の諸郡にも少量の分布が見受けられる。材質は主に緑泥片岩を使っているが、すべてそうであるのではなく、砂岩やその他の材質の石もある。形態的には阿波型板碑という一定の形式を持ち、全国的に関東型・九州型とならぶ様式のものである。標識(本尊仏)には、弥陀・観音・勢至のいわゆる弥陀三尊仏の種子(梵字)のものが最も多く、弥陀画像を線刻した画像板碑や五輪塔を碑面に線刻したものなどは他県に比べてその数が多いようである。大型のものでは阿波郡市場町の春日神社の3m
に余るものや名西郡石井町内谷の高さ 2.7m
もあるものもあれば、小型では 30cm
にみたないものなど千差万別である。場所的には、寺院や庵舎の境内・墓地・神社や路傍、畑の側などに立っている。
阿波型板碑の初発期は鎌倉時代中期から南北朝を盛期として室町中期以降の文安・宝徳(1440〜1450)頃からその数が減少し、歴史の言葉を借りれば中世から近世へ移っていくつなぎめの時期にパッタリ板碑が消えていく。
これは一体どういうことであろうか。板碑というのは本当に解らないことばかりで、問題がつぎつぎに出てくる。中世から近世へ移り変りといっても、武士団が出来てそれが板碑とどのような関係にあるのか。板碑のある村はかつてどんな人が住んでいた社会であったかということもまだわかっていない。それに板碑となると仏教の世界にふれないわけにはいかない。そうなると百万言をついやし膨大な資料を引くことになる。それでも板碑との関係になると資料不足となる。結局のところ中世に生活していた無名の人間の供養塔であるからいろいろな問題を引き出す糸口となり、中世の歴史を知る手がかりとなる。その意味では、貴重な石造文化財であり、今後大切に保存しなければならない。
A 長安口 藤倉神社の板碑
国道長安口の橋を渡り菖蒲谷にそって登って行くと
500m ほどで、長安の村落に着く。
此処より徒歩で急坂の道を200mほど登り詰めた村落の一番上に通称藤倉神社が鎮座している。社殿の鳥居の前には地神塔が建っていて、その前の石段を登ると立派な社殿があり、板碑は社殿の裏に洞穴を造りその中に横にして納めてある。上那賀町教育委員会社会教育主事の横山尚純氏と村落の人が板碑を外へ持ち出してくれたので水洗をして拓本をとった。此処には総数で4基の板碑があったが今回見た限りでは、完全なもの1基と上部の右側が欠損しているもの1基、下部の残欠で右側に銘文を刻しているもの1基で他のものは細破して形態は不明である。材質は総てが緑泥片岩であり、岩質から考えておそらく吉野川下流の徳島市佐古山か石井町内かの石である。この程度の重量なら人間一人で、背負って持ち帰ることも出来たと思える。あるいは牛か馬の背に負せて運んだのかも知れない。まず便宣上番号を付けて説明する。

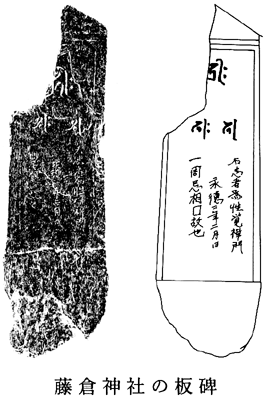
(1)の板碑は全長 93cm、幅 25cm、厚さ4cmで頂部を山形に尖らし項部から
10cm
ほど下ったところに横二線を刻し、碑面上部にキリーク・サ・サクの阿弥陀三尊の種子を配し、下部の左右に銘文を刻しているが右側の文字は磨滅して読めない。左側は永徳□年□月日と読めた。
(2)の板碑は上部右側が大きく破損している。全長
93cm、幅 25cm、厚さ 3.5cm。上部に阿弥陀三尊の種子、キリーク・サ・サクを刻している。その下に三行の銘文があり、右志者為性覚禅門 永徳二年正月日 一周忌相□故也、の二十一文字の銘文が読める。永徳2年(1382)は南北朝時代の北朝の年号で今日から606年昔に性覚禅門の一周忌の供養の為に造立したことが知れる。思えば南北朝時代からすでに600年も幾星霜を経てそのままの姿を今日に残していることは実に偉観である。
(3)この板碑の全体はわからないが碑面下部の右側だけが残っていて、現在全長
30cm
のもので、その面に銘文が刻されている。為沙弥禅覚七年忌也と読める。書体から見てこれも南北朝時代の板碑の一部と見て間違いない。
B 藤倉神社上の一石五輪塔線刻板碑
藤倉神社の裏を少し登ったところに普通の五輪塔が2基あり、その側に一石五輪の線刻がある。材質は砂岩で、全長
50cm、幅 14.5cm、厚さ 10cm
ほどで表面いっぱいに五輪塔の線刻がある。上から空輪・風輪・火輪・水輪・地輪と5つの各輪を線刻し各輪には五大種子、すなわち![]() (キャ)
(キャ)![]() (カ)
(カ)![]() (ラ)
(ラ)![]() (バ)
(バ)![]() (ア)の発心門の梵字を線刻している。
(ア)の発心門の梵字を線刻している。
室町時代に入るとすべての石造文化財は小型化とともに簡略化する傾向が強くなり、この一石五輪塔線刻はこの傾向を最もよく反映しているものといってよい。造立年代は室町末期から桃山時代であろう。このように小型化、簡略化が徹底して盛んになったのは、より低い階級の人々が造立するようになったからであり、これらの階級の人々の間に仏教が普及したことを示すものである。
前にも述べたように中世の末期には板碑が急に減少し姿を消してしまう。その後江戸時代の承応・明暦(1652〜1655)頃から爆発的に今日に見る墓碑が出現する。此間の中間に出現し近世以後の墓標につながるものである。このように見てくると、この一石五輪塔線刻は、中世の供養塔から近世の墓標に至る過程形式を示すものといってよく、その意味では貴重な石造文化財資料である。
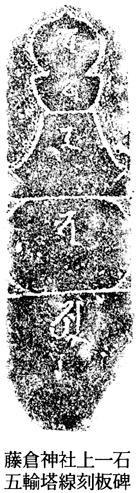
C 白石の板碑
国道ぞいの市宇から約1km
ほど登ると、白石郷字白石に着く。此所に白石観音堂という切妻造りに流れの付いたお堂がある。板碑はこのお堂の中にあり、取り出して水で洗って拓本をとった。全長
43cm、幅 21cm、厚さ4cmの緑泥片岩製で頂部を山形にとがらしその下に二線の横線を入れ、標識には阿弥陀三尊の種子すなわち、キリーク・サ・サクを刻している。輪郭の線はなく銘文も当初から刻していなかったらしく文字跡も見えない。下部は折れたのか全体としては短かすぎる。種子の線も細く、時代的には室町時代後期のものであろう。

D 荒谷峠の御堂の板碑
この御堂の中に2某の板碑が祠られている、標識には、阿弥陀三尊の種子と阿弥陀立像の画像碑である。
(1) 本尊には弥陀立像の画像を線刻し、下に花瓶を刻し花瓶には蓮華の花をさしている。寸法は、全高
64cm、幅 15cm、厚さ3cm
で緑泥片岩製で碑面上部に踏割台座の上に右手を上にあげ左手を前下に出し、いわゆる弥陀来迎の画像で頭部に月輪光背を付け台座から光背まで
24cm
の画像である。下部には花瓶を彫り蓮華をさしている。時代は南北朝時代の造立と考えられる。
(2) もう一つの板碑は、本尊に弥陀三尊の種子、キリーク・サ・サクとすなわち弥陀、勢至、観音である。上部を山形にとがらしその下に二線を入れ輪郭を入れてある。銘文は読めないが左右に文字跡が見える。時代はやはり南北朝時代のものと考えられる。全高
71cm、幅 21cm、厚さ3cm
で材質は緑泥片岩を使っている。
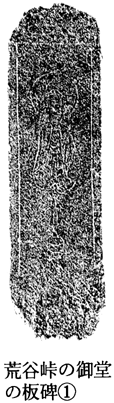
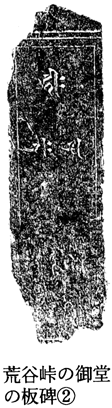
3.おわりに
あらためていうまでもないが、石造文化財にかぎらず一般の金石文の調査は、拓本が唯一至高の方法であり手段である。つまり拓本をとらずして金石文の調査はまずありえないといっても過言ではない。しかも石造文化財の多くは多年の雨露にさらされて磨滅損傷し、はなはだしいものになると、わずかに痕跡をとどめるに過ぎない。さらにいえばそれも認めがたいまでに消滅してしまったものもあることは容易に考えられることである。
例えば、長安の藤倉神社の板碑の銘文の如きは、『上那賀町誌』によれば「○○○○○惟背■門 永徳三年正月三日」と書き、他の板碑の銘文に「秀 ○司 ○一周桐○田故○○ 月 日」と書いてある。今度の拓本によれば「右志者為性覚禅門 永徳二年正月□日 一周忌相□故也」と解読できた。更に荒谷峠御堂の2基の板碑の中1基に町誌は「板碑は1枚が地蔵を線刻した下に花瓶を描いてある」と書いてあるが、今度の調査で拓本をとり調べたところ踏割台座の上に立つれっきとした弥陀来迎の立像であることを確認した。
拝宮和紙について(森本嘉訓)
郷土班の一員として「産業遺跡調査」というテーマで調査を始めた。が、上那賀町で盛んに行われていた拝宮和紙が減少の一途をたどっていることを聞いて緊急調査の必要を感じ、まず現状把握と古老からの聞き取りを行った。また現在紙漉きの伝統を伝えている拝宮の西谷重行家と轟の中村功家の施設と紙漉き用具を拝見し話を伺った。戦前からの経験者では、拝宮出身で徳島市在住の花本角市氏(明治37年生)夫妻にその体験を伺う他、岡本郁枝さん(明治38年生)、山本フサエさん(明治42年生)そして隣接する木沢村出身徳島市在住の湯浅福一氏(大正2年生)夫妻にも話を伺った。他にも現地の方若干名に協力をいただいた。
また「楮と和紙に関するアンケート」と題して、上那賀町の全地区に質問用紙を送付し現状把握を試みた。
近世末から戦前にかけて、上那賀町や木沢村では障子紙や宇陀紙の製造が盛んに行われていた。しかし戦後ガラス戸の普及等により生産はしだいに減少し、現在は拝宮・轟地区に3戸残っているのみで、それも後継者難という問題を抱えて、今後この伝統工芸が存続していくかどうか一抹の不安がある。ただ轟地区の中村功氏が若い情熱で拝宮和紙の伝統を受け継ぎ、次代に伝える役割りを果たそうとしており厳しい山村状況の中で「山村ルネッサンス」の灯を掲げて頑張っている姿に、この調査において深く感動した。
今回の調査では、聞き取りによる現状報告とアンケート調査のみに終ったが、引き続いて、古文書調査による歴史的変遷、民具学的調査、そして原料の植物学的調査にも及びたいと願い、また機会があるならば実際に手漉き和紙を経験の中に組み込みたいと思っている。
A 紙漉きの工程と道具(原料から製品まで)
1 原料
紙の原料は上那賀町では「カミソ」と呼ばれ、俗に「アカソ」と呼ばれているカジである。カジは山野にも自生しているがこれは「ヤマソ」と呼ばれている。また「アオソ」と呼ばれるカジは、西谷家では「ウシカジ」の事と言い、またこれをマカジと呼ぶ人もある。
上那賀町ではアカソが圧倒的に多い。
カジは畑の畔や茶畑等に作り一般に粗放栽培である。肥培管理は畑作物に施したものが流れてカジに行き渡る程度で、石垣の間にもできる強い植物である。増やすのは株分けが主で2月頃に分け、根差しもできる。1年畑で肥培したあと翌年に植付ける。戦前は、焼畑でもカジを作り現在もボツボツ残っているという。西谷家では1町5反余のカジを栽培している。本報告では「コウゾ(楮)」という言葉を使わず、地元で一般的な「カジ」に統一した。

刈り取りは葉が落ちてからで、西谷家では正月の棚が下りてすぐ刈り始めるという。一般に南向に凸状にためて切ると腐りにくいがそこまではなかなか手が回らない。カジは2〜3m1年に伸びるので先の細い部分をカットして束ねる。昔はビランカズラで束ねたという。拝宮だけでなく他地区(木沢村の下流域も含めて)の紙漉き農家では、自家生産のカジだけでは原料不足なので海川や平谷方面に買いに行った。この方面ではカジの栽培をし、蒸して皮をむいたクロソを紙漉き農家に供給していた。土地によって品質が違いカジの良いのは成瀬と言われた。男では14・5貫、女では8貫位を担いで帰った。質はシロソの部分が厚いものが良く、これだときめが細かく良質の紙が取れる。宇陀紙の場合は少々悪いカジが混っていても良い。
買う時にマカジという質の悪いカジが混っていることがあった。これは繊維が長く紙に漉くとブツブツができる。葉が落ちてしまうとカジとマカジと区別がつきにくいので、良心的でない生産農家ではこれを混ぜ込んだりするので困ったという。
10貫のクロソを買うと4貫位のシロソができこれで100間の紙が漉けた。終戦直後1貫25銭位であったという。
2 カジムシ
カジカワむきをするためにカジを蒸す作業を行う。大きな羽釜(西谷家では口の周囲が3mという。)をクドの上に置き、上には滑車をつけたコシキを置く。コシキは昔は木の桶で、桶屋が回って来ては製作や修理をしていた。西谷家では桶のコシキは壊れやすいので止めて4〜5年前からトタン製にしたという。釜には大きさに合わせて束ねたカジを入れる。燃料は松か雑木が良く2時間程焚く。途中水をかけるとむさりやすく、皮が収縮し木質部が見える状態ででき上がりである。蓆の上にカジを出すと下一尺は真黒になっている。
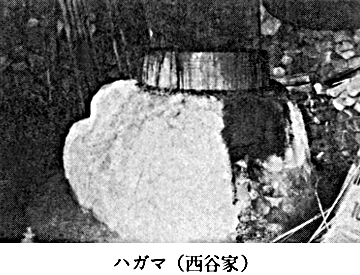

3 カワムキ・アラカワトリ
むさったカジはまだ熱さが残っているうちにむくと簡単にむける。むけたカジはクロソと呼び、竹ハデで天日に干す。1〜3日で乾燥するが束ねた部分が乾いておらず腐りやすいので、よくほぐしてもう一度蓆の上に乾す。生産農家は大体この段階で終り漉く家に売るのである。
干し上がったクロソは二通りの方法で皮を取る作業を行う。1つはソーダ灰でたく場合で、1本1本包丁で丁寧に表皮の部分を取り、次いでその下層にあるアマカワをはずす。最後の白い部分がシロソと呼ばれ製紙の原料となる。昔はランプやタイマツの火で夜なべ仕事であったという。もう1つは苛性ソーダでたく場合で、これは薬品がきつくまた漂白剤を使うので前者のように丁寧にはしない。カワタクリ器(鉄製と竹製がある)に引っかけて節やヤケソの部分を削ってしまう。


4 カジタキ
カミソ(紙の原料)は前述の釜に入れ、薬品を加えてたかれる。薬品は、木灰―石灰―ソーダ―灰―苛性ソーダと変遷してきた。木灰は杉や桧また藁等酸性の強いものより、広葉樹のアルカリ性の強いものが良いという。
中村家では今でもソーダ灰を使っている。朝6時頃から8時頃までにクロソを釜に入れ10時頃からたき始める。浅木を焚きパーと沸騰したらソーダ灰を原料の15%位入れて2時間ほどたく。その日の4時頃上げるか1晩置いて次の日に上げる。1晩置く理由はたきむらをなくするためである。上げる時は木か竹の棒で上げすぐ水をかけてソーダ灰のアクを抜くか、または3〜4日木の桶に入れて汁を漉す「ネセコミ」をしてから水洗いをする。
石灰や苛性ソーダの場合は谷川の水でないとアクが抜けないが、ソーダ灰の場合は水道の水でも良い。消石灰はかたまりになったり、附着するとなかなか取れないので大量の水が必要である。花本角市さんは昭和15・6年頃石灰でカジをたいた経験があるそうである。
西谷家では苛性ソーダを使ってカジをたいている。90束のクロソを釜に入れ、苛性ソーダを1回目は2貫、2回目に1貫800匁入れて約3時間たく。でき上がりは爪でもげる程度という。次に水さらしを行うが、西谷家ではコンクリートの水漕が設けられてありその中にカミソを入れ、水でさらして赤汁(ジゲと呼ぶ)を出してしまう。抜けると、カルキを入れて漂白する。夜置いて次の日に出すが、3日も置くと真白になるという。紙の白さはカルキのかけ具合によるが大変熟練のいる作業である。
紙漉きの水は、ミズアカを取るためにいつもトイの口に袋を吊ってあった。1日で袋が真赤になったという。
5 チリヨリ
たき上がったカミソは流れの中でチリを取る。ソーダ灰の場合は「ミズヨリ」、苛性ソーダの場合は「オカヨリ」といって網の上で行う。1回ヨリ、2回ヨリ、3回ヨリ位まで行う。この作業は単純であるが紙の品質に影響するので重要であった。
カジにはカズラの巻き付いたものやネズミがかじったもの等いわゆるヤケソと呼ばれる
ものがあり、これらは薬ではなかなか直らない。
6 カミタタキ
打盤と呼ばれる真石で作られた石の盤の上にカミソを置き、樫製の横槌で叩く。この時カミソの繊維を傷めないように叩かなければいけないので難しい作業という。繊維の長いのはカジで次にミツマタそしてガンピという順である。下手な人が叩くと繊維の先が傷みチンチラが出る。繊維を打ち切らないように押し付けるように打つのがコツで、舟に入れても叩き方が悪いのは水に溶けない。1回に1時間程この作業を行うから根気を要する仕事である。
中村家では 20kg のカミソを叩くと3割の6kg
のキャベツ大になるという。花本家では4貫叩いて端(ハシガミ)を加えたりすると110間の障子紙が漉け、100間だと下手という。1シメ3貫で漉く人は上人、3貫100、200、300と厚くなる。4貫のカミソを叩くとしても3石(ミイシ)か4石(ヨイシ)で叩く。大きい玉だとこなれにくく、小さいと石を叩いてしまう。横槌は大小あり最初は大きいのを使い次には小さいので叩いていく。
現在西谷家ではアラ(大まかには)は横槌で叩き次に40分程発動機の叩解機で回す。40分程でドロドロになる。

7 スベリ
舟にといたカミソにはネリが必要である。ネリはカミソと水をくっつける役目をする。水だけだとカミソが下に沈み簀に乗らない。昔はネリにノリウツギ(上那賀町ではこれをスベリとかサナギとか呼ぶ。)を使った。中村家では今でもこのノリウツギを使っている。
山で採集したノリウツギは表皮をはいでアマハダを出し、木質部が出るほどに削り水の中に入れると樹液が出る。これを木綿袋に入れて絞るとでき上がりである。紙漉きをしていない平谷方面では、このスベリを採集し樽に詰めて出荷していた。紙漉き農家ではこれを買い、担いで帰り石の重しをして水をかけてあった。
次に出てきたのがヒルハナという黄色の花が付く植物で、瀬戸内海のイントウ物が良い
という。ヒルハナは漉きにくくやがて現在のノリ(ネリ)を使うようになった。
カミソを入れスベリを入れるとマゼ(混ぜ)棒で100回位混ぜる。この棒は木か竹で混ぜるが、竹の節の部分が液を分散させるので良いという。ある程度まで混ぜると「ウマグワ」と呼ばれる道具で前後にゆすって混ぜる。
舟に入れる水は清水は良くなく、長いこと遊んでいるやわらかい水が良いという。清水は一見良いように思われるがキメがつまず雲が見える。

8 漉く作業
スキブネは杉の赤身が良いという。松で作る場合もある。簀とスゲタは、花本家の場合土佐の高岡から引いた。以前は製紙が盛んであり、土佐にはスゲタ工場があったという。明治期拝宮では高い山で採集した茅を簀の材料に使っていたと伝えられている。舟に合わせて簀とスゲタが入れられ、天井から竹を天秤にして吊る。6枚漉きで2本位、8枚漉きで5本使って漉く。
漉き方はその人の技術で、厚い薄いがなく目がつむのが上手ということになる。少しすくって何回もゆすったのが良い。ゆすりはしわしわ(ゆっくり)ゆるのがよくつむがゆすりが効きすぎると乗らないし反対に悪いと雲になる。また紙漉きの上手下手は水の音によっても分かるという。紙の液を汲んだ時「パカンパカン」と音を出すのは下手で、上手な人は「チャンチャン」という音がする。「ああ紙漉きが上手になった。水が鳴り出た」という。


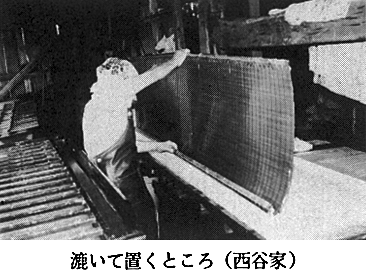
9 ミズトリ
漉き上げた紙は締めて水を出す。昔はハネ木に石を吊り天秤にしてジリジリ1日〜4〜5回締め込んだ。締め具合にコツがある。

10 紙張り
以前は板干しであった。干し板は幅1m程(継いだもの)に高さ2m程のもので松材で作ることが多かった。紙漉きの家なら1軒に30枚やそこらはあった。この干し板に締めて水分を抜いた紙をハケ(馬の毛やシュロで作る)で貼り付けていく。紙はハケで掃いた方がザラザラしていて裏、板の方はツルツルしているので表になる。現在西谷家では鉄板に張り付けて熱(蒸気)で乾燥させている。板でも鉄板でもゴミが付いていると「カミオキ」といい、紙がはがれてしまい良い紙ができない。
11 紙切り・梱包
でき上がった紙は、定規に合わせ「カミキリガマ」で切る。狂うと売り物にはならないので、カマを下ろしていくように一発で切ってしまう。カミキリガマは農作業で使うものより一回り大きい鎌で紙漉きの農家では必ず一つ持っていた。普段は危ないので油紙に包んでしまわれている。
紙は1シメ100間で、10間ごとに小束にした。小さい時は5間が小束である。1シメは上と下にアテ板を当てた。上にはハナ花を切って紙のこよりを巻いてあった。きれいに包んであってもちょっと開いて見られるようにしてあった。8枚漉きの時代になるとアテ板を当てずに厚い紙で包んだ。紙の小口にはその家の印(木刻印)が捺してあった。赤口はソーダ灰漉き、白口は苛性ソーダ漉きであった。


12 販売
昔は紙問屋が徳島や和食にあり取り引きをしていた。昭和初めの頃、徳島に紙を出荷す
る場合、拝宮から東尾を通り上勝町の田野々まで3時間をかけて担いで行ったことがある。
朝早くに拝宮を出、東尾を上がる時はまだ暗く、田野々で昼を食べて荷を作り(ブリキ樽のソーダ灰等を担いで帰った。)、引き返して東尾で2番茶であった。
花本角市氏が子供の頃、和紙を漉く家ごとに商人が来て取り引きをしていた。それが組合ができて神社や庵に紙を持ち寄り商人が来て取り引きが行われるようになった。戦時中紙は統制品となったので、ヤミで高く売る人も出てきた。
現在西谷家で漉いている紙は、ほとんど上勝町や和食までに売れてしまうという。
B 楮と和紙に関するアンケート調査報告
上那賀町の各地区の通信員の方々45名にそれぞれアンケート用紙を送付し、そのうち9名の方からご報告をいただいた。その結果を以下の通り報告したいと思う。
問(1)貴地において楮の栽培が行われていましたでしょうか。
A 止まった場合―何年頃まで栽培されていたでしょうか。
B 現在も行われている場合―何戸の家がどの程度の量を生産しているでしょうか。
(2)楮(梶)の栽培について、生産・加工・販売その他何でもけっこうですのでご教示下さい。
(3)楮と共に三椏(みつまた)の生産はどうだったでしょうか。
(4)貴地において紙漉きが行われていたでしょうか。
A 止まった場合―何年頃まで何戸位の家が漉いていたでしょうか。
B 現在も行われている場合―何戸の家が従事しているでしょうか。
(5)紙漉きにまつわる話や苦労したことについてご教示下さい。
(6)上那賀町で、紙漉き道具や林業用具またイカダ等の資料を収集して「上那賀町民俗資料館」を作ろうとする芽が出始めましたがご意見をお願いします。
答
(臼ケ谷地区―佐藤章市氏)
(1)私が小学校に通っている頃(50年余り前)、楮を大きな釜でむして皮をはいでいるのを覚えている程度です。当地では楮皮を生産して拝宮地区に売っていた。
(3)昭和初期に植え付けしたのが、山林に三椏が今でも少々ある様です。
(4)当町内で現在でも拝宮、轟地区で障子紙と和紙を製造している様です。
(6)大変良いことだと思います。
(海川東地区―森本由多恵氏)
(1)私達の所では現金収入がなく各戸で生産していたようです。
(2)楮の生産は終戦後までしていました。
(3)三椏も楮と同じで現在は栽培されていません。
(4)上那賀町拝宮部落で1・2戸生産・加工・販売しています。
(5)私達の爺さん婆さん等は苦労したそうです。
(上海川地区―株田光春氏)
(1)A 昭和27年頃。
B 不明。
(3)共通。
(6)可。
(平谷地区―山田利行氏)
(1)A 昭和40年頃までと思います。
B 現在は栽培していません。
(2)栽培―茶畠の間、焼畑(山林伐採後)。
(3)ありません。
(4)松久保部落などで行なわれていました。
A 昭和30年頃まで6戸位です。
B 現在行なわれていません。
(下御所谷―新居一輝氏)
(1)A 昭和30年頃迄、長安口ダムの為中止。
(平谷地区―湯浅節子氏)
(1)A 平谷周辺では10戸位の家で梶の栽培をしていた。昭和45年頃まで続いていた。(生産のみ)。
B 現在は全く行われていない。
(2)平谷地区では主として生産をし拝宮地区へ加工に出していた。
(3)三椏の生産はなかった。
(4)紙漉きは行われていなかった。しかし拝宮和紙は強くて障子紙としては有名でした。
(5)うす皮をはぐのに苦労されていたようです。実際にたずさわっていないので十分なことは分かりません。
(6)伝統的な物は後世に残しよきものはいつまでも受け継いでほしい。そのためには資料館は作るべきです。
(小浜上地区―西田勘次郎氏)
(1)私は大正3年、小浜と桜谷の間にある臼ケ谷という部落で生まれまして15才まで臼ケ谷で育ちました。その頃は農家で山畑や山田の周囲には楮を沢山作って居りました(昭和の始めごろ)。16才頃小浜に転居し農家をやめました。旧宮浜地区でも西の方の(出合橋の上)拝宮部落や轟部落では戦時中まで栽培していたようです。栽培した楮は自家用として、紙漉きも盛んにしておりました。
(3)三椏はぼつぼつありましたが少なかったです。
(4)旧宮浜地区でも紙漉きをしていたのは拝宮・轟の2部落だったようです。終戦時頃2つの部落で50〜60戸ありましたが、ほとんどの家で紙漉きをしていたように思います。現在は2戸だけです。
(6)大変よいことです。資料なども次第になくなって行きますから出来るだけ早く実現するように願います。
(海川西地区―蔭藤美智子氏)
(1)昭和30年頃まで栽培していた。
(2)茶畑や畑の畔、一部山などに栽培し、冬休み(12月下旬)に大釜でこしきをかけてむして皮をはぎ、乾燥させ5貫目(約20kg)ほどの束にして販売していた。正月の貴重な収入源でした。皮をはいた後の木は、カジガラと言ってかまどのたきつけにしていた。カジガラで子供達は人形や焼いていろいろな模様を入れて遊んだ。また楮をむす時に桶の上に芋を乗せてむした。梶の香がして大変甘くておいしかった。
(姥ケ谷地区―山脇功氏)
(1)31年頃まで栽培していた。
(2)大正、昭和初期、戦前頃まで杉材に次ぐ重要な換金作物であったようです。
(3)当地区では全く生産していなかった。
(4)行なわれていなかった。
(6)大変結構だと思います。