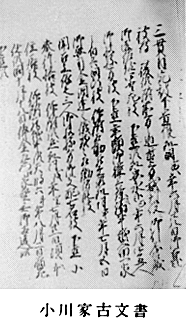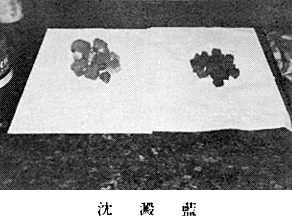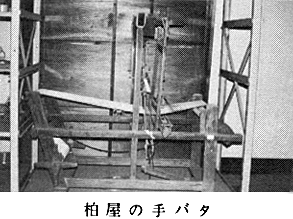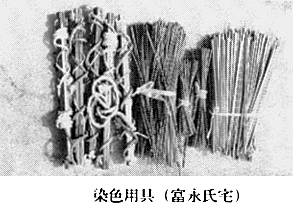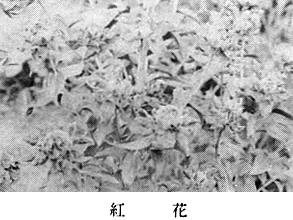藍商と藍作・紺屋・織物・棉と麻の栽培・養蚕・焔硝の採取・藍作地の年中行事と信仰
染織班(徳島染織学会)
班長 上田利夫
調査員 上田利夫・武市幹夫・
真見宣光・笠井孝純
藍商とは、■(すくも)や沈澱藍、葉藍等を売買する人をいい、藍作人は藍を耕作する人をいう。藍師は、■や沈澱藍を製造する人をいい、藍商を兼ねる人もあった。
藍商には、屋号と商号があった。志摩利右衛門は、屋号は利■。商号は志摩屋である。播州田中村から移住したので、田中屋。のちに田中となり、上田知賀太郎は大和から来たので、商号を大和屋。屋号をヨ■というようになった。
藍商人の中でも、前述の志摩屋利右衛門は、幼名を萬といい、生長に従って勘五郎となり、五代目利右衛門となった。明治維新には、勤王の志士と交わり、藩政期には藩財政に貢献し、大藍商として奥羽・関東・東海・北陸・京都等、31カ国に藍を送り、明治17年1月14日、76才で歿したが、大正4年になって、その功績に対して正五位が贈られた。
高畑の中村桐香は、藍商の家に生まれ、幼名を豊。長じて久吉となり、弘法大師流の筆道を学び、明治25年に、入木道個條相伝正統第47世となり、明治38年には、明治天皇の天覧に浴した。九州豊前(現大分県)等へ藍を送っていたが、明治42年、豊前の国で65才で客死した。
高畑の小川八十左衛門は、高畑城主高畠半衛門の7世で、藍の品種改良、藍の製法の工夫をして、生産量を3倍に引上げ、藩より賞詞を賜った。数年後犬伏久助の協力で、さらに藍製法に改良を加え、藍中興の祖となつた。
明治から大正にかけて、高原の上田知賀太郎は、政界の要人と親交を重ね、政界陰の人として尽し、家業の藍商にも励み、関東・東海・浪速・京都、九州の筑後・薩摩、四国の伊予に藍を送り、阿波藍の名声を高揚せしめた。この功によって、賞勲局より銀盃を賜った。
石井町における藍商人名は次の通りである。藍の商品名としては、葉藍・■・沈澱藍(別名、阿波正藍・玉藍・御玉成という)等があった。さらに沈澱藍には印として椿・玉椿・金椿があり、■には青藍金紫等があった。

藍商の家では、藍作人から葉藍を購入して寝床で■に製造したり、外の藍商から■を購入して、種々混合調製して出荷する家もあった。
藍商が得意先へ藍を輸送するには、高畑の田中屋、徳里の大栗などは、自家用船で奥羽や九州へ送っていた。ほかの家では、廻船問屋に依頼して、西覚円・高瀬・第十の浜などの船付場から送り出した。
このほか、吉野川・江川・飯尾川・渡内川には、それぞれ船付場があって、この船付場で舟積みして、吉野川川口の古川港や、新町川の徳島まで送り、更に大きい五百石舟や、千石舟に積替えて、遠く輸送していたものである。
藍商の中で、屋号のない家は、名字が屋号として使われていた。
焔硝の採取について
焔硝は、藍師の居宅の土間や,寝床の土間で、■醗酵時にアンモニアが析出結晶してできる白い粉末で、寄せ板の隙間にできる。焔硝は、火打石のほくちに点火するための添加料。火薬として狩猟用。鉄砲・大砲には、黒色火薬として、硫黄・木炭粉と配合して使われ、160匁が10〜15銭で、川島の焔硝屋に買い取られ、藍師の現金収入源となっていた。
徳島藩が10,000石当り全国一の保有量を保持できた背景には、藍師の副産物の焔硝があった。徳島藩は、常に43,150貫の焔硝を保有し、普通の藩の20,000貫の倍量で、大砲の所有数は、1位鹿児島290門。2位盛岡250門。徳島は50門であった。
小銃は、1位山口。2位鹿児島22,000丁。3位金沢10,000丁。4位名古屋、5位徳島8,500丁で、一般の藩はほぼ3,000丁であった。各所に焔硝蔵が置かれていて、高原32戸。藍畑25戸。高川原5戸。浦庄3戸。石井にはなく、集荷された焔硝は、焔硝蔵で貯蔵された。
藍作について
藍は、新世代第3〜4紀に、地球上に蓼科や豆科の植物として出現し、4,500年程前に、エジプトのギーザのクフ王の麻布の藍染に始まる。
我国では、応神天皇の14年、37年。雄略天皇の16年。欽明天皇・推古天皇の代に、中国や朝鮮からもたらされ、栽培された。阿波では、出雲族・美馬族・長族・海部族などが、郡里・長生・赤阿内村の久望、牟岐村の平野川西村で藍作をしていた。忌部族は、名西山分や、高越山麓の呉島で、藍作を行ったとみられる。
天智天皇は、藍作奨励の詔勅を下し、元明天皇の和銅7年や、村上天皇の代には、全国産藍の中で阿波藍が最優秀であった。宇多天皇や醍醐天皇の時代にも、藍作が行われ、文治年間には、藍の輸出が盛んで、正親町天皇の代には藍染したものが貴重品扱いされ、豊臣秀吉も■染したものを大切にし、織田信長に献上している。
天正13年蜂須賀家政が入国し、元和2年呉島で、藍を耕作させた。元和4年には、藍畑で9歩の蓼藍を作らせた。
播磨国田中村より、播磨屋与右衛門。山口村より数名藍作技術者を招き、藍作指導に当らせ、その子孫は、高畑の田中屋関の山口となって永住した。寛文二年藍方役所ができて、藍の栽培が盛んとなった。貞享元年には、■藍・大藍・丸藍・山藍などが作られていた。正徳4年には、香美村の喜兵衛が青藍採取法を発明し、生産を始めた。
宝暦6年になって、高原村で藍玉一揆が起き、翌年3月5名が鮎喰川原で處刑され、藍税は軽減された。明和3年、藍畑村高畑の小川八十左衛門は、藍の製法の改良を行い、藍増産に寄与した。
文化9年には、水藍・陸藍・菘藍・円葉藍・蓼藍が作られ、雑波藍は作付け禁止となった。天保年間になると、青藍を青■黒・藍精■として生産され、高級染色用として京都へ出荷された。
慶応3年、藍師の中から、玉師として高原村池北の元木多吉、西覚円の平田弥平が任命され、東覚円の平左衛門や、西覚円・下浦・高川原に、それぞれ1名が玉師として選ばれた。
残されている数々の記録については、次の通りである。




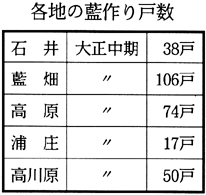
表に組むと以上の通りである。しかし、現在では、旧高原村天神と、旧浦庄村諏訪で、各1戸づつの藍作が行われているだけで、収穫量も10トン半に過ぎない。
大正中期の記録では、地域によって、1戸当りの作付反別に差があったようである。また、葉藍反当り平均はほぼ80貫で、沈澱藍は反当り5〜10貫で、樽詰の場合で藍玉にすると、2貫位しか採取できなかったが、値段がよいので、■以上の収入があった。
葉藍は、1俵10貫入りと20貫入り。■の藍玉は、1俵16貫と20貫入り。藍玉は、1俵10貫入。沈澱藍は1本10匁、20匁。160匁として和紙に包み、樽詰は10斤、20斤入りにして出荷する。
藍玉を搗つ時には砂を加える。池北・平島・高川原に砂屋があり、葉藍に撒水してねせこみを行い、終り水近くになると渥打ちをする。渥屋は、中島・西高原・高畑・中須にそれぞれ1戸あった。沈澱藍は泥状で、樽屋に注文して樽をつくり、樽の横腹には屋号と藍の印名を書く。
価格も、明治34年には、上質の葉藍1貫当り50銭であった。安いものは35銭であった。葉藍を醗酵させて■にすると、六〜七割の量になる。
洪水によって藍作圃場が冠水し、刈取りができない状態となり、加えて雨が降りつづく時には、水につかって藍を刈り、桶に漬け込みして沈澱藍を採取して、■以上の収益を挙げた藍作農家の話が伝えられている。
現在の堤防ができるまでの吉野川中・下流域は、少し雨が続くと洪水が起る氾濫原であった。この地域の藍師の家は、家敷を石垣を作って高く盛土をした作りになっている。その上、軒に避難の小舟をつるした家もある程である。
大正8年に、沈澱藍の生産戸数は、西覚円12戸、1戸当り5〜7貫。高原13戸、1戸当り5〜14貫。池北4戸、1戸当り5〜12貫。高畑5戸、1戸当り5貫。桜間1戸、5貫。高川原2戸、1戸当り4〜6貫を生産しており、これが昭和6年になると、全域に6戸の沈澱藍の生産者のみになっている。
藍の価格年表は次の通りである。

阿波の藍の商品名としては、葉藍・■・藍玉・茎■・茎玉・阿波正藍があり、阿波正藍は、又の名を沈澱藍や御玉成、藍精■ともいい、地域によって違う。
藍は旧暦2月上旬に、苗床に1反分5勺を1坪に播種し、3月から4月にかけて度々間引を行い、5月上旬に、麦畑の畝間に、1反歩4,500株〜5,000株さ藍植を行う。■にするために藍こなしを行うが、藍こなしとは、7月上旬に藍刈りして、3寸の長さに切断し、莚の上に拡げて乾燥して、葉と茎を別けて、づきん(莚の袋)に入れて寝床に貯蔵する作業をいう。莚2枚を縫い合せた袋に、乾いた葉藍を20貫詰める。茎は庭の隅に積む。
得意先の希望によっては、葉藍のまま出荷する。一般には■に製造して出荷する。12月の寒の水の時期になると、葉藍を寝床の土間に拡げて撒水を行い、覆いをしてねせこみ(醗酵工程)をする。5〜7日に1回づつ撒水を行い、20回目から清酒2斗を、20回目5升、23回目に5升、25回目に1斗と撒布する。この時に草木灰をとかした上澄液を、一床に3〜5斗を撒布して■にする。茎■は、外庭で■と同じようにして造り、藍玉や茎玉は、玉臼に入れて練り搗いて固め、1貫玉にして乾燥して造る。
得意先の注文染めの糸に光沢を出すためには、小松島の根井砂を5%位入れて藍玉にする。■は1俵15貫入りにするが、500匁〜700匁は余分に入れる。
叺に入れて、更に印入りの莚で製俵するときは、莚には、右側に藍の印(金紫青藍)、左側に商号又は屋号を書く。藍玉は菰に包み、■同様の製俵とする。
沈澱藍は、7月上旬に刈取り、六石入りの桶に入れて、押蓋、重石をして、水を一杯入れて、中2〜3日の後、入れた藍は取り出して、畑の隅に積む。残った液に擢を入れ、4,050回〜5,000回攪拌すると、青藍が沈澱する。
攪拌する際、上等の消石灰を溶解した上澄液を投入し、表面が金紫色になると攪拌を中止する。これで泡立ちができて、青藍は沈澱する。また一つの方法として、攪拌を行わずに四斗樽に入れて、雨水が入らないように庭の隅に放置すると、青藍は凝固して浮き、攪拌すると青藍が沈澱する。このあたりは、家によって方法が違い、それぞれ家伝として秘密にされている。
樽や桶の底に溜った青藍は、上澄液を捨てて取り出し、斗樽や半樽詰めにする。乾燥して玉藍にもする。玉藍は10匁、20匁などのものを、160匁の大きさにして和紙に包み、菰包みにして出荷する。このことについては、前述の通りである。
沈澱藍の用途は、画家の絵之具や、高級染色用として、手描友禅や捺染に使われていた。現在作られている藍の品種としては、小上粉だけになっている。
紅花について
紅花は、大正10年頃高川原・藍畑・高原で、30戸位の農家で、1戸当り5畝〜1反歩余りが耕作された。収穫した紅花は、袋に入れて、徳島の商人に売渡していた。
藍の品種について
栽培された藍の品種も、時代によって変り、明治40年頃には、赤(青)茎1,000本・赤茎100貫・上粉(上精)100貫・両面半張・じゃん切・るりこん千本・青千本播磨育・おりき1,000本・赤茎(大中小)1,000本・赤茎(大小)大柄・大葉100貫・椿葉・縮葉・越後・青茎(大中小)1,000本・大(小)柄100貫等があり、現在は、小上粉(明治34年に徳島県で改良された品種)だけで、外には山藍といって、琉球藍がつくられていた。狭い地域でも、所によって、同じ藍でも呼び名が異なったりする場合があった。
藍につく虫の消毒について
藍につく虫には、キラリ・ヨトウ虫・ウラ虫があり、これを消毒するには、苦木(にがき)の葉・枝・幹等を水に2〜5日間浸して出た汁を、帯につけて掃く。苦木は、藍商や藍師の家では、屋敷に1〜2本は植えていたものである。石井町には、2ケ所植えている家が、残っている。
藍作地の信仰
藍作農家では、昔から藍苗を立てるのに、その行事としては、上り正月より始まる。つげの木を、藍染(せん)さんの旅に出る枝として、苗床の隅にさす。
苗床を整地し、2月に藍種を蒔くようになると、藍染さんは旅から帰り、お迎えをする。山海の品や、かき餅・御神酒をお供えして、種蒔きが終ると、お供物は附近の人に振舞い、藍生育の無事を祈る。
藍商人、藍作人の藍の守護神として、古くから伊勢の豊受大神宮、出雲大社、大麻比古神社、明治末からは五社明神が尊崇され、家の神棚に、藍染明神として祀られて、毎月1日、15日には、神官を招いて、山海の品等をお供えして礼拝した。
藍こなしに入る藍刈前にも、藍染明神にお供えものをして、藍こなしの無事を祈る。
藍こなしが終ると、その年に収穫や採取された葉藍や、沈澱藍をお供えして、藍染明神に感謝の礼拝をする。夜の食事も御馳走が出る。
春の祈念祭や秋祭りには、各神社にその家の主人が参詣し、新しい神符を受けて帰り、神棚に御神体として祀る。12月の藍のねせこみが始まる前に、藍染明神や寝床に祭ってある藍染さんに、山海の肴と神酒を供え、■の成熟を祈る。
その時から、寝床へは女人の立入が禁止されて、清浄な場となり、男子のみ出入りが許される。
藍のねせこみは、旧正月前に終り、正月に初荷が出て、出荷が終ると、女人禁制が解け、女人の寝床への出入りが許される。できた■は、藍染明神に供えて感謝する。
正月には、藍染明神の各神社へ、初詣に参拝するのが習慣となっているが、伊勢や出雲への旅は、年2回のことになるので、毎年には参らず、商用ででかけた時等に参拝することがある。むろん、近くの五社明神はその限りではなかった。
藍商の家でも、家によっては、四国霊場88箇所のうち、一番霊山寺から十番切幡寺へ参詣して、守符を受けて帰り、藍染明王として祀り、藍作豊穣を祈ったりする家もあった。
時代が変って、今の藍作人や藍商人も、秋祭以外は、各神社へ参詣せず、近くの神社だけに参詣しているという。
藍作地の年中行事
藍作地の正月は、旧正月にするのが習慣で、上り正月が終るとつげの木を杖の形にして、藍苗床の予定地にさして置く。
2月上旬に苗床を耕し、施肥し、種蒔の準備をし、2月上旬、おそい家で2月末に、1坪に5勺の割合で藍種を蒔く。苗床1坪が藍畑1反歩の藍苗になる。■用と沈澱藍用では、藍の品種が違う。■用には小上粉・100貫。沈澱藍用には椿葉・紺葉・縮葉・赤茎1,000本等で、時には■用に赤茎1,000本を使い、種蒔きをする。
3・4月になって間引きし、藍苗は3〜5本ずつ、1反歩4,500〜5,000株の割合で、5月をまって、麦畑の畝間に植えて7〜10日後施肥し、7月上旬に第1回の刈取りをする。那賀・海部から季節農業者が手伝いにきたものである。
刈取った藍は、なえ切りで束ね、庭へ持ち帰り、3丁切りやなたで一寸位の大きさに刻み、莚の上に拡げて、かり竿で打ったり、摺り台で摎って天日乾燥するが、直射日光で藍の葉を赤くすることがあるので、注意を怠らないようにする。
夕方になると風やりして、茎と葉を選別し、葉は、づきん(莚で編んだ袋)に入れて、寝床に貯蔵する。
一方、沈澱藍は、刈取った藍を束ねて持ち帰り、水で泥を洗い去り、六石入りの桶(家によって違う)に入れ、押蓋・重石をして、水を一杯入れて4・5日目に藍を取り出し、畑の隅に堆肥として積む。残った液に摺を入れて、半日位攪拌する。
家によっては、消石灰を使ったり、攪拌せずにそのまま放置して、青藍分を沈澱せしめ、上澄液は捨て、桶の底に溜った沈澱藍は、2斗樽や1斗樽の樽詰にするか、乾燥して藍玉とする。
刈取った藍畑には施肥を行い、8月30日頃と、9月末と、3回藍刈りをして、藍こなしを行う。11月から12月にかけて、藍種を採取する。
沈澱藍用の藍は、20日目に1回の割で刈取りを行うので、6回以上になり、重労働の作業になる。これを嫌う奉公人もいたが、日役銭を多くして就労してもらうようにする。沈澱藍は、9月から10月にかけて、高級染色用として手描友禅、捺染用として京都・大阪・遠州・関東へ出荷する。
沈澱藍の良否は、和紙に筆で書いて、黒か濃紺色に発色するものが最上で、淡青色は下等品とされている。
12月の寒の水の声を聞くと、寝床を整理し、大黒柱にある神棚の藍染さんに山海の肴と神酒を供え、ねせこみに従事する人々が、礼拝する以後、寝床へは女人の出入りが禁止される。
貯蔵された葉藍は、寝床の土間に拡げ、湯と水を混合して葉藍に撒水して積み重ね、莚で覆いをして重石を置く。家によって違うが、5〜7日に1回葉藍に撒水を行い、25回の水をして■にするが、終り水に清酒2斗と木灰汁を打ち、水に混合して使っていた家もあった。
できた■は叺に1俵、上物は10貫、普通は15貫として、余分の入目として、それぞれ500〜700匁を入れて俵にしていた。印入り(家の屋号と藍の名前を書いた莚)の莚で巻いて製俵し、全国各地へ正月の初荷として出荷する。出荷が終ると、寝床へ女人の出入りが許され、藍の一年が終る。
■のできる頃には、藍の仲買人が和紙に■の見本100匁入りを幾つも藍商の家に持参して、手板で品質の鑑定、即ち、5匁の■に水を入れて練り団子にし、その汁を団子につけて、美濃紙に印捺し、濃緑色を最上とし、淡緑色や淡褐色は下等品と定め、値段の交渉が行われて取引が成立する。
また藍商の家では、藍作人から葉藍を購入する時に、品質の鑑定、即ち、木の皮に葉藍に少量の水を入れて練り、摺りつけて色合いを見る。濃紺色が最良品で、淡緑色は品質が悪いので値段が定まる。
藍商と仲買人で■買入れの約束ができると、藍商は■の受取りに行き、代金の支払が行われて受取ることになる。その時に手打式があって、御馳走がでる。藍商は持ち帰り、他の■と配合して、値段に応じた■をつくって、得意先ヘ出荷する。
藍の代金は、藍商が出荷して2ケ月経過して集金に行くが、長い家では、3〜6ケ月で代金が支払われる。従って、藍商の家でも資金繰りに苦労した家もあった。
石井町の養蚕について
阿波の祖神大宜都比賣命・天日鷲命が、忌部族に養蚕を行わせた。また、石井町高原の地で、豊玉姫命が養蚕をしたと伝えられている。
応神天皇の37年、呉の国より蚕種を持ち帰り、呉島郷で養蚕をしており、以降、仁徳天皇・元明天皇・桓武天皇の時代や、仁明天皇の承和2年、光孝天皇の仁和2年に養蚕が行われた。
醍醐天皇の延喜5年、阿波国呉島郷浦之庄で採取された、絹の上糸が献上されている。この年、全国の繭生産のうち、三河国に次いで、阿波国が多額の生産をしている。順徳天皇の建保2年、阿波国浦之庄で収穫された繭の糸で、新曼陀羅織が織られ、大和国当麻寺に勅額として奉納された。
元享元年11月19日、降って、寛文8年4月10日に、繭の生産があつた記録が残っている。
明治2年には、藍畑村高畑ほか5ケ所で、桑が植えられ、養蚕が始まった。明治年代には隆盛期を迎えた。
次に、年次別・地区別に、桑園面積・繭収穫量・養蚕戸数を表に組む。

大正10年の苗価は、春蚕5円11銭、夏秋蚕は4円70銭である。1反歩の桑園から繭24貫の収穫があり、1戸当り1反7畝で、蚕種72グラム、繭35貫500匁の収量であった。大正12年には、高原の上田佐代次が、養蚕功労者として表彰された。
昭和8年、浦庄で381戸が、春繭12,950貫、夏繭14,019貫を生産し、桑園は750反あった。昭和21年になると、春繭150円、夏秋繭126円、昭和28年には、春繭773貫、夏繭231貫、秋繭442貫、桑園18反と落ち込んでいる。
高川原では、昭和9年春繭10,688貫、夏繭12,112貫の収穫があったが、昭和29年には、春繭206貫、夏繭160貫と激減している。
高原では、大正から昭和にかけて、1,389反の桑園があり、相応の繭の収穫を得ていた。
藍畑では、昭和24年47戸となり、昭和30年には、石井町全部で桑園60反、繭の飼育戸数は、蠢繭188戸、夏繭131戸、秋繭155戸となっている。これが、昭和40年には、桑園3アール、春蚕14戸、夏秋繭12戸、昭和50年には、桑園1アール、春夏秋共1戸が養蚕をするのみとなっている。現在は皆無である。
昭和7年の繭収穫量は、藍原41,087貫、高原29,158貫、浦庄18,942貫、高川原15,203貫、石井14,813貫で、繭価は、春繭2円62銭、夏秋は4円36銭で、繭1斗は1貫500匁である。桑園1反歩から、繭約24貫が収穫されていた。繭1石は、10斗である。
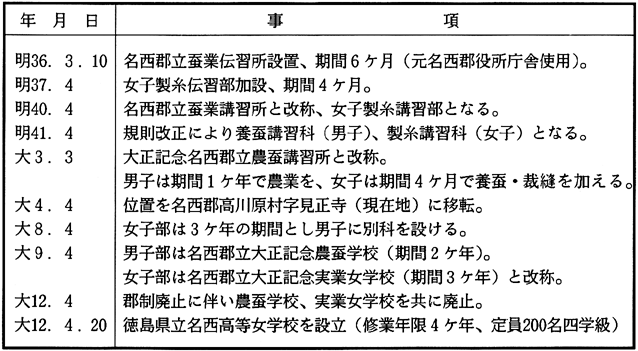
以上の様な経過で県内養蚕業を寄与した。
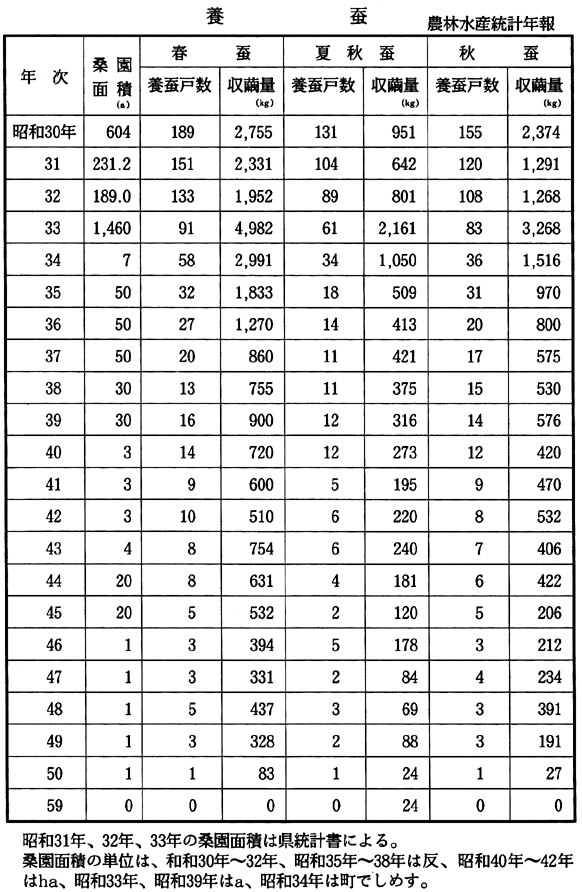
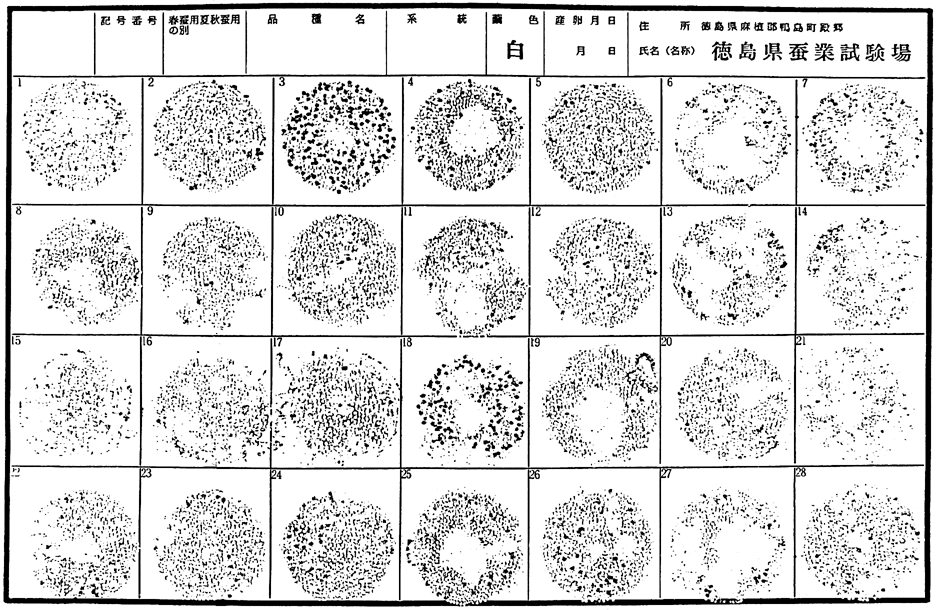
織物と衣料について
石井地区では400戸が、大正年代から昭和5年頃まで、地域によっては、藩政時代から明治にかけて、織物として絹縞・木綿縞を織り、大正・昭和と403戸が、2,800反の木綿縞・絹縞・つむぎを主に、町筋60戸が賃織りし、他の家では自家用衣料にした。
中村では、5戸が明治末まで木綿縞を、中でも大石は、織機4台で織っていた。北石井で10戸あり、うち三木工場で8名が木綿縞、ガス糸縞を、明治40年頃から昭和3年頃まで織っていた。
内谷・鳥坂・尼寺で、木綿縞の賃織りしていた家は30戸であったが、その内手ばた5戸、足踏機5、ほかはしゃくり織機であった。織元は白鳥の大栗・佐藤で、矢野の森忠も織元として木綿縞・絣・絹縞の糸を提供し、昭和5年頃まで織っていた。
白鳥・徳里で60戸が木綿縞の賃織りや、自家用衣料を織った。賃織りの織元は大栗で、昭和5・6年頃まで続いた。
城の内では、50戸が木綿縞を自家用衣料に織っていたが、大正15年頃にはやめた。重松では、90戸が木綿縞・地絹を中心に織り、なかに1〜2戸が賃織を大正5年頃までしていた。
山路では、30戸が自家用衣料として、昭和22年頃木綿縞を織っていた。大東では、農家の農閑期に副業として、10戸が木綿縞、銘仙の賃織りをし、10戸は自家用衣料として、おのおの昭和5年頃まで織っていた。
高川原地区では、明治43年に、織物生産が8,006反。明治45年には、3,416反。大正2年には、3,412反。昭和9年には生産がなかった。
生糸は、明治43年に260貫、明治45年に250貫、大年2年に1,400貫、昭和9年に369貫600匁の生産があった。大正元年から10年にかけて、絹縞・つむぎ・木綿縞・かすり・白木綿などを、100戸余りが自家用に、20戸が賃織りをしていた。織機も、大正元年の暮より、手ばたから足踏機に変り、織元の古間井内和夫が糸を提供していた。
なかでも、高川原の結城鶴吉・井内太吉は賃織専業であった。市楽で10戸、加茂野で10戸が木綿縞やつむぎ、天神で20戸が木綿縞、高川原で15戸が、桜間で30戸、南島で20戸が木綿縞や絣を自家用衣料として、大正15年頃まで織っていた。
はたおり機も、一般農家ならどの家にも1台はあって、自家用衣料に織っていたが、下流階級の家にはなかった。
藍畑地区では、大正15年頃まで、600戸の家で木綿縞・絹縞を自家用衣料として織り、一部の家では副業に賃織りをしていた。西覚円では80戸の農家が、木綿縞を自家用に、大正13年頃まで、なかには、昭和10年頃まで絣を織る家もあった。
東覚円では、福島宇一が女工を使って、木綿縞を織っていた。一般農家でも、自家用に80戸余りがめくら縞を織っていた。高畑東や西島でも百戸余りが、木綿縞や絣を、大正末期まで織っていた。
高畑中須では10戸が木綿縞を賃織りし、他の90戸は自家用に、第十では木綿縞を織っていたが、屑繭から糸を取り、地絹やつむぎを20戸位の家で、大正15年頃まで織っていた。一般農家は、自家用衣料として娘の嫁入りの着物地・帯地も織っていた。どの地区でも、織物用の糸は、近くの紺屋で色別に染めてもらっていた。中には、自分の家で、藍や草木を使って染める場合もあった。
高原地区では、大正2年に二子縞木綿(これはしじら織の原型)350反絣に、羽二重3,600反を生産していたが、大正15年頃にはやまった。
羽二重や地絹を賃織りしていた家は、600戸の中で、30戸ばかりであった。他の家は、自家用衣料に、藍商の家では奉公人の衣料として、厚司やめくら縞の木綿が織られていたものである。
桑島の近藤勝三郎は、明治20年頃久留米で絣の製織技術を習い、婦女子に教え、生産したのが、徳島における絣織りの始めといわれている。池北の大崎徳之平・阿部松三郎・池北半蔵は、寝床を改造して羽二重の製織を行い、毎日数10反を生産した。
昭和初年頃、森長左衛門は、村長として村の振興を計るため、屑繭を利用した織物を、県立工業学校染織科職員上田孝雄に依頼して、絹織物を試織してもらい、これを高原織として、桑島・池北・高原・平島で生産し、関西地方へ売出したが、屑繭の生産量が少なくなり、原料高となったので、昭和25年頃には中止した。
高原地区の織物も、一般には昭和の始めに衰退していた。高原織で一時復活したが、長くはつづかなかった。
中流以上の家であれば、各戸に1〜2台の織機を持っており、白木綿や木綿縞を織っていたものである。
浦庄地区は、昔は呉島郷の東端に当り、阿波国織物の先進地であったので、曼陀羅織やあらたえが織られ、四世紀から6世紀にかけて盛んであった。建治2年、お玉はんが麻の白絹(あらたえ)を織っていたという碑が、山麓にある。
江戸時代から棉を作り、木綿縞を自家用衣料に織っていた。4世紀の頃、鴨島唐人と共に、養蚕も行われていたが、本格化したのは、明治30年頃からで、製糸所ができて、撚糸業を営む者が出てきた。
大正2年から10年にかけて、44,655反の織紺・しじら織・神代縞(曼陀羅織の別名)・絣を、150戸が賃織りしていた。大万では60戸が、木綿縞を大正末期まで、うち2戸は昭和20年頃まで織っていた。
国実では、木綿縞・地絹を昭和5年頃まで、諏訪・上浦・下浦では、100〜200戸がしじら織・神代縞・織紺・紺絣の生産を、大正10年頃まで盛んに織っていた。農家の副業として農閑期には織物が盛んで、どの家でも多忙であった。
国実の武市氏は、まんだら織に金糸・銀糸を使った織物を僅かに保存している。300年ほど前の物であり、これからの織物の研究には、貴重な資料である。
浦庄は呉島郷内の地域である。浦庄・石井・高川原の各地区では、蚊帳地を木綿や麻で織っていた家が、何軒もあった。手織の蚊帳を藍で染めたので、虫除けにも役立ったと伝えられている。
浦庄は呉島郷の東端に当り、曼陀羅織・あらたえ等の、古い時代の織物の生産地である。これらが残っているのは当然で、まんだら織がよく使われている。殊に古文書の裏張には適していた。
自家用衣料とするために、各地域の家庭では、白木綿・地絹・銘仙・絹縞・紬・紺絣・しじら織・木綿縞等を利用していた。中流以上の家庭では、麻織物・絹織物・毛織物が用いられ、中流以下では、木綿織物や太布が、厚司として使われていた。
肌着として襦袢・袴下・褌・腰巻・シャツ・パッチ・股引・足袋があり、常着の着物には、長着・でんちゅう・はんこ・丹前・綿入れの長着でんちゅう等がある。他に、三尺帯・手拭・浴衣地・手甲・脚絆が、外出用には羽織・合せの長着・足袋・長襦袢・襟巻・兵古帯・角帯・丸帯等がある。
礼装用には、紋付の羽織・着物・袴・帯、女の人は、裾模様の振袖・訪問着・中振・打掛等があり、不祝儀用には白無垢・黒紋付・黒帯、履物としては、下駄(桐)・草履・高下駄・利久下駄・中浜・甲堀(ポンポン下駄)がある。仕事着には、厚司・はっぴ・股引、作業用の履物としては、藁草履や、わらじ・とんぼ草履等があった。
日常に使う物としては、風呂敷大中小・ゆたん・幕・幟・敷物があり、日常生活に欠かせないものであった。時代の変遷に伴い、寝具・衣類も形が変り、その変り方に即応して、生活に合致したものとなった。
寝具の蒲団も綿入れも、真綿や羽根蒲団ができて軽くなり、毛布が多用されるように変った。和風の着物も利用度が低くなり、洋装化されて洋服が着られるようになった。昔の蚊帳も、石井の町内で極く一部の家で使っている程度で、殆どの家では昔の遺物として、物置入りになった。
藍商人の家の中で、一部の家では、奉公人用の衣料として、厚司・半天・股引・足袋の布地を造るために、藍がめを据えて、6本〜12本位の糸を、藍や草木で染めて織上げ、布地にして仕立てて衣料にしていた。
これらの場合は、冬季の農閑期を作業にあてるものである。はた織りは女性が、藍染めは、奉公人のなかでも、手先の器用な人がしていた。中には、馬の世話と藍染めの職人を兼ねたものもいた。
棉と麻の栽培
高原地区中流以上の農家では、原野を開き、棉・亜麻・苧麻等を作り、商品として売却したり、自家用の織物原料の糸にして織ったり、ふとん綿としても利用していた。
藩政期から明治・大正にかけて、100〜160戸が棉作り、10戸余りが大正5年頃まで、亜麻・大麻・苧麻を作っていた。麻は、良質の繊維が採取されておりながら、織物にしての商品価値のあるものは、できていない。
藍畑地区は、主として棉の栽培であったが、吉野川の改修工事で棉作地がなくなった。砂木・高鉾・西覚円・高畑・中須・第十で、100戸位の農家が、大正8年頃まで作っていた。麻作りしていた家はなく、棉作だけで、明治の始め頃からのものである。
高原地区は、明治から大正にかけて棉作りが各集落に1〜2戸で行われ、自家用にしていた。他の家では、他村から棉を買入れて使っていた。麻は苧麻で市楽に3戸作って自家用にしていた以外は、殆ど耕作がなかった。耕作者も、自家の夏の着物用として苧麻を作ったものである。
石井地区内谷・尼寺・鳥坂・白鳥・利包・山路・城ノ内の山麓地域で棉が作られ、自家用にも使われたが、上質の棉は商品として、他村へ売却していた。
山路では3戸、北石井で8戸が、明治43年頃まで、白鳥では50戸が、重松では3戸が大正15年頃まで、鳥坂で3戸、内谷・尼寺で2戸、利包で3戸、城ノ内で10戸が棉の栽培をしていた。
渡内川畔に綿打屋、町筋にも綿打屋があって、収穫された綿で品質の悪いものは、綿打ちして蒲団に使っていた。
麻は、町筋の人が、山路の山間で亜麻を栽培して、衣料用として使っていた。
浦庄地区は、度々強調した通り、呉島郷の東端に当って織物は往昔より盛んで、麻は苧麻を文永年間より栽培し、飯野川で晒して打ち、糸にしてあらたえを織っていた。栽培地域も上浦が多く、下浦がこれに次ぐと記録にある。
200戸の農家が、苧麻の栽培を、藩政期から明治40年頃にかけて、行っていた。自家用だけでなく、他村へも商品として売却していた。棉作りは、大万・国実は少く、下浦・上浦・諏訪に集中し、約200戸が大正の中期まで行い、自家用に使っていた。
石井町の紺屋
紺屋のことを「こう屋」または、「染物屋」さらには「繰屋」とも呼ぶ。旧高原村には大正2年頃16・7軒の紺屋に、50名の人が染物をして、16,950貫の染色加工をしていた。
中塚に木村が2軒あって、糸屋といい、藍がめ16本で木綿の糸染めをしていたが、昭和3年頃までであった。中島の宗重は、藍がめ12本で、明治・大正・昭和の三代にわたって木綿の糸染めをしていた。平島の高橋木蔵と喜平は、木綿の糸布染めを大正末期まで、杉ノ本の上田熊太郎は、藍がめ12本で糸・布の型染めを、昭和3年まで続けていた。
ほかには、西高原薮の内に1戸、桑島に谷村・鴻野も糸染めをしていた。池北や閏にも1戸あったが、詳細不明。古い記録では、弘化4年9月30日に他界した、桑島の長左衛門が、糸染めを行ったとある。
旧藍畑村では、藩政時代に高畠に、■九兵衛が紺屋をしていた記録がある。高畑東には西沢が、木綿や絹の糸染めと、布の無地染めや、幕や幟を藍がめ6本で、昭和15年頃まで染めていた。
高畑南に丸徳小川幸吉が、幕や幟を大正の終りまで、高畑東に福本が、昭和22年頃まで、第十の榎本道恵が明治の終りまで糸染めを、東覚円の小川が糸染めを大正の始めまで、西覚円の中村に中島が、大正8年頃まで藍がめ6本で、糸染・幕・風呂敷・幟などを染めていた。このほか、色々事情を尋ねて廻ったが、確定的な判断ができなかった。
砂屋は、池北の長岡、平島に1戸。高川原村では天神の上田が、糸染専門に藍がめ6本で大正の終りまで。高川原北の■上田英作が糸染めを大正の終りまで。市楽に紺屋があって、糸染めや幕幟を大正の始めまで。南島にも紺屋があって、糸染めだけを大正の始めまでしていたが、何れも、屋号や名前を忘れていて聞き出せなかった。
石井町では、北石井に吉成紺屋・吉田紺屋があって、糸染めだけを大正3年頃まで。石井東に楠木勘太郎が藍がめ12本で糸染めを、大正の始めまで。石井中の木栓が、藍がめ12本で糸染めを大正の終りまで。町筋の笠井が、藍がめ12本で糸染めや、布の無地染めを、大正の終りまで。中村の中川が、藍がめ12本で糸染めを大正の始めまで。重松の宮本が、藍がめ12本で糸染め。佐藤カガが藍がめ6本で糸染め。増田太郎が糸染めを大正8年頃まで。白鳥の因幡と大栗は、明治末まで。鳥坂の佐藤甚平は、藍がめ20本で、幕や幟、風呂敷等を、昭和5年頃まで染めていた。
城ノ内の武市安次郎は、糸染めを大正初期まで、糸の染賃は、壱反分20銭〜25銭で、絹糸の場合は10銭高かった。
旧浦庄村では、大万の柏屋は新開遠江守の末裔で、この地に移住して紺屋を始めた古い歴史があり、藍がめ24本で、幕・幟・ふとんの型染、柄染めを、職人も使って昭和6年まで。河野政吉・岩本・竹内も、糸染めを大正末期まで。国実の大西八紺屋は糸染めを、新井とは別に一軒大正末期頃まで、糸染専門にしていた。
下浦の鎌田は、藍がめ3本で幕や幟だけを昭和10年頃まで。山口は藍がめ6本で糸染め、川崎一宮利兵衛も、糸染めを大正の終りまで行っていた。
諏訪の川端岩蔵は糸染めを、八本松の堀江も糸染めを、それぞれ大正の終りまで、続けていたようである。
一般の家や藍商の家では、藍がめを何本も据えて、家族や娘の嫁入りの衣料等を、職人を置いて、自分の藍を使用して糸染めをし、織り上げていた。奉公人の衣料にもした。
奉公人の中には、職人ではないが、紺屋の職人に優る技を持った人がいた。どの紺屋でも、家伝の秘密があって染色の方法が違うが、葉藍と石灰だけで染色液を造る方法のように、藍を艾(い)り、根茎を除け、菰包にして池水に浸すこと一日で水を切り、莚二層に敷き並べ、その上にも莚二層で蓋をし、宿蒸し20日を経て採り出す。この熱気をよくさまして良く揉み、ふるいにかけて茎節を去り、乾燥して揉藍として瓶に入れて染色すると、色浅青く染まって美しいことは格別である。
また、ふるいに通さなかったものは、臼で搗き、餅のようにし、玉藍としてこれに石灰・鉄漿・槌打台・箴子・片紙・切れ地・豆のご、赤揚実・渋木・張木・酢樽・染処・干場等を必要とする。国実には、このような古い技術で、寛政年間に染めた幕が、現に残っている。
容器として瓶が使われ、2石・1石8斗・1石3斗・1石入りの、それぞれの瓶があり、川島焼・大谷焼の1石八斗入りが、土間に埋設されている。
古い方法では、1本のかめに■15貫、草木灰汁(水一と草木灰一の割合で溶かしたもの)と水を加え、瓶の8分目にしてよく攪拌し、1ケ月後に染色液ができる。又■15貫、灰汁2斗、しじみの石灰1升、水飴(ない時は麦のよまし一升)か、さつま芋を煮てつぶしたもの500匁を入れ、湯を加えて8分目にし、よく攪拌すると1週間後に染色液ができる。
この中に、水で潤して置いた糸を、静かに浸して取りあげ、平均に絞り、空気に曝して色が変るのを待って、瓶に浸して回数を重ね、適当な色合いになるまで繰返して染める。程よい色合いに染まれば、水洗いして乾燥する。布染も亦同じで、型染の場合は引染めするので、淡色は刷毛引きして仕上げ、中色からは荳汁(ごじる)(大豆を浸してすりつぶして絞った汁)に前もって浸して乾燥した布を使う。濃色になると、荳汁の中に煤煙を混ぜて使う。
糸染の用具として、ふまえ竹、絞り竹(万引)、布染には張木・伸子・桶が必要で、染めた後は櫂で瓶の中をよく攪拌して手入れを行う。これと同時に、調子の悪い時には、添加物として灰汁・飴を入れて調製して置くようにする。
藍の他、山野に自生する桜・南天・銀杏・萩・桃・栗・櫟・柿・よもぎ・かや・黒豆・茜・柳・げんのしょうこ・いたどりがあり、之に媒染剤として、明ばん・草木灰・消石灰・硫酸第一鉄・塩化第一錫・硫酸銅・醋酸アルミナが使用され、容器として鉄鍋や桶が使用され、藍染にも使用された。
沈澱藍は、泥状のまま、型染や友禅染に、高原・石井・浦庄の紺屋で使われたが、化学染料が入手できるようになって、沈澱藍は、特別注文のほかは使用されなくなった。
化学染料の中でも、硫化染料が一番よく使われ、直接染料、酸性染料と塩基性染料も使われた。
以上の通り調査報告します。暑く忙しい時期にもかかわらず、「ふるさと学ぶ会」の皆さんを始め、諸地域の古老の方や町民各位の御協力を頂きました。誌上ですが、厚くお礼を申し上げます。この報告書が何かのお役に立てばと存じております。何時までもお達者でお過し下さい。
石井町のみなさん、有難うございました。