史学班 田中省造
はじめに
奈良県北葛城郡当麻町にある当麻寺は、古い由緒を伝える名刹である。この寺の創建については諸説あるが、寺伝等によれば、推古天皇20年(612)、用明天皇の皇子・麻呂子親王が創建した万法蔵院を、その後、天武天皇が現在地に遷したものとされる。天武天皇14年(686)落慶して、当初、禅林寺と号したが、後、当麻寺と改称したという。
もっとも、以上の伝承には疑問の余地もあり、今日では一般に、その遺構等から、奈良遷都(710)前後の時期に、当地の豪族・当麻氏によって創建されたものと考えられている。
寺宝の藕糸(ぐうし)曼荼羅は、樹佩(よこはき)大臣の娘・中将姫がこの寺に入寺し、藕糸(蓮茎の糸)を用いて、一夜にして観無量寿経の説法を描いた阿弥陀浄土変相図を織
り出したものとされており、この中将姫の物語は能や浄瑠璃に作られて、人口に膾炙している。とはいえ、この当麻曼荼羅自体は、今日では藕糸ではなく、上質の絹糸で織った綴織(つづれおり)であることが明らかにされている。
中世、わが石井町から鴨島町にかけて置かれていた荘園・浦荘は、実にこの当麻曼荼羅と浅からぬ因縁で結ばれている(本稿では現在の石井町浦庄の地称と区別するためもあって、この荘園を、荘園の正字を用い「浦荘」と表記する)。以下に、絹の荘園・浦荘とこの曼荼羅との縁(えにし)を、曼荼羅新写にかかわった人々を経糸とし、阿波における絹の歴史を緯糸として、綴れ織ってみたい。
1.当麻曼荼羅新写
土御門天皇の承元2年(1208)のことである。当麻寺の住侶・恵阿弥陀仏達は、諸人に勧めて、曼荼羅の御前で不断念仏を行った。念仏の間、静かに曼荼羅を拝見していた恵阿弥陀仏達衆僧は、同心して次の様に歎かざるをえなかった。「そもそも、この当麻曼荼羅は我が国無双の霊像である。しかし、織り奉ってから早くも数百年に及ぼうとしている。ようやく破損もひどくなってきた。このまま放置し、新しく写し留めないでおくと、将来悲しむべきことになろう」と。ここに、時の廟堂を主宰する後鳥羽院にお願いし、曼荼羅を新写し奉ろうと、衆議は一決したのである。
その後、順徳天皇の建保2年(1214)10月のころ、恵阿弥陀仏をはじめとする30余人の衆徒達は、熊野に参詣して、早く曼荼羅新写の院宣が下されんことを祈請した。その時、何という幸運であろう、院使・藤原光親が熊野に参詣するのに出会ったのである。恵阿弥陀仏達は、喜悦の思いをなし、宿願の趣を陳べたところ、光親の快諾を得ることができた。光親によって後鳥羽院の叡聞に達し、新写の事業が開始されたのである。
新写の絵師に選ばれたのは良賀法印と源慶法眼である。両者は後鳥羽院の仙洞御所・高陽院(かやのいん)において、建保3年(1215)2月8日からはじめて5日間で、模写を完成している。直ちに後鳥羽院の叡覧にそなえ、清書してよろしい旨の返答をえて、翌年の建保4年、阿波国浦荘において1丈5尺4方の絹を織り、いよいよこれに新写することになった。しかし、その功ならずして源慶が逝去したため、その子・源尊が後を継ぎ、彼が中心となって、同5年3月16日から浦荘で書写し始め、同6月23日に完了した。
これを後鳥羽院の叡覧にそなえたところ、すこぶる御意にかなう出来ばえであり、源尊はその功により法橋に叙されたという。(「天気犬叶」とあるから、厳密にいえば、当今=順徳天皇の御意に叶ったことになるが、ここでは、前後の事情から後鳥羽院のことと解しておく)。こうして、新曼荼羅は一旦、京都の蓮華王院(いわゆる三十三間堂)の宝蔵に納められた。
これが第一転新曼荼羅あるいは建保曼荼羅と称ばれるもので、後世、盛んに製作された当麻曼荼羅の模本の嚆矢であり、規矩となったものである。
以上は、主として永享8年(1436)に編まれた『当麻曼荼羅疏』(1)巻八に基づいて、建保時の曼荼羅新写の有様を描写したものであるが、他の史料もほぼ同巧異曲の話を伝えている。
ここで曼荼羅新写に係った人達について考えてみたい。
まず、この事業に奔走した、当麻寺の住侶・恵阿弥陀仏であるが、その他の事蹟については一切知られていない。やや判然としない部分も残るが、私としては、俊乗房重源の同行衆の一人に比定したい。
恵阿弥陀仏が帯する「何某阿弥陀仏」という名号は、後世、浄土宗・律宗・時宗等の信者に多くみかけるものであるが、この当時としては非常に珍しく、旧仏教の僧侶から非難の的とされたものである。重源は京都・醍醐寺の僧であるが、治承4年(1180)、平氏によって焼き打ちされ、灰燼に帰した東大寺を再建した勧進聖として著聞している。一方で重源は浄土教の信仰をもっていたようで(浄土宗系の人々は重源を法然の弟子とする(2)、重源が「南無阿弥陀仏」と自称し、さらに、彼に従う同行衆にかってに阿弥陀仏号を付したと、慈円はその著『愚管抄』の中でにがにがしく述べている。
この重源の同行衆の1人に恵阿弥陀仏がおり、重源が東大寺再建のために賜った知行国・周防国に設けた周防別所に付属する寺用の料田畠の中・田1丁・畠5段を、正治2年(1200)11月に与えられている(3)。この恵阿弥陀仏を、当麻寺の住侶に比定できるか否かが当面の問題であるが、両者が同時代人であることは勿論、当麻曼荼羅新写を推進した後者からも勧進聖的相貌を窺うことができる。『愚管抄』の記述からみて、慈円が『愚管抄』を執筆していた当時(大部分は承久の変直前に書かれた)、阿弥陀仏号を帯するのは重源の同行衆が中心であったことが察せられる。また、貞応2年(1223)以前、当麻寺に見阿(弥陀仏)なる僧侶がいたことが知られる(4)が、この人物も前述の正治2年に周防別所寺用田畠の一部を与えられた、重源の同行衆に、同名の僧侶を見出しうる(5)。以上の諸点から、両恵阿弥陀仏を同一人と推定しておきたい。
また、治承4年の平氏による南都焼き打ちによって、当麻寺も多くの堂宇が焼失している(6)。当時、当麻寺は興福寺と深い関係にあったので、このような災害をこうむることになったのではないかと考えられている(7)が、これら堂宇の再建には、東大寺と同様、勧進的方法がとられたのではなかろうか。やや時代は降るが、当麻寺に勧進聖がいたことは、文永5年(1268)に、同寺の大勧進・良観房によって曼荼羅堂の屋根が修理されていること(8)からも知られる。同寺に勧進聖が置かれた時期は不詳だが、建保7年(1219)に同寺の西塔が修理されており(9)、遅くともこのころまでには設置されていたとみなしうる。また、時期的にみて、後者の修理に恵阿弥陀仏・見阿(弥陀仏)が関与したことも確実であろう。
重源は建永元年(1206)6月に示寂している(10)が、おそらく、この重源の死の前後に、重源の推挙によって、恵阿弥陀仏・見阿(弥陀仏)が当麻寺の勧進聖に就任したとみてよかろう。そうである以上、恵阿弥陀仏達と院使・藤原光親との熊野での邂逅も、単なる偶然ではかたづけられないものを含んでいる。恵阿弥陀仏達の熊野への参詣は、厚く熊野を信仰する後鳥羽院の援助を求める、勧進活動の一環とみとめられよう。光親が院使として熊野へ参詣することを、恵阿弥陀仏はよく承知していたのであろう。
新写を担当した絵師の中、良賀法印と源慶法眼とは、ともに高位の僧綱位を帯ぶるところからみて、当時、最高の絵師として自他ともに認じていたと思われるが、当然、この人選には後鳥羽院の意向がはたらいていたとみられる。良賀法印について、渡辺一氏は『門葉記』建仁2年(1202)11月6日条にみえる勝雅(賀)の弟子・良雅(賀)とされ(11)、河原由雄氏は建暦3年(1213)4月26日に営まれた、御鳥羽院御願の法勝寺九重塔供養の際、勧賞については追って申請すべしとされた絵師良賀(12)に比定される(13)。前者によれば、宅磨派の絵師ということになるが、後者によれば、後鳥羽院の信任厚いのも当然といえよう。
一方の源慶について、河原氏は、巨勢系図に兼茂の子として記される人物(14)に比定される(15)。同じ系図で、源慶の兄と目される有宗は、(絵所)長者であり、後白川(河)院上北面と記されているので、時代的には合致するが、その事蹟は全く知られていない。また、この系図には、源慶の子として丹後房と号した隆慶の名が見えるだけで、曼荼羅新写を引継いだ源尊の名は見えない。巨勢源慶が曼荼羅新写を担当したとする確かな徴証はみあたらないのである。
一方、同時代の著名な仏師・運慶の弟子に同じく源慶なる仏師がおり、この人物を曼荼羅新写の絵師に比定することも可能ではなかろうか。運慶が主宰する慶派仏師と重源の親密な関係は周知の事実である。そもそも東大寺再建に慶派仏師が主導的役割を演じるのは、両者のこの親密な関係に基づくのであるし、快慶は重源に帰依して安阿弥陀仏の名号を付されている。運慶が担当した興福寺北円堂の本尊弥勒仏像の中尊の頭仏師は源慶が担っており(16)、源慶は運慶の弟子中でも最上位の地位を占めたと考えられる。建暦2年(1212)現在僧綱位を有していない(17)ので、建保3年(1215)までに法眼位を帯ぶることができたか、疑問の余地もあるが、仮に恵阿弥陀仏を重源の同行衆の一人とする私見がみとめられるとすれば、曼荼羅新写の絵師・源慶が慶派仏師である蓋然性も高いといわねばならない。恵阿弥陀仏が自身の知悉する仏師を後鳥羽院に推挙したとみられるからである。
最後に、完成した模本が奉納された蓮華王院宝蔵に関する問題について考えてみよう。
蓮華王院は、長寛2年(1164)、後白河院の御願によって、平清盛が造進したものである。その宝蔵に納めるため、後白河院は実に多くの絵巻物等を製作させており、そこに、小松茂美氏は、南都東大寺正倉院・鳥羽の勝光明院宝蔵(鳥羽院御願)・宇治の平等院宝蔵(藤原頼通発願)に対抗しようとする後白河院の烈々たる気魄を読みとっておられる(18)。おそらく、後鳥羽院の胸中にも、祖父・後白河院の事業を引継ぎ、蓮華王院宝蔵をより一層充実したものにしたいとする気概があったと思われる。模本の蓮華王院宝蔵への奉納には、後鳥羽院の意向が強くはたらいていたとみられるし、ひるがえって、この事業全体のパトロンであり推進者は後鳥羽院その人に他ならないと判断されるのである。
2.浦荘
鎌倉時代を通じてその存在が確認される阿波国の荘園・浦荘を、沖野舜二氏は名西郡の旧浦庄村(現石井町内)およびその西に隣接する麻植郡の旧牛島村大字上浦村(現鴨島町内)の一帯に比定しておられる(19)。この沖野氏の比定は、遺存する地称に基づくものであり、まことに当をえたものといえよう。
ところで、浦荘に冠された「浦」の名称は、その荘域あるいはこの荘園の成立以前に「浦」と称された一定の地域が、本来、河海と接していたことを示唆している。この場合、河海とは吉野川を意味しようが、それが後世の河道の変遷や、付近の開発などのため、いつしか吉野川と切りはなされ、現在の石井町浦庄(上浦・下浦)・鴨島町上浦の地域を指す地称として固定したとみられるのである。また、上浦・下浦の地称も、吉野川の上流寄り・下流寄りという意味をもつのだろう。
その意味で注目されるのが、『吉野川』(毎日新聞社編)による吉野川の旧河道の比定である。同書は、鴨島町西尾に源を発し、鴨島町上浦・石井町浦庄の中央部を貫通して、現吉野川と並行して流れる飯尾川を吉野川の旧河道と断定している(20)。近代にいたるまで、吉野川はしばしば氾濫を繰返しており、その度に大きく河道を改めたとみられるが、ある時代、吉野川は現在よりずっと南寄りの現飯尾川を本流としていたのである。貧弱な自然堤防を乗越えて、吉野川の氾濫はしばしばこの地を直撃したことであろう。しかし、こうした氾濫は大きな災害とともに、肥沃な土壌とそれによる豊かな稔りとをこの地にもたらしたはずである。
当地が古代において国府(現徳島市国府町内)の設置された名方郡に属し、はやくから阿波国の先進地帯の一画を構成してきたというのも、そのあたりに理由が存していよう。国分尼寺址・石井廃寺址・浦庄廃寺址などの遺構およびそこからの出土品は、現在の石井町の地域に仏教文化の開花するのが、奈良時代にまで遡ることを教えてくれる。
その後、寛平8年(896)、名方郡は名方東郡(名東郡)・名方西郡(名西郡)の東西両郡に分割され、国府は前者に、当地は後者に属することになった。更に、おそらくは平安時代末期になってであろう、名東郡の西部・南部をさいて以西郡が独立し、名西郡はその東の郡境をこの以西郡と接することになった。こうして、かつての国府所在郡であった名方郡は名東・以西・名西の三郡に分割されるに至ったのである。もっとも、このころになると全国的に国郡郷の整然とした律令的地方行政制度が崩壊し、多数の郡が分立し、国家(国衙)や荘園領主によって、郡・郷・荘等がそれぞれ独立した単位として把握されるようになったとみられている。以西郡の分立も、このような全国的趨勢と無縁ではなかろう。
この時代、国府所在郡には国衙領が集中的に存在し、国衙の在庁官人の在庁名が濃密に分布することが知られている。あるいは「以西」郡の本来の字義は「鮎喰川以西」を意味するところにあったのではないかとみられるが、在庁官人を中心とする勢力が、自分達の勢力の扶植の場として、以西郡を一郡として独立させたものであろう。こうして、国府所在郡としての以西郡に国衙領を確保する一方、国府所在郡としての地位をとかれた名東郡に属する自己の所領を、荘園として中央の貴顕・大社寺に寄進する道を開こうとしたのではなかろうか。
とにもかくにもこの時代、国衙領であれ荘園であれ、国衙膝下の地域として、名東・以西・名西の三郡には在庁官人の所領が集積されていったとみられるのである。石井町高原には「はんぐゎんだい」の地称があり、阿波に上陸した源義経が平氏追討のため屋島に向かう途中、この地で一時休息したとされ、その後、同地には判官大明神が祀られたという(21)。義経が検非違使尉(判官)であったことにちなむ地称というのであるが、この伝承はやや疑わしく、「はんぐゎんだい」には、在庁官人の官途として諸史料にしばしば登場する「判官代」をあてるべきであろう。国衙膝下の地であることからみて、おそらく在庁官人である判官代の給田等があったと思われる。また、同じく石井町内にのこる利包・国実などの地称、慶長の検地帳にみえる下浦のながのぶ、明治初期まで上浦の字名の一であったとしとふなどの地称は、国衙の在庁名に由来するのではなかろうか。
更に、石井廃寺祉にほど近い童学寺は、阿波における藤原仏の宝庫である。国の重要文化財に指定されている薬師如来像をはじめとして、阿弥陀如来像・聖観音菩薩像・持国天像・畏沙門天像などがあるが、これらは平安時代の当地の在庁官人を有力な外護者として造仏されたと考えて大過なかろう。
このような地にやがて浦荘が設置されることになるのである。ここで、この荘園に関する一連の事項について、考察を加えてみたいのであるが、確かなことは殆んど知られていないのが実情である。以下、若干の推測をまじえながら、考えてみることにする。
まず、この荘園の成立時期と設置の期間に関してみてみよう。浦荘が史料に初めて姿をみせるのは、これまで述べてきた当麻曼荼羅との関連においてであって、それ故、源尊が当地に下ってきた建保5年(1217)を遡りえないことになる。遅くともこの時までに浦荘が設置されたことが知られる。また、建武2年(1335)付西園寺家所蔵文書(22)にその名がみえ、少なくともこのころまで存続したことが確認できる。一方、『阿波国徴古雑抄』は建治2年(1276)付名西郡城内村幸蔵所蔵鎌倉判物なるもの(23)を採録しており、同文書には「浦新庄」なる文言が見えるが、現在同文書の行方は不明であり、全体としてその文言もやや整わず、伝来の経緯にも疑念がのこる。おそらく、疑文書とみてよかろう。とはいえ、かえって疑文書であるが故に、いつの時にか浦新荘がもうけられたのは確かなことと推測したい。後世、この荘園が地称としてのこり、人々から浦新荘とよばれる一地域が存したからこそ、疑文書に「浦新庄」と記されたのであろうから。ただ、浦新荘の成立時期は不明というほかなく、同荘および浦荘がいつまで存在したかについても不詳である。
次に、浦荘の荘園領主・在地領主など、この荘園に関係した人々について考えてみよう。
当時の荘園制度においては、今日の一元的な近代的土地所有制度と異なり、一個の土地に、複数の人々による重層的な権利が及んでおり、その権利関係も多様であった。通常、一個の荘園には、荘園領主として領家がおり、更に上位の本家が存在する場合もあった。
おそらく、建保時における浦荘の本家は、後鳥羽院その人と考えてよかろう。曼荼羅新写における後鳥羽院の立場は既に述べた。それ故、浦荘が曼荼羅新写の地に選ばれた背景には、後鳥羽院の意向があったと判断される。後鳥羽院が浦荘を選んだのは、当荘が上質の絹を産する絹の荘園であるという理由だけではなく、自身の荘園であったためとみられるのである。それ故、浦荘は後鳥羽院の膨大な所領の一であり、広義の皇室御領であったに相違ないと思われるが、それ以上のことは分からない。完成した曼荼羅が蓮華王院宝蔵に納められたことからして、蓮華王院領であった蓋然性も高いと思うのだが、そう断定できる史料はみあたらないのである。
領家については、時代は降るが、確実な史料がのこされている。建武2年(1335)7月12日、後醍醐天皇によって西園寺公重に安堵された所領の中に、当の浦荘が含まれている(24)。西園寺家に安堵されているから、領家職とみてよかろうが、この時、公重はわずかに19才であった(25)。実は、この直前、公重の兄・公宗の後醍醐天皇打倒の陰謀が発覚し、そのため公宗は8月2日に誅されている(26)。その陰謀とは、北条高時の弟・泰家が京都に潜入して、公宗にかくまわれ、時興と改名しており、この時興が京都の大将となり、信濃にひそむ高時の遺児と相呼応して兵を起こし、持明院統の後伏見院を奉じようとするものだったという(27)。そして、この陰謀を密告したのが公重だったのである(28)。その功により、公重は西園寺家の家督相続を許され、前述の所領を安堵されたのだった。
それ故、公重以前の浦荘の領家は公宗であったとみられるが、西園寺家の領家職伝領は何時の時点まで遡及させることができるのだろうか。私は、少なくとも曼荼羅が新写された建保年間まで遡らせることができると考える。
一体、建保時の曼荼羅新写に触発された気味があるが、鎌倉時代は、当麻曼荼羅信仰が盛んであった時代である。
中将姫が織ったとされる綴織の曼荼羅原本は、製作当初から扉のない大厨子の中に掛けられていた。恵阿弥陀仏達が嘆息するように、鎌倉時代の初め既に破損が目立つようになっていたのは、そのせいでもあった。そのため、仁治3年(1242)、厨子の周囲に扉や連子を取付ける修理が行われた。この大厨子の改造は鎌倉将軍・藤原頼経が行ったものと推定されているが、扉には、その他の多くの結縁者の交名が記されている。
この結縁者中、頼経の隣にみえる「寂静恵」を、河原由雄氏は、頼経の母・西園寺倫子の法名と推定しておられる(29)。同じ交名の中に、頼経の父で倫子の夫である九条道家、両者のもう一人の息子・九条教実の名もみえ、河原氏の推定が正鵠を得たものであることを証している。
仁治時の大厨子改造が将軍頼経を中心に、その生家・九条家、その外戚・西園寺家の助力をえて実施されている事実は重要である。おそらく、建保時の後鳥羽院を中心とした曼荼羅新写にも、九条家・西園寺家の結縁があったとみてよかろう。更に、第一転曼荼羅新写後まもなく、後鳥羽院后・宜秋門院(九条任子)御願の第二転曼荼羅が製作され、女院は手ずから蓮糸を繰取り常の絹糸に副え(30)、嘉禎3年(1237)、女院の甥・道家の沙汰として同曼荼羅が信濃の善光寺に納められていること(それ故、この曼荼羅は善光寺曼荼羅とよばれる(31)も、九条家(及び西園寺家)が第一転曼荼羅に関与したことを推測させる。
後鳥羽院が浦荘を曼荼羅新写の地に選んだもう一つの理由は、建保時のこの荘園の領家が西園寺家(おそらくは当主・公経)であったためと思われるのである。それ故、領家職は公経から彼の子孫へと、代々西園寺家によって伝領され、建武時の公重に至ったと考えられる。ここで、関係者の略系図上に、浦荘の領家職伝領順位を示してみよう。

次に浦荘の在地領主について考えてみよう。鎌倉幕府が成立すると、阿波守護には佐々木経高が任じられ、佐々木氏は石井町の鳥坂城に守護所を置いたとされている。あるいは浦荘には地頭が置かれ、その地頭として佐々木氏がこの地に入部してきたのではなかろうか。かりにこの時点で、当荘に地頭が置かれなかったとしても、この荘園は後鳥羽院の領有する広義の皇室御領であった。それ故、承久の変(1221)後、一旦鎌倉幕府に没収され、その後当荘に地頭が設置されたはずである。それ以前佐々木氏一族が当地の地頭であったとしても(当荘には地頭が設置されていなかった可能性もあるが)、佐々木氏は承久の変で京方として滅んでいるので、他氏への交替がみられたはずである。しかし、承久の変後の地頭については、何も分かっていないのが実情である。
それでは、他の在地領主についてはどうだろうか。時代は降るが、戦国時代に当地を領有したのは、田口重能(成良)の子孫と称する有用(ありもち)氏であった(32)。田口氏は平氏方の有力な家人として、治承・寿永の内乱期(1180〜85)に活躍したことで名高いが、その本貫は名西郡桜間郷とされる。田口重能は鎌倉において誅されているが(33)、本町在住の石川重平氏は、田口氏の子孫が鎌倉時代に入っても桜間郷を中心にその勢力を維持したのではないかと、強調しておられた。五味文彦氏も鎌倉時代の田口氏が阿波国の有力在庁の地位を保ったとみておられる(34)。田口氏が本貫に近いこの地に進出し、土着する可能性も大きいのではなかろうか。その子孫が戦国期にあらわれる有用氏であると考えておきたい。『阿府志』は有用氏が「代々当地頭ニテ」とするが(35)、鎌倉幕府が西国の武士を地頭に補任するのは稀れである。曼荼羅新写の建保時には、当荘の在地領主として田口氏がいたとみられるが、地頭ではなく、荘官としてであったと思われる。そして、後鳥羽院が曼荼羅新写に当地を選んだ更なる理由の一に、この荘官・田口氏の存在があったとみられるのである。
実は田口氏は俊乗房重源と深い関係にあった。そもそも、治承4年の平氏による南都焼き打ちに、侍大将として加わっていたのが田口重能であった。重能は前非を悔い、自身の罪根を救わんがため、重源に託して、東大寺に浄土堂を建立し、この堂のために丈六仏九躰を寄進したのである(36)(重能の遺族がそうしたと考えることもできるが、今は重能自身のことと解しておく)。
一方、この時の平氏の南都焼き打ちによって、当麻寺も罹災し、それ故、重源の推挙によって恵阿弥陀仏等が当麻寺の勧進聖に任じられたことは既に述べた。田口氏にすれば、当麻寺を焼き払ったのは、彼等の祖先(あるいは近親者)である重能ということになる。あるいは、彼等の中にも、南都焼き打ちに参加したものがいた可能性もある。彼等が、重能にならって、祖先あるいは自分自身の罪根を救うため、曼荼羅新写を積極的に助力した蓋然性も高い。おそらく、恵阿弥陀仏達は重源との関係から、この様な阿波の在地の事情を熟知しており、浦荘を曼荼羅新写の地として推薦したと思われる。
以上、後鳥羽院が浦荘を選んだ理由は、多岐にわたるが、考えぬかれた判断によるものだったといえよう。この荘の本家・領家・荘官が、それぞれの立場において、この事業を推進し、援助したのである。
3.阿波国と絹
浦荘が曼荼羅新写の地に選ばれた理由の中、いまだふれていないいま一つのものがある。それは、この荘が絹の荘園であり、この地で上質の絹を容易に手に入れることができたということに他ならない。それこそ、最大にして絶対の理由であったはずである。
しかし、上質の絹の生産が、一朝一夕に成就するはずのないことも確かである。律令政府は、租税の中、調を主として、絹・■(あしぎぬ)・糸・綿(真綿)など絹製品で徴収しており、それ故、絹製品は全国各地で生産され、古代日本においては、確かにある意味でありふれた日用品であった。阿波国も例外ではない。現在、正倉院の御物中には、「阿波国麻植郡川島少楮里戸主忌部為麻呂戸調黄絶一疋 天平4年10月」の銘文のある■(あしぎぬ)が蔵されている。しかし、上質の絹となれば話は別である。そのような絹は、熟練した技術者の何代にもわたる研鑚によってはじめて織成されうるものだろうから。当地あるいは阿波国には、そうした技術的背景、伝統が存したことになる。以下では、この問題について考えてみよう。
愉快なことに、阿波国と絹(あるいは養蚕)との関係は、神代にまで遡らせることができる。
『古事記』の国生み神話によれば、伊邪那岐命・伊邪那美命二柱の神が伊予之二名島(四国島)を生んだ時、この島は身一つにして面(おも)が四つあり、その一つ阿波国は大宜都(おおげつ)比売といったという。この大宜都比売に、速須佐之男命が食物を乞った時、大宜都比売は鼻・口・尻よりこれを取り出したので、怒った速須佐之男命はこの女神を殺してしまった。この時、女神の身体の各部分から種々の穀物が生い出たが、女神の頭には蚕が生(な)ったという。この世の創めに女神が殺され、その遺体から栽培植物が発生し、農耕が始まるとする神話は、南太平洋の各地に広く分布しているそうであるが、大宜都比売もこのような植物神(穀物神)的性格を有しているとみられる。女神が阿波の神でもあることは、わが国養蚕の歴史が阿波国に始まった何よりの証左であると主張すれば、強弁のそしりを免れえないであろうが、忌部氏の阿波への拓植伝説を考えあわせると、古代における阿波国の繊維生産の隆盛ぶりを反映した神話ともみられよう。
また、次のような伝承もある。
『日本書紀』によれば、応神天皇37年(306)2月1日、阿知使主(あちのおみ)父子を呉(中国の江南地方、当時は南朝の宋の代であった)に派遣し縫工を求めしめたが、呉王はこれに応えて、工女兄媛・弟媛・呉織(くれはとり)・穴織(あなはとり)の四人の女を与えた。この阿知使主の子孫の一が漢人村主(あやひとのすぐり)で、彼らは阿波以下の五ケ国に分置されたという(37)。また、『鴨島町誌』はこれら工女の子孫である呉服部(くれはとりべ)が、麻植郡に移住し織物を伝えたとし(38)、『阿府志』は麻植郡飯尾村(現鴨島町内)の韓人(からふと)(現在、地元の人達はカロウトと発音し、唐人の字を宛てている)に、呉部・穴部の織人を指し置いたと述べている(39)。両者とも『倭名類聚抄』の麻植郡呉島(くれしま)郷の郷名は、彼等の故国の名に負うというのである。
吉田東伍氏は『大日本地名辞書』の中で、この呉島郷を牛島・鴨島・西尾の諸村(いずれも現鴨島町内)なるべしとされ、郷名は忌部の率いた呉服部の住処に基づくのではないかとされた。吉田氏は、『古語拾遺』の説く、忌部氏が麻植郡に拓植し、穀・麻を植え、歴代の践祚大嘗会に荒妙を貢進したという伝承を重視されたのである。また、『阿波志』は後述する和銅年間の排文師の派遣との関係で、呉島郷の郷名を説明している。
私にはいずれの説も納得しかねる部分があるように感じられるが、ともあれこれらの伝承(あるいは大宜都比売の神話を含めて)は、律令時代以前から、麻植郡を中心として阿波国でも、絹の生産がなかなか盛んであった史実を反映したものといえよう。
ただ、高級な絹織物の生産は奈良時代を待たねばならなかったし、このころになると、確かな史料も散見する。前述した正倉院御物中の■は、阿波国において絹が生産されていた最も確かな徴証といえよう。それを遡る和銅4年(711)閏6月、政府は諸国に排文師(あやとりし)を派遣し、錦・綾の織成技術を伝え(40)、ほぼ1年後の同5年(712)7月には、阿波をはじめとする21ケ国ではじめて錦・綾を織らしめている(41)。『阿波志』はこの織成の地を麻植郡呉島郷とするが(42)、一般にこのような高級絹織物の生産は、国衙のもとに設置された工房においておこなわれたと考えられている。櫛木謙周・栄原永遠男両氏は、この七月という織成の時期が、賦役令にいう、調の納入期限とかかわりをもつとみておられる(43)。
もっとも、時代と場所はやや異なるが、延喜2年(902)の板野郡田上郷戸籍断簡をはじめとする諸史料に、錦部・服部・漢人・秦氏・忌部など、織物に関係の深い人々の名がみえ、阿波における繊維生産が、かなり広汎な地域に普及しはじめていたことを窺わせる。
いま、平安時代初期の阿波の絹を考えるために、『延喜式』をとりあげてみよう。同書によって、阿波国の輸する調などの中、繊維製品(及び染料)に関係するものを次表に示す。
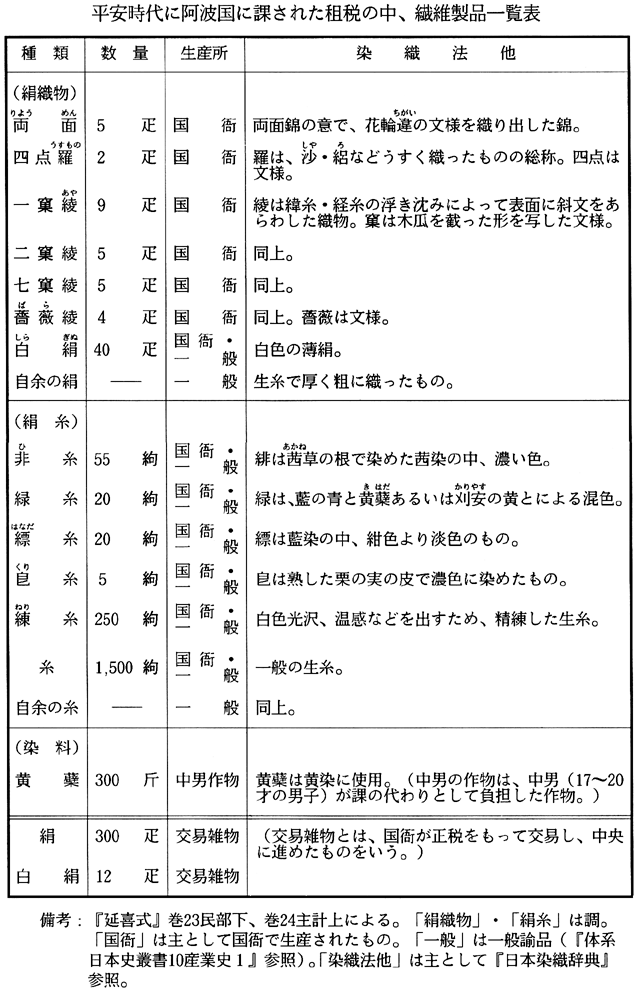
以上、実に多様な絹織物・絹糸が調として輸されており、その他、国衙が正税でもって購入し、中央に進めた交易雑物にも絹織物が含まれている。
『延喜式』によれば、調として絹織物を輸する国は合計39ケ国、これが絹を輸する29ケ国と■(一般により糸があらく、粗悪な絹織物とされる)を輸する10ケ国の二階梯に区分されたが、阿波を含め四国各国は前者に属している。一方、調として絹を輸する国は合計48ケ国、これが上糸国12ケ国・中糸国25ケ国・麁糸国11ケ国の3階梯に区分されたが、南海道で上糸国に分類されているのは、紀伊を除けば阿波一国である。『延喜式』によるかぎり、南海・山陽・山陰の三道の中では、阿波の絹生産が最大であった様子が窺われる。
仁和3年(887)6月、阿波をはじめとする19ケ国に対し、その貢献する絹織物が粗悪であるとして、政府は正倉院の旧様の絹を各国に1疋ずつあたえて、旧様により織成させるよう命じている(44)。これをもって在地の織成技術水準が低下したとする見解があるが、事実は全く逆と考えた方がよいようである。優良品は、対価を得ることのできる交易雑物(前掲の表に示したように、阿波でもかなりの量の絹織物が交易雑物とされている)や、さらには私的な交易へまわされ、残った不良品が中央に貢納されたらしいのである(45)。
平安時代中期に著わされた『新猿楽記』には、諸国の物産の中、「阿波絹」の名があげられている。おそらく、上述した阿波における絹生産の発展にささえられて、この時代、上質の絹を求める都の人々に「阿波絹」がもてはやされるようになったのだろう。
ただ、この「阿波絹」が浦荘(あるいは荘園成立前の当地)で生産されたかどうか、あるいは、奈良・平安時代の国衙工房における上質の絹の織成技術が、直接、鎌倉時代の浦荘における当麻曼荼羅新写に使用した絹の織成技術と結びつくかどうかは、やや疑念ものころう。しかし、何といっても浦荘は国衙膝下の地にあった。浦荘(あるいは荘園成立前の当地)に、またそこに置かれた在庁名に、国衙工房の専業的織工達の免田等が設定されていたとしても不思議ではなかった。また、織工達が浦荘の地に居住していた蓋然性も高いのではなかろうか。
当地における技術的継続性は別として、そうした土壌は一貫して培われていたと判断されよう。この土壌を基盤として、絹の荘園・浦荘における絹生産が開花・発展したとみられよう。後鳥羽院が曼荼羅新写の地に浦荘を選んだのも、当然といえば当然の選択ではあったのである。
おわりに
浦荘の人々が丹誠こめて織り上げた絹に新写された建保曼荼羅は、貞応2年(1223)4月7日、それまで預け置かれていた蓮華王院宝蔵から出され、同年6月17日には当麻寺に納められた(46)。この背景には当麻曼荼羅を厚く信仰した、京都西山善峯寺の善恵房証空(浄土宗西山派の祖)の意志が強く働いていたに違いないとの見解があるが、私見はやや異なる。後鳥羽院が、蓮華王院宝蔵を正倉院にも匹敵する宝庫にしたいという、後白河院の事業を継続したのではないか、とする私見は既に述べた。貞応2年のこの曼荼羅移徙には、承久の変(1221)に敗れた後鳥羽院が隠岐に遷幸したことが深くかかわっているとみたい。後鳥羽院の事業継続の願望が絶たれた以上、曼荼羅が本来あるべき場所、当麻寺に奉納されたのは当然のことといえよう。
しかし、この建保曼荼羅は、室町時代に行方不明になってしまう。延徳3年(1491)、建保曼荼羅は興福寺一乗院殿によって借り出され、再び京都に運ばれて、細かく計測された。これは翌明応2年(1492)より織成された文亀曼荼羅製作のための準備と考えられているが(47)、これ以後の足跡が明らかにされないのである。深まりゆく戦国の混乱の中で、人々はもはやこの曼荼羅のことなど気にかける余裕を失ってしまったようだ。あるいは、建保曼荼羅は既に地上から消滅しているのかも知れず、それ故、われわれが鎌倉時代の浦荘の人々の高度な絹の織成技術を検証する機会は、もはや永遠にやってこないのかも知れない。
しかし、歴史の流れの中で、その波間に消えさったものを大げさに嘆いてみせるに終始するのは、歴史に対する公平な態度といえないだろう。今日、浦庄の龍王山の麓に、お霊藪(たまやぶ)とよばれる場所がある。文字通り、あたり一帯、藪におおわれた所であるが、その中に二基の五輪塔が寄りそうように立っている。石川重平氏によれば、この五輪塔は鎌倉時代中期の特徴をよく示すものとのことである(48)。


その前方に大正8年3月に地元の氏子達によって建立された「御霊社」の石碑がある。碑文によれば、この五輪塔は、建武2年(1335)、時の朝廷に「麻ノ曼荼羅」を織成貢献した夫婦の墓であり、後世、「御霊社」として祀られているのである。地元の人によれば、夫婦の中、妻の名をお霊(たま)さんといい、彼女が優れた技術でこの曼荼羅を織成したという。この地における建保曼荼羅織成の史実が、やや混乱したかたちではあるが、口碑として伝わってきたのである。それにしても、何と素晴らしい伝承であろう。浦庄の人々の郷土愛が、子々孫々にこの伝承を語り継がせ、この口碑が、五輪塔を神社に変え、大正年間の石碑として結晶したのである。
そうはいうものの、碑文にみえる「麻ノ曼荼羅」の「麻」は、「当麻曼荼羅」の「当」の一字が欠落したものとみなしてはなるまい、やはり、繊維の麻をさすと考えるべきであろう。また、お霊藪が、鎌倉時代の曼荼羅織成の工房の跡と速断することもつつしむべきだろう。お霊さんという織工の実在性についても、否と答える方が無難だろう。お霊さんの名は五輪塔に基づくもので、その逆ではないからである。しかし、この五輪塔と石碑とは、浦荘の地に展開された高度な絹織物生産の伝統と、そこに生起した人々の当麻曼荼羅製作のための絹織成にかたむけた情熱とを、物語ってあまりある。現在、お霊藪は深い藪におおわれ、この五輪塔と石碑にはつる草がまとわりつき、まわりにも深い草木が生い茂っている。もっともっと両者とも大事に保存され、顕彰されてしかるべきと思われる。
もう一つの興味深い伝承と史実とが、鴨島町飯尾にのこされている。同地に呉の国からの織工たちが分置されたという伝承は既に述べた。これらの人々は、飯尾字唐人に、萬陀羅御前を祀る呉羽神社を建立したという(49)。『鴨島町誌』によれば、鴨島町敷地に、「呉谷(くれだに)」・「唐谷(からだに)」という渓流があり、ここで麻を晒して織物を生産したといい、この織物は「萬陀羅織」と称され、神代の昔から明治35年ごろまで、隆盛を極めたという(50)。上田利夫氏によれば、「まんだら織」は、経糸が絹糸・緯糸が麻糸(あるいは両方とも麻糸)で織られ、明治年間に入って「神代縞(じんだいじま)」と呼び名が改められたという(51)。用途としては、掛軸の一文字などに使用されたという。これらの伝承もまた、飯尾における「まんだら織」が、神代にまで遡ることを証するものではない。むしろ、「まんだら織」の名称は、麻と絹とを用いるところから、「まだら(斑)」の意味で使われている気配もある。おそらく、このまんだら織はわが国における絹生産が中国製品におされて衰退した後、江戸時代に復活した絹織物にその起源を求めるべきであろう。それ故、江戸後期を遡らないとみたい。
しかし、「まんだら織」の名称が、それを使用する人々の意識にあったか否かは別にして、鎌倉時代の建保曼荼羅に基づいていることは疑いを容れない。鴨島町飯尾と石井町浦庄とは飯尾川で密接に結ばれている。両者の交流の中から、江戸後期の織物の名称に「まんだら」の名が再生したとみられるのである。
今日、どちらかといえば、建保曼荼羅のことは人々の脳裡から消えようとしている。浦荘における優れた絹生産の歴史も、忘却の淵に沈もうとしているようにみえる。時代の推移は、人々の衣服を合成繊維にかえた。その中心部を貫通する国道、その道をひっきりなしに往来する車の群れ、その両側に林立する近代的な建築など―今日の浦庄も典型的な都市近郊農村に変貌しようとしている。しかし、お霊藪からの帰り道近くを散策して、よく耕された田畑と、なだらかな四国山脈を見ていると、急に鎌倉時代の昔が甦ったような気分に襲われた。感傷的になったのではなく、伝統の力が今でもそこに生きていることが、直感的に理解できたからである。繰返しになるが、お霊藪の保存が大事であると強調したい由縁である。(田中記)
付記:本稿をなすにあたっては、本町在住の石川重平先生・上田利夫先生の御教示・御高配をえた。何度か突然お邪魔したにかかわらず、懇切なご指導を賜わった両先生に深謝申上げます。
注
(1)『大日本史料』第4編之14 建保5年是歳条
(2)小林剛氏『俊乗房重源の研究』17ページ
(3)『鎌倉遺文』1163号
(4)『当麻曼荼羅注』巻第1、『当麻寺』(『大和古寺大観』第2巻)所収
(5)注(3)に同じ。
(6)『一遍聖絵』第8
(7)毛利久氏「当麻寺の歴史と美術」(注(4)書所収)10ページ
(8)注(7)書11ページ
(9)同上
(10)『明月記』建永元年6月6日条
(11)渡辺一氏「東寺12天屏風考」(『美術研究』60号所収)
(12)『明月記』建暦3年4月26日条
(13)河原由雄氏「綴織当麻曼荼羅図」(注(4)書所収)88ぺージ・注(19)
(14)『大乗院寺社雑事記』文明4年12月23日条
(15)注(13)に同じ。
(16)興福寺弥勒像台座框墨書銘(久野健氏『運慶の彫刻』188ページ)
(17)同上
(18)『年中行事絵巻』(『日本絵巻大成』8)120ページ
(19)沖野舜二氏「阿波国庄園考」浦庄項
(20)『吉野川』27ページ
(21)『名西郡誌』156ページ
(22)『阿波国徴古雑抄』巻4
(23)同上書巻1
(24)注(22)同じ。
(25)『公卿補任』建武2年条藤公重項
(26)『公卿補任』建武2年条藤公宗項
(27)『太平記』巻第13「北山殿謀叛事』
(28)同上
(29)河原由雄氏『「当麻曼荼羅縁起」の成立とその周辺』(注(4)書所収)123ぺージ
(30)この絹糸も浦荘で生産された可能性があろう。
(31)注(4)書に同じ。
(32)『阿府志』巻第28
(33)『延慶本平家物語』巻6末、七建礼門院小原へ移給事阿波民部並中納言忠快之事
(34)五味文彦氏「東大寺浄土堂の背景」(『院政期社会の研究』所収)
(35)注(32)同じ。
(36)『南無阿弥陀仏作善集』、『東大寺造立供養記』
(37)「坂上系図引用姓氏録第23巻」(太田亮氏『姓氏家系大辞典』漢人条所収)、出口大士氏の御示教による。
(38)『鴨島町誌』149ページ
(39)『阿府志』巻第23
(40)『続日本紀』和銅4年閏6月丁巳条
(41)『続日本紀』和銅5年7月壬午条
(42)『阿波志』麻植郡条
(43)櫛木謙周・栄原永遠男氏「技術と政治―律令国家と技術」(三浦圭一氏編『技術の社会史』1 所収)126ページ
(44)『三代実録』仁和3年6月2日甲辰条
(45)注(43)書、137・8ページ
(46)注(1)に同じ。
(47)注(13)書、85ぺージ
(48)『浦庄村史』41・2ぺージ
(49)『鴨島町誌』1034・5ぺージ
(50)同上
(51)上田利夫氏『補稿改訂阿波藍民俗史』332ページ