民俗班 岡田一郎
1.調査対象地・池田町の概況
池田町は、徳島市から約80kmの西部にあって、吉野川が大きく南曲する支点に位置している。昭和31年に箸蔵村が、昭和34年に三縄村と佐馬地村が池田町に合併して、人口約2万4千人、面積約168平方キロメートルとなっている。町の姿は、商業を主とする池田の町を取り囲むように東部に三好町、井川町があり、北西に旧佐馬地村、南に山城町と旧三縄村などの山村集落がある。
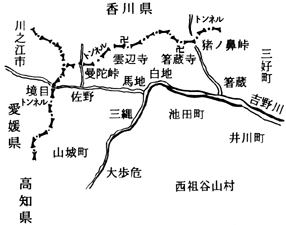
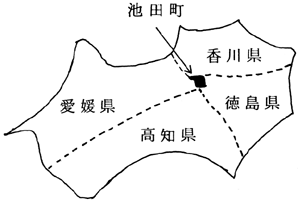
また、池田町は、香川県、愛媛県、高知県(山城町を通して)の三県に接しており、昔から交通の要路であり、県西における経済と文化の中心地であり、三好文化の拠点となっている。
ことに、山地畑作農業の特性を生かしたタバコは、「阿波きざみ」を生み、日本専売公社の支社が池田町におかれている。また、コウゾ、ミツマタなどの和紙原料や、木材、森林資源にも恵まれている。
このほか、この地には、名刹、雲辺寺(四国霊場第66番)や、箸蔵寺などがあり、県境を越えて参拝者が多い。
2.婚姻習俗
調査日程が3日という短期間であったため、比較的古い婚姻習俗の残っていると考えられる漆川(しつかわ)及び香川県境に近い馬地(うまじ)、愛媛県境に接している佐野(さの)の地区を中心に調査を実施した。
調査のねらいは、最も古い婚姻習俗である聟入婚(むこいりこん)(嫁方で式をあげ一定の期間聟が嫁方へ妻問いをする婚姻方式)から、足入婚(あしいれこん)(聟方で式をあげるか、一定の期間妻は里に留まり聟が嫁方へ通う婚姻方式)を経て、嫁入婚(聟方で式をあげ、嫁はそのまま聟の家に留まる現在一般に行われている婚姻方式)に至る婚姻習俗と、それに関係のあるさまざまな土地の風俗や習慣について調査し、池田町の婚姻習俗の特色をつかみたいと考え、この調査を実施した。
この結果、婚姻習俗の古い型であるとされている聟入婚の習俗は殆ど消滅しており、わずかながら、明治、大正ごろのヨバイの風習と、嫁入婚における聟の嫁迎えの風習の中に古い聟入婚の原型をうかがうことができたに過ぎなかった。
3.若衆組とヨバイの風習
年令階梯制の一集団である若者組の組織は、青年団組織ができる以前のものであり、その呼称は若連中(わかれんちゅう)とか若衆組(わかしゅうぐみ)とかいっていた。漆川では八幡組とか、二宮組などともいっていた。
ヨバイの風習は、若衆組の時代とほぼ一致しており、この地方でもかなり盛んであった。
祖谷の粉ひき唄の中に「臼も早まえ廻ってしまえ、外じゃヨバイどが侍ちござる…」とか、「阿波の北方女のヨバイ…」などにもみられる。明治以前の男女の交際は、ヨバイから始まり、これが婚姻に結びつくケースが多かった。青年に達した男が、年頃の娘のもとへ通うのは古来からの風習で、決して現代人が考えるような猥せつな男女の交遊ではなく、当時は、社会から容認されていたごくあたりまえのことであった。
このようなヨバイの風習は、若衆組の解散と、時を同じくして消滅したのであるが、山深い農山村においては、大正から、昭和の初期に至るまで続いていた。
池田町においては、馬地、佐野地区では、明治の末年ごろまで、漆川地域では、大正年代までヨバイの風習が残っていた。しかし、他の町村にみられるような若衆宿とか娘宿等の特設の泊り宿はなく、寺社の拝殿とか、お堂、野芝居の舞台等が若衆組の集合場として使用されていた。また、村の気安い、ものわかりのよい大人のいる民家を宿がわりにしていたこともある。
娯楽設備の少なかった当時の若者たちは、村の祭りや、盆おどり(寺社の境内で行うまわりおどり)などが唯一のたのしみで、近郷近在の若い男女が大勢集まって夜が明けるまでたのしんだという。
池田町内においては、神山町焼山寺の「ボボイチ」とか、一宇村の「アミダイチ」に類するものは、聞くことはできなかったが、古くは、箸蔵寺や雲辺寺等の縁日には、讃岐や伊豫の若連中が大勢集まって、国境を越えて男女の交際があったことが想像される。
このように、村祭りや盆おどり、寺社の縁日が男女接触の最もよい機会であり、これが契機となって男女の交際が始まり、ヨバイヘと発展するケースが多かった。
また、娘の夜なべ仕事(粉ひき、米つき、ギン槌)場へ若者が寄り集まり、意気統合すれば若衆組の承認において1対1のヨバイが開始されることもあった。
ヨバイの風習は社会から容認されていたとはいえ、なかには理解のない親たちもあって苦労した話が残っている。
男が今晩訪ねるという合図のしるしに昼間そっと相手の庭を通っておくとか、いざ夜中に娘の家を訪ねたが裏の戸がきしってあかない。無理をすると大きな音がするので、敷居に小便をして音なく戸を開き成功した話などを佐野の老人から聞いた。また、男がヨバイに来ても娘の好きな人でなければ「はじく」といって声を出して追い返すこともあったという。
漆川地域では、80歳以上の者であればたいていヨバイの体験をしていると聞かされた。
しかし、ヨバイによって婚姻が成立するのは約半数ぐらいであったという。
このように、ヨバイが成功し、親の承認を得て、或一定の期間娘のもとへ通い婚姻を結ぶという風習は、古い聟入婚のなごりであると考えられる。
4.通婚圏
交通の不便であった明治、大正年代までは主として村内婚であった。村内婚であっても「つりあい」を重んじ地主は地主と、小作人は小作人という通婚で、近親結婚や同族結婚が多かった。ろうがい(結核)と犬神の家すじを嫌う風習があったという。
佐馬地村の者は、香川県や愛媛県へ嫁入する者が比較的多かった。しかし、香川県や愛媛県から佐馬地村へ嫁に来る者は少なかったといわれる。これは、稲作のできる豊かな平地へ、畑作で苦労の多い佐馬地村の娘たちがあこがれたものといえる。「讃岐男に阿波女」といわれたように、よく働くやさしい阿波女が讃岐男に歓迎されたのであろうか。
また、香川県や愛媛県から峠を越えて魚や肉の行商人がよく来ていた。この行商人が池田の町に住みつき阿波女を妻にして成功している例が多いという。また、季節労務者として岡山県児島方面ヘイ草取りの出稼に出る者があり、岡山方面との通婚も少しみられた。
佐野は、境目峠を越えて愛媛県の川之江との通婚が比較的多かった。
漆川は、他に比較して村内婚が多く近年まで続いていた。
池田の町へ祖谷山地方から降りてきて居を構える傾向が昭和30年代の高度経済成長期にみられた。そして、その時期を同じくして池田町から、徳島市をはじめ中央都市へ転出する者がみられた。
池田町佐野は、昭和3年に三好橋が開通するまでは、吉野川によって切断されていた。そのために、曼陀峠を越えて観音寺に通じる道と、境目峠を越えて川之江に通じる道の分岐点であったため、宿場町として知られていた。明治、大正の全盛期には、7軒の旅館があった。この地が、借耕牛の引き渡しの地で、山城や三縄方面の牛は、ここで讃岐の農家の人々に渡されていた。また、木材や炭はこの地で讃岐の業者に渡され、カジ屋は、伊豫の商人に渡っていた。讃岐米や海産物は曼陀峠を越えて佐野に集められていた。このように佐野は物資の集散地として、にぎわったのである。峠を馬車にひかせて物資を運ぶために「はながけ」といって馬の先に牛をつなぐ二頭立てであったという。
このような人と物の動きが通婚にも影響し佐野地区の人々は川之江や観音寺方面との通婚が多くみられた。
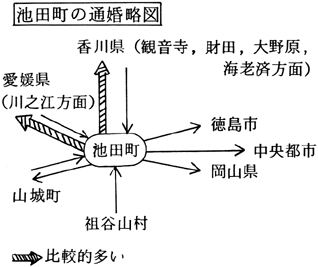
しかし、近年は交通機関の発達や産業構造の多様化によって人の動きがめざましく通婚圏における地域的特色も次第に稀薄なものとなっている。
ちなみに、池田町佐野の中川ヨシノ(明治34年生れ)の10人の子供の通婚先を記してみたい。
1.長男→家を継ぎ佐野に居住。
2.長女→池田町内へ嫁ぐ。
3.次男→高松市へ。
4.三男→東京都へ。
5.四男→箸蔵へ(池田町)
6.五男→白地へ(池田町)
7.三女→伊豫三島へ。
8.四女→東京都へ。
9.五女→佐野(池田町)
10.男1人はお産時に死亡。
以上のように、この1例からみても、約半数は地元に留まっているものの、かなり広範に遠くまで通婚していることがわかる。
5.嫁入婚
先に述べたように婚姻習俗は聟入婚から嫁入婚へと変化し発展してきた。このことは、全国的においても変わるものでない。
嫁入婚は、中世における武家社会がつくりだしたもので、男子中心、家中心のものであり、室町時代にできた伊勢流とか、小笠原流の礼法が主流となっている。武家社会において流行した伊勢流を江戸時代以降に庶民がまねるようになり嫁入婚が一般化し今日に至っている。この伊勢流は仲人により両人の合意を得て嫁入婚が成立するもので見合結婚の形式によるものである。
池田地方においても、戦後の昭和30年〜40年代の高度経済成長期においては、青年の都市志向現象による恋愛結婚、自由結婚が目立ったが、昭和40年の後半より青年のユーターン傾向がみられるようになり、再び仲人による見合結婚が比較的多くなっている。
仲人が相手を選択し仲介する場合どうしても「家のつりあい」を考慮するようになるので自然に保守的な嫁入婚となる。しかし、これは、従来の旧憲法上における家中心、男子中心の婚姻ではなく、あくまでも両性の合意による嫁入婚である。
嫁が実家を出るとき茶わんを割る風習は現在もなお池田町にみられるが、藁火を炊く風習は消滅している。
聟は婚礼の当日、嫁迎えに行く。聟は、仲人、聟の介添、親戚代表と共に嫁の家へ「嫁迎え」に行くが、聟と聟の介添は一足先に帰る。これを「聟の喰い逃げ」という。この風習は、県下でも県南の一部と県の北西部(池田町を含む)にのみ残っている。
嫁入時の嫁送りは、嫁の介添、仲人、両親、樽持、荷持ち(両がけ、柳ごうり)嫁方の親戚代表(兄弟、叔父、祖母)が聟の家まで同伴する。途中他の嫁入組とすれ違った場合は、傘(タカラバチ)を用意していて交換する。
嫁入り行列が近ずくと聟側の代表が門先きまで出迎える。そのとき聟側の代表が嫁側の代表と仲人に迎え酒(立酒)をふるまう。
嫁が聟の家に入るのは勝手口からということになっているが、そのとき「足洗い」を行う。これは、タライに水を入れて女人が嫁の足を洗う風習である。近年は実際に足を洗うのでなく、その動作をするだけになっているが、足洗いの女人には御祝儀を出すことになっている。このような風習は県南にはみられない。
座敷に上がると先づ仏壇をおがむ、そして夫婦の盃(かための盃という)、親子、親戚の盃をかわした後で「床入」をさせる。古くは若者組が床入りの確認をしていたが、現在は、形式だけで、仲人が無事に床入りを済ませたことを一同に宜言している。仲人のなかには「床入」をやらない者もある。
被露宴は夜通し賑かに行なわれた。朝になり日がさしてくるのを防ぐため戸を閉めて続けられたという。しかし、今日は聟の実家で行なうのは稀で、田舎の人でも町の結婚式場で行う例が多い。
とりの盃は、5合ほども入る朱塗りの大盃を座持がまわして終宴となる。池田地方では、祖谷山村でおこなわれたような「えびすおどり」や「かかまわし」の風習はみられない。
結婚式場で行う被露宴には実家の近所の人々の参加は少なく、昔のような部落共同体的な認識は薄れ、村を挙げて嫁とりをよろこぶという風習は消滅しつつある。
結婚式の当日、夫婦の盃を済ませて被露宴に入ると、新婦はすぐに赤いタスキをかけて炊事場に下り酒宴の接侍をしていた(明治、大正の頃)。しかし、近年は、被露宴の終るのをまたずに新婚旅行に出る者も多く、昔の嫁とは隔世の感がある。
また、嫁入すれば歯を染め(おはぐろ)、懐姻すれば眉をそる風習は、明治の中頃までみられた。現在は、このような「カネツケ」を想像することすら困難になっているが、注意深くみると今日なお旧家の片隅にカネツケ道具を発見することもできる。
若妻を「お新造さん」と呼んでいたが、これは新妻を迎えるために新たに別棟の寝室を造っていた名残りであろうが、これは、かなり裕福な家庭でのことで、貧しい農山村の家ではとうていかなえられないことであった。池田地方には「隠居制」の風習はみられない。
婚礼の翌日、近所の子供たちが嫁さんの土産をもらいに行く「嫁さん菓子」を配る風習や、姑が嫁の手を引いて近所まわりする「初歩き」の風習はまだ残っている。また、3日目に新郎、新婦が嫁の里へ行く「里帰り」の風習も今なお続いている。
池田町は、戦後各地の婦人会が卒先して結婚改善を呼びかけ、花嫁の衣裳をはじめ、婚礼用具一切を揃えて一般貸出しを行ない町民から喜こばれていたが近年は再び婚礼が派手になり、婦人会の貸出衣裳を続けているのは旧三縄村だけであるという。
池田町の婚姻習俗が比較的派手なのは、讃岐と伊豫の影響によるものであるという。
おわりに
伊豫と讃岐の接点にある池田町の婚姻習俗について、全県的な視野から考慮し、その特色を探ぐろうと試みたが、3日間という限られた調査日数ではどうしようもなく、まことに御粗末な記録に留まった。後日機会をみて精査したく考えている。
常民の生活用具である民具等の有形民俗文化財もさることながら、冠婚葬祭、年中行事等、無形民俗文化財の記録保存の緊急性を痛感する。こうした意味において、このささやかな婚姻習俗の記録が今後何かに役立つことがあれば幸甚である。
この調査に当り、池田町教育委員会をはじめ、直接御指導をいただいた漆川の佐藤光義(明治36年6月30日生)、馬地出身の滝品吉(明治31年4月13日)、佐野の西吉秋(大正8年生)、吉本元次郎(明治29年12月生)、中川ヨシノ(明治34年4月16日生)の各氏に対し、深甚の敬意と感謝を申し上げたい。